管理人のshinchikupapaです
家を建てることは、多くの人にとって一生に一度の大きな決断です。
だからこそ、工事の安全やその後の家族の幸せを願うのは当然のことでしょう。
その中で、「建築してはいけない日」という言葉を耳にして、不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
古くからの言い伝えや暦には、建築や契約といった重要な行動を避けるべきとされる日が存在します。
具体的には、三隣亡や仏滅といった六曜、さらには十二直や土用の期間、そして何事も成就しないとされる不成就日など、さまざまな種類があるのです。
これらの日を知らずに地鎮祭や上棟式、あるいは重要な契約を進めてしまうと、後から「あの日にしておけば良かった」と後悔するかもしれません。
しかし、建築してはいけない日を正しく理解し、逆に建築吉日と呼ばれる天赦日や一粒万倍日などの幸運な日を選べば、安心して家づくりを進めることができます。
この記事では、家づくりに関わる縁起の良い日と悪い日について、その意味や由来、そしてどのように向き合っていけば良いのかを詳しく解説していきます。
◆このサイトでわかる事◆
- 建築してはいけない日とされる日の具体的な種類と意味
- 三隣亡や六曜が建築に与える影響
- 土用の期間中に建築を避けるべき科学的根拠と迷信
- 地鎮祭や上棟式、契約に最適な日取りの選び方
- 天赦日や一粒万倍日といった建築吉日の活用法
- 暦の吉凶と上手に付き合っていくための心構え
- 安心して家づくりを進めるための知識全般
-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |
家づくりで知るべき建築してはいけない日の種類
◆この章のポイント◆
- 隣家を滅ぼすとされる三隣亡
- 建築と六曜(大安や仏滅)の関係性
- 十二直における建築の吉凶判断
- 土用の期間の工事を避けるべき理由
- 何も成就しないといわれる不成就日
隣家を滅ぼすとされる三隣亡
家づくりを計画する際に、多くの方が気にする凶日の一つに「三隣亡(さんりんぼう)」があります。
この日に建築関連の行事を行うと、「火災を引き起こし、その災いが両隣と向かいの三軒まで滅ぼす」とされているため、建築業界では特に注意が払われている日です。
そのため、地鎮祭や上棟式といった重要な儀式は、三隣亡を避けて日程が組まれるのが一般的となっています。
多くのカレンダーにも記載があるため、一度は目にしたことがあるかもしれません。
三隣亡の由来と歴史
三隣亡の由来には諸説ありますが、元々は「三輪宝(さんりんぼう)」という字が当てられ、建築に良い吉日だったという説が有力です。
それがいつしか暦の誤記や解釈の変更によって、「亡」という字が使われるようになり、現在のような恐ろしい意味を持つ凶日へと変化したと考えられています。
つまり、歴史を遡ると本来は吉日であった可能性が高いのです。
しかし、現代においては「火事を招く」という迷信が根強く残っており、施主や近隣住民への配慮から、多くの建築会社はこの日を避ける傾向にあります。
私の経験上、特に年配の方や地域によっては、三隣亡を非常に気にするケースが見られます。
2025年の三隣亡カレンダー
実際にいつが三隣亡にあたるのかを知っておくことは、家づくりのスケジュールを立てる上で非常に重要です。
参考までに2025年の一部の三隣亡の日を以下に示します。
家づくりの計画を立てる際は、契約や地鎮祭、上棟式などの重要な日程がこれらの日に重なっていないか、事前に確認しておくと安心です。
| 月 | 2025年の三隣亡の日 |
|---|---|
| 1月 | 3日、15日、27日 |
| 2月 | 8日、20日 |
| 3月 | 4日、16日、28日 |
| 4月 | 9日、21日 |
| 5月 | 3日、15日、27日 |
| 6月 | 8日、20日 |
| 7月 | 2日、14日、26日 |
| 8月 | 7日、19日、31日 |
| 9月 | 12日、24日 |
| 10月 | 6日、18日、30日 |
| 11月 | 11日、23日 |
| 12月 | 5日、17日、29日 |
もちろん、これはあくまで暦の上の話であり、科学的な根拠があるわけではありません。
しかし、家づくりは多くの人が関わる一大プロジェクトです。
施主自身が気にしなくても、親族やご近所の方が気にする場合もあるため、無用な心配やトラブルを避けるという意味で、三隣亡を避けることには一定の意義があると言えるでしょう。
最終的には、どこまで気にするかは個人の判断によりますが、このような日があることを知識として持っておくことが、円滑な家づくりにつながります。
建築と六曜(大安や仏滅)の関係性
「六曜(ろくよう)」は、日本で最も広く知られている暦注の一つです。
カレンダーに「大安」や「仏滅」と書かれているのを見て、その日の吉凶を意識する方は多いのではないでしょうか。
もちろん、建築の世界でもこの六曜は深く関係しており、地鎮祭や上棟式、引き渡しなどの日取りを決める際の重要な判断基準とされています。
六曜の基本的な意味
六曜は、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種類が一巡りするもので、それぞれに異なる意味があります。
建築との関連性で言えば、一般的に以下のように解釈されています。
- 大安(たいあん):「大いに安し」の意味で、終日万事において大吉。建築に関連するすべての行事に最適です。
- 友引(ともびき):朝晩は吉、昼は凶。「友を引く」という意味から、祝い事には良い日とされますが、葬儀は避けます。建築の契約や地鎮祭にも向いています。
- 先勝(せんしょう):午前中は吉、午後は凶。「先んずれば即ち勝つ」という意味で、何事も急ぐのが良いとされます。
- 先負(せんぶ):午前中は凶、午後は吉。「先んずれば即ち負ける」という意味で、午後の時間帯から行動するのが良い日です。
- 赤口(しゃっこう):正午のみ吉で、それ以外は凶。特に火の元や刃物に注意すべき日とされ、建築では凶日とみなされることが多いです。
- 仏滅(ぶつめつ):「仏も滅するような大凶日」とされ、終日万事において凶。祝い事を避ける傾向が強く、建築関連の行事も延期されることがほとんどです。
このように見ると、家づくりにおいて最も好まれるのは「大安」であり、逆に最も避けられるのが「仏滅」と「赤口」であることがわかります。
建築行事と六曜の選び方
私であれば例えば、地鎮祭や上棟式の日程を決める際には、まず大安の日を第一候補として探します。
もし大安の日に都合がつかない場合は、次に友引の日を検討するという流れが一般的です。
どうしても日程の都合がつかない場合でも、仏滅や赤口は避けるのが賢明と言えるでしょう。
ただし、仏滅であっても「物滅」と捉え、「一度物が滅び、新たに物事が始まる」として、何かを新しくスタートするには良い日だという解釈も存在します。
考え方次第では仏滅も選択肢になり得ますが、周囲の理解を得る必要はあるかもしれません。
また、六曜はもともと中国から伝わったものが日本で独自に変化したものであり、仏教とは直接的な関係はありません。
そのため、あくまで縁起を担ぐための指標と捉えるのが良いでしょう。
現代の家づくりでは、施主の考え方やライフスタイルも多様化しているため、六曜を全く気にしないという方も増えています。
しかし、家づくりに関わる職人さんや関係者の中には、日柄を大切にする方も少なくありません。
皆が気持ちよく作業を進めるためにも、六曜の意味を理解し、可能であれば日柄の良い日を選ぶ配慮をすることが、円満な家づくりの秘訣の一つと言えるかもしれません。
十二直における建築の吉凶判断
六曜ほど一般的ではありませんが、建築業界で古くから重視されてきた暦注に「十二直(じゅうにちょく)」があります。
これは、北斗七星の動きを基にした暦で、日の吉凶を判断するための指標の一つです。
十二直は「建(たつ)」「除(のぞく)」「満(みつ)」など12種類の漢字で表され、それぞれに固有の意味があり、建築に関連する作業の向き不向きが定められています。
建築における十二直の吉日
十二直の中で、特に建築に関連して吉とされる日は以下の通りです。
- 建(たつ):万物を建て生じる日とされ、建築始めに最も良い大吉日です。柱立てや棟上げ(上棟式)に最適とされています。
- 満(みつ):全てが満たされる日として吉日です。建築や移転、契約事など、新しいことを始めるのに向いています。
- 平(たいら):物事が平らかになる日とされ、地固めや地鎮祭、壁塗りなど、地面に関することに吉です。
- 定(さだん):物事が定まる日であり、建築や移転、開店などに向いています。
- 成(なる):物事が成就する日とされ、新規に物事を始めるのに良い日です。
- 開(ひらく):開き通じる日とされ、建築や移転、結婚などに大吉です。
これらの日は、建築のプロセスにおける様々なイベント、例えば地鎮祭、着工、上棟式などの日取りを決める際に、積極的に選ばれます。
建築における十二直の凶日
一方で、建築を避けるべきとされる凶日も存在します。
- 除(のぞく):障害を取り除く日とされ、本来は吉日ですが、土木工事や建築には不向きとされます。
- 破(やぶる):物事を冲破(突き破る)する日とされ、建築や契約、祝い事には大凶です。
- 危(あやぶ):万事において危うい日とされ、特に高い場所での作業は危険とされます。旅行や登山も凶です。
- 閉(とづ):閉じ込めるという意味があり、金銭の収納などには吉ですが、柱立てや棟上げなどの建築行事には凶となります。
このように、十二直は建築の各工程に対して、より具体的で専門的な吉凶を示しています。
プロの建築関係者の中には、六曜よりも十二直を重視する人もいるほどです。
家づくりの計画を立てる際には、六曜だけでなく、この十二直も併せて確認することで、より縁起の良い日を選ぶことができます。
とはいえ、すべての吉日が重なる日を探すのは非常に困難です。
そのため、例えば「大安」で、かつ十二直の「建」や「満」が重なる日を最優先候補にするなど、優先順位をつけて日取りを検討するのが現実的でしょう。
暦の考え方は様々ですが、多くの人が「良い日」と信じている日を選ぶことは、家づくりを精神的に支え、安心感をもたらす効果が期待できます。
土用の期間の工事を避けるべき理由
「土用の期間」と聞くと、多くの人は「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣を思い浮かべるかもしれません。
しかし、この土用は、建築や土木工事の世界では特に注意が必要な期間とされています。
古くからの言い伝えでは、この期間中に土を動かす作業、例えば基礎工事や地鎮祭、井戸掘りなどを行うことは禁忌とされてきました。
土用の期間とは何か?
土用は、立春、立夏、立秋、立冬の直前の約18日間を指し、年に4回訪れます。
古代中国の陰陽五行説では、万物は木・火・土・金・水の5つの元素から成ると考えられていました。
春は「木」、夏は「火」、秋は「金」、冬は「水」の気が割り当てられましたが、「土」の気だけが余ってしまいました。
そこで、各季節の終わりの18日間に「土」の気を割り当て、これを「土用」と呼ぶようになったのです。
この期間は、季節の変わり目であり、陰陽の気が乱れやすく、不安定な時期とされています。
そして、この土用の期間は、土を司る神様である「土公神(どくしん)」が支配する期間と考えられていました。
そのため、この時期に土を掘り起こしたり、動かしたりすることは、土公神の怒りに触れ、災いを招くと信じられていたのです。
なぜ土を動かしてはいけないのか
迷信的な側面だけでなく、土用の期間に土いじりを避けることには、現実的な理由もあったと考えられます。
第一に、土用の期間は季節の変わり目にあたり、気候が非常に不安定です。
夏の土用は酷暑と多湿、梅雨の終わりと重なることも多く、体調を崩しやすい時期です。
このような環境で無理に土木作業を行えば、熱中症や過労で倒れるリスクが高まります。
また、大雨によって地盤が緩み、工事の安全性にも影響が出かねません。
つまり、農作業や土木作業に従事する人々の健康と安全を守るための、先人の知恵であったとも解釈できるのです。
「間日」なら工事は可能?
約18日間も工事ができないとなると、工程に大きな影響が出てしまいます。
そこで設けられているのが「間日(まび)」です。
これは、土公神が天上界に帰っていて地上にいないとされる日で、土用の期間中であっても土を動かしても良いとされています。
間日は各土用ごとに決まっており、この日を狙って作業を進めることもあります。
| 土用の種類 | 間日となる日 |
|---|---|
| 春の土用 | 巳の日、午の日、酉の日 |
| 夏の土用 | 卯の日、辰の日、申の日 |
| 秋の土用 | 未の日、酉の日、亥の日 |
| 冬の土用 | 寅の日、卯の日、巳の日 |
現代の建築では、工期やコストの観点から、土用を完全に避けることは難しいかもしれません。
しかし、基礎工事の開始日や地鎮祭など、特に重要なイベントの日取りについては、土用の期間を避けるか、少なくとも間日を選ぶといった配慮をすることで、施主も作業員も安心して家づくりに臨むことができるでしょう。
何も成就しないといわれる不成就日
家づくりにおける日取りを考える上で、ぜひとも知っておきたい凶日の一つが「不成就日(ふじょうじゅび)」です。
その名の通り、「何事も成就しない日」とされており、新しいことを始めるのには全く向いていない日とされています。
月に約4回ほど巡ってくるため、意識していないと重要な契約や行事がこの日に重なってしまう可能性もあるため、注意が必要です。
不成就日の意味と影響
不成就日は、陰陽道における考え方が基になっており、この日に始めたことは、どのようなことであっても悪い結果を招くとされています。
具体的には、以下のような行動は避けるべきだと考えられています。
- 契約事:住宅ローンや工事請負契約など、重要な契約を結ぶこと。
- 建築行事:地鎮祭、上棟式、着工など、家づくりの新たなスタートを切るイベント。
- 開店・開業:新しいビジネスを始めること。
- 結婚・入籍:新しい人生の門出となる祝い事。
- 願い事:神社への参拝なども、この日は避けた方が良いとされます。
このように、不成就日は建築に限らず、人生の節目となるような大切なイベント全般に対して凶日とされているのです。
家づくりにおいては、施主と建築会社が初めて顔を合わせる日や、間取りの最終決定日なども、可能であればこの日を避けた方が精神的な安心感が得られるかもしれません。
吉日と重なった場合はどうなる?
ここで一つの疑問が浮かびます。
もし、大安や天赦日といった大変縁起の良い吉日と、不成就日が重なってしまった場合、その日の吉凶はどのように判断すれば良いのでしょうか。
これには諸説ありますが、
一般的には、不成就日の持つ「凶」の力が、吉日の効果を打ち消してしまう、あるいは半減させてしまうと考えられています。
せっかくの吉日のパワーを最大限に活かすためにも、不成就日と重なっている日は、重要な決断や行動を避けるのが無難と言えるでしょう。
もちろん、これも他の暦注と同様に、あくまで古くからの言い伝えであり、信じるか信じないかは個人の自由です。
しかし、「縁起が悪い」とされる日にわざわざ大切な一歩を踏み出すよりは、「縁起が良い」とされる日を選んだ方が、気持ちよく新しいスタートを切れるのではないでしょうか。
家づくりは、性能やデザインといった物理的な側面だけでなく、家族の想いや願いといった精神的な側面も非常に重要です。
不成就日という存在を知っておくことは、後悔のない家づくりを実現するための一つの知恵と言えます。
スケジュールを立てる際には、カレンダーでこの日を確認する習慣をつけておくと良いでしょう。
建築してはいけない日と行事の最適な進め方
◆この章のポイント◆
- 地鎮祭や上棟式の日取りの考え方
- 重要な契約を避けるべき日とは
- 建築に良い日とされる建築吉日
- 最強の開運日である天赦日の活用
- 一粒万倍日を建築に活かす方法
- 後悔しないための建築してはいけない日との向き合い方
地鎮祭や上棟式の日取りの考え方
家づくりにおける二大セレモニーといえば、「地鎮祭」と「上棟式」です。
地鎮祭は工事の安全を祈願する儀式であり、上棟式は建物の骨組みが完成したことを祝い、感謝する儀式です。
どちらも家づくりの重要な節目となるため、日取りの選定には特に気を配りたいものです。
日取りを決める際の優先順位
地鎮祭や上棟式の日程を決める際には、以下の順序で考えていくとスムーズです。
- 関係者の都合の確認:まずは施主家族、建築会社の担当者、そして工事関係者のスケジュールを調整し、候補日をいくつかリストアップします。
- 凶日を避ける:次に、リストアップした候補日から、これまで解説してきた「建築してはいけない日」を除外していきます。具体的には、三隣亡、仏滅、赤口、十二直の凶日、土用の期間(土を動かす地鎮祭の場合)、不成就日などを避けます。
- 吉日を選ぶ:残った候補日の中から、最も縁起の良い日を選びます。理想は、大安や友引といった六曜の吉日と、十二直の「建」や「満」などの吉日が重なる日です。さらに天赦日や一粒万倍日が重なれば、これ以上ない吉日と言えるでしょう。
このプロセスを経ることで、関係者全員が納得し、かつ縁起の良い日を選ぶことができます。
地鎮祭に最適な日
地鎮祭は、その土地の神様に工事の安全と家族の繁栄を祈る大切な儀式です。
日取りとしては、
六曜では大安、友引、先勝が好まれます。
十二直では、「建」「満」「平」「定」「成」「開」が吉とされます。
特に、地面を平らにするという意味を持つ「平」は、地鎮祭に適していると言われています。
逆に、三隣亡や仏滅、そして土を動かすことが禁忌とされる土用の期間(間日を除く)は避けるのが一般的です。
上棟式に最適な日
上棟式(棟上げ)は、家の骨格が完成し、建物の最上部に棟木を取り付ける際に行われる儀式です。
この日も工事の安全と家の堅固さを願う重要な日です。
日取りは地鎮祭と同様に、大安、友引、先勝などが選ばれやすいです。
十二直では、万物を建て生じる日とされる「建」が最も良い日とされています。
一方で、火災を連想させる赤口や、物事が成就しない不成就日は避けるべきです。
また、「危」や「破」といった十二直の凶日も、高所での作業が伴う上棟式にはふさわしくありません。
私としては、日取りの決定は、建築会社とよく相談することが重要だと考えています。
地域の慣習や、会社としての方針もあるため、施主の希望を伝えつつ、プロの意見を参考にしながら最終決定するのが良いでしょう。
縁起の良い日を選ぶことは、単なる迷信ではなく、家づくりに関わるすべての人々の気持ちを一つにし、工事の安全意識を高めるための大切なプロセスなのです。
重要な契約を避けるべき日とは
家づくりは、決断と契約の連続です。
土地の売買契約、建物の工事請負契約、そして住宅ローンの契約など、その一つひとつが将来を左右する重要なステップとなります。
だからこそ、これらの重要な契約を結ぶ日取りにも、縁起を担ぎたいと考えるのは自然なことです。
物理的な工事とは異なりますが、契約もまた「新しいことを始める」という点では同じです。
そのため、契約に不向きとされる日を避けることは、精神的な安心感につながります。
契約に最も不向きな「不成就日」
契約において最も避けるべき日は、やはり「不成就日」です。
前述の通り、この日は「何事も成就しない」とされる大凶日であり、この日に結んだ契約は、将来的にトラブルに見舞われたり、思い通りに進まなかったりすると言われています。
例えば、工事請負契約を不成就日に結んだ場合、「工事が遅延する」「追加費用が発生する」といった問題が起こりやすくなると考える人もいます。
もちろん科学的根拠はありませんが、
後から何か問題が起きた際に、「あの日に契約したからかもしれない」と後悔の念に駆られる可能性は否定できません。
無用な心配を避けるためにも、契約日は不成就日を外して設定するのが賢明です。
その他の避けるべき日
不成就日以外にも、契約を避けた方が良いとされる日があります。
- 仏滅・赤口:六曜における凶日です。特に仏滅は終日凶とされ、お祝い事や契約には向いていません。赤口も、争い事を招きやすいとされ、契約トラブルを避ける意味で選ばない方が良いでしょう。
- 十二直の「破」「危」「閉」:物事が破れるとされる「破」、危ういとされる「危」、そして将来への展望を閉ざす意味合いの「閉」は、契約事には凶とされます。
- 三隣亡:直接契約に関係するわけではありませんが、建築に関連する凶日として広く知られているため、気にする人が多い日です。不動産関連の契約であれば、避けておくと無難です。
契約に最適な日
逆に、契約に良い日としては、六曜の「大安」が最も人気です。
また、「友を引く」という意味から契約相手との良好な関係を期待して「友引」を選ぶ人もいます。
さらに、後述する「一粒万倍日」は、小さな元手で始めたことが何倍にもなって返ってくるとされる吉日で、住宅ローンの契約など、お金が関わる契約には特に縁起が良いとされています。
重要な契約は、人生における大きな一歩です。
スケジュール調整が難しい場合もあるかもしれませんが、可能であれば凶日を避け、吉日を選ぶことで、晴れやかな気持ちで新しいスタートを切ることができるでしょう。
契約前にはカレンダーを確認し、最適な日を選ぶことをお勧めします。
建築に良い日とされる建築吉日
これまで建築してはいけない日、つまり凶日を中心に解説してきましたが、もちろんその逆で、建築に特に良いとされる「建築吉日(けんちくきちじつ)」も存在します。
家づくりという一大イベントを、最高の形でスタートさせるために、これらの吉日を知っておくことは非常に有益です。
建築吉日は、主に六曜や十二直の中から、特に建築に適した日を選んで組み合わせたものです。
代表的な建築吉日
建築会社や地域の慣習によって多少の違いはありますが、一般的に建築吉日とされるのは以下のような日です。
| 吉日の種類 | 内容 | 適した行事 |
|---|---|---|
| 大安(たいあん) | 六曜の一つ。終日万事において大吉。 | 地鎮祭、上棟式、契約、引渡しなど全て |
| 友引(ともびき) | 六曜の一つ。祝い事に吉。 | 契約、地鎮祭、上棟式 |
| 建(たつ) | 十二直の一つ。万物を建て生じる大吉日。 | 地鎮祭、着工、上棟式 |
| 満(みつ) | 十二直の一つ。全てが満たされる吉日。 | 地鎮祭、着工、上棟式、契約 |
| 平(たいら) | 十二直の一つ。物事が平らかになる吉日。 | 地鎮祭、基礎工事、地固め |
| 成(なる) | 十二直の一つ。物事が成就する吉日。 | 契約、着工、上棟式 |
| 開(ひらく) | 十二直の一つ。開き通じる大吉日。 | 上棟式、引渡し、開店 |
これらの吉日が、さらに複数重なる日は、より縁起が良いとされています。
例えば、「大安」であり、かつ十二直が「建」である日は、建築を始めるのにこの上ない日と言えるでしょう。
建築吉日の探し方
では、具体的にどのようにして建築吉日を探せば良いのでしょうか。
まず、家づくりのスケジュールがある程度固まったら、建築会社と相談しながら、地鎮祭や着工、上棟式を行いたい時期の候補を挙げます。
次に、その期間内のカレンダーを見て、先ほど挙げたような吉日をピックアップしていきます。
市販されている暦(こよみ)や、最近ではインターネットの暦サイトを利用すると、六曜や十二直が一覧で表示されるため非常に便利です。
その中から、凶日(三隣亡、不成就日など)と重なっていない日を選び出します。
最終的に残った日が、あなたの家づくりにおける最高の吉日の候補となります。
その中から、関係者の都合がつく日を最終決定するという流れになります。
建築吉日を選ぶという行為は、単に縁起を担ぐだけではありません。
それは、これから始まる新しい生活への期待感を高め、工事の安全を心から願うという、施主の想いの表れでもあります。
また、日柄を大切にすることで、職人さんたちも「この家は大切に思われているな」と感じ、より一層仕事に熱が入るという効果も期待できるかもしれません。
せっかくのマイホーム計画ですから、ぜひ建築吉日を意識して、幸先の良いスタートを切ってください。
最強の開運日である天赦日の活用
数ある吉日の中でも、特に強力なパワーを持つとされるのが「天赦日(てんしゃにち/てんしゃび)」です。
これは日本の暦の上で最上の吉日とされており、「天が万物の罪を赦(ゆる)す日」という意味があります。
この日に始めたことは何事もうまくいくと言われており、建築や契約といった人生の大きな転機において、これ以上ないほどの幸運な日です。
天赦日の希少性とその価値
天赦日は、年に5~6回しか訪れない非常に貴重な吉日です。
その希少性も相まって、特別な開運日として多くの人に知られています。
「すべての障害が取り除かれる」とされるため、これまで躊躇していたことや、新しいチャレンジを始めるのに最適な日です。
家づくりにおいては、以下のような重要なイベントを天赦日に行うことで、その後の家庭の繁栄や工事の安全にご利益があると考えられています。
- 工事請負契約や住宅ローン契約を結ぶ
- 地鎮祭や着工式を行う
- 上棟式を行う
- 建物の引渡しを受ける
- 新しい家への引越し
もちろん、年に数回しかないため、建築スケジュールと天赦日を合わせるのは簡単ではないかもしれません。
しかし、もしタイミングが合うようであれば、積極的に活用したい日です。
天赦日と他の吉日が重なる「最強開運日」
天赦日は、それだけでも非常に縁起の良い日ですが、他の吉日と重なることで、その効果がさらに倍増すると言われています。
特に、「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」と天赦日が重なる日は、「最強の開運日」として注目されます。
私の立場ではたとえば、このような日に住宅ローンの契約を結べば、将来の資産形成が順調に進むといった縁起を担ぐことができます。
家づくりの計画を立てる際には、まず年間の天赦日をチェックし、その日が契約や地鎮祭の候補日にならないか検討してみることをお勧めします。
工務店やハウスメーカーの担当者に「天赦日に地鎮祭を行いたいのですが」と相談してみるのも良いでしょう。
日柄を大切にしたいという施主の想いは、きっと真摯に受け止めてもらえるはずです。
ただし、一つだけ注意点があります。
それは、天赦日であっても「不成就日」と重なる場合は、その効果が半減、あるいは打ち消されるという考え方があることです。
最強の開運日の恩恵を最大限に受けるためにも、不成就日と重なっていないかどうかの確認は忘れないようにしましょう。
天赦日という特別な日を知り、それを家づくりに活かすことは、計画そのものをより楽しく、意義深いものにしてくれるに違いありません。
一粒万倍日を建築に活かす方法
「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」は、天赦日と並んで人気のある吉日の一つです。
「一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になる」という意味があり、この日に始めたことは、やがて大きな成果となって返ってくるとされています。
特に、何かを新しくスタートさせたり、お金に関連することを行ったりするのに最適な日とされており、家づくりにおいても様々な形で活用することができます。
一粒万倍日と建築の相性
一粒万倍日は、その「増える」「発展する」という意味合いから、建築との相性が非常に良い吉日です。
この日に家づくりに関連するアクションを起こすことで、家族の幸せや財産が末永く発展していくという縁起を担ぐことができます。
具体的には、以下のようなシーンで一粒万倍日を活用するのがおすすめです。
- 契約:工事請負契約や住宅ローン契約に最適です。支払った頭金やローンが、将来的に何倍もの価値や幸せになって返ってくると考えられます。
- 地鎮祭・着工:工事の安全と、これから建つ家での生活が豊かになることを願うスタートの日にふさわしいです。
- 引越し・入居:新しい家での生活を始める日として選ぶことで、新生活が実り多いものになることを期待できます。
- 新しい家具や家電の購入:新居で使うものをこの日に購入し始めるのも良いでしょう。
一粒万倍日は月に4~6回ほど巡ってくるため、天赦日に比べるとスケジュールに組み込みやすいというメリットもあります。
一粒万倍日の注意点
良いこと尽くめに見える一粒万倍日ですが、一つだけ注意しなければならないことがあります。
それは、「増える」という性質は、良いことだけでなく、悪いことにも作用してしまうという点です。
つまり、
この日に借金をしたり、人から物を借りたりすると、その苦労や負債が万倍に膨れ上がってしまうと言われています。
住宅ローンは、将来への投資と考えるため問題ないとされていますが、その他の借金や、人間関係のトラブルにつながるような行動は慎むべきです。
また、吉日の効果を最大限に引き出すためには、やはり凶日と重なっていないかを確認することが大切です。
特に「不成就日」と重なる一粒万倍日は、効果が打ち消されるとされるため、避けた方が無難でしょう。
逆に、大安や天赦日といった他の吉日と重なる日は、運気がさらにアップする絶好のチャンスです。
家づくりという大きなプロジェクトの中で、一粒万倍日を意識的に取り入れることは、計画にポジティブなリズムを生み出します。
「今日は縁起の良い日だから、きっと良い打ち合わせができる」といった前向きな気持ちは、より良い家づくりへとつながっていくはずです。
カレンダーで一粒万倍日を見つけたら、ぜひ家づくりの計画に活かしてみてください。
後悔しないための建築してはいけない日との向き合い方
ここまで、建築してはいけない日とされる様々な凶日と、逆に縁起の良い建築吉日について詳しく解説してきました。
三隣亡、六曜、十二直、土用、不成就日、そして天赦日や一粒万倍日。
多くの情報に触れ、「全部気にしていたら、家なんて建てられないのでは?」と感じた方もいるかもしれません。
実際その通りで、すべての吉凶を完璧に守ろうとすると、スケジュールが非常に窮屈になってしまいます。
大切なのは、これらの情報を知識として持ちつつ、自分たちの価値観に合わせて柔軟に付き合っていくことです。
優先順位を決める
まず、自分たちが「何を一番大切にしたいか」を考えることが重要です。
- 絶対に避けたい凶日を決める:例えば、「三隣亡だけは絶対に避けたい」「不成就日の契約はしたくない」など、自分たちの中で譲れない一線を決めます。
- 特にこだわりたい吉日を選ぶ:「せっかくだから天赦日に契約したい」「子どもの誕生日に近い大安に地鎮祭をしたい」など、ポジティブな目標を立てます。
- 気にしない部分は割り切る:すべての暦注を気にするのではなく、「六曜は気にするけど、十二直は気にしない」といったように、ある程度の割り切りも必要です。
このように優先順位をつけることで、日取りの選択肢が広がり、精神的な負担も軽くなります。
家族や関係者とのコミュニケーション
日柄に対する考え方は、人それぞれです。
自分たちは気にしなくても、両親や親戚が非常に気にしているというケースは少なくありません。
また、建築に関わる職人さんたちも、安全祈願の意味を込めて日柄を重視する方が多いです。
後から「あの日じゃなければ…」といった声が出てこないように、事前に家族や建築会社と日取りに関する考え方を共有し、相談しておくことが非常に大切です。
皆が納得できる日を選ぶことが、円満な家づくりの第一歩となります。
最終的には「気持ち」が大切
暦の吉凶は、あくまで先人たちが残してくれた知恵や、縁起を担ぐための指標です。
科学的な根拠があるわけではなく、その日に何かが起こることを保証するものではありません。
最も重要なのは、施主であるあなた自身が「この日に決めて良かった」と心から思えることです。
たとえ仏滅であっても、家族の記念日など、自分たちにとって特別な日であれば、それが最高の吉日になることもあります。
建築してはいけない日という知識は、不安を煽るためのものではなく、後悔を避けるために活用するツールです。
これらの情報に振り回されるのではなく、上手に使いこなし、納得のいく日取りを選んでください。
そうすれば、これから始まる新しい家での生活を、晴れやかで前向きな気持ちでスタートさせることができるでしょう。
本日のまとめ
- 建築してはいけない日とは三隣亡や仏滅などの凶日のこと
- 三隣亡は火災で近隣三軒を滅ぼすとされる建築の大凶日
- 六曜では仏滅や赤口が建築行事に不向きとされる
- 十二直では「破」や「危」が建築の凶日となる
- 土用の期間中は土を動かす基礎工事や地鎮祭を避けるべき
- 不成就日は契約や着工など新しいこと全般に適さない
- 地鎮祭や上棟式は凶日を避け大安や友引などの吉日を選ぶ
- 重要な契約も不成就日や仏滅を避けるのが賢明
- 建築吉日とは大安や十二直の「建」「満」などが重なる日
- 天赦日は年に数回しかない最上の吉日で建築に最適
- 一粒万倍日は始めたことが万倍になる契約や着工に良い日
- 吉日と凶日が重なった場合は凶の影響が強いと考えるのが一般的
- すべてを気にせず自分たちの優先順位を決めることが大切
- 家族や建築会社と日柄について事前に話し合うことが円満の秘訣
- 最終的には暦に振り回されず納得できる日を選ぶのが最良
-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |
参考サイト
三隣亡にやってはいけないことは?2025・2026のカレンダーも紹介 – 東急リバブル
【2025年版】お家づくりの良い日と悪い日【建築吉日】 – 株式会社アラカワ
解体工事の着工日はお日柄の良い日が良い?してはいけない日や大安についてを解説
【2024年版】お家づくりの良い日と悪い日【建築吉日】 – 株式会社アラカワ
建築吉日とはなに?お日柄の重要性をわかりやすく解説

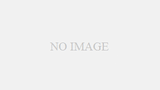
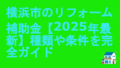
コメント