こんにちは、サイト管理人です
ご家族の安全のために、あるいはご自身の将来のために、家に手すりをつけたいとお考えではありませんか。
しかし、リフォームには費用がかかるため、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
実は、特定の条件を満たせば、公的な補助金制度を利用して費用の負担を大きく軽減できる可能性があります。
その代表的なものが、介護保険制度における住宅改修の支援です。
家に手すりをつける補助金は、高齢者が安全に暮らせる住環境を整備することを目的としており、要介護認定を受けた方などが対象となります。
この記事では、家に手すりをつける補助金を受け取るための詳しい条件や、具体的な申請方法、手続きの流れについて、網羅的に解説していきます。
介護保険を利用した住宅改修の仕組みから、補助金の対象となる費用の範囲、ケアマネージャーとの連携の重要性、さらには賃貸住宅にお住まいの場合の注意点まで、あらゆる疑問にお答えします。
自治体によっては独自の助成制度を設けている場合もあり、そうした情報もあわせてご紹介します。
適切な知識を持つことで、スムーズに手続きを進め、経済的な負担を抑えながら、安心して暮らせる住まいを実現させましょう。
◆このサイトでわかる事◆
- 家に手すりをつける補助金の基本的な仕組み
- 補助金の対象となるための要介護認定の条件
- 介護保険以外に利用できる自治体独自の制度
- 賃貸物件で補助金を利用する際の注意点
- 補助金申請におけるケアマネージャーの役割
- 具体的な申請方法と手続きのステップ
- 申請から補助金受け取りまでの流れと期間

| 【PR】 リフォームをしようとする時に大切なのは「比較をすること」です。しかし実際には、自分で行おうとするととても大変ですし、数多く見積もりをしようとしたら心も折れてしまいます。 そこでおすすめなのがタウンライフの「一括見積り」です。日本全国の600社以上のリフォーム会社の中から、あなたに適したリフォーム会社から見積もりを受ける事ができます 見積もり比較することで、最大100万円程度節約になる事も!自宅に居ながらにして、いくつか項目を記入するだけで、簡単に完全無料で資料を取り寄せる事ができます |
あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪
家に手すりをつける補助金の基本と対象条件
◆この章のポイント◆
- 介護保険を使った住宅改修とは?
- 補助金の対象となるための要介護認定
- 自治体独自の制度も確認しよう
- 賃貸物件でも補助金は使える?
- 補助金でまかなえる費用の範囲
介護保険を使った住宅改修とは?
家に手すりを設置する際に利用できる公的な支援制度として、最も代表的なものが介護保険制度における「住宅改修費の支給」です。
これは、要支援・要介護認定を受けた高齢者が、自立した在宅生活を続けられるように、住環境を整備するための小規模なリフォーム費用の一部を補助する制度となっています。
手すりの設置は、この住宅改修の代表的な例の一つです。
制度の目的は、住み慣れた自宅での転倒などの事故を予防し、被介護者の身体的な負担を軽減すると同時に、介護を行う家族の負担を軽くすることにあります。
具体的には、廊下やトイレ、浴室、玄関など、日常生活で移動や立ち座りの動作が多い場所に手すりを設置することで、安全性を高める工事が対象となります。
この制度を利用することで、工事にかかった費用のうち、所得に応じて7割から9割が保険から給付されます。
つまり、自己負担は1割から3割で済むということになります。
ただし、支給には上限額が設けられており、原則として一人あたり生涯で20万円までと定められています。
この20万円という枠は、一度に使い切る必要はなく、複数回に分けて利用することも可能です。
例えば、まず10万円分の工事で玄関に手すりをつけ、数年後に残りの10万円分の枠を使って浴室に手すりを追加するといった使い方ができます。
重要な点として、この補助金は「償還払い」が原則であるということです。
償還払いとは、工事が完了した後、利用者がまず施工業者に費用の全額を支払い、その後に市区町村の窓口に申請手続きを行うことで、自己負担分を除いた金額が後から払い戻される仕組みを指します。
そのため、一時的に工事費用全額を立て替える必要がある点を理解しておくことが大切です。
ただし、自治体によっては、利用者の負担を軽減するために「受領委任払い」という制度を導入している場合があります。
これは、利用者が自己負担額のみを事業者に支払い、残りの保険給付分は市区町村から直接事業者に支払われる仕組みです。
お住まいの自治体でどちらの方式が採用されているか、事前に確認しておくとよいでしょう。
この住宅改修制度を適切に活用することで、経済的な負担を抑えつつ、安全で快適な住環境を手に入れることができます。
補助金の対象となるための要介護認定
家に手すりをつける補助金、すなわち介護保険の住宅改修費支給制度を利用するためには、前提として「要支援」または「要介護」の認定を受けている必要があります。
この認定は、日常生活においてどの程度の介護や支援が必要かを客観的に判断するための公的な区分です。
介護保険の被保険者は、年齢によって2種類に分けられます。
- 第1号被保険者:65歳以上の方
- 第2号被保険者:40歳から64歳までの医療保険に加入している方
第1号被保険者の場合は、老化が原因で日常生活に支援や介護が必要になった場合に認定の対象となります。
一方で、第2号被保険者の場合は、がん末期や関節リウマチなど、加齢に伴って生じる特定の16種類の疾病(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合にのみ、認定の対象となります。
要介護認定を受けるための手続きは、以下の流れで進みます。
- 市区町村の窓口への申請:まず、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に「要介護認定」の申請を行います。申請は本人または家族のほか、地域包括支援センターやケアマネージャーに代行してもらうことも可能です。
- 認定調査:市区町村の調査員が自宅などを訪問し、心身の状態に関する聞き取り調査(認定調査)を実施します。同時に、市区町村からの依頼で主治医が「主治医意見書」を作成します。
- 審査・判定:認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定が行われ、その後、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で二次判定が行われます。
- 結果の通知:審査会の判定結果に基づき、市区町村が要介護度を決定し、申請から原則30日以内に本人に結果が通知されます。
認定結果は、「自立(非該当)」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかに区分されます。
住宅改修の補助金対象となるのは、「要支援1」以上の認定を受けた方です。
また、この補助金制度を利用するためには、被保険者証に記載されている住所、つまり住民票がある家屋の改修であることが条件となります。
入院中や介護施設に入所中に自宅の改修を行うことは可能ですが、あくまで退院・退所後にその家屋に戻り、在宅生活を続けることが前提です。
まだ要介護認定を受けていない方は、まずはお住まいの地域の地域包括支援センターに相談し、認定申請の手続きから始める必要があります。
自治体独自の制度も確認しよう
介護保険の住宅改修制度は全国共通の制度ですが、それに加えて、各市区町村が独自に高齢者や障害者のための住宅リフォーム支援制度を設けている場合があります。
これらの制度は、家に手すりをつける補助金として活用できる可能性があり、介護保険制度と併用できるケースや、介護保険の対象とならない方でも利用できるケースがあるため、必ず確認しておくことをお勧めします。
自治体独自の制度には、様々な種類があります。
例えば、以下のようなものが考えられます。
介護保険制度の上乗せ・横出しサービス
一部の自治体では、介護保険の支給限度額である20万円を超えた部分に対して、さらに補助を行う「上乗せ」制度を設けていることがあります。
また、介護保険の対象とならないような小規模な改修(例:電灯のスイッチの交換など)に対して補助を行う「横出し」サービスを提供している自治体も存在します。
高齢者向けの住宅改修助成制度
要介護認定を受けていない、または「自立」と判定された高齢者であっても、一定の年齢以上(例:65歳以上)であれば利用できる住宅改修の助成制度です。
所得制限などの条件が設けられていることが多いですが、介護保険の対象外となった場合の有力な選択肢となります。
障害者向けの住宅改修助成制度
身体障害者手帳などをお持ちの方を対象とした制度です。
手すりの設置や段差解消など、バリアフリー化のための改修費用を助成するもので、介護保険制度とは別の枠組みで申請できます。
これらの制度の有無や内容、申請条件は、自治体によって大きく異なります。
情報を得るためには、まずはお住まいの市区町村のウェブサイトを確認するか、高齢福祉課や介護保険課、障害福祉課といった担当窓口に直接問い合わせることが最も確実です。
また、地域包括支援センターでも、こうした地域独自の制度について情報提供や相談に応じてくれる場合があります。
介護保険の申請準備と並行して、こうした自治体独自の制度についてもリサーチを進めることで、より手厚い支援を受けられる可能性があります。
利用できる制度を漏れなく活用し、経済的な負担を最小限に抑えながら、安心して暮らせる住環境を整えましょう。
賃貸物件でも補助金は使える?
「持ち家ではなく賃貸住宅に住んでいるけれど、家に手すりをつける補助金は利用できるのだろうか」という疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
結論から言うと、賃貸物件であっても、条件を満たせば介護保険の住宅改修費支給制度を利用することは可能です。
介護保険制度は、あくまで被保険者が実際に居住している家屋の安全性を高めることを目的としているため、その家屋の所有形態(持ち家か賃貸か)は問いません。
ただし、賃貸物件で住宅改修を行う際には、持ち家の場合とは異なる、非常に重要な注意点があります。
それは、工事を行う前に、必ず物件の所有者(大家さんや管理会社)から「承諾」を得る必要があるという点です。
住宅改修は、壁に穴を開けて手すりを固定するなど、建物そのものに手を加える工事です。
借主の判断で勝手に工事を進めてしまうと、後々、所有者との間でトラブルに発展する可能性があります。
最悪の場合、契約違反として退去時に原状回復費用を請求されることも考えられます。
そのため、市区町村に補助金の申請をする際には、申請書類の一部として「住宅所有者の承諾書」の提出を求められるのが一般的です。
この承諾書は、所有者が今回の住宅改修について同意していることを証明する公的な書類となります。
承諾を得るための手順としては、まずケアマネージャーや施工業者と相談して具体的な工事内容を固めた上で、その計画を大家さんや管理会社に丁寧に説明し、理解を求めることが大切です。
なぜこの工事が必要なのか、利用者の身体状況や日常生活での困りごとを具体的に伝えることで、承諾を得やすくなるでしょう。
万が一、所有者の承諾が得られない場合は、残念ながらその物件での住宅改修は実施できません。
その場合は、工事を伴わない「福祉用具のレンタル(貸与)」で対応できないかを検討することになります。
例えば、壁に固定するタイプの手すりの代わりに、置くだけで設置できる据え置き型の手すりや、突っ張り棒タイプの手すりをレンタルするといった代替案が考えられます。
これら福祉用具のレンタルも介護保険の給付対象となるため、ケアマネージャーに相談してみましょう。
補助金でまかなえる費用の範囲
家に手すりをつける補助金、つまり介護保険の住宅改修制度を利用する際、どのような工事が対象となり、どのくらいの費用が補助されるのかを正確に理解しておくことは非常に重要です。
補助の対象となる工事は、主に以下の6種類が定められています。
- 手すりの取付け:廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒予防や移動の補助を目的として設置する手すりが対象です。
- 段差の解消:居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差や、玄関から道路までの通路の段差を解消するための工事です。スロープの設置や敷居の撤去、床のかさ上げなどが含まれます。
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更:居室では畳敷から板製床材(フローリング)へ、浴室では滑りにくい床材への変更などが対象です。
- 引き戸等への扉の取替え:開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンなどに取り替える工事が対象です。扉の撤去やドアノブの変更も含まれます。
- 洋式便器等への便器の取替え:和式便器を洋式便器に取り替える工事が対象です。すでに洋式であっても、暖房便座や洗浄機能付きのものへの交換も含まれる場合があります。
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修:上記の工事を行うために必要となる壁の下地補強や、給排水設備工事、柱の改修などが含まれます。
支給限度基準額は、要介護度にかかわらず一律で20万円です。
これは工事費の上限であり、この20万円に対して、所得に応じた自己負担割合(1割、2割、または3割)を差し引いた額が支給されます。
例えば、工事費用が20万円で自己負担が1割の方の場合、支給額は18万円(20万円×9割)、自己負担額は2万円となります。
もし工事費用が25万円だった場合は、上限である20万円が計算の基礎となるため、支給額は同様に18万円、自己負担額は残りの7万円(20万円の1割である2万円+上限超過分の5万円)となります。
この支給限度額20万円は、原則として「同一住宅・同一居住者」につき生涯にわたるものです。
ただし、例外として、要介護度が著しく高くなった場合(3段階以上上昇した場合)や、転居した場合には、再度20万円までの支給限度額が設定されます。
これにより、身体状況の変化や住環境の変化に対応できるよう配慮されています。
費用の見積もりを取る際は、どの部分が補助金の対象となり、どの部分が対象外なのかを施工業者に明確に区分してもらうことが重要です。
あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪
家に手すりをつける補助金の具体的な申請ステップ
◆この章のポイント◆
- まずはケアマネージャーへの相談から
- 申請方法と手続きの流れを解説
- 事前に準備すべき書類と注意点
- 工事完了後に必要な報告とは
- 家に手すりをつける補助金を活用しよう
まずはケアマネージャーへの相談から
家に手すりをつける補助金の申請を考え始めたら、最初に行うべきことは、担当のケアマネージャー(介護支援専門員)に相談することです。
要支援認定を受けている場合は、地域包括支援センターの担当者が相談窓口となります。
ケアマネージャーは介護保険サービスの専門家であり、住宅改修の手続き全体をサポートしてくれる最も重要なパートナーです。
なぜ最初にケアマネージャーへの相談が必要なのでしょうか。
その理由は、住宅改修の申請に不可欠な「理由書」を作成できるのが、原則としてケアマネージャーなどの専門職に限られているからです。
「理由書」とは、利用者の心身の状況や日常生活の動線を踏まえ、「なぜ、家のこの場所に手すりが必要なのか」を医学的・専門的な観点から具体的に説明する書類です。
この理由書の説得力が、市区町村の審査を通過し、補助金の支給決定を得るための鍵となります。
相談の際には、まず利用者本人や家族が、日常生活のどのような場面で不便を感じているか、どこに危険を感じるかを具体的に伝えましょう。
例えば、「トイレで立ち上がる時にふらついて怖い」「廊下を歩くときによろけて壁に手をついている」「浴室の出入りで滑りそうで不安だ」といった具体的な状況を伝えることが重要です。
ケアマネージャーは、その情報と専門的なアセスメント(評価)に基づき、利用者の身体能力や生活習慣に本当に合った手すりの位置や種類を検討します。
また、ケアマネージャーは信頼できる施工業者を紹介してくれたり、複数の業者から見積もりを取る際のアドバイスをしてくれたりもします。
介護保険を使った住宅改修の実績が豊富な業者を選ぶことは、スムーズな手続きと適切な工事のために非常に大切です。
自己判断で業者を探して契約し、工事を進めてしまうと、後から介護保険の対象として認められず、全額自己負担になってしまうリスクがあります。
必ず工事を始める前にケアマネージャーに相談し、適切な手順を踏むことが、家に手すりをつける補助金を確実に受給するための第一歩となります。
ケアマネージャーと密に連携を取りながら、二人三脚で計画を進めていきましょう。
申請方法と手続きの流れを解説
家に手すりをつける補助金(住宅改修費)の申請は、正しい手順に沿って進めることが非常に重要です。
特に、「工事の前に必ず事前申請を行い、市区町村の承認を得る」という点が最大のポイントです。
承認前に着工してしまうと、原則として補助金の対象外となってしまうため、注意が必要です。
一般的な手続きの流れは、以下のようになります。
- ステップ1:ケアマネージャーへの相談:前述の通り、まずは担当のケアマネージャーに住宅改修をしたい旨を相談します。
- ステップ2:施工業者の選定と現地調査・見積もり:ケアマネージャーと相談しながら、住宅改修を行う施工業者を選定します。業者が決まったら、自宅に来てもらい、改修が必要な箇所の現地調査を依頼します。その上で、詳細な工事費の見積書を作成してもらいます。
- ステップ3:事前申請:必要な書類一式を揃え、市区町村の介護保険担当窓口に提出します。これを「事前申請」と呼びます。提出する書類については次の項目で詳しく説明します。
- ステップ4:審査・承認:市区町村は提出された書類を審査し、その改修が保険給付として適切かどうかを判断します。問題がなければ、改修工事の承認通知が届きます。
- ステップ5:工事の着工・完了:市区町村からの承認を受けてから、施工業者と契約し、工事を開始します。工事が完了したら、内容を確認します。
- ステップ6:費用の支払い:工事完了後、利用者は施工業者に工事費用の全額を支払います。この時、必ず日付と内訳が明記された領収書を受け取ってください。
- ステップ7:事後申請(支給申請):工事完了後、領収書など指定された書類を再度市区町村の窓口に提出します。これが正式な「支給申請」となります。
- ステップ8:支給決定・振込:市区町村が事後申請の書類を確認し、問題がなければ支給が決定されます。その後、指定した口座に、自己負担額を除いた補助金が振り込まれます。
この一連の流れは、申請から補助金の振り込みまで、通常1ヶ月から3ヶ月程度の時間がかかります。
特に事前申請の承認が下りるまでには数週間かかることがあるため、余裕を持ったスケジュールで計画を進めることが肝心です。
自治体によっては、前述した「受領委任払い」制度を利用できる場合があります。
その場合、ステップ6の支払いが自己負担額のみとなり、ステップ7・8の手続きは業者が代行してくれるなど、流れが簡略化されることがあります。
利用を希望する場合は、対応可能な登録事業者を選ぶ必要があるため、業者選定の段階でケアマネージャーに確認しておきましょう。
事前に準備すべき書類と注意点
家に手すりをつける補助金の「事前申請」には、複数の書類を正確に揃えて提出する必要があります。
不備があると承認が遅れる原因になるため、ケアマネージャーや施工業者と連携しながら、一つひとつ確実に準備しましょう。
一般的に必要となる主な書類は以下の通りですが、自治体によって書式や名称、追加で必要な書類が異なる場合があるため、必ずお住まいの市区町村の規定を確認してください。
事前申請に必要な書類リスト
- 介護保険住宅改修費支給申請書:申請者の氏名や被保険者番号、工事内容などを記入する基本の申請書です。
- 住宅改修が必要な理由書:ケアマネージャーなどが、利用者の心身の状況や家屋の状況を踏まえ、なぜこの改修が必要なのかを専門的見地から作成する書類です。申請の核となる重要な書類です。
- 工事費見積書:施工業者が作成した、材料費や施工費などの内訳が詳細に記載されたものです。
- 改修前の写真:改修予定の場所の状況がわかる写真です。必ず日付を入れて撮影する必要があります。どこをどのように改修するのかが分かるように、少し引いた写真とアップの写真を撮っておくと良いでしょう。
- 改修後の完成予定図:手すりをどこに、どのような形で設置するのかが分かる簡単な図面です。平面図に見積書に記載された手すりの位置や長さを書き込んだもので構いません。
- 住宅所有者の承諾書:賃貸住宅の場合に必要となります。物件の所有者が工事を承諾していることを証明する書類です。
書類を準備する上での注意点として、まず写真は必ず「日付入り」で撮影することが挙げられます。
これは、事前申請のため、工事着工前に撮影された写真であることを証明するために不可欠です。
カメラの日付設定機能をオンにして撮影しましょう。
また、見積書は複数の業者から取得する「相見積もり」を推奨します。
これにより、費用の妥当性を比較検討できるだけでなく、自治体によっては相見積もりの提出が義務付けられている場合もあります。
理由書の内容と、実際に行う工事内容、見積書の内容が一致していることも非常に重要です。
例えば、理由書では「廊下の移動を安全にするため」と書かれているのに、見積書に庭の工事が含まれているなど、整合性が取れない場合は審査で承認されない可能性があります。
書類作成の多くはケアマネージャーや施工業者がサポートしてくれますが、最終的な申請者として、利用者本人や家族も内容をしっかりと確認し、理解しておくことが大切です。
工事完了後に必要な報告とは
市区町村から事前申請の承認を得て、無事に手すりの設置工事が完了した後、補助金を受け取るためには最後にもう一度、手続きが必要になります。
これが「事後申請(本申請・支給申請)」と呼ばれるもので、工事が計画通りに行われ、費用が支払われたことを証明するための報告手続きです。
この事後申請が完了して初めて、補助金が指定の口座に振り込まれます。
工事完了後に提出が必要となる主な書類は以下の通りです。
事後申請に必要な書類リスト
- 住宅改修完了報告書(兼支給申請書):事前申請の内容に基づき、工事が完了したことを報告するための書類です。
- 領収書(原本):利用者が施工業者に工事費用全額を支払ったことを証明する書類です。申請者の氏名、工事内容、支払年月日、領収金額、そして施工業者の社名と押印があるものが必要です。
- 工事費内訳書:領収書の金額の内訳を示す書類です。材料費や工事費など、何にいくらかかったのかが明記されています。見積書と内容が一致しているか確認しましょう。
- 改修後の写真:改修前の写真と同じアングルから撮影した、工事完了後の写真です。こちらも必ず「日付入り」で撮影し、手すりが適切に設置されたことを示します。
- その他(口座振込依頼書など):補助金の振込先となる金融機関の口座情報を記入する書類など、自治体指定の書類が必要になる場合があります。
事後申請で最も重要な書類は、何といっても「領収書」です。
これがなければ、費用を支払った事実を証明できず、補助金を受け取ることができません。
必ず原本を保管し、提出の際はコピーではなく原本を求められることが多いため、事前に確認しておきましょう。
また、事前申請時の見積額と、最終的な工事費用(領収書額)が大きく異なる場合は、その理由を説明する書類の提出を求められることがあります。
やむを得ず工事内容に変更が生じた場合は、速やかにケアマネージャーに相談し、必要であれば市区町村への変更申請の手続きを行う必要があります。
工事が終わって安心してしまうと、この事後申請を忘れてしまうケースも稀にあります。
申請には期限が設けられていることがほとんどですので、工事が完了したら速やかに書類を整え、提出することが大切です。
通常は、ケアマネージャーが提出までサポートしてくれますので、指示に従って書類の準備を進めましょう。
家に手すりをつける補助金を活用しよう
ここまで、家に手すりをつける補助金について、その基本的な仕組みから対象条件、具体的な申請手続きに至るまで詳しく解説してきました。
介護保険の住宅改修制度は、高齢期を迎え、身体機能に変化が生じた際に、住み慣れた我が家で安全・安心に暮らし続けるための非常に心強い味方となる制度です。
廊下の一本の手すり、トイレの縦手すり、浴室のL字手すり。
これらがあるだけで、転倒のリスクは大幅に減少し、日々の立ち座りや移動が驚くほど楽になります。
それはご本人の自立した生活を支えるだけでなく、介護するご家族の身体的・精神的な負担を軽減することにも直結します。
手続きには、ケアマネージャーとの連携、複数の書類準備、事前申請など、いくつかのステップを踏む必要があり、少し複雑に感じられるかもしれません。
しかし、一つひとつの手順を確実に踏んでいけば、決して難しいものではありません。
最も重要なことは、自分だけで抱え込まず、まずは専門家であるケアマネージャーや地域包括支援センターに相談することです。
そして、工事ありきで話を進めるのではなく、「生活のどこに困っているのか」という視点から、本当に必要な改修を見極めていくことが大切です。
費用面での不安から改修をためらっていた方も、自己負担1割から3割で済むこの制度を知ることで、前向きに検討できるようになったのではないでしょうか。
家に手すりをつける補助金を賢く活用し、これからの生活をより安全で快適なものにしていきましょう。
あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪
本日のまとめ
- 家に手すりをつける際は介護保険の住宅改修制度が使える
- 対象者は要支援1以上の認定を受けた方
- 支給限度額は生涯で20万円まで
- 自己負担は所得に応じて1割から3割
- 原則は工事後に費用が払い戻される償還払い
- 申請にはケアマネージャーの作成する理由書が必須
- 工事開始前に必ず市区町村への事前申請と承認が必要
- 賃貸物件でも家主の承諾があれば利用可能
- 申請には見積書や工事前の写真など複数の書類が必要
- 工事完了後には領収書や工事後の写真を添えて事後申請を行う
- 手続き全体で1ヶ月から3ヶ月程度の期間を見ておく
- 自治体独自の補助金制度も確認すると良い
- まずはケアマネージャーや地域包括支援センターに相談から始める
- 自己判断で工事を進めると補助金の対象外になるリスクがある
- 家に手すりをつける補助金は安全な在宅生活を支える重要な制度

| 【PR】 リフォームをしようとする時に大切なのは「比較をすること」です。しかし実際には、自分で行おうとするととても大変ですし、数多く見積もりをしようとしたら心も折れてしまいます。 そこでおすすめなのがタウンライフの「一括見積り」です。日本全国の600社以上のリフォーム会社の中から、あなたに適したリフォーム会社から見積もりを受ける事ができます 見積もり比較することで、最大100万円程度節約になる事も!自宅に居ながらにして、いくつか項目を記入するだけで、簡単に完全無料で資料を取り寄せる事ができます |
あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪
●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇
銚子市のリフォーム補助金を徹底解説!条件や申請方法、注意点まで
小さいお風呂のリフォーム完全ガイド|費用相場から広く見せるコツまで
●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇
参考サイト
介護用手すりの設置は補助金がもらえる?条件と申請方法を解説 – ミツモア
介護保険における住宅改修 – 厚生労働省
介護保険の利用で手すりの取り付け!条件や内容、申請から設置までの流れ、注意点などを解説
介護保険住宅改修制度の利用方法(手すり・段差解消スロープ) 手すり通販と工事|高齢者・介護
住宅改修費の支給 – 介護保険制度とは – 大阪市
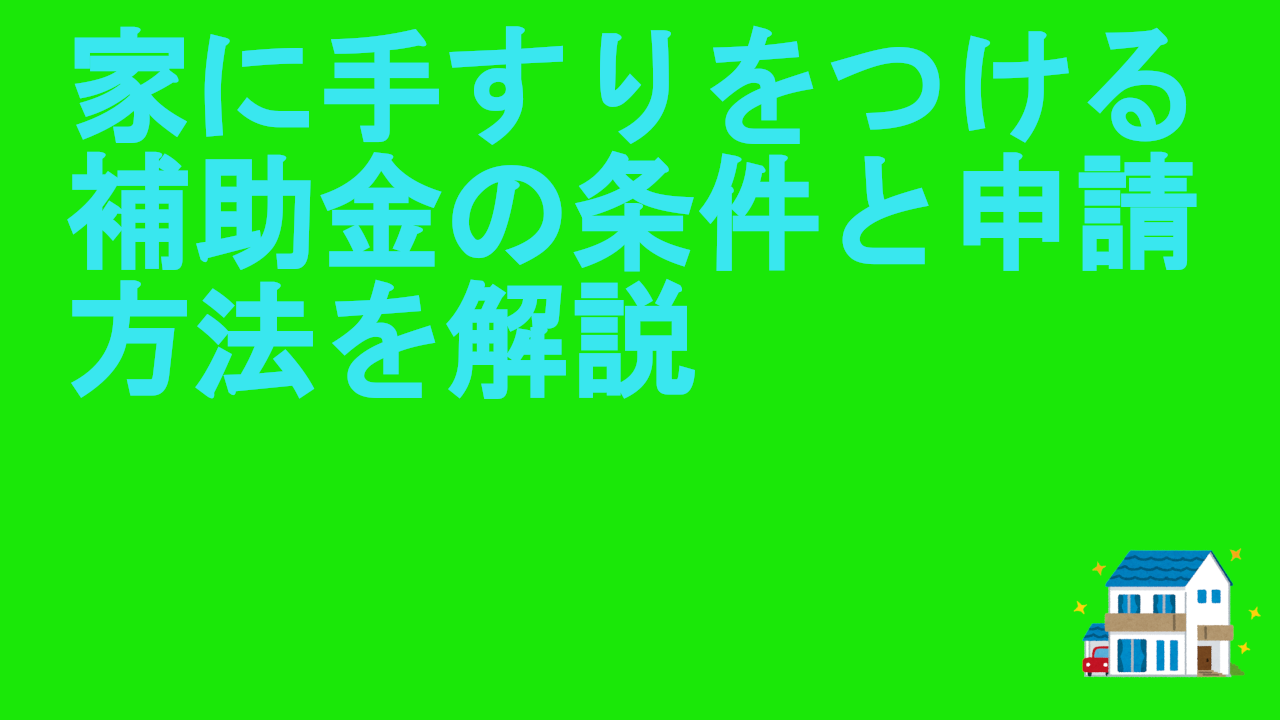


コメント