こんにちは、サイト管理人です
マイホームの購入は、人生で最も大きな買い物の一つです。
特に新築の注文住宅となれば、夢が膨らむ一方で、資金計画に頭を悩ませる方も少なくないでしょう。
しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません。
実は、新築を建てる時の補助金制度を国や自治体が数多く用意しており、これらを賢く活用することで、経済的な負担を大幅に軽減できる可能性があるのです。
2024年現在、特に注目されているのが、省エネ性能の高い住宅に対する支援です。
具体的には、子育てエコホーム支援事業やZEH支援事業、給湯省エネ2024事業といった国の制度があります。
これらの補助金は、種類によって対象となる住宅の条件や金額、申請期間が異なります。
また、住宅ローン減税との併用が可能か、補助金を受け取った場合に確定申告は必要なのか、といった疑問も出てくるでしょう。
この記事では、新築を建てる時の補助金について、2024年の最新情報を基に、その種類から申請の流れ、併用や税金に関する注意点まで、網羅的に解説します。
これから家づくりを始める方が、損をすることなく、最大限に制度を活用するための一助となれば幸いです。
◆このサイトでわかる事◆
- 2024年に利用できる国の主要な新築補助金の種類
- 子育てエコホーム支援事業やZEH支援事業の具体的な内容
- 各補助金の対象条件と受け取れる金額
- 補助金を申請するための基本的な流れと手続き
- 住宅ローン減税と補助金を併用する場合のルール
- 補助金を受け取った後の確定申告の必要性
- 補助金を利用する上での注意点と賢い活用法
-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |
【2024年版】新築を建てる時の補助金はこの4つ

◆この章のポイント◆
- 子育て世帯が対象の子育てエコホーム支援事業
- 省エネ住宅のZEH支援事業とは
- 高効率な給湯器を導入する給湯省エne2024事業
- LCCM住宅整備推進事業の概要
- 補助金を受け取るための条件と金額
子育て世帯が対象の子育てエコホーム支援事業
2024年における新築住宅市場で最も注目されている補助金の一つが、子育てエコホーム支援事業です。
これは、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯を支援し、同時に2050年のカーボンニュートラル実現に向けた省エネ住宅の普及を促進する目的で設けられました。
この事業の前身である「こどもエコすまい支援事業」の理念を引き継ぎつつ、より時代に即した形で制度が設計されています。
補助の対象となるのは、主に「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」です。
具体的には、申請時点で2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯、または申請時点で夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯が該当します。
この制度の大きな特徴は、住宅の省エネ性能に応じて補助額が変動する点です。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた「長期優良住宅」を新築する場合、1戸あたり100万円が補助されます。
一方で、太陽光発電などによるエネルギー創出と省エネ設備によるエネルギー消費削減で、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロ以下にすることを目指す「ZEH住宅(ゼッチじゅうたく)」の場合は、1戸あたり80万円が補助される仕組みです。
申請手続きは、住宅を建築・販売する事業者が代行するのが一般的です。
そのため、施主自身が複雑な書類を作成する手間はほとんどありません。
ただし、事業者が「子育てエコホーム支援事業者」として登録されている必要があるため、契約前に必ず確認することが重要です。
予算には上限が設けられており、申請額が予算上限に達した時点で受付が終了となるため、早めの情報収集と計画が成功のカギを握ります。
| 住宅の性能 | 補助額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 長期優良住宅 | 100万円/戸 | 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁の認定を受けていること。 |
| ZEH住宅 | 80万円/戸 | ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Orientedのいずれかの基準を満たしていること。 |
省エネ住宅のZEH支援事業とは
ZEH支援事業は、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の普及を目指して国が推進している補助金制度です。
そもそもZEHとは、高い断熱性能をベースに、高効率な設備やシステムを導入することで、快適な室内環境を保ちながら大幅な省エネルギーを実現し、さらに太陽光発電などでエネルギーを創り出すことにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅のことを指します。
このZEH支援事業は、環境省、経済産業省、国土交通省が連携して実施しており、それぞれの省庁で管轄するZEHの種類や補助金の詳細が若干異なります。
一般的に利用されることが多い経済産業省の事業では、性能に応じて「ZEH」「ZEH+」「次世代ZEH+」などの区分があり、それぞれ補助額が設定されています。
例えば、最も基本的な「ZEH」では一戸あたり55万円、さらに高性能な「ZEH+」では100万円の補助が受けられます。
この補助金を受けるためには、SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)に登録された「ZEHビルダー/プランナー」が設計、建築、または販売する住宅であることが必須条件です。
したがって、ZEH支援事業の活用を検討する場合は、まず依頼する工務店やハウスメーカーが登録事業者であるかを確認する必要があります。
申請は公募制で、期間内にZEHビルダーを通じて行います。
注意点として、子育てエコホーム支援事業とは併用できないケースが多いことが挙げられます。
どちらの補助金が自身の計画にとってより有利であるか、住宅の性能や世帯の状況を考慮して慎重に選択することが求められます。
ZEH住宅は初期コストがかさむ傾向にありますが、この補助金制度と、入居後の光熱費削減という長期的なメリットを考慮すると、非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
| ZEHの種類 | 補助額(例) | 概要 |
|---|---|---|
| ZEH | 55万円/戸 | 基本的なZEH基準を満たす住宅 |
| ZEH+ | 100万円/戸 | ZEHの基準をさらに強化し、追加の省エネ設備を導入した住宅 |
| 次世代ZEH+ | 100万円/戸 | ZEH+の要件に加え、V2H設備や蓄電システム等を導入した住宅 |
高効率な給湯器を導入する給湯省エネ2024事業
給湯省エネ2024事業は、家庭におけるエネルギー消費の大きな割合を占める給湯分野に特化した補助金制度です。
特にエネルギー効率の高い特定の給湯器を導入する際に、その購入・設置費用の一部が補助されます。
この事業の目的は、省エネ性能に優れた給湯器の普及を促進し、家庭部門のCO2排出量削減に貢献することにあります。
補助の対象となるのは、主に以下の3種類の高効率給湯器です。
- ヒートポンプ給湯機(エコキュート):空気の熱を利用してお湯を沸かす、非常にエネルギー効率の高い給湯器です。
- ハイブリッド給湯機:ガスと電気の長所を組み合わせた給湯器で、効率的にお湯を供給します。
- 家庭用燃料電池(エネファーム):都市ガスやLPガスから水素を取り出し、空気中の酸素と化学反応させることで電気と熱(お湯)を同時に作り出します。
補助額は導入する機器の性能や種類によって異なり、基本額に加えて、特定の性能要件を満たすことで加算される場合があります。
例えば、エコキュートであれば基本額が8万円、特定の基準を満たせば最大13万円まで補助額が上がります。
この給湯省エネ2024事業の大きなメリットは、子育てエコホーム支援事業などの他の補助金と併用が可能であるという点です。
新築住宅を建てる際に、子育てエコホーム支援事業で建物全体の補助を受けつつ、給湯器の導入に対してはこの給湯省エネ事業の補助を別途申請することができます。
これにより、トータルでの補助金額を最大化することが可能になります。
申請手続きは、他の補助金と同様に、登録された事業者が行うのが一般的です。
新築を計画する際には、どのような給湯器を導入するか、そしてそれが補助金の対象となるか、早い段階でハウスメーカーや工務店に相談しておくことが重要です。
LCCM住宅整備推進事業の概要
LCCM住宅整備推進事業は、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)をさらに一歩進めた、次世代の環境配慮型住宅「LCCM住宅」の普及を目的とした補助金制度です。
LCCMとは「ライフ・サイクル・カーボン・マイナス」の略です。
これは、住宅の建設時から居住中、そして最終的に解体されるまで、その一生(ライフサイクル)を通じてのCO2排出量を全体としてマイナスにすることを目指す住宅を指します。
具体的には、ZEHの基準を満たした上で、建設時や解体時によりCO2排出量の少ない建材や工法を採用し、さらに太陽光発電によるエネルギー創出量を増やすことで、住宅のライフサイクル全体でのCO2収支をマイナスに転じさせます。
まさに、究極の省エネ・創エネ住宅と言えるでしょう。
このLCCM住宅整備推進事業では、設計費や建設工事等における補助対象費用の2分の1以内で、1戸あたり最大140万円の補助が受けられます。
補助額が大きい一方で、その認定基準は非常に厳しく、高度な設計技術やノウハウが求められるため、対応できる工務店やハウスメーカーは限られます。
また、建設コストも一般的な住宅やZEH住宅と比較して高くなる傾向があります。
申請は、事業の要件を満たす住宅の建築主が、採択されたプロジェクトの事業者を通じて行います。
公募期間が定められており、その期間内に申請を完了させる必要があります。
この補助金は、環境性能に対して非常に高い意識を持ち、初期投資をかけてでも将来にわたって環境に貢献したいと考える方に適した制度です。
ZEH支援事業と同様に、子育てエコホーム支援事業との併用は認められていないため、どちらを選択するかは慎重な検討が必要です。
補助金を受け取るための条件と金額
新築を建てる時の補助金は、それぞれに独自の目的と要件がありますが、共通する基本的な条件もいくつか存在します。
これらの条件を理解し、計画段階から準備を進めることが、補助金を確実に受け取るための第一歩となります。
まず、ほとんどの国策補助金は、一定以上の「省エネ性能」を持つ住宅を対象としています。
これは、国が2050年のカーボンニュートラル達成という大きな目標を掲げているためです。
具体的には、「長期優良住宅」や「ZEH住宅」といった特定の認定を取得していることが条件となる場合が多く、断熱性能や一次エネルギー消費量に関する厳しい基準をクリアする必要があります。
次に、世帯に関する要件です。
「子育てエコホーム支援事業」のように、子育て世帯や若者夫婦世帯に対象を限定している補助金もあります。
年齢や家族構成が条件に含まれる場合は、申請時点での状況が問われるため注意が必要です。
また、建物の床面積にも規定があることが一般的です。
極端に小さい、あるいは大きすぎる住宅は対象外となることがあります。
補助金額は、制度や住宅の性能、導入する設備によって大きく異なります。
以下に、これまで紹介した主要な国の補助金制度の概要を比較表としてまとめました。
| 補助金制度名 | 主な対象者 | 最大補助額 | 主な住宅要件 | 併用の可否(代表例) |
|---|---|---|---|---|
| 子育てエコホーム支援事業 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 | 100万円 | 長期優良住宅またはZEH住宅 | 給湯省エネ事業と併用可 |
| ZEH支援事業 | 全世帯 | 100万円(ZEH+の場合) | ZEH、ZEH+など | 子育てエコホーム事業と併用不可 |
| 給湯省エネ2024事業 | 全世帯 | 機器により異なる(最大20万円) | 対象の高効率給湯器を導入 | 他の多くの補助金と併用可 |
| LCCM住宅整備推進事業 | 全世帯 | 140万円 | LCCM住宅の認定 | 子育てエコホーム事業と併用不可 |
これらの国の制度に加えて、各地方自治体が独自に設けている補助金制度も多数存在します。
例えば、地元産の木材を使用することを条件とする補助金や、三世代同居を支援する補助金など、地域の実情に合わせた多様な制度があります。
国の補助金と自治体の補助金は併用できる場合も多いので、建築予定地の市区町村のウェブサイトなどで情報を確認することをおすすめします。
新築を建てる時の補助金の申請と注意点
◆この章のポイント◆
- 補助金申請の基本的な流れ
- 住宅ローン減税と補助金の併用は可能か
- 補助金利用時の注意点を解説
- 補助金をもらったら確定申告は必要?
- 知って得する新築を建てる時の補助金の賢い活用法
補助金申請の基本的な流れ
新築を建てる時の補助金を活用する上で、申請の基本的な流れを理解しておくことは非常に重要です。
多くの補助金制度では、施主(建築主)自身が直接手続きを行うのではなく、住宅の建築や販売を行うハウスメーカーや工務店が「事業者」として申請を代行する形が取られています。
これにより、施主の負担は軽減されますが、流れを把握しておくことで、計画がスムーズに進みます。
一般的な申請から受け取りまでの流れは以下の通りです。
- 1. 補助金事業者の選定:まず、利用したい補助金制度の登録事業者となっているハウスメーカーや工務店を選定し、建築請負契約を結びます。この際、補助金を利用したい旨を明確に伝え、協力体制を築くことが大切です。
- 2. 補助金の予約申請(該当する場合):「子育てエコホーム支援事業」など、着工前に補助金の予算枠を確保するための「予約申請」が必要な場合があります。事業者が施主に代わって申請を行います。
- 3. 建築着工:補助金の要件を満たす住宅の仕様で工事を開始します。
- 4. 補助金の交付申請:建物の工事がある程度進んだ段階、または完了後に、事業者が正式な「交付申請」を行います。必要な書類を揃え、事務局に提出します。
- 5. 工事完了・完了報告:建物が完成し、引き渡しが行われた後、事業者が事務局へ「完了報告(実績報告)」を提出します。この報告が承認されることで、補助金額が確定します。
- 6. 補助金の交付:完了報告が承認されると、補助金が交付されます。この交付先は、まず申請を行った事業者となります。その後、予め交わした契約に基づき、事業者が建築費用の一部に充当するか、施主に現金で還元するかのいずれかの方法で施主に渡ります。
最も重要なポイントは、補助金が実際に支払われるのは、建物が完成し、すべての手続きが終わった後であるという点です。
建築途中の支払いに直接充てることはできないため、資金計画は補助金がないものとして立てておく必要があります。
住宅ローン減税と補助金の併用は可能か
家づくりにおける大きな支援制度として、補助金と双璧をなすのが「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」です。
年末のローン残高の一定割合が所得税(および一部住民税)から控除されるこの制度と、補助金を一緒に利用できるのかは、多くの方が気にするポイントでしょう。
結論から言うと、新築を建てる時の補助金と住宅ローン減税は、原則として併用可能です。
ただし、そこには一つ重要なルールが存在します。
それは、住宅ローン減税を計算する際の「住宅の取得対価」から、受け取った補助金の額を差し引かなければならない、という点です。
少し分かりにくいので、具体例で見てみましょう。
計算例
・住宅の建築費用(取得対価):4,000万円
・住宅ローン借入額:4,000万円
・受け取った補助金額:100万円(子育てエコホーム支援事業)
この場合、住宅ローン減税の計算の基礎となる住宅の取得対価は、以下のようになります。
4,000万円(実際の建築費用) – 100万円(補助金) = 3,900万円
したがって、このケースでは年末のローン残高がいくらあっても、減税対象となるローン残高の上限は3,900万円となります。
つまり、補助金を受け取った分だけ、住宅ローン減税の対象となる金額が減る、ということです。
これは、国の支援が二重にならないようにするための措置です。
とはいえ、補助金は返済不要の現金(またはそれに準ずるもの)であり、住宅ローン減税はあくまで税金の控除です。
多くの場合、両方の制度を最大限活用することが、トータルで見て最も経済的メリットが大きくなります。
この計算は、確定申告の際に自身で行う必要がありますので、補助金を受け取ったことを証明する書類などを大切に保管しておきましょう。
補助金利用時の注意点を解説
新築を建てる時の補助金は、家計にとって大きな助けとなりますが、その利用にあたってはいくつかの注意点があります。
これらを知らずに計画を進めると、期待していた補助金が受けられなくなったり、思わぬトラブルにつながったりする可能性もあります。
ここでは、特に重要な注意点をいくつか解説します。
- 申請期間と予算の上限:国の補助金制度は、多くの場合、年度ごとに予算が組まれています。申請受付期間が定められているだけでなく、申請額が予算の上限に達した時点で、期間内であっても受付が終了してしまいます。人気の補助金は、締切日よりもずっと早く受付終了となることも珍しくありません。常に最新の情報を公式サイトで確認し、早めに準備を進めることが肝心です。
- 補助金は後払い:前述の通り、補助金が振り込まれるのは、住宅が完成し、すべての報告手続きが完了した後です。建築費用の支払いは、契約に基づいて進めていく必要がありますので、補助金をあてにした資金計画を立てるのは危険です。自己資金やローンの計画は、補助金がない前提でしっかりと組んでおく必要があります。
- 登録事業者を選ぶ必要性:多くの補助金制度では、申請手続きを行えるのが、事務局に登録された「登録事業者」に限られています。デザインや価格だけで工務店を選んで契約した後に、その事業者が登録事業者でなかったため補助金が使えなかった、というケースも起こり得ます。必ず契約前に、利用したい補助金の登録事業者であるかを確認しましょう。
- 併用できない補助金の存在:補助金の中には、併用が認められていない組み合わせがあります。特に、国の補助金同士で、補助対象となる工事内容が重複するものは併用できないことがほとんどです。例えば、「子育てエコホーム支援事業」と「ZEH支援事業」は、どちらも住宅本体の省エネ性能を対象とするため、両方を受け取ることはできません。どちらの制度を利用するのが得策か、住宅の性能や世帯状況に合わせて慎重に検討する必要があります。
- 仕様変更の制限:補助金の交付が決定すると、原則として申請時の仕様から大きな変更はできません。もし、工事の途中で間取りや導入する設備などを変更すると、補助金の対象外となってしまう可能性があります。やむを得ず変更が必要な場合は、必ず事前に事業者と事務局に相談することが不可欠です。
補助金をもらったら確定申告は必要?
新築を建てる時の補助金を受け取った後、多くの方が気になるのが「税金」の問題、特に「確定申告」の必要性についてです。
国や自治体から受け取る補助金は、税法上「一時所得」として扱われます。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価でも、資産の譲渡による対価でもない一時的な性質の所得を指します。
しかし、「一時所得=すぐに税金がかかる」というわけではありません。
一時所得には、最高50万円の特別控除額が設けられています。
課税対象となる一時所得の金額は、以下の計算式で算出されます。
(一時所得の総収入金額 – その収入を得るために支出した金額 – 特別控除額50万円) × 1/2
ここで重要なのは、住宅建築の補助金の場合、「その収入を得るために支出した金額」が明確に算出できないため、通常は支出額を0円として計算します。
したがって、計算は以下のようになります。
(受け取った補助金額 – 特別控除額50万円)
この計算結果がプラスになる場合、つまり、その年に受け取った一時所得の合計(住宅補助金以外にも、生命保険の一時金や懸賞金なども含む)が50万円を超えた場合に、超えた額の2分の1が課税対象となります。
具体例
・子育てエコホーム支援事業で100万円の補助金を受け取った。
・他に一時所得はない。
この場合、100万円 – 50万円 = 50万円がプラスになります。
この50万円のさらに2分の1、つまり25万円が課税対象所得として、給与所得などの他の所得と合算されて最終的な所得税額が計算されます。
したがって、このケースでは確定申告が必要です。
一方で、受け取った補助金額が50万円以下で、他に一時所得がなければ、特別控除の範囲内に収まるため課税所得は発生せず、この補助金に関する確定申告は不要となります。
ただし、住宅ローン減税の初年度の適用を受けるためには、いずれにせよ確定申告が必要となります。
その際に、一時所得の申告も併せて行うことになります。
知って得する新築を建てる時の補助金の賢い活用法
ここまで、新築を建てる時の補助金について、その種類や申請方法、注意点を解説してきました。
最後に、これらの情報を踏まえ、補助金制度をより賢く、効果的に活用するためのポイントをまとめます。
家づくりは情報戦とも言われます。
特に、毎年のように内容が更新される補助金制度においては、最新の情報をいち早くキャッチし、自身の計画に落とし込むことが成功の鍵となります。
国の制度だけでなく、建築を予定している自治体独自の補助金も必ずチェックしましょう。
意外な支援制度が見つかるかもしれません。
また、補助金ありきで計画を進めるのではなく、まずは自分たちがどのような家に住みたいのか、どのような暮らしを実現したいのかという本質的な要望を固めることが大切です。
その上で、その理想の家づくりに合致する補助金を探し、活用していくという順序が望ましいでしょう。
例えば、高い省エネ性能を持つ快適な家に住みたいという希望があれば、ZEH支援事業や子育てエコホーム支援事業が有力な選択肢となります。
補助金は、あくまで家づくりの負担を軽減するための一つのツールです。
制度に振り回されることなく、主体的に情報を集め、信頼できるパートナー(工務店やハウスメーカー)と共に計画を進めることで、後悔のない、満足度の高い家づくりが実現できるはずです。
新築を建てる時の補助金は、知っているか知らないかで、最終的な支出に大きな差が生まれる可能性があります。
ぜひこの記事を参考にして、あなたの夢のマイホーム実現に役立ててください。
本日のまとめ
- 2024年の新築補助金は省エネ性能が重要なカギ
- 子育てエコホーム支援事業は子育て若者世帯が対象
- 長期優良住宅なら最大100万円の補助が受けられる
- ZEH支援事業は省エネ住宅の普及を目的とする国の制度
- 給湯省エネ事業は高効率給湯器の導入を支援
- LCCM住宅は究極の環境配慮型住宅で補助額も大きい
- 補助金の申請は登録事業者が代行するのが一般的
- 補助金は工事完了後に後払いで支払われる
- 人気の補助金は予算上限で早期に終了する場合がある
- 国の補助金同士では併用できない組み合わせに注意
- 住宅ローン減税と補助金は原則として併用できる
- ローン減税の計算では取得価額から補助金額を差し引く
- 補助金は税法上「一時所得」として扱われる
- 一時所得が50万円を超えなければ確定申告は不要
- 新築を建てる時の補助金は国と自治体の両方を調べることが重要
参考サイト
2024年最新|注文住宅を建てるときに利用できる補助金・助成金、減税制度をご紹介! – 一建設
【2024年】新築時に活用できる補助金と減税制度をわかりやすく解説
【2024−2025年最新】家を建てるなら活用するべき補助金・減税制度一覧|申請の注意点も解説
【2024年】新築住宅の購入にかかわる補助金一覧|いつ・いくらもらえる?優遇・減税制度について
【2024年】新築住宅の補助金一覧|国・自治体の助成金や減税制度を紹介 | 家と暮らしのコラム
-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |
●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇
2000万の家で土地込みの新築は可能?費用内訳から後悔しない注意点まで解説
新築を建てる費用はいくら?相場・内訳・節約術を完全解説
●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇
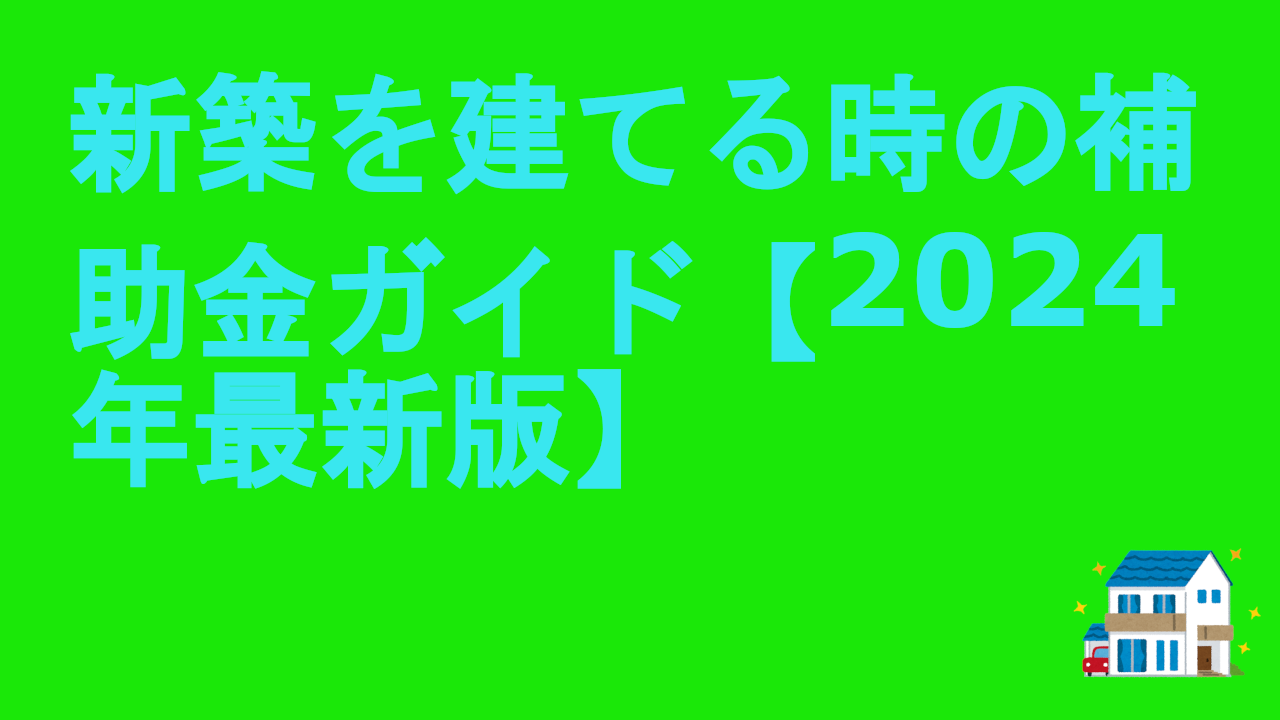


コメント