こんにちは、サイト管理人です
「そろそろマイホームが欲しいな」と考え始めたとき、誰もが最初に直面するのが「一体、新築を建てる費用はいくらかかるのだろう?」という大きな疑問ではないでしょうか。
夢のマイホーム実現に向けた第一歩は、この費用に関する不安を解消することから始まります。
新築を建てる費用と一言で言っても、その総額は様々な要因で大きく変動します。
例えば、土地を持っているかどうか、建物の坪数はどのくらいか、そしてどのようなハウスメーカーに依頼するかによって、見積もりは全く異なるものになるでしょう。
多くの方が、まず費用の内訳や、一般的な相場について知りたいと考えているはずです。
また、自己資金はどの程度準備すれば良いのか、住宅ローンの賢い組み方、見落としがちな税金の問題など、考えるべきことは山積みです。
家づくりは、人生で最も大きな買い物の一つだからこそ、後悔だけはしたくありません。
幸いなことに、現在はオンラインで手軽に費用を計算できるシミュレーションツールがあったり、国や自治体が提供する補助金制度を活用したりすることで、負担を軽減する方法も存在します。
この記事では、新築の家を建てる際に必要となる費用について、あらゆる角度から徹底的に解説していきます。
あなたの家づくりが成功に終わるよう、資金計画の段階からしっかりとサポートします。
◆このサイトでわかる事◆
- 新築を建てる費用の全体像と総額の目安
- 土地の有無が総費用に与える大きな影響
- 建物本体以外にかかる費用の詳細な内訳
- 住宅ローンを組む際の重要なポイント
- 必要な自己資金や頭金の考え方
- 費用を賢く抑えるための具体的な節約術
- 活用できる補助金や税金の基礎知識
-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |
新築を建てる費用の内訳と全国的な相場

◆この章のポイント◆
- 家づくりの総額は土地の有無で変わる
- 費用の内訳は3つのカテゴリーで構成
- 坪数で見る注文住宅の価格目安
- 住宅ローンを組む際のポイントと注意点
- 自己資金はどのくらい準備すべきか
- かかる税金の種類とタイミングを知る
家づくりの総額は土地の有無で変わる
新築の家を建てる計画を立てる上で、最も大きく総額を左右する要因が「土地の有無」です。
すでに親から譲り受けた土地がある場合や、自己所有の土地に建て替えるケースと、これから土地を探して購入する場合とでは、必要な資金が数千万円単位で変わることも珍しくありません。
そのため、資金計画は「土地ありき」か「土地探しから」かを明確にすることからスタートします。
国土交通省の調査によれば、土地を購入して注文住宅を建てる場合の費用総額は、全国平均で約5,400万円台というデータがあります。
このうち、土地取得費用が約2,000万円、建築費用が約3,400万円というのが大まかな内訳です。
一方で、すでに土地を持っている「土地あり」の場合、建築費用の全国平均は約3,900万円となっており、土地購入組と比べて総額が大きく抑えられることが分かります。
もちろん、これらの金額はあくまで全国平均値です。
土地の価格は、都心部と地方では大きく異なります。
例えば、首都圏で土地を購入して家を建てるとなると、総額は6,000万円から7,000万円、あるいはそれ以上になることも十分に考えられます。
逆に、地方であれば土地の価格が比較的安いため、総額を抑えやすい傾向にあります。
このように、自分が家を建てたいエリアの土地相場を把握することが、現実的な予算を組むための第一歩と言えるでしょう。
土地探しから始める場合は、不動産情報サイトや地元の不動産会社を活用して、希望エリアの坪単価や売地の情報をリサーチすることをおすすめします。
その際、土地の価格だけでなく、その土地に課される建ぺい率や容積率などの法規制、上下水道やガスの引き込み状況なども確認が必要です。
これらの条件によっては、追加の工事費用が発生する可能性があるからです。
家づくり全体の予算を考える際には、土地代と建物代を合算した総額で捉え、両者のバランスをうまく取ることが重要になります。
土地に予算をかけすぎると建物のグレードを下げざるを得なくなり、逆に建物にこだわりすぎると希望のエリアに住めなくなるかもしれません。
最初に総予算の上限を決め、そこから土地と建物にいくらずつ配分するかを検討するアプローチが賢明です。
費用の内訳は3つのカテゴリーで構成
新築を建てる費用は、大きく分けて「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」という3つのカテゴリーで構成されています。
多くの人が「建築費」と聞いてイメージするのは、このうちの「本体工事費」だけであることが多いのですが、実際にはそれ以外にも様々な費用がかかります。
これらの内訳を正しく理解しておくことが、後々の資金計画で「こんなはずではなかった」と慌てないための鍵となります。
まず、最も大きな割合を占めるのが「本体工事費」です。
これは、建物そのものを建てるためにかかる費用を指し、総費用の約70%~80%を占めるのが一般的です。
具体的には、基礎工事、構造躯体の工事、屋根や外壁の工事、内装仕上げ、キッチンやお風呂、トイレといった住宅設備の設置費用などが含まれます。
ハウスメーカーや工務店の広告で目にする「坪単価」は、多くの場合、この本体工事費を延床面積(坪数)で割ったものを指しています。
次に、総費用の約15%~20%を占めるのが「付帯工事費」です。
これは、建物の本体以外で、敷地内で必要となる工事にかかる費用全般を指します。
例えば、古い家の解体費用、土地の地盤が弱い場合に行う地盤改良工事、敷地の造成費用、駐車場や庭を造る外構工事、上下水道やガス管を道路から敷地内に引き込む工事などがこれに当たります。
これらの費用は土地の条件によって大きく変動するため、見積もりを取る際には必ず内訳を確認する必要があります。
最後に、総費用の約5%~10%に当たるのが「諸費用」です。
これは、工事そのものではなく、家を建てて取得するまでに関連して発生する様々な手続きの費用や税金を指します。
具体的には、住宅ローンの契約時に金融機関に支払う手数料や保証料、火災保険や地震保険の保険料、建物の所有権を記録する登記費用、不動産取得税や固定資産税といった税金、建築確認申請の手数料などが含まれます。
これらの諸費用は、現金で支払う必要がある項目が多いため、自己資金の中で別途準備しておくことが不可欠です。
以下に、3つの費用の内訳をまとめた表を示します。
| カテゴリー | 割合の目安 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 本体工事費 | 総費用の70~80% | 基礎工事、構造工事、内外装工事、住宅設備費など |
| 付帯工事費 | 総費用の15~20% | 解体工事、地盤改良、外構工事、給排水・ガス工事など |
| 諸費用 | 総費用の5~10% | ローン手数料、保険料、登記費用、税金、申請費用など |
このように、新築の費用は単純な建物の価格だけではないことを理解し、付帯工事費や諸費用まで含めた総額で資金計画を立てることが、失敗しない家づくりの基本です。
坪数で見る注文住宅の価格目安
注文住宅の価格を考える際に、多くの人が参考にする指標の一つが「坪単価」です。
坪単価とは、建物の本体価格を延床面積(坪数)で割ったもので、1坪(約3.3平方メートル)あたりの建築費を示します。
この坪単価を知ることで、希望する家の広さ(坪数)から、おおよその建築費を計算することができます。
例えば、坪単価が70万円のハウスメーカーで、40坪の家を建てる場合、「70万円 × 40坪 = 2,800万円」が本体工事費の目安となります。
ただし、この坪単価には注意が必要です。
前述の通り、坪単価の計算にどこまでの費用を含めるかは、ハウスメーカーや工務店によって定義が異なります。
一般的には本体工事費のみを指すことが多いですが、中には付帯工事費の一部を含んでいるケースもあります。
広告などで坪単価を見るときは、その単価に何が含まれているのかを必ず確認するようにしましょう。
また、坪単価は建物のグレードや仕様によって大きく変動します。
ローコスト住宅を売りにしているハウスメーカーでは坪単価40万円台から可能な場合もありますが、大手ハウスメーカーやデザイン性の高い設計事務所に依頼する場合は、坪単価が80万円、100万円以上になることも珍しくありません。
さらに、家の形状や構造によっても坪単価は変わってきます。
一般的に、正方形に近いシンプルな総二階建ての家はコストを抑えやすく、凹凸の多い複雑なデザインや平屋建ては、屋根や基礎の面積が大きくなるため坪単価が上がる傾向にあります。
以下に、一般的な住宅の坪数と、坪単価別の本体工事費の目安をまとめました。
| 延床面積(坪数) | 坪単価60万円の場合 | 坪単価80万円の場合 | 坪単価100万円の場合 |
|---|---|---|---|
| 30坪(約99㎡) | 1,800万円 | 2,400万円 | 3,000万円 |
| 35坪(約115㎡) | 2,100万円 | 2,800万円 | 3,500万円 |
| 40坪(約132㎡) | 2,400万円 | 3,200万円 | 4,000万円 |
| 45坪(約148㎡) | 2,700万円 | 3,600万円 | 4,500万円 |
この表はあくまで本体工事費の目安であり、実際にはこれに付帯工事費と諸費用が加わります。
総額としては、この表の金額にプラス1,000万円程度を見ておくと、より現実に近い予算感を掴めるでしょう。
坪数を決める際には、現在の家族構成だけでなく、将来のライフプランの変化も見据えることが大切です。
子供の成長や独立、親との同居の可能性などを考慮して、最適な広さを検討しましょう。
無駄に広すぎる家は建築費がかさむだけでなく、将来の光熱費やメンテナンス費用、固定資産税の負担も大きくなることを忘れてはいけません。
住宅ローンを組む際のポイントと注意点
新築を建てる人のほとんどが利用するのが住宅ローンです。
数千万円という大きな金額を、数十年にわたって返済していくことになるため、ローン選びと資金計画は家づくりにおいて最も重要なプロセスの一つと言えます。
ここで正しい知識を持って慎重に判断することが、将来の家計を安定させることにつながります。
住宅ローンを選ぶ際に、まず決めなければならないのが金利タイプです。
金利タイプは大きく分けて「変動金利型」「固定金利期間選択型」「全期間固定金利型」の3種類があります。
- 変動金利型: 半年ごとに金利が見直されるタイプ。一般的に固定金利よりも当初の金利が低いのが魅力ですが、将来金利が上昇するリスクがあります。
- 全期間固定金利型: 借入時の金利が返済終了まで変わらないタイプ。代表的なものに「フラット35」があります。金利は変動型より高めですが、返済額が一定で計画を立てやすいのがメリットです。
- 固定金利期間選択型: 当初3年、5年、10年など一定期間だけ金利が固定され、期間終了後に変動金利にするか再度固定金利にするかを選べるタイプです。
どの金利タイプを選ぶべきかは、その人の経済状況やリスク許容度によって異なります。
金利上昇リスクを許容できる、あるいは繰り上げ返済を積極的に行う予定がある人は変動金利、子育て世代などで将来の支出増が見込まれ、安定を重視したい人は全期間固定金利が向いていると言えるでしょう。
次に重要なのが、借入額の決定です。
金融機関は年収などから「借りられる額(借入可能額)」を提示してくれますが、大切なのは「無理なく返せる額」でローンを組むことです。
一般的に、年間の返済額が年収に占める割合(返済負担率)は20%~25%以内に収めるのが安全圏とされています。
例えば、年収600万円の人なら、年間の返済額は120万円~150万円、月々にすると10万円~12.5万円が目安となります。
この返済額を基準に、金利や返済期間から逆算して借入額を決定するべきです。
また、住宅ローンを組む際には「団体信用生命保険(団信)」への加入が必須となるのが一般的です。
これは、ローン契約者に万が一のことがあった場合に、保険金でローンの残債が完済される仕組みで、残された家族の生活を守るために非常に重要な保険です。
最近では、がんや三大疾病など、特定の病気と診断された場合にローンがゼロになる特約付きの団信も増えているので、保障内容もしっかり比較検討しましょう。
住宅ローンの審査は、土地の契約後や建物のプランがある程度固まった段階で「事前審査(仮審査)」を受け、建物の建築請負契約を結んだ後で「本審査」に進むのが一般的な流れです。
審査では、年収や勤務先、勤続年数、他の借入状況などが総合的に判断されます。
希望額のローンを組めるよう、クレジットカードの支払遅延など、個人の信用情報に傷をつけないように日頃から注意しておくことも大切です。
自己資金はどのくらい準備すべきか
新築を建てるにあたり、住宅ローンと並んで重要になるのが「自己資金」の準備です。
自己資金とは、住宅の購入費用に充てるために、ローンに頼らず自分で用意する現金のことです。
かつては「購入価格の2割は頭金が必要」などと言われていましたが、現在では低金利を背景に「フルローン」、つまり自己資金ゼロで全額をローンで賄うことも不可能ではありません。
しかし、自己資金をある程度準備しておくことには、多くのメリットがあります。
自己資金の主な使い道は、「頭金」と「諸費用」の2つです。
頭金とは、物件価格の一部を現金で支払うもので、頭金を多く入れるほど住宅ローンの借入額を減らすことができます。
借入額が減れば、毎月の返済額が軽くなる、あるいは返済期間を短縮できるだけでなく、支払う利息の総額も少なくなるという大きなメリットがあります。
また、金融機関によっては、物件価格に対する頭金の割合が高いと、より有利な金利プランを適用してくれるケースもあります。
もう一つの重要な使い道が、諸費用の支払いです。
前述の通り、新築時にはローン手数料や登記費用、税金、保険料といった様々な諸費用が発生します。
この諸費用の合計額は、一般的に物件価格の5%~10%程度が目安とされています。
例えば、4,000万円の家なら200万円~400万円の諸費用がかかる計算になります。
これらの諸費用は、住宅ローンに含めて借りられる場合もありますが、基本的には現金での支払いを求められることが多いため、最低でもこの諸費用分は自己資金として用意しておくことが望ましいです。
では、具体的に自己資金はいくら準備すれば良いのでしょうか。
理想を言えば、物件価格の10%~20%程度を自己資金として準備できると、資金計画にかなり余裕が生まれます。
例えば、総額4,500万円の家を建てる場合、450万円~900万円の自己資金があれば、諸費用を支払った上で、残りを頭金に充てることができます。
しかし、注意点もあります。
それは、貯蓄の全てを自己資金につぎ込んでしまうのは避けるべきだということです。
家を建てた後も、子供の教育費や万が一の病気や怪我、固定資産税の支払いなど、様々な出費が待ち構えています。
新しい生活を始めるための引っ越し費用や、家具・家電の購入費用も必要です。
そのため、自己資金とは別に、生活費の半年分から1年分程度の「手元に残すお金(予備費)」を必ず確保しておくようにしましょう。
自己資金が少ないからといって家づくりを諦める必要はありませんが、計画的に準備を進めることで、より安全で有利な資金計画を立てられることは間違いありません。
かかる税金の種類とタイミングを知る
マイホームの取得は喜ばしいことですが、同時に様々な税金を納める義務も発生します。
新築を建てる費用を考える際には、これらの税金の存在を忘れてはいけません。
税金は、支払うタイミングがそれぞれ異なるため、いつ、どのくらいの金額が必要になるのかをあらかじめ把握し、資金計画に組み込んでおくことが非常に重要です。
家づくりに関連する主な税金は以下の通りです。
- 印紙税: 土地の売買契約書や建物の建築工事請負契約書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書など、契約書を取り交わす際に課税されます。契約金額に応じて税額が決まり、収入印紙を契約書に貼付して納付します。
- 登録免許税: 土地や建物の所有権を法的に確定させるための登記(所有権保存登記、所有権移転登記)や、住宅ローンを組む際の抵当権設定登記の際に課税されます。税額は固定資産税評価額やローン借入額に一定の税率をかけて計算されます。
- 不動産取得税: 土地や建物を取得したことに対して、一度だけ課税される都道府県税です。取得後、しばらくしてから納税通知書が送られてきます。軽減措置が適用されるケースが多いですが、忘れた頃にやってくる大きな出費なので注意が必要です。
- 固定資産税・都市計画税: 毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に対して課税される市町村税です。家を建てた翌年から、毎年支払う必要があります。将来にわたって継続的にかかる費用なので、ランニングコストとして計算に入れておくべきです。
- 消費税: 建物の建築費に対して課税されます。土地の購入代金には消費税はかかりません。見積書を確認する際は、表示価格が税込なのか税抜なのかを必ず確認しましょう。
これらの税金は、それぞれ軽減措置が設けられています。
例えば、一定の要件を満たす新築住宅は、登録免許税や不動産取得税、固定資産税が大幅に減額されます。
これらの軽減措置を最大限に活用することで、数十万円単位の節約につながることもあります。
どのような条件で適用されるのか、ハウスメーカーや司法書士、税務署などに確認しておくと良いでしょう。
以下に、税金を支払う大まかなタイミングをまとめました。
| タイミング | 主な税金 |
|---|---|
| 契約時 | 印紙税 |
| 建物の完成・引渡し時 | 登録免許税、消費税(建物分) |
| 入居後 | 不動産取得税 |
| 入居翌年から毎年 | 固定資産税、都市計画税 |
特に、引渡し時に支払う登録免許税や、入居後に請求が来る不動産取得税は、諸費用として現金で準備しておく必要があります。
住宅ローンとは別に、これらの税金支払いのための資金をしっかりと確保しておくことが、スムーズな家づくりのポイントです。
また、住宅ローンを利用して家を建てた場合、「住宅ローン控除(減税)」という非常に大きなメリットがあります。
これは、年末のローン残高に応じて、所得税や住民税が一定期間還付される制度です。
初年度は確定申告が必要ですが、忘れずに行うようにしましょう。
新築を建てる費用を賢く抑える方法
◆この章のポイント◆
- ハウスメーカーと工務店の違いを比較
- 便利なシミュレーションの活用法
- 国や自治体の補助金制度を調べる
- オプション費用を抑えるための考え方
- 総まとめ:後悔しない新築を建てる費用の計画
ハウスメーカーと工務店の違いを比較
新築の依頼先をどこにするかは、費用だけでなく、家の品質やデザイン、アフターサービスにも大きく影響する重要な選択です。
依頼先の選択肢は、主に「ハウスメーカー」「工務店」「設計事務所」の3つがありますが、多くの人がハウスメーカーか工務店で悩むことになります。
両者の特徴を理解し、自分の家づくりに合ったパートナーを見つけることが、費用を賢く抑え、満足度の高い家を実現する第一歩です。
ハウスメーカーは、全国規模で事業を展開している大規模な住宅会社です。
資材の大量生産やシステムの効率化により、品質が安定しており、工期も比較的短いのが特徴です。
また、住宅展示場にモデルハウスを持っていることが多く、実物を見ながらイメージを膨らませることができます。
ブランド力があり、倒産のリスクが低く、長期保証やアフターサービスが充実している点も大きな安心材料と言えるでしょう。
一方で、広告宣伝費や人件費が価格に反映されるため、工務店に比べて坪単価は高くなる傾向があります。
また、商品は規格化されていることが多く、デザインや間取りの自由度は工務店に比べて低い場合があります。
次に、工務店は、地域に密着して事業を行う比較的小規模な会社です。
最大の魅力は、ハウスメーカーに比べて設計の自由度が高いことと、コストを抑えやすい点にあります。
広告費などの経費が少ない分、同じ仕様の家ならハウスメーカーより安く建てられる可能性があります。
また、地域での評判を大切にしているため、親身に相談に乗ってくれる会社が多く、施工後のメンテナンスなどでも柔軟な対応が期待できます。
ただし、会社によって技術力やデザイン力にばらつきがあるため、良い工務店を見極める目が必要です。
保証やアフターサービスの体制も会社ごとに異なるため、契約前にしっかりと確認しておく必要があります。
どちらが良いと一概には言えず、何を重視するかによって選択は変わってきます。
以下に、ハウスメーカーと工務店の主な違いをまとめました。
| 項目 | ハウスメーカー | 工務店 |
|---|---|---|
| 価格 | 高め | 比較的安め |
| 設計の自由度 | 低い(規格商品が多い) | 高い |
| 品質 | 安定している | 会社による差が大きい |
| 工期 | 比較的短い | 比較的長い |
| 保証・アフターサービス | 充実している | 会社による |
| 会社の安定性 | 高い | 会社による |
コストを抑えつつ、こだわりの家を実現したいなら、優秀な工務店を探すのが良い選択肢となります。
一方で、品質の安定やブランドの安心感、手厚い保証を求めるなら、ハウスメーカーが有力候補となるでしょう。
複数の会社から相見積もりを取り、提案内容や担当者の対応、価格などを総合的に比較検討することが、最適な依頼先を見つけるための最良の方法です。
便利なシミュレーションの活用法
「新築を建てる費用は、結局のところ総額でいくらになるのか?」という疑問に、具体的な数字で答えてくれるのが、オンラインの住宅ローンシミュレーションや費用シミュレーションツールです。
金融機関やハウスメーカーのウェブサイトで無料で提供されていることが多く、これらを活用することで、漠然としていた資金計画を具体化することができます。
シミュレーションにはいくつかの種類がありますが、まず試してみたいのが「毎月の返済額から借入可能額を算出する」シミュレーションです。
現在の家賃などを参考に、「毎月このくらいの金額なら無理なく返済できそうだ」という希望返済額と、希望する返済期間、おおよその金利を入力することで、借り入れできるローンの総額が分かります。
これにより、自分たちがどのくらいの価格帯の家をターゲットにできるのか、大枠を掴むことができます。
逆に、「借りたい金額から毎月の返済額を算出する」シミュレーションも重要です。
建てたい家のイメージが固まり、おおよその建築費が分かったら、その金額を借入希望額として入力します。
すると、金利や返済期間に応じた毎月の返済額が算出され、その返済額が現在の家計にとって現実的かどうかを判断する材料になります。
これらのシミュレーションを行う際には、金利の設定がポイントになります。
変動金利を想定している場合でも、将来の金利上昇リスクを考慮して、現在の金利よりも1%~2%程度高めの金利でも返済を続けられるか、試算してみることを強くおすすめします。
「ストレステスト」と呼ばれるこの試算を行っておくことで、将来の金利変動に対する備えができます。
また、ハウスメーカーが提供する費用シミュレーションでは、より詳細な見積もりに近い金額を算出できる場合があります。
希望する家の坪数やグレード、キッチンやバスルームの仕様、導入したいオプションなどを選択していくことで、本体工事費だけでなく、付帯工事費や諸費用まで含めた総額の概算を出してくれるツールもあります。
このようなツールを使えば、どこに費用がかかり、どこを削ればコストダウンできるのかといった、費用の内訳をより深く理解することができます。
ただし、シミュレーションの結果は、あくまでも概算であるということを忘れてはいけません。
土地の条件や選択する仕様、時期によって実際の費用は変動します。
シミュレーションは、自分たちの予算感を知り、資金計画の叩き台を作るためのツールとして活用し、最終的な正確な金額は、必ず複数の会社から正式な見積もりを取って確認するようにしましょう。
国や自治体の補助金制度を調べる
新築を建てる費用を抑える上で、非常に有効な手段となるのが、国や地方自治体が実施している補助金や助成金制度の活用です。
これらの制度は、省エネルギー性能の高い住宅や、子育て世帯向けの住宅の普及を目的としており、要件を満たすことで数十万円から百万円以上の補助を受けられる可能性があります。
制度の内容は毎年変わるため、常に最新の情報をチェックすることが重要です。
近年、国の代表的な住宅取得支援策として注目されているのが、子育て世帯や若者夫婦世帯を対象とした補助金制度です。
例えば「こどもエコすまい支援事業」の後継事業として、高い省エネ性能(ZEHレベル)を持つ住宅の取得に対して補助金を交付する制度が実施されています。
こうした制度を活用するためには、対象となる住宅の性能基準を満たす必要がありますが、長期的に見れば光熱費の削減にもつながるため、積極的に検討する価値は大きいでしょう。
また、ZEH(ゼッチ、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)住宅そのものに対する補助金制度も存在します。
ZEHとは、断熱性能の向上や高効率な設備の導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅のことです。
ZEHの基準を満たす住宅を建てることで、国から補助金が交付されます。
初期コストはかかりますが、補助金の活用と将来の光熱費削減を考えれば、十分元が取れる可能性があります。
国の制度だけでなく、都道府県や市区町村といった地方自治体が独自に設けている補助金制度も見逃せません。
- 地域産材の木材を使用して家を建てる場合の補助金
- 三世代同居や近居を目的とした住宅取得への補助金
- 太陽光発電システムや家庭用蓄電池の設置に対する補助金
- 耐震性の高い住宅に対する助成金
上記のように、自治体によって様々なユニークな制度が用意されています。
自分が家を建てる予定の自治体のホームページを確認したり、役所の担当窓口に問い合わせたりして、利用できる制度がないか必ず確認しましょう。
これらの補助金制度には、それぞれ申請期間や予算の上限が定められています。
人気の制度はすぐに受付が終了してしまうこともあるため、家づくりの計画段階からアンテナを張り、早めにハウスメーカーや工務店に相談して、申請の準備を進めることが大切です。
補助金の申請手続きは複雑な場合もありますが、多くの場合は建築を依頼する会社が代行してくれます。
利用できる制度を漏れなく活用することが、新築を建てる費用を賢く節約するための重要なポイントです。
オプション費用を抑えるための考え方
注文住宅の魅力は、自分のライフスタイルに合わせて間取りや仕様を自由に決められる点にありますが、これが費用を押し上げる原因にもなり得ます。
ハウスメーカーや工務店との打ち合わせを進める中で、担当者から様々な「オプション」を提案されることになります。
魅力的な提案に心を動かされ、あれもこれもと追加していくと、当初の見積もりから数百万円も費用がアップしてしまった、というケースは決して珍しくありません。
オプション費用を賢く抑えるためには、「標準仕様」と「オプション仕様」の違いを正しく理解し、自分たちにとって本当に必要なものを見極める「優先順位付け」が不可欠です。
「標準仕様」とは、ハウスメーカーなどが提示する坪単価に含まれている、基本的な設備や建材のことです。
一方で「オプション仕様」は、標準仕様からグレードアップしたり、追加したりするものを指し、その分の費用が加算されていきます。
例えば、キッチンをよりグレードの高いものに変更する、床材を無垢材にする、床暖房を追加する、食洗機を大型化する、といったものがオプションにあたります。
これらのオプションを検討する際に有効なのが、「絶対に譲れないもの」「できれば採用したいもの」「なくても我慢できるもの」の3つのカテゴリーに仕分ける方法です。
家族で話し合い、それぞれの要望に優先順位を付けてリストアップしてみましょう。
例えば、「キッチンの作業スペースの広さは絶対に譲れない」「リビングの床暖房はできれば採用したい」「2階のトイレはなくても我慢できる」といった具合です。
このように優先順位を明確にしておくことで、予算オーバーしそうになった際に、どこを削るべきかの判断がしやすくなります。
また、「後からでも工事できるか」という視点も重要です。
例えば、壁の中の断熱材のグレードアップや、建物の構造に関わるような工事は、後から変更するのが非常に困難です。
こういった家の基本性能に関わる部分は、初期投資と割り切って優先的に費用をかけるべきかもしれません。
一方で、カーテンや照明器具、外構の植栽などは、入居後にDIYしたり、専門業者に別途依頼したりすることも可能です。
いったん標準仕様で進めておき、暮らしながら必要に応じて追加していくという考え方も、コストを抑える上では有効です。
最終的な見積もりを確認する際には、何が標準で何がオプションなのか、一つ一つの項目を丁寧にチェックし、納得した上で契約に臨む姿勢が大切です。
その場の雰囲気で安易に決断せず、冷静に必要性を見極めることが、予算内で満足度の高い家づくりを実現するコツと言えるでしょう。
総まとめ:後悔しない新築を建てる費用の計画
これまで、新築を建てる費用に関する様々な側面を解説してきました。
家づくりは、多くの人にとって一生に一度の大きなプロジェクトです。
そして、その成否を分ける最大の要因が、しっかりとした資金計画に基づいているかどうか、という点に尽きます。
後悔しないためには、費用の内訳を正しく理解し、無理のない予算を立て、賢くコストを管理していく視点が欠かせません。
新築を建てる費用は、「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」の3つで構成されていることを、まずは念頭に置いてください。
広告の坪単価だけを見て判断するのではなく、土地の条件によって変動する付帯工事費や、現金で必要になることが多い諸費用まで含めた「総額」で予算を考えることがスタートラインです。
土地の有無は総額を大きく左右します。
土地探しから始める場合は、土地代と建物代のバランスを常に意識し、総予算の上限を超えないように計画を進める必要があります。
住宅ローンは「借りられる額」ではなく「返せる額」で組むのが鉄則です。
シミュレーションを活用し、将来の金利上昇リスクも考慮に入れた上で、家計を圧迫しない返済計画を立てましょう。
また、諸費用分は最低限、自己資金で準備しておくことが望ましいです。
費用を抑えるための工夫も積極的に取り入れましょう。
ハウスメーカーと工務店の違いを理解して最適なパートナーを選び、国や自治体の補助金制度を徹底的にリサーチすることが、数百万円単位の節約につながることもあります。
そして、オプションの選択は慎重に行い、自分たちの暮らしにとって本当に必要なものに投資するというメリハリのある判断が大切です。
家づくりは、情報収集と計画が全てと言っても過言ではありません。
この記事で得た知識を元に、ぜひご自身の状況に合わせた資金計画を立ててみてください。
一つ一つのステップを丁寧に進めていくことが、夢のマイホームを、後悔のない最高の形で実現するための最も確実な道筋となるでしょう。
本日のまとめ
- 新築を建てる費用は本体工事費・付帯工事費・諸費用の3つで構成される
- 総額の目安は土地なしで約3,900万円、土地ありで約5,400万円が全国平均
- 費用総額を最も大きく左右するのは土地の有無と価格である
- 本体工事費は総費用の7~8割を占める建物の基本的な費用
- 付帯工事費は外構や地盤改良など土地の条件で変動する費用
- 諸費用は税金やローン手数料など現金での準備が必要な費用
- 坪単価は建築会社によって定義が異なるため内訳の確認が必須
- 住宅ローンは返済負担率を年収の25%以内に抑えるのが安全
- 自己資金は最低でも諸費用分、理想は総額の1~2割を準備したい
- 家づくりでは印紙税や不動産取得税など様々な税金がかかる
- 費用を抑えるにはハウスメーカーと工務店の比較検討が重要
- オンラインの費用シミュレーションは資金計画の第一歩として有効
- 国や自治体の補助金制度は積極的に情報収集し活用すべき
- オプションは優先順位をつけ、本当に必要なものを見極める
- 後悔しないためには総額で予算を考え、無理のない計画を立てることが最も重要
-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |
参考サイト
注文住宅を建てる際にかかる費用相場を価格・広さ別に解説 – 一建設
【相場付き】家を建てる費用の目安はいくら?土地あり/なしのシミュレーションも解説 – イシカワ
新築住宅購入でかかる諸費用はいくら?費用の内訳と節約法を解説 – コスモ建設
家を建てるのに平均でいくらかかる? 費用と安く抑えるためのポイントを紹介 – ホームズ
注文住宅の相場・価格は? 1000・2000・3000・4000万円台の違い、家を建てる費用や流れを一級建築士が解説! | SUUMOお役立ち情報


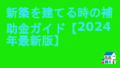
コメント