こんにちは、サイト管理人です
「マイホームを手に入れたいけれど、予算はあまりかけられない」と考える方にとって、ローコスト住宅で700万円という響きは非常に魅力的かもしれません。
しかし、その価格だけで判断してしまうと、後から「こんなはずではなかった」と後悔する可能性もゼロではありません。
この記事では、ローコスト住宅で700万円の家を建てることは現実的に可能なのか、その価格に隠されたからくりから、実際に必要となる総額の内訳までを徹底的に解説します。
具体的には、広告などで目にする700万円という金額が、多くの場合「本体価格」のみを指しているという事実、そして、それ以外に必ず発生する付帯工事費や諸費用の存在について詳しく掘り下げていきます。
さらに、費用を抑えつつ満足度の高い家を実現するための間取りの工夫や、平屋を選択するメリット、信頼できるハウスメーカーを見極めるための注意点にも触れていきます。
もちろん、価格が安いことによるデメリットや、契約前に知っておくべきリスクについても包み隠さずお伝えしますので、ぜひ最後までご覧いただき、賢い家づくりの第一歩を踏み出してください。
◆このサイトでわかる事◆
- ローコスト住宅700万円の価格の「からくり」
- 建物本体価格以外にかかる費用の種類と金額
- 最終的に必要となる「総額」のリアルな目安
- 予算内で実現可能なおすすめの間取りや坪数
- 平屋にすることでコストを抑えられる理由
- 知っておくべきローコスト住宅のデメリットと注意点
- 信頼できるハウスメーカーの選び方

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |
ローコスト住宅で700万円の家は本当に建てられる?
◆この章のポイント◆
- 価格のからくりと隠れた費用
- 700万円は本体価格のみ
- 別途必要になる付帯工事費
- 忘れてはいけない諸費用とは
- 実際に支払う総額の目安
価格のからくりと隠れた費用
ローコスト住宅の世界では、「700万円で家が建つ」といった魅力的な広告がしばしば見受けられます。
この価格設定は、マイホームを夢見る多くの人々にとって大きな希望となるでしょう。
しかし、この数字を鵜呑みにして計画を進めるのは非常に危険です。
なぜなら、広告で提示される金額には、家を建てて実際に住み始めるまでに必要となる全ての費用が含まれていないケースがほとんどだからです。
この価格の「からくり」を正しく理解し、見えない場所に隠れている費用を把握することが、後悔しない家づくりの第一歩となります。
多くの場合、700万円という価格は「建物本体工事費」のみを指しています。
これは、文字通り家の建物そのものを建てるための費用であり、基礎工事や構造体、屋根、外壁、内装、そして最低限の設備(キッチン、トイレ、バスなど)が含まれるのが一般的です。
しかし、これだけでは生活を始めることはできません。
建物本体以外にも、「付帯工事費」や「諸費用」といった、決して無視できない大きなコストが別途発生します。
これらの追加費用について事前に知らなければ、最終的な総額が予算を大幅に超えてしまい、資金計画が破綻してしまう恐れもあります。
したがって、広告の価格はあくまでも出発点であると認識し、そこからどれだけの費用が上乗せされるのかを具体的にシミュレーションすることが極めて重要になるのです。
この後のセクションで、建物本体価格、付帯工事費、そして諸費用という3つの主要なコストについて、それぞれどのような内容が含まれるのかを詳しく解説していきます。
それぞれの費用の役割と目安を理解することで、ローコスト住宅で700万円というプランの全体像がより明確に見えてくるはずです。
700万円は本体価格のみ
ローコスト住宅の広告で大々的に打ち出されている「700万円」という価格は、ほとんどのケースで「建物本体価格」または「本体工事費」を指しています。
この点をまず初めにしっかりと理解しておく必要があります。
建物本体価格とは、家の骨格や内外装など、建物そのものをつくるための費用のことです。
具体的にどのようなものが含まれるのか、一般的な内訳を見ていきましょう。
まず、家を支える最も重要な部分である「構造躯体工事」の費用が含まれます。
これには基礎工事、柱や梁といった骨組みの組み立てなどが該当します。
次に、屋根や外壁、窓や玄関ドアなどを取り付ける「外装工事」、壁紙や床材、内部のドアなどを設置する「内装工事」も本体価格の一部です。
さらに、キッチン、ユニットバス、トイレ、洗面台といった基本的な「住宅設備」の費用もここに含まれるのが一般的です。
ただし、注意が必要なのは、これらの設備が最低限のグレード、つまり「標準仕様」のものであるという点です。
もしデザイン性の高いものや高機能な製品を選びたい場合は、追加料金として「オプション費用」が発生します。
一方で、建物本体価格に含まれないものを把握することも同様に重要です。
例えば、カーテンレールや照明器具、エアコン、テレビアンテナなどは、多くの場合、本体価格には含まれていません。
また、庭や駐車場をつくる外構工事や、水道・ガス・電気を敷地内に引き込む工事も別途費用がかかります。
つまり、700万円という金額は、あくまで「建物の箱」をつくるための費用であり、生活に必要なインフラや設備を整えるための費用は含まれていないと考えるべきです。
この認識がなければ、見積もりを見た際に「話が違う」と感じてしまうことになりかねません。
ハウスメーカーや工務店によって、どこまでを本体価格に含めるかの基準は異なりますので、契約前には必ず見積書の内訳を詳細に確認し、「この価格には何が含まれていて、何が含まれていないのか」を明確に質問することが不可欠です。
別途必要になる付帯工事費
建物本体価格に加えて、家づくりには必ず「付帯工事費」というコストが発生します。
これは、建物を建てる前後の段階で必要となる、敷地内での様々な工事にかかる費用の総称です。
この付帯工事費は、土地の形状や状態、周辺環境によって大きく変動するため、一律の金額で語ることが難しいのが特徴です。
一般的に、付帯工事費は総額の約15%~20%を占めると言われており、決して軽視できない費用項目です。
具体的にどのような工事が含まれるのか、主要なものをいくつか見ていきましょう。
まず、「地盤調査・改良工事」があります。
家を建てる前には、その土地の地盤が建物の重さに耐えられるかどうかを調査する必要があります。
調査の結果、地盤が弱いと判断された場合には、地盤を強化するための改良工事が必須となります。
この費用は数十万円から、場合によっては100万円以上かかることもあり、土地の状態次第で大きく変わります。
次に、「給排水・ガス・電気の引き込み工事」です。
前面道路に通っている水道管やガス管、電線を敷地内に引き込み、建物に接続するための工事です。
道路から建物までの距離が長い場合や、引き込みに特殊な工事が必要な場合は費用が高くなる傾向にあります。
また、「外構工事」も付帯工事の大きな要素です。
これには、駐車場やアプローチの整備、門扉やフェンスの設置、庭の造成などが含まれます。
どこまでこだわるかによって費用は青天井ですが、最低限の整備でも数十万円は見ておく必要があるでしょう。
その他にも、古い家が建っている土地の場合は「解体工事費」、建築確認申請などの手続きにかかる「設計・申請費用」、そして忘れてはならないのが「消費税」です。
これらの付帯工事費は、建物の価格が700万円であっても、別途150万円から250万円程度はかかると考えておくのが現実的です。
ハウスメーカーによっては、見積もりの初期段階でこれらの費用を概算でしか提示しないこともあります。
そのため、契約を進める際には、どの工事にいくらかかるのか、できるだけ詳細な見積もりを提出してもらい、資金計画に余裕を持たせておくことが非常に重要です。
忘れてはいけない諸費用とは
家づくりにかかる費用は、「建物本体価格」と「付帯工事費」だけではありません。
工事そのものではないものの、住宅の購入や建築に伴って発生するさまざまな手数料や税金のことを「諸費用」と呼びます。
これもまた、総額を計算する上で絶対に忘れてはならない重要なコストです。
諸費用は、現金で支払う必要がある項目が多いため、住宅ローンとは別で自己資金を準備しておく必要があります。
一般的に、諸費用の目安は総額の5%~10%程度とされています。
では、具体的にどのような費用が含まれるのでしょうか。
まず、住宅ローンを組む際に発生する費用があります。
金融機関に支払う「ローン手数料」や、万が一の場合に備える「団体信用生命保険料」、そして融資の対象となる建物や土地に設定される抵当権の「登記費用」などです。
これらは借り入れる金額によって変動しますが、数十万円単位で必要になることがほとんどです。
次に、不動産に関連する税金が挙げられます。
土地や建物の売買契約書に貼る「印紙税」、不動産を取得した際に一度だけかかる「不動産取得税」、そして所有権を法的に登録するための「登録免許税」です。
これらの税金も、物件の価格に応じて金額が決まります。
さらに、万が一の火災や自然災害に備える「火災保険料」や「地震保険料」も必須の費用です。
特に住宅ローンを組む際には、火災保険への加入が融資の条件となっていることがほとんどです。
保険期間や補償内容によって保険料は大きく異なりますが、これも数十万円のまとまった支払いが必要となります。
その他にも、地鎮祭や上棟式といった建築儀式を行う場合の費用、新しい家具や家電の購入費用、引っ越し費用なども、広い意味での諸費用として予算に組み込んでおくと安心です。
仮に建物と土地、付帯工事を合わせて1,200万円だった場合、その5%~10%にあたる60万円から120万円程度の諸費用が現金で必要になると考えておくべきです。
これらの費用は、家づくりの最終段階で次々と支払いが必要になるため、計画の初期段階からしっかりと予算を確保しておくことが、スムーズなマイホーム実現の鍵となります。
実際に支払う総額の目安
ここまで、「建物本体価格」「付帯工事費」「諸費用」という3つの主要な費用について解説してきました。
ローコスト住宅で700万円というプランを検討する上で最も重要なのは、これらの費用をすべて合算した「総額」で資金計画を立てることです。
広告に掲げられた700万円という数字だけを見ていては、現実的な予算からは大きくかけ離れてしまいます。
では、実際に支払うことになる総額は、一体どれくらいになるのでしょうか。
ここで、具体的なシミュレーションをしてみましょう。
まず、出発点となるのが「建物本体価格」です。
これを広告通り700万円と設定します。
次に、「付帯工事費」です。
これは一般的に、建物本体価格の20%~30%が目安とされています。
仮に25%とすると、700万円の25%で175万円が付帯工事費として必要になります。
ただし、これはあくまで目安であり、地盤改良が必要になったり、外構にこだわったりすると、この金額はさらに膨らみます。
そして最後に、「諸費用」です。
これは、建物本体価格と付帯工事費を合計した金額の5%~10%が目安です。
ここでは、建物700万円+付帯工事175万円=875万円を基準に計算してみましょう。
仮に8%とすると、875万円の8%で70万円が諸費用としてかかります。
これらの数字を合計すると、以下のようになります。
- 建物本体価格:700万円
- 付帯工事費:175万円
- 諸費用:70万円
これを合計すると、総額は945万円となります。
つまり、「700万円の家」を建てるためには、実際には1,000万円近い資金が必要になる可能性があるということです。
もちろん、これはあくまで一例です。
土地を既に所有しているかどうか、どのようなオプションを追加するか、どの金融機関でローンを組むかなど、個別の条件によって総額は大きく変動します。
以下の表は、費用の内訳をまとめたものです。
| 費用項目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 建物本体価格 | 家の構造、内外装、基本設備など | 総額の70%~80% |
| 付帯工事費 | 地盤改良、給排水工事、外構工事など | 総額の15%~20% |
| 諸費用 | 税金、登記費用、ローン手数料、保険料など | 総額の5%~10% |
ローコスト住宅を検討する際には、必ず複数のハウスメーカーから「総額」での見積もりを取り、詳細な内訳を比較検討することが不可欠です。
目先の安さだけに惑わされず、最終的にいくら必要なのかを冷静に見極めることが、予算オーバーを防ぎ、満足のいく家づくりを成功させるための鍵となります。
ローコスト住宅で700万円を建てる具体的な方法
◆この章のポイント◆
- おすすめの間取りと坪数
- 平屋にすることで費用を抑える
- 知っておくべきデメリット
- 主要なハウスメーカー一覧
- 契約前に確認すべき注意点
おすすめの間取りと坪数
ローコスト住宅で700万円という厳しい予算内で家を建てるためには、建物の規模と形状をいかにシンプルにするかが極めて重要になります。
コストに最も大きな影響を与えるのが、延床面積(坪数)と間取りの複雑さだからです。
限られた予算を最大限に活かすためのおすすめの間取りと坪数について考えてみましょう。
まず坪数ですが、700万円の本体価格で実現可能なのは、おおよそ15坪から25坪程度が現実的なラインとなるでしょう。
坪単価を30万円~45万円と仮定すると、700万円では最大でも23坪前後となります。
これは、単身者や夫婦二人暮らし、あるいは小さなお子様が一人の3人家族向けのコンパクトな住まいを想定することになります。
次に間取りですが、コストを抑えるための基本原則は「総二階のシンプルな箱型」にすることです。
建物の形状が正方形や長方形に近いほど、外壁の面積が最小化され、材料費や施工の手間を削減できます。
凹凸の多い複雑なデザインは、見た目はおしゃれかもしれませんが、その分だけ壁の量や角の処理が増え、コストアップに直結します。
間取りの内部においても、工夫が必要です。
部屋数をむやみに増やすと、壁やドアの数が増えて費用がかさみます。
そこで、LDKを一体化させたり、廊下を極力なくしたりすることで、空間を広く見せつつコストを削減する工夫が求められます。
例えば、リビング階段を採用すれば、階段ホール分のスペースを節約できます。
また、水回り(キッチン、浴室、洗面所、トイレ)を1箇所に集中させることも効果的です。
配管の距離が短くなるため、工事費用を大きく抑えることができます。
収納については、ウォークインクローゼットのような大きな収納を一つ設けるよりも、各部屋に必要最低限のクローゼットを設置する方が、壁の面積が減りコストダウンにつながる場合があります。
具体的な間取り例としては、「1階にLDKと水回りを集中させ、2階に寝室と子供部屋を配置する」といったシンプルな2LDKなどが考えられます。
この際、各部屋の広さは最低限に留め、多目的に使えるフリースペースを設けるなどの工夫も有効でしょう。
予算が限られているからこそ、自分たちのライフスタイルに本当に必要なものは何かを見極め、無駄を徹底的にそぎ落とした間取りを考えることが、成功の鍵となります。
平屋にすることで費用を抑える
ローコスト住宅を検討する際、意外な選択肢として「平屋」がコスト削減につながるケースがあります。
一般的に、同じ延床面積であれば2階建てよりも平屋の方が坪単価は高くなる傾向にありますが、これは基礎と屋根の面積が大きくなるためです。
しかし、総額で考えた場合、平屋ならではのメリットがコストダウンに寄与することがあるのです。
まず、平屋には階段が必要ありません。
階段そのものの設置費用が不要になるだけでなく、階段が占めるスペース(通常1坪~1.5坪程度)を他の居住空間や収納として有効活用できます。
これにより、同じ居住スペースを確保するために必要な延床面積を、2階建てよりも小さくできる可能性があります。
また、2階部分がないため、建物の構造がシンプルになります。
2階の床を支えるための太い梁や柱、複雑な構造計算が不要になり、構造材のコストを削減できます。
さらに、工事においても大きなメリットがあります。
2階建ての場合、高所での作業が必要になるため、足場の設置が必須です。
この足場の設置と解体には数十万円の費用がかかりますが、平屋であれば大規模な足場が不要になるケースが多く、その分の費用をまるごと削減できるのです。
メンテナンスの面でも平屋は有利です。
将来的に外壁の塗り替えや屋根の修理が必要になった際も、足場を組む必要がないか、あるいは小規模で済むため、メンテナンス費用を長期的に見て安く抑えることができます。
700万円という予算内で考えるなら、例えば15坪程度のコンパクトな平屋であれば、2階建てよりも総額を抑えられる可能性があります。
夫婦二人で暮らす終の棲家として、あるいはミニマムな生活を目指す単身者にとって、小さな平屋は非常に合理的な選択肢となり得ます。
ただし、平屋を建てるには、2階建てよりも広い敷地面積が必要になるというデメリットもあります。
土地の価格が高い都市部では、かえって総額が高くなってしまうことも考えられます。
土地の条件と建物のコストバランスを総合的に判断し、平屋という選択肢も視野に入れて検討してみる価値は十分にあるでしょう。
知っておくべきデメリット
ローコスト住宅で700万円という価格は非常に魅力的ですが、その安さを実現するためには、何らかのトレードオフ、つまり妥協すべき点が存在することを理解しておく必要があります。
価格の安さというメリットの裏にあるデメリットを事前に知っておくことで、住み始めてからの後悔を避けることができます。
最も大きなデメリットの一つは、「間取りやデザインの自由度が低い」ことです。
ローコスト住宅は、あらかじめ決められた規格やプランの中から選ぶ「規格住宅」であることがほとんどです。
建材の大量一括仕入れや、設計・施工プロセスの効率化によってコストを削減しているため、注文住宅のように「壁をここに作りたい」「窓のサイズを変えたい」といった自由な要望に応えることは難しくなります。
外観や内装も似たようなデザインになりがちで、個性的な家を建てたい方には物足りなく感じるかもしれません。
次に、「標準仕様のグレードが低い」という点も挙げられます。
キッチンやバス、トイレなどの住宅設備は、基本的に最低限の機能を持つエントリーモデルが標準となっています。
より高機能なものやデザイン性の高いものを求めると、その都度オプション料金が発生し、積み重なると当初の予算を大幅に超えてしまうことがあります。
「安かったはずなのに、結局高くなってしまった」という事態に陥らないよう、どこまでが標準でどこからがオプションなのかを契約前に細かく確認する必要があります。
また、「住宅性能に不安が残る場合がある」という点も見過ごせません。
もちろん建築基準法はクリアしているため、安全性に問題はありません。
しかし、断熱性や気密性、遮音性といった快適性に直結する性能は、一般的な注文住宅に比べて劣る可能性があります。
断熱材の厚みや窓の性能などがコストカットの対象になりやすく、結果として「夏は暑く冬は寒い家」になり、光熱費が高くついてしまうことも考えられます。
さらに、アフターサービスや保証期間が短い場合があることもデメリットとして認識しておくべきです。
長期的な視点で見た場合、メンテナンス費用がかさむ可能性も考慮に入れておく必要があるでしょう。
これらのデメリットを理解した上で、自分たちのライフスタイルや価値観と照らし合わせ、何を優先し、何を妥協できるのかを明確にすることが、ローコスト住宅で成功するための重要なポイントです。
主要なハウスメーカー一覧
ローコスト住宅で700万円台のプランを提供している、あるいはその価格帯に近い家づくりが可能なハウスメーカーや工務店は、全国にいくつか存在します。
それぞれに特徴や強みがあるため、自分の希望に合った会社を見つけることが重要です。
ここでは、ローコスト住宅で知られる主要なハウスメーカーをいくつかご紹介します。
ただし、表示価格は常に変動する可能性があり、700万円という価格が現在も有効であるか、またどの費用まで含まれているかは、必ず各社に直接確認する必要があります。
まず、ローコスト住宅の代名詞ともいえるのが「タマホーム」です。
全国展開しており、テレビCMなどでも知名度が高いハウスメーカーです。
過去には「シフクノいえ」シリーズなどで1,000万円を切るプランを提供していました。
規格住宅をベースにコストを抑えつつも、一定の品質を確保しているのが特徴です。
次に、「アイダ設計」も低価格帯の住宅で有名です。
「555万円の家」といったキャッチーな商品を過去に展開しており、徹底したコストカットで驚異的な価格を実現しています。
設計から施工まで自社で一貫して行うことで、中間マージンを削減しています。
また、住宅設備メーカーの「LIXIL」グループである「アイフルホーム」も、ローコスト帯のフランチャイズを展開しています。
全国の加盟工務店が施工するため、地域に密着した対応が期待できるのが強みです。
LIXIL製の設備を標準仕様としているため、品質面での安心感もあります。
このほかにも、地域密着型の工務店の中には、独自の工夫で非常に低価格なプランを提供している会社が数多く存在します。
インターネットや住宅情報誌などで、「ローコスト住宅」「規格住宅」といったキーワードで地元の会社を探してみるのも一つの方法です。
以下の表は、代表的なローコスト系ハウスメーカーの特徴をまとめたものです。
| ハウスメーカー名 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| タマホーム | 全国的な知名度と実績。規格住宅が中心。 | 標準仕様のグレード確認が必要。 |
| アイダ設計 | 徹底したコスト管理による低価格が魅力。 | デザインや間取りの自由度は低い傾向。 |
| アイフルホーム | LIXILグループ。地域密着の工務店が施工。 | 加盟店によって対応や品質に差が出る可能性。 |
| 地域の工務店 | 独自のプランや柔軟な対応が期待できる。 | 実績や保証内容をしっかり確認する必要がある。 |
重要なのは、複数の会社から同じ条件で見積もりを取り、価格だけでなく、標準仕様の内容、オプション料金、保証制度などを総合的に比較することです。
会社の担当者との相性も大切ですので、実際にモデルハウスを訪れたり、相談会に参加したりして、信頼できるパートナーを見つけることが成功への近道です。
契約前に確認すべき注意点
ローコスト住宅で700万円というプランは、多くの制約の中で成り立っています。
そのため、契約書にサインをする前には、いくつかの重要なポイントを自分の目で確かめ、納得しておく必要があります。
後から「知らなかった」「聞いていない」ということにならないよう、細心の注意を払いましょう。
まず、最も重要なのが「見積書の内容を徹底的に精査する」ことです。
特に「総額でいくらになるのか」を必ず確認してください。
建物本体価格だけでなく、付帯工事費や諸費用がすべて含まれた「コミコミ価格」での見積もりを提出してもらいましょう。
その上で、見積書の項目を一つひとつチェックし、「標準仕様」に何が含まれていて、何が「オプション」になるのかを明確にします。
例えば、「照明器具は本体価格に含まれるが、取り付け工事費は別途必要」といった細かい規定がある場合もあります。
不明な点があれば、どんなに些細なことでも遠慮せずに質問し、書面で回答をもらうようにすると安心です。
次に、「標準仕様の現物を確認する」ことも大切です。
カタログや写真だけでは、質感や使い勝手は分かりません。
モデルハウスやショールームに足を運び、実際に使われるキッチンや床材、壁紙などを自分の目で見て、触れて、納得できる品質かどうかを判断してください。
もし標準仕様に満足できない場合、グレードアップにどれくらいの追加費用がかかるのかも事前に把握しておきましょう。
また、「保証とアフターサービスの内容」も契約前に必ず確認すべき重要事項です。
建物の構造部分に関する保証(瑕疵担保責任)は法律で10年間と定められていますが、それ以外の設備や内装に関する保証期間はハウスメーカーによって異なります。
引き渡し後の定期点検の有無や頻度、トラブルが発生した際の連絡先や対応の流れなど、長期的に安心して住むためのサポート体制が整っているかを確認しましょう。
さらに、「契約後の追加変更が可能か、可能な場合は費用がどうなるか」も聞いておくべきです。
ローコスト住宅では、コスト管理を厳格に行うため、契約後の間取り変更や仕様変更には高額な追加料金がかかったり、そもそも変更が一切認められなかったりするケースがあります。
工事が始まってから「やっぱりこうしたい」と思っても手遅れになる可能性を理解しておく必要があります。
これらの注意点を一つひとつクリアにし、すべての疑問や不安が解消された状態で初めて、契約という次のステップに進むべきです。
後悔しないローコスト住宅で700万円の計画を
この記事を通じて、ローコスト住宅で700万円の家を建てることの現実性と、そのために知っておくべき多くの事柄を解説してきました。
結論として、700万円という金額はあくまで「建物本体価格」であり、実際に住み始めるためには付帯工事費や諸費用を含めた総額で1,000万円近い資金が必要になる可能性が高いということをご理解いただけたかと思います。
しかし、計画の立て方次第で、この価格帯でも十分に満足のいくマイホームを手に入れることは可能です。
後悔しないための計画で最も重要なのは、「正しい知識」と「明確な優先順位」です。
まず、価格のからくりを理解し、総額で予算を考える習慣をつけましょう。
広告の安さに惑わされず、複数のハウスメーカーから詳細な見積もりを取り、冷静に比較検討することが第一歩です。
次に、自分たちのライフスタイルにとって「絶対に譲れないもの」と「妥協できるもの」を家族で話し合い、優先順位を明確にしてください。
予算が限られている以上、すべてを理想通りにすることはできません。
「デザイン性よりも断熱性能を重視する」「部屋の広さよりも収納の多さを優先する」など、自分たちの価値観をはっきりさせることが、後悔のない選択につながります。
間取りはシンプルに、坪数はコンパクトに。
これがコストを抑えるための鉄則です。
無駄な廊下をなくし、水回りを集中させるなど、設計上の工夫で費用を削減できるポイントはたくさんあります。
また、平屋という選択肢も、土地の条件によっては有効なコストダウン策となり得ます。
そして、ローコスト住宅のデメリットから目をそらさないでください。
標準仕様のグレードや住宅性能、保証内容など、価格が安い理由をきちんと理解し、納得した上で契約に臨むことが不可欠です。
ローコスト住宅で700万円の計画は、決して簡単な道のりではありませんが、情報収集を怠らず、賢く選択を重ねていくことで、夢のマイホームを実現することは十分に可能です。
この記事が、あなたの家づくり計画の一助となれば幸いです。
本日のまとめ
- ローコスト住宅の700万円は多くの場合「建物本体価格」のみを指す
- 実際に住むためには別途「付帯工事費」と「諸費用」が必要
- 付帯工事費は地盤改良や給排水工事、外構工事などにかかる費用
- 諸費用は税金や登記費用、ローン手数料や保険料など
- 総額は700万円に数百万程度上乗せされるのが一般的
- 総額の目安は950万円から1100万円程度になることが多い
- コストを抑えるにはシンプルな箱型の形状が基本
- 延床面積は15坪から25坪程度が現実的な広さ
- 廊下を減らし水回りを集中させる間取りが効果的
- 土地の条件が合えば平屋もコスト削減の選択肢になる
- デメリットとして間取りの自由度が低く、標準仕様のグレードも低い
- 断熱性などの住宅性能が一般的な注文住宅より劣る場合がある
- 契約前には総額での見積もりと標準仕様の現物確認が必須
- 保証内容やアフターサービスの詳細も必ず確認する
- 譲れない点と妥協点を明確にすることが後悔しない計画の鍵

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |
参考サイト
【必見】タマホームで700万円台の家を建てる方法と注意点 – はなまる家づくり
ローコスト住宅のコミコミ700万・800万・900万円の家の間取りや坪数は? – リフォらん
ローコスト住宅のデメリットとは?後悔しないために安い理由や問題点を知ろう – 株式会社住宅市場
ローコスト住宅のデメリットは?なぜ安いのか?後悔しないための注意点も解説 – イシカワ
ローコスト住宅を建てる場合、総額でいくらかかる? 費用の内訳について紹介 – ホームズ

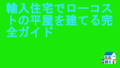

コメント