管理人の新築パパです
マイホームの購入は、人生で最も大きな買い物の一つと言えるでしょう。
だからこそ、建てた後の安心を支える保証制度は、ハウスメーカー選びの重要な比較ポイントになります。
特に、ハウスメーカーの10年保証は、多くの人が耳にする言葉ですが、その具体的な内容まで深く理解している方は少ないかもしれません。
この保証が、実は「品確法」という法律で定められた義務であること、そして保証には明確な保証範囲と保証対象外の項目があることをご存知でしょうか。
例えば、家の基本となる構造耐力に関する部分や雨漏りを防ぐ箇所は保証されますが、一方でシロアリによる被害は対象外となるケースがほとんどです。
また、10年間の初期保証が終わった後、大切な住まいを守り続けるためには、延長保証という選択肢があります。
しかし、この延長保証を受けるには、定期的な点検や有償メンテナンスが条件となることが一般的です。
この記事では、ハウスメーカーの10年保証の基礎となる瑕疵担保責任の考え方から、具体的な保証内容、延長保証の仕組み、さらには賢いメーカー選びのポイントまで、専門的な内容を分かりやすく解説していきます。
家づくりを始める前に、また、すでにお住まいの方も、ご自身の家の保証内容を再確認するために、ぜひご一読ください。
◆このサイトでわかる事◆
- ハウスメーカーの10年保証が法律上の義務であること
- 品確法に基づく保証の具体的な範囲
- 保証の対象となる構造耐力と雨漏りの詳細
- 保証対象外となる意外なケースとシロアリ被害の扱い
- ハウスメーカーの10年保証を延長するための条件と方法
- 有償メンテナンスの重要性と費用感
- 主要ハウスメーカーの保証内容を比較する視点

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |
ハウスメーカーの10年保証は法律で定められた義務

◆この章のポイント◆
- 法律で定められた品確法とは
- 瑕疵担保責任が保証範囲の基本
- 構造耐力と雨漏りは保証される
- 意外と知られていない保証対象外の項目
- 実は保証されないシロアリ被害
法律で定められた品確法とは
住宅の購入を検討する際に、多くの人が目にする「10年保証」という言葉。
これは、実はハウスメーカーが独自に設定しているサービスというだけではなく、法律によって義務付けられた制度です。
その根拠となるのが、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、通称「品確法」と呼ばれる法律になります。
品確法は、住宅購入者が安心して質の高い住宅を取得できるように、2000年に施行されました。
この法律の大きな柱の一つが、新築住宅の請負人や売主に対して、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を義務付けた点です。
つまり、ハウスメーカー側は、引き渡しから10年間、家の最も重要な部分に欠陥(瑕疵)が見つかった場合、無償で修理などに応じなければならないということです。
この法律が制定される以前は、住宅の保証期間は契約内容によって様々であり、中には2年程度の短い保証しか設けていないケースも存在しました。
そのため、入居後すぐに重大な欠陥が発覚しても、買主が多額の修繕費用を負担せざるを得ないというトラブルが後を絶たなかったのです。
このような状況を改善し、住宅の品質に対する信頼性を高め、購入者を保護するために品確法は作られました。
法律によって最低限の保証基準が定められたことで、私たちはどのハウスメーカーから家を購入しても、基本的な構造部分については10年間という長期の安心を得られるようになったわけです。
この法律は、住宅という高額で長期にわたって使用する財産の価値を守るための、非常に重要なセーフティネットと言えるでしょう。
したがって、ハウスメーカーの10年保証を理解する上で、この品確法がすべての基本になっているという点をまず最初に押さえておくことが大切です。
ハウスメーカーが提示する保証内容は、この法律で定められた義務をベースとして、さらに独自の保証を追加している形となります。
ですから、保証内容を比較検討する際には、どこまでが法律で定められた範囲で、どこからがメーカー独自のサービスなのかを区別して考えることが、より正確な理解につながります。
この法律の存在を知っているだけで、万が一のトラブルの際に冷静に対応できるだけでなく、家づくりの計画段階においても、より本質的な視点でハウスメーカーの姿勢や信頼性を評価することができるようになるでしょう。
瑕疵担保責任が保証範囲の基本
品確法によって定められた10年保証の核心にあるのが、「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という考え方です。
少し難しい法律用語ですが、これは住宅の保証を理解する上で欠かせないキーワードとなります。
まず、「瑕疵(かし)」とは、一言で言えば「隠れた欠陥」や「キズ」のことです。
住宅における瑕疵とは、契約時に買主が通常の注意を払っても発見できなかったような、建物の性能や品質に関する不具合を指します。
例えば、見ただけでは分からない基礎のひび割れや、壁の内部の断熱材の施工不良などがこれに当たります。
そして、「担保責任」とは、こうした瑕疵が後から見つかった場合に、売主(ハウスメーカーや工務店)が買主に対して負う責任のことです。
具体的には、買主は売主に対して、欠陥の修繕を求める「修補請求」や、それによって生じた損害の賠償を求める「損害賠償請求」などを行うことができます。
この瑕疵担保責任を、新築住宅の特に重要な部分について「引き渡しから10年間」義務付けたのが品確法なのです。
この責任は、民法にもともと規定がありましたが、品確法ではそれを住宅購入者にとってさらに有利な形で強化しています。
重要なのは、この責任が「隠れた」瑕疵に対して適用されるという点です。
契約時や引き渡し時に、すでに買主が知っていたり、説明を受けていたりした不具合については、原則として瑕疵担保責任を追及することはできません。
あくまで、専門家ではない一般の買主が発見できなかった、専門的な欠陥が対象となります。
この瑕疵担保責任という制度があるからこそ、私たちは引き渡し後に発覚した重大な欠陥に対しても、ハウスメーカーに責任ある対応を求めることができるのです。
ハウスメーカーの保証書を確認すると、多くの場合、この瑕疵担保責任という言葉が記載されているはずです。
保証内容は、この法律上の責任を具体的にどのように履行するかを定めたものと考えることができます。
保証範囲や条件をチェックする際は、この「瑕疵」という概念を念頭に置くと、より深く内容を理解できます。
例えば、「経年劣化は保証対象外」とされるのは、時間の経過とともに自然に発生する部材の劣化は、隠れた欠陥である「瑕疵」には当たらない、という考え方に基づいています。
このように、瑕疵担保責任はハウスメーカーの10年保証の根幹をなす法的な考え方であり、私たちの住まいを守るための強力な権利の基盤となっているのです。
構造耐力と雨漏りは保証される
品確法が定める10年間の瑕疵担保責任は、家のすべての部分に適用されるわけではありません。
法律は、特に建物の安全性や居住性に直結する、最も重要な二つの部分に限定してこの長期保証を義務付けています。
それが、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。
この二つのポイントを正確に理解することが、ハウスメーカーの10年保証の保証範囲を把握する上で極めて重要になります。
構造耐力上主要な部分
これは、建物の重さや地震、風圧といった力に耐え、家全体を支える骨格となる部分を指します。
もしこの部分に欠陥があれば、建物の安全性そのものが脅かされることになりかねません。
具体的には、以下のような箇所が該当します。
- 基礎:建物を地面に固定し、建物全体の重さを支える土台。
- 基礎ぐい:軟弱な地盤の場合に、建物を支えるために地中深くまで打ち込む杭。
- 壁:耐力壁など、地震や風の力に抵抗する主要な壁。
- 柱:屋根や床の重さを支える垂直の部材。
- 床版:建物の床を構成する構造体。
- 屋根版:屋根を構成する構造体。
- 梁(はり)、桁(けた):柱と柱の間に渡され、床や屋根を支える水平の部材。
- 筋かい、火打ち:地震や風の力による建物の変形を防ぐために、柱や梁の間に斜めに入れる補強材。
これらの部分に、施工不良によるひび割れや鉄筋の不足といった瑕疵が見つかった場合、引き渡しから10年間はハウスメーカーが責任を持って修補しなければなりません。
雨水の浸入を防止する部分
これは、文字通り、雨水が建物の内部に侵入するのを防ぐための部分です。
雨漏りは、建材を腐食させたり、カビの発生原因となったりして、建物の耐久性や住環境を著しく損ないます。
具体的には、以下のような箇所が該当します。
- 屋根:屋根材(瓦、スレートなど)やその下地材。
- 外壁:サイディングやモルタルなどの外壁材やその下地。
- 開口部:窓やドアなどの建具と、壁との取り合い部分(防水処理など)。
これらの部分の防水処理の不備や、材料の施工ミスによって雨漏りが発生した場合も、10年間の保証対象となります
このように、法律で定められたハウスメーカーの10年保証は、「家の骨格」と「雨漏りを防ぐ外皮」という、住まいの根幹を守るための保証であると言えます。
逆に言えば、これ以外の部分、例えば内装の仕上げや住宅設備などは、この法律による10年保証の対象とはならず、通常は1〜2年程度のメーカー保証や部位別の短期保証が適用されることが一般的です。
この点を明確に区別して理解しておくことが、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。
意外と知られていない保証対象外の項目
ハウスメーカーの10年保証は、家の基本性能を守る強力な制度ですが、万能ではありません。
「10年間はすべての不具合を無償で直してもらえる」と誤解していると、いざという時に「これは保証の対象外です」と言われてしまい、思わぬ出費に繋がる可能性があります。
法律で定められた保証範囲は、前述の通り「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵に限られます。
したがって、それ以外の多くの事象は保証の対象外となるのです。
ここでは、具体的にどのような項目が保証対象外になることが多いのか、代表的な例を挙げて解説します。
1. 経年劣化
最も代表的な保証対象外の項目が、時間の経過とともに自然に発生する部材の劣化や摩耗、いわゆる「経年劣化」です。
例えば、外壁の色あせやチョーキング(表面が粉状になる現象)、フローリングのすり傷、壁紙の日焼けや汚れ、パッキン類の硬化などがこれに当たります。
これらは製品の欠陥(瑕疵)ではなく、通常の使用に伴う自然な変化と見なされるため、保証の対象にはなりません。
2. 設備機器の故障
キッチン、ユニットバス、トイレ、給湯器、換気扇といった住宅設備機器は、建物の構造体とは別物として扱われます。
これらの設備には、通常、それぞれの機器メーカーが設定する1〜2年程度のメーカー保証が適用されます。
したがって、入居後5年目に給湯器が故障した、といったケースはハウスメーカーの10年保証の対象にはならず、修理や交換は自己負担となります。
3. 内装・外装の仕上げに関する不具合
壁紙の継ぎ目のすき間や浮き、床鳴り、建具の立て付けのズレといった、内装や仕上げに関する軽微な不具合も、多くは1〜2年の短期保証の対象となります。
これらは建物の安全性に直接影響する瑕疵とは見なされにくいため、10年保証の範囲外とされるのが一般的です。
4. 自然災害による損傷
地震、台風、洪水、落雷といった、予測を超える規模の自然災害によって受けた被害は、保証の対象外です。
例えば、台風で屋根瓦が飛んでしまった、地震で外壁に大きな亀裂が入った、といったケースは、建物の瑕疵ではなく天災による損害と判断されます。
これらの損害については、火災保険や地震保険で備えるのが基本となります。
5. 使用者の過失やメンテナンス不足による不具合
住まい手の故意や過失、あるいは適切なメンテナンスを怠ったことが原因で発生した不具合も、保証の対象にはなりません。
例えば、換気扇を全く掃除しなかったためにカビが大量発生した、排水溝の掃除を怠って水漏れが起きた、といったケースが該当します。
住まいを長持ちさせるためには、日頃の適切なお手入れが不可欠です。
これらの項目を理解しておくことで、ハウスメーカーの保証に対する過度な期待を避け、必要なメンテナンスや保険への備えを計画的に行うことができます。
実は保証されないシロアリ被害
家の耐久性に深刻なダメージを与えるシロアリの被害。
木造住宅の多い日本では、非常に気になる問題です。
「家の構造に関わる重大な問題だから、当然ハウスメーカーの10年保証の対象になるだろう」と考えている方が非常に多いのですが、ここに大きな落とし穴があります。
結論から言うと、
品確法に基づく10年間の瑕疵担保責任には、シロアリによる被害は含まれていません。
これは、シロアリ被害が建物の初期の欠陥(瑕疵)ではなく、後から外部の要因によって発生する「虫害」と見なされるためです。
法律が保証を義務付けているのは、あくまで設計や施工の段階で存在した欠陥であり、その後の自然現象や生物による被害は対象外という考え方が基本にあります。
そのため、もし引き渡し後にシロアリが発生し、土台や柱が食い荒らされたとしても、その修繕費用をハウスメーカーの10年保証でカバーすることは原則としてできないのです。
では、シロアリ対策はすべて自己責任なのでしょうか。
そうではありません。
多くのハウスメーカーでは、このシロアリ被害に対して、品確法の保証とは別に、独自の「防蟻保証(ぼうぎほしょう)」または「シロアリ保証」という制度を設けています。
これは、新築時に行う防蟻処理(土台や地面から一定の高さまでの木部に薬剤を散布・塗布する処理)の効果を保証するものです。
防蟻保証の一般的な内容
- 保証期間:一般的に5年間。一部のハウスメーカーでは10年保証を提供している場合もありますが、5年が主流です。これは、防蟻薬剤の効果が持続する期間がおおむね5年とされているためです。
- 保証内容:保証期間内にシロアリ被害が発生した場合、駆除費用や被害箇所の修繕費用を一定額まで補償する、という内容が一般的です。補償額には上限(例:500万円までなど)が設けられていることが多いです。
- 保証の延長:5年間の保証期間が終了する際に、再度、有料の防蟻処理を行うことで、さらに5年間保証を延長できる仕組みになっていることがほとんどです。
このように、シロアリ対策は「構造の保証」と「防蟻の保証」という、二つの異なる保証制度によってカバーされていると理解する必要があります。
ハウスメーカーと契約する際には、10年保証の内容だけでなく、このシロアリ保証の期間、保証内容、そして保証を延長するための条件や費用についてもしっかりと確認しておくことが、長期的な安心につながります。
特に、保証延長のための再処理費用は数万円から十数万円かかることもあるため、将来のメンテナンス計画に組み込んでおくことが重要です。
ハウスメーカーの10年保証を延長する方法と比較
◆この章のポイント◆
- 初期保証以降はどうなるのか
- 保証の延長は有償メンテナンスが条件
- 主要メーカーの延長保証を比較
- 賢いハウスメーカー選びのポイント
- ハウスメーカーの10年保証を正しく理解しよう
初期保証以降はどうなるのか
法律で定められたハウスメーカーの10年保証は、引き渡しから10年という節目で一つの区切りを迎えます。
この「初期保証」と呼ばれる期間が満了すると、法的な瑕疵担保責任は終了します。
では、11年目以降に家の構造部分や雨漏りに関する不具合が発生した場合、一体どうなるのでしょうか。
答えはシンプルで、原則としてすべての修繕費用が自己負担(家の所有者の負担)となります。
10年という歳月は、住宅にとってはまだまだ初期段階ですが、様々な部分で変化が現れ始める時期でもあります。
例えば、屋根や外壁の防水性能は少しずつ低下し、目に見えない部分で劣化が進行している可能性も否定できません。
もし、10年と1日目に雨漏りが発覚した場合、法的な保証期間は過ぎているため、修理費用はすべて自分で賄わなければならないのです。
これは、住宅の維持管理における大きなリスクと言えるでしょう。
このようなリスクに備え、長期的な安心を提供するために、ほとんどのハウスメーカーが用意しているのが「延長保証制度」です。
これは、10年の初期保証が満了するタイミングで、一定の条件を満たすことを前提に、保証期間をさらに10年、20年、あるいはそれ以上へと延ばしていくことができる仕組みです。
大手ハウスメーカーの中には、最長で60年といった超長期の保証を謳っているところもあります。
この延長保証制度を利用するかどうかは、所有者の任意です。
延長保証を選ばない場合は、10年でメーカーとの保証関係は一旦終了し、以降は何か問題が起きた際に、その都度自分でリフォーム会社などを探して対応していくことになります。
一方で、延長保証を選択すれば、引き続きハウスメーカーという「家の専門家」に、住まいの状態を定期的にチェックしてもらい、万が一の際には保証を受けられるという安心感を得ることができます。
つまり、初期保証以降の選択肢は大きく分けて二つ。一つは保証を延長してメーカーとの関係を継続する道、もう一つは保証を終了させて自己管理へと移行する道です。
どちらの選択が良いかは、個々の価値観やライフプラン、そして経済的な状況によって異なります。
しかし、この選択をするためには、延長保証がどのような仕組みで、どのような条件が必要なのかを、あらかじめ正確に理解しておくことが不可欠です。
次のセクションでは、その具体的な条件について詳しく見ていきましょう。
保証の延長は有償メンテナンスが条件
「最長60年保証」といった魅力的なキャッチフレーズを目にすると、「一度家を建てれば、60年間ずっと無償で修理してもらえる」と期待してしまうかもしれません。
しかし、これは大きな誤解です。
ハウスメーカーの10年保証を延長し、長期保証を維持するためには、避けて通れない重要な条件があります。
それが、「定期的な点検」と「有償メンテナンス(指定工事)」の実施です。
これは、保証延長の仕組みを理解する上で最も重要なポイントと言えます。
具体的には、以下のような流れで保証が延長されていきます。
- 初期保証満了前の点検:10年の初期保証期間が終了する少し前(9年目など)に、ハウスメーカーによる詳細な建物点検が行われます。この点検自体は無償の場合が多いです。
- メンテナンス工事の提案:点検の結果、建物の耐久性や防水性を維持するために必要と判断された修繕箇所やメンテナンス工事がリストアップされ、見積もりとともに所有者に提案されます。
- 有償メンテナンスの実施:所有者は、その提案されたメンテナンス工事を、そのハウスメーカー(または指定業者)に依頼し、費用を支払って実施してもらう必要があります。この工事を行わない場合、保証は延長されません。
- 保証の延長:指定された有償メンテナンスを完了することで、初めて保証が次の10年(あるいは5年など、メーカー規定の期間)へと延長されます。
このプロセスは、20年目、30年目と、保証を延長し続ける限り繰り返されることになります。
つまり、
長期保証とは、無料で提供されるサービスではなく、定期的な有料メンテナンスを継続的に行うことを前提とした「有料の安心サービス」なのです。
有償メンテナンスの具体例
では、具体的にどのような工事が有償メンテナンスとして必要になるのでしょうか。
建物の仕様や立地条件によって異なりますが、一般的には以下のようなものが挙げられます。
- 外壁の再塗装・シーリングの打ち替え:紫外線や雨風にさらされる外壁や、部材の継ぎ目を埋めるシーリング材は、10年〜15年で劣化が進むため、メンテナンスが必要になります。
- 屋根の補修・再塗装・葺き替え:屋根材の種類にもよりますが、防水性能を維持するためのメンテナンスが求められます。
- 防蟻処理の再施工:前述の通り、シロアリ保証を延長するためには、5年または10年ごとに有料の防蟻処理が必要です。
- バルコニーの防水工事:雨水が溜まりやすいバルコニーの床面は、定期的な防水層のメンテナンスが欠かせません。
これらの工事費用は、決して安いものではありません。
工事の内容や家の規模によっては、10年ごとの節目で100万円から200万円、あるいはそれ以上の費用がかかることも珍しくありません。
ハウスメーカーを選ぶ際には、保証の長さだけでなく、この保証を維持するために将来どれくらいのメンテナンス費用がかかるのか、その概算についても事前に確認し、長期的な資金計画に組み込んでおくことが非常に重要です。
主要メーカーの延長保証を比較
ハウスメーカーの10年保証とその延長制度は、各社が顧客への安心と自社製品の品質をアピールするための重要な要素です。
そのため、保証期間の長さや条件には、それぞれのメーカーの考え方や強みが反映されています。
ここでは、具体的な社名は挙げませんが、一般的な大手ハウスメーカーの延長保証制度を比較する際に注目すべきポイントを、表形式で分かりやすく整理します。
ハウスメーカーを比較検討する際には、ぜひこの表のような視点で各社の保証内容をチェックしてみてください。
| 比較ポイント | A社(堅実タイプ) | B社(長期保証アピールタイプ) | C社(柔軟対応タイプ) | 解説・チェックポイント |
|---|---|---|---|---|
| 初期保証(義務) | 10年間 | 10年間 | 10年間 | この期間は品確法により全社共通です。 |
| 延長単位 | 10年ごと | 5年または10年ごと | 10年ごと | 保証が更新されるスパンを確認します。短いスパンの方がこまめに点検できるという見方もできます。 |
| 最長保証期間 | 30年 | 60年 | 永年 |
最長期間の数字だけでなく、それを実現するための条件が現実的かどうかが重要です。
延長の条件定期点検と有償メンテナンスの実施定期点検と有償メンテナンスの実施定期点検と有償メンテナンスの実施条件は全社ほぼ同じですが、その「中身」が異なります。
有償メンテナンスの内容10年目に外壁・屋根の基本メンテナンスを推奨15年目までに外壁、屋根、防蟻など包括的なメンテナンスが必須点検結果に基づき、必要な箇所のみのメンテナンスを提案メーカーによって必須工事の範囲やタイミングが異なります。費用に大きく影響する部分です。
シロアリ保証初期5年(有償で延長可)初期10年(有償で延長可)初期5年(有償で延長可)シロアリ保証の初期期間や延長条件は、構造保証とは別に確認が必要です。
独自保証・特徴構造体に加え、防水についても30年間の長期保証「60年保証プログラム」としてブランド化。点検履歴を管理するシステムが充実。オーナー専用サイトでメンテナンス履歴や相談が可能。リフォーム部門との連携が強い。各社が付加価値として提供しているサービスにも注目しましょう。
比較の際の注意点
この表から分かるように、単に「60年保証」という数字だけを見てB社が最も優れていると判断するのは早計です。
保証を延長するための有償メンテナンスの内容や費用、そしてそのハウスメーカーが採用している建材の耐久性などを総合的に比較する必要があります。
例えば、C社のように柔軟な対応を謳うメーカーは、不要な工事を避けられる可能性がある一方で、個々の判断に委ねられる部分が多くなるかもしれません。
A社のように30年と期間は短めでも、その間のメンテナンス計画が明確で、費用感が掴みやすいというメリットも考えられます。
重要なのは、自分のライフプランや予算感に合った保証制度を提供しているメーカーを選ぶことです。
モデルハウスを訪れたり、営業担当者と話をしたりする際には、保証期間の長さだけでなく、「保証を維持するために、いつ、どのような工事に、およそいくら費用がかかるのか」という具体的な質問を投げかけてみることが、後悔しないメーカー選びにつながります。
賢いハウスメーカー選びのポイント
ここまで、ハウスメーカーの10年保証とその延長制度について詳しく解説してきました。
これらの知識を踏まえて、これから家を建てる方々が、保証という観点から後悔しないハウスメーカーを選ぶためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
ここでは、賢い選択をするための具体的なポイントを3つに絞ってご紹介します。
1. 「保証の長さ」だけでなく「保証を維持するコスト」を見る
多くの人が「60年保証」といった最長保証期間の数字に目を奪われがちです。
しかし、これまで見てきたように、その長期保証は「有償メンテナンス」という継続的なコストとセットになっています。
本当に見るべきは、保証期間の長さそのものよりも、その保証を維持するために生涯でどれくらいの費用がかかるのか、という「ライフサイクルコスト」の視点です。
ハウスメーカーを検討する際には、必ず「保証延長に必要なメンテナンスの具体的な内容と、その概算費用」を確認しましょう。
できれば、10年後、20年後、30年後に想定されるメンテナンスメニューと費用のモデルケースを提示してもらうのが理想です。
A社は保証30年だがメンテナンス総額が300万円、B社は保証60年だが総額が700万円、といった具体的な数字が見えてくると、より現実的な比較が可能になります。
2. 企業の「長期的な安定性」を評価する
どれだけ立派な長期保証制度があっても、その保証を提供するハウスメーカー自体が30年後、50年後に存在していなければ、保証書はただの紙切れになってしまいます。
特に、超長期の保証を契約するということは、その企業と非常に長い付き合いをすることになります。
したがって、企業の経営状態や将来性、つまり「長期的な安定性」も重要な判断基準となります。
上場企業であれば財務諸表を確認したり、創業からの歴史や年間の建築実績、オーナーからの評判などを調べたりすることも有効です。
急成長中の新しい企業も魅力的かもしれませんが、長年にわたり安定した経営を続けてきた実績のある企業の方が、長期保証という観点では安心感が高いと言えるかもしれません。
3. 保証内容の「詳細」を自分の目で確認する
営業担当者の「うちは保証が手厚いですよ」という言葉を鵜呑みにせず、必ず「保証規定書」や「アフターサービス基準書」といった公式な書類を取り寄せ、自分の目で詳細を確認する習慣をつけましょう。
特にチェックすべきは、「保証の対象となる事象」と「保証の対象外(免責)となる事象」がどのように記載されているかです。
細かい文字で書かれていることが多いですが、この部分にこそメーカーの姿勢が現れます。
例えば、「雨漏り」の定義はどこまでか、「構造体の歪み」とは具体的に何ミリまでを指すのか、など、疑問に思った点は遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求めることが大切です。
これらのポイントを意識することで、単なるイメージや宣伝文句に惑わされることなく、自分の大切な住まいを長期にわたって安心して任せられる、本当に信頼できるパートナーとしてのハウスメーカーを見極めることができるはずです。
ハウスメーカーの10年保証を正しく理解しよう
この記事を通じて、ハウスメーカーの10年保証という、家づくりにおける非常に重要なテーマについて、多角的に掘り下げてきました。
最後に、これまでの内容を振り返り、私たちが押さえておくべき最も重要なポイントをまとめて、本日の結論としたいと思います。
まず第一に、ハウスメーカーの10年保証は、単なるメーカーのサービスではなく、「品確法」という法律に基づいた公的な義務であるという事実です。
この法律が、私たちの住まいの根幹である「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」を、引き渡しから10年間、事業者の責任で守ることを定めています。
この法的背景を理解することは、保証制度の土台を把握する上で不可欠です。
第二に、保証には明確な「範囲」があるということです。
保証されるのは家の骨格と雨漏りを防ぐ部分の「瑕疵」に限られ、経年劣化や設備機器の故障、そして多くの人が勘違いしがちなシロアリの被害などは、原則として対象外となります。
この「保証されるもの」と「保証されないもの」の線引きを正しく認識することが、将来の無用なトラブルを避ける鍵となります。
そして第三に、10年を超える長期保証は、「有償メンテナンス」と引き換えに得られる有料のサービスであるという現実です。
「最長60年保証」という言葉の裏には、定期的な点検と、時には百万円単位となる指定工事の実施が条件として存在します。
このライフサイクルコストを考慮せずにハウスメーカーを選ぶことは、将来の家計に大きな影響を与えかねません。
結論として、ハウスメーカーの10年保証とは、法律で守られた最低限の安心をベースに、各社が提供する有料の長期維持管理プログラムと捉えるのが最も正確な理解と言えるでしょう。
賢い消費者は、保証期間の長さという表面的な数字に惑わされることなく、その保証を維持するための具体的なコスト、保証の詳細な内容、そして提供する企業の信頼性を総合的に見極めます。
この記事が、これから家を建てる皆様にとって、そしてすでにお住まいの皆様にとっても、ご自身の住まいと保証について改めて考えるきっかけとなり、より安心で豊かな暮らしを実現するための一助となれば幸いです。
本日のまとめ
- ハウスメーカーの10年保証は品確法に基づく法的義務である
- 保証の対象は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入防止部分
- この二つ以外の保証は法律で定められたものではない
- 瑕疵担保責任とは隠れた欠陥に対する事業者の責任のこと
- 経年劣化や自然災害による損傷は保証対象外
- 給湯器などの設備機器は通常1年から2年の短期保証
- シロアリ被害は10年保証の対象外で別途防蟻保証が必要
- 防蟻保証は多くの場合5年で有料の再処理で延長する
- 10年の初期保証終了後は原則すべての修理が自己負担となる
- 10年を超える長期保証は任意で加入する延長保証制度
- 保証の延長には定期点検と有償メンテナンスが必須条件
- 有償メンテナンスには100万円以上の費用がかかることもある
- 保証の長さだけでなく維持コストを含めた比較が重要
- 保証を提供する企業の長期的な安定性も判断材料になる
- 契約前に保証規定書で免責事項など詳細を確認することが賢明

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |
参考サイト
【2025】ハウスメーカーの保証を比較|確認・比較すべきポイントをわかりやすく解説 | まかろにお動画資料館 – メグリエ(MEGULIE)
新築に関わる保証とは?知っておくべき範囲や条件をわかりやすく解説 – YUI 結
Value Report 2023 – 積水ハウス
耐久年数とは?知っておきたい基礎知識とその重要性共起語・同意語も併せて解説!
「住宅メーカー」の英語・英語例文・英語表現 – Weblio和英辞書

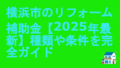

コメント