こんにちは、サイト管理人です
オール電化とガスどっちがお得か、という疑問は、新築やリフォームを検討する多くの方が直面する大きな悩みではないでしょうか。
光熱費は毎月の家計に直接影響するため、慎重な比較が求められます。
この問題に結論を出すためには、初期費用やランニングコストといった金銭的な側面はもちろん、それぞれのメリット・デメリットを総合的に理解することが不可欠です。
例えば、オール電化は基本料金を一本化できる魅力がありますが、災害時や停電の際にはすべての機能が停止してしまうリスクも考慮しなければなりません。
一方で、ガス併用は調理時の火力が魅力ですが、ガス漏れなどの安全性に関する懸念を持つ方もいるでしょう。
さらに、ご自身のライフスタイルや家族構成によっても、最適なエネルギーの選択は変わってきます。
都市ガスが利用できる地域なのか、あるいはプロパンガスしか選択肢がないのかによっても、料金プランは大きく変動します。
IHクッキングヒーターの使い勝手や、エコキュートでの給湯システムが本当に自分の生活に合っているのか、具体的なイメージを持つことが重要です。
この記事では、オール電化とガスどっちがお得かという疑問を解消するため、導入費用からメンテナンス、節約効果、そして太陽光発電との連携といった多角的な視点から、徹底的に比較・解説していきます。
どちらを選ぶべきか、あなたの家庭にとって最適な答えを見つけるためのお手伝いをします。
◆このサイトでわかる事◆
- オール電化とガス併用の初期費用の具体的な違い
- 月々の光熱費やランニングコストのシミュレーション
- オール電化のメリットと知っておくべきデメリット
- ガス併用の利点と注意が必要なポイント
- IHクッキングヒーターとガスコンロの安全性の比較
- 災害時や停電時の復旧や対応力の違い
- ライフスタイルや家族構成に合わせた最適な選択肢

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |
費用で見るオール電化とガスどっちがお得かの比較

◆この章のポイント◆
- 初期費用と導入コストの違いとは
- 月々の光熱費やランニングコストを検証
- オール電化のメリットとデメリット
- ガス併用のメリットとデメリット
- 安全性で比較するIHとガスコンロ
初期費用と導入コストの違いとは
オール電化とガス併用、どちらを選ぶか考える際に、まず大きな判断基準となるのが初期費用です。
導入時にどれくらいのコストがかかるのかを正確に把握することは、全体の資金計画を立てる上で非常に重要になります。
結論から言うと、一般的にはオール電化の方がガス併用に比べて初期費用は高くなる傾向があります。
その最大の理由は、導入が必要な機器の違いにあります。
オール電化住宅にする場合、主に「エコキュート」と「IHクッキングヒーター」の設置が必要です。
エコキュートは、空気の熱を利用してお湯を沸かす高効率な給湯器ですが、その本体価格と設置工事費を合わせると、40万円から80万円程度が相場となっています。
タンクの容量や機能によって価格は変動します。
一方のIHクッキングヒーターも、10万円から30万円程度の費用がかかるのが一般的です。
これらを合計すると、オール電化の導入には最低でも50万円以上、高機能なモデルを選ぶと100万円を超えるケースも少なくありません。
それに対して、ガス併用住宅の場合、給湯器には「ガス給湯器」を、キッチンには「ガスコンロ」を設置します。
高効率なガス給湯器である「エコジョーズ」を選んだ場合でも、設置費用を含めて20万円から40万円程度が相場です。
ガスコンロは5万円から20万円程度で設置できるため、合計すると25万円から60万円程度に収まることが多いでしょう。
このように、機器本体の価格差が、初期費用の差として直接的に現れるわけです。
ただし、この初期費用はあくまで目安であり、いくつかの要因で変動する点を忘れてはなりません。
例えば、国や自治体が提供している補助金制度を活用することで、初期費用を抑えることが可能です。
特にエコキュートのような省エネ性能の高い機器は、補助金の対象となりやすい傾向があります。
導入を検討する際には、必ずお住まいの地域の補助金情報を確認することをおすすめします。
また、新築かリフォームかによっても工事内容は変わってきます。
リフォームでオール電化にする場合は、既存のガス管の撤去費用や、エコキュートを設置するための基礎工事、IHクッキングヒーター用の200V電源の配線工事などが追加で必要になることがあります。
これらの追加工事が、予想以上に費用を押し上げる可能性も考慮しておく必要があります。
以下に、初期費用の目安を簡単な表でまとめました。
| 項目 | オール電化 | ガス併用 |
|---|---|---|
| 給湯器 | エコキュート:40万~80万円 | ガス給湯器:20万~40万円 |
| コンロ | IHクッキングヒーター:10万~30万円 | ガスコンロ:5万~20万円 |
| 合計目安 | 50万~110万円 | 25万~60万円 |
このように、初期費用だけを見るとガス併用の方が有利に見えますが、長期的な視点でランニングコストも含めて総合的に判断することが、後悔しない選択につながるのです。
月々の光熱費やランニングコストを検証
初期費用と並んで、オール電化とガスどっちがお得かを判断する上で最も重要な要素が、月々の光熱費、すなわちランニングコストです。
日々の生活に直結するこのコストをいかに抑えるかが、家計管理の鍵を握ります。
ランニングコストの比較は、それぞれのエネルギー供給の仕組みと料金体系を理解することから始まります。
オール電化の最大の特徴は、家庭で使うすべてのエネルギーを電気でまかなう点にあります。
これにより、ガス会社との契約が不要になり、支払う基本料金が電力会社の分だけで済むというメリットが生まれます。
ガスの基本料金は月に2,000円前後かかることが多いため、この分がまるごと節約できるのは大きな魅力と言えるでしょう。
さらに、多くの電力会社はオール電化住宅向けの特別な料金プランを用意しています。
これらのプランは、一般的に昼間の電気料金単価を割高に設定する代わりに、夜間の電気料金単価を大幅に安くしているのが特徴です。
オール電化の主要機器であるエコキュートは、この割安な深夜電力を使ってお湯を沸かし、タンクに貯めておく仕組みになっています。
家庭のエネルギー消費の中で給湯が占める割合は非常に大きいため、この部分のコストを深夜電力で抑えられることは、ランニングコスト削減に大きく貢献します。
一方で、ガス併用の場合は、電気とガスの両方を契約するため、それぞれの基本料金が発生します。
光熱費の合計は「電気代+ガス代」となり、料金体系が二元化します。
ガス代は使用量に応じて変動しますが、都市ガスかプロパンガスかによって単価が大きく異なる点に注意が必要です。
一般的にプロパンガスは都市ガスに比べて1.5倍から2倍ほど料金が高いとされており、プロパンガスエリアにお住まいの場合は、オール電化の方が光熱費を安く抑えられる可能性が高まります。
では、具体的な光熱費はどれくらい違うのでしょうか。
家族構成やライフスタイルによって大きく異なりますが、一般的な4人家族のモデルケースで考えてみましょう。
- オール電化の場合:月々の電気代が約15,000円~20,000円
- ガス併用(都市ガス)の場合:電気代約10,000円+ガス代約7,000円=合計約17,000円
- ガス併用(プロパンガス)の場合:電気代約10,000円+ガス代約12,000円=合計約22,000円
このシミュレーションを見ると、都市ガスエリアではオール電化とガス併用の差はそれほど大きくないか、使い方によってはガス併用が安くなることもあります。
しかし、プロパンガスエリアでは、オール電化にすることで光熱費を大幅に削減できる可能性があることがわかります。
ただし、オール電化には注意点もあります。
それは、昼間の電気代が割高であることです。
日中に在宅している時間が長く、電気を多く使う家庭の場合、オール電化のメリットを活かせず、かえって電気代が高くなってしまうケースも考えられます。
太陽光発電システムを導入し、昼間の電気を自家発電でまかなうといった工夫をすることで、このデメリットは解消可能です。
ランニングコストの比較は、単純な料金単価だけでなく、ご家庭の生活パターンやエネルギーの使い方を考慮して、総合的に判断することが何よりも重要です。
オール電化のメリットとデメリット
オール電化住宅は、その名の通り、調理、給湯、冷暖房など、家庭内で必要となるすべてのエネルギーを電気で供給する住まいの形です。
この選択には多くのメリットがある一方で、理解しておくべきデメリットも存在します。
両方の側面を正しく把握し、ご自身の家庭に合っているかを見極めることが大切です。
オール電化のメリット
まず、最大のメリットとして挙げられるのが、光熱費の管理のしやすさと基本料金の一本化です。
ガスを契約する必要がないため、支払う基本料金は電気代のみとなります。
これにより、毎月の固定費を削減できる可能性があります。
また、多くの電力会社が提供するオール電化向けの料金プランを活用できる点も大きな利点です。
夜間の電気料金が割安になるプランを選び、エコキュートや食洗機などをタイマーで夜間に稼働させることで、月々の電気代を効率的に節約できます。
次に、安全性の高さも見逃せないメリットです。
キッチンではIHクッキングヒーターを使用するため、火を直接使いません。
そのため、ガス漏れや一酸化炭素中毒、火の消し忘れによる火災のリスクがなくなります。
特に、小さなお子様や高齢のご家族がいる家庭にとっては、この安全性は大きな安心材料となるでしょう。
さらに、IHクッキングヒーターは表面がフラットなため、調理後の掃除が非常に簡単な点も、日々の家事負担を軽減してくれます。
災害時の復旧の速さも、近年注目されているメリットの一つです。
地震などの災害が発生した際、電気、水道、ガスといったライフラインの中で、電気が最も早く復旧する傾向にあります。
また、エコキュートのタンク内には常に数百リットルの水が貯まっているため、断水時にはその水を非常用の生活用水として活用することができます。
これは、万が一の事態に備えるという観点から、非常に心強い備えと言えます。
オール電化のデメリット
一方で、デメリットについてもしっかりと目を向ける必要があります。
最も大きなデメリットは、停電時にすべての機能が停止してしまうことです。
IHクッキングヒーターでの調理はもちろん、エコキュートによる給湯もできなくなります。
長時間の停電が発生した場合、生活に大きな支障が出る可能性があることは覚悟しておかなければなりません。
このリスクを軽減するためには、蓄電池や太陽光発電システムを導入したり、カセットコンロやポータブル電源を備えておいたりするなどの対策が有効です。
次に、初期費用が高額になりがちな点もデメリットです。
前述の通り、エコキュートやIHクッキングヒーターといった専用機器の購入・設置には、ガス機器に比べてまとまった費用が必要となります。
長期的に見ればランニングコストで元が取れる可能性はありますが、導入時の負担が大きいことは事実です。
また、エコキュート特有のデメリットとして、「湯切れ」のリスクがあります。
エコキュートは深夜電力で沸かしたお湯をタンクに貯めておく仕組みなので、来客などで急にお湯の使用量が増えた場合、お湯が足りなくなってしまう可能性があります。
タンクの容量を家族構成に合わせて慎重に選ぶことが重要です。
さらに、オール電化向けの料金プランは昼間の電気代が割高なため、日中の電気使用量が多い家庭では、かえって電気代が高くつくケースがあることも理解しておく必要があります。
これらのメリット・デメリットを総合的に比較検討し、ご家庭のライフスタイルに本当にマッチするかどうかを判断することが、後悔のない選択への第一歩となります。
ガス併用のメリットとデメリット
ガス併用住宅は、古くから日本の家庭で採用されてきた、電気とガスという2つのエネルギーを組み合わせて利用するスタイルです。
オール電化が普及する中でも、依然として根強い人気を誇るガス併用には、特有のメリットと、考慮すべきデメリットが存在します。
ガス併用のメリット
ガス併用住宅の最大のメリットの一つは、調理における火力の強さと使いやすさです。
ガスコンロがもたらす直火は、中華料理の炒め物や、食材を炙るといった調理法に最適で、料理好きの方からは絶大な支持を得ています。
炎が見えることで火加減の調節が直感的に行える点も、長年ガス調理に慣れ親しんだ方にとっては大きな利点でしょう。
また、ガス給湯器は、使いたいときにお湯を瞬間的に沸かす「瞬間式」が主流です。
これにより、オール電化のエコキュートのように「湯切れ」の心配がありません。
家族の入浴時間がバラバラだったり、急な来客があったりしても、お湯がなくなることを気にせずに使えるのは、日々の生活において大きな安心感につながります。
初期費用の安さも、ガス併用を選ぶ際の大きな動機となります。
ガス給湯器やガスコンロは、オール電化で必要となるエコキュートやIHクッキングヒーターに比べて、機器本体の価格が安価な傾向にあります。
そのため、住宅の新築やリフォーム時の初期投資を抑えたい場合には、ガス併用が有力な選択肢となるでしょう。
さらに、エネルギー源が電気とガスに分散されているため、停電時にもガスが使えるというメリットがあります。
もちろん、最近のガス機器は電力を必要とするものも多いですが、乾電池で点火できるタイプのガスコンロや、電気がなくても使えるガスストーブなどがあれば、停電時でも調理や暖房が可能になります。
この災害時のリスク分散という観点は、近年ますます重要視されています。
ガス併用のデメリット
一方で、ガス併用にはいくつかのデメリットも存在します。
まず、光熱費の管理が二元化し、電気とガスの両方で基本料金が発生することが挙げられます。
たとえガスの使用量がゼロの月であっても、基本料金は支払わなければなりません。
この基本料金の二重払いが、月々の固定費を押し上げる要因となります。
次に、安全面に関する懸念です。
ガスを使用する以上、ガス漏れや不完全燃焼による一酸化炭素中毒のリスクはゼロではありません。
もちろん、現在のガス機器には安全装置が搭載されており、定期的な点検も行われるため、過度に心配する必要はありませんが、火を直接扱うことへの不安を感じる方もいるでしょう。
また、プロパンガス(LPガス)を利用している地域では、ガス料金が割高になるという大きなデメリットがあります。
プロパンガスは都市ガスに比べて料金が高く、料金体系も自由化されているため事業者による価格差が大きいです。
プロパンガスエリアにお住まいの場合、ガス併用を続けると光熱費が非常に高額になる可能性があるため、オール電化への切り替えが有力な節約手段となることがあります。
最後に、ガスコンロは凹凸が多く、IHクッキングヒーターに比べて掃除に手間がかかるという点も、日々の家事を考えると無視できないデメリットかもしれません。
これらのメリット・デメリットを踏まえ、ご家庭の料理へのこだわり、初期費用の予算、そしてお住まいのガス供給状況などを総合的に考慮して、最適な選択をすることが求められます。
安全性で比較するIHとガスコンロ
毎日の食事作りで欠かせないコンロは、キッチンの中心的な設備です。
オール電化を選ぶかガス併用を選ぶかによって、このコンロがIHクッキングヒーターになるかガスコンロになるかが決まります。
この二つの調理機器は、熱源が違うだけでなく、安全性においても大きな違いがあります。
それぞれの安全上の特徴を理解し、どちらがご家庭にとってより安心できる選択肢かを考えることが重要です。
IHクッキングヒーターの安全性
IHクッキングヒーターの最大の安全上の特徴は、火を直接使わないことです。
IHは「Induction Heating(電磁誘導加熱)」の略で、磁力線の働きによって鍋自体を発熱させる仕組みです。
炎が出ないため、調理中に衣服の袖口などに火が燃え移る「着衣着火」のリスクがありません。
また、火の消し忘れによる火災の心配も大幅に軽減されます。
多くのIHクッキングヒーターには、切り忘れ防止機能や鍋なし自動OFF機能、高温になりすぎると自動で加熱を停止する機能など、多彩な安全機能が標準で搭載されています。
これらの機能が、うっかりミスによる事故を防いでくれます。
さらに、ガスコンロと異なり、燃焼を伴わないため、室内の空気を汚すことがありません。
ガスが燃焼する際には二酸化炭素や水蒸気が発生し、換気が不十分だと一酸化炭素中毒のリスクも伴いますが、IHクッキングヒーターならその心配は不要です。
トッププレートがフラットであることも、安全性に寄与しています。
鍋が安定しやすく、調理中に誤って鍋を倒してしまうリスクが低減されます。
掃除が簡単で、常に清潔な状態を保ちやすいことも、衛生的な観点からの安全性と言えるでしょう。
ただし、IHクッキングヒーターにも注意点はあります。
調理直後のトッププレートは非常に高温になっており、火傷の危険性があります。
また、電磁波が発生するため、心臓ペースメーカーなど医療用電子機器を使用している方は、事前に医師に相談する必要があります。
ガスコンロの安全性
一方、ガスコンロは火を直接扱うため、本質的に火災や火傷のリスクを伴います。
しかし、現在のガスコンロは、安全性を飛躍的に向上させるための様々な技術が導入されています。
2008年以降に製造された家庭用ガスコンロには、すべてのバーナーに「調理油過熱防止装置」と「立ち消え安全装置」の搭載が義務付けられています。
調理油過熱防止装置は、鍋底の温度をセンサーが監視し、油が発火する危険な温度になる前に自動でガスを止めたり、火力を弱めたりする機能です。
立ち消え安全装置は、煮こぼれや風などで火が消えてしまった際に、自動でガスを遮断し、ガス漏れを防ぐ機能です。
これに加えて、消し忘れ消火機能や、グリルが過熱すると自動で消火する機能なども一般的になっています。
これらの安全装置(Siセンサー)の普及により、ガスコンロによる火災件数は大幅に減少しています。
また、ガスを使用する上で懸念されるガス漏れについても、ガス漏れ警報器の設置が義務付けられており、万が一の際には迅速に異常を検知できる体制が整っています。
それでもなお、火を使っているという事実に変わりはなく、特に高齢者や小さなお子様がいるご家庭では、IHクッキングヒーターの方がより安心感が高いと感じるかもしれません。
最終的にどちらを選ぶかは、これらの安全機能への理解と、ご自身のライフスタイルや家族構成を考慮して判断することが求められます。
安全性を最優先するならばIHクッキングヒーターに軍配が上がりますが、最新の安全機能を搭載したガスコンロも、従来のものとは比較にならないほど安全性が高まっていることを知っておくべきでしょう。
状況別で見るオール電化とガスどっちがお得かの選び方
◆この章のポイント◆
- エコキュートの仕組みと注意点
- 災害時や停電時の復旧スピード
- 家族構成とライフスタイルに合う料金プラン
- 都市ガスとプロパンガスの料金差
- 太陽光発電と組み合わせるメリット
- 結論としてオール電化とガスどっちがお得か
エコキュートの仕組みと注意点
オール電化住宅の心臓部とも言える設備が、高効率給湯器「エコキュート」です。
オール電化のランニングコストの低さは、このエコキュートの性能に大きく依存しています。
その仕組みを正しく理解し、メリットと注意点の両方を把握しておくことは、オール電化を選ぶ上で非常に重要です。
エコキュートの仕組み
エコキュートの正式名称は「自然冷媒ヒートポンプ給湯機」と言います。
最大の特徴は、ヒートポンプ技術を利用してお湯を沸かす点にあります。
これは、エアコンの暖房と同じ原理を応用したものです。
具体的には、まず屋外に設置されたファンが外気の熱を吸収します。
その熱を、CO2(二酸化炭素)を冷媒として圧縮することで、さらに高温にします。
そして、その高温になった冷媒の熱を利用して水を温め、お湯を作るのです。
電気の役割は、主にこのヒートポンプを動かすためのコンプレッサー(圧縮機)に使用されます。
電気ヒーターのようにお湯を直接温めるのではなく、空気中の熱を効率よく集めて利用するため、使用する電気エネルギーの3倍以上の熱エネルギーを生み出すことができます。
この高いエネルギー効率が、エコキュートが省エネであると言われる所以です。
そして、この仕組みと組み合わされるのが、割安な深夜電力の活用です。
エコキュートは、電気料金が安い夜間(例えば午後11時から午前7時まで)に1日分のお湯をまとめて沸かし、それを「貯湯タンク」に保温して貯めておきます。
そして、日中はそのタンクに貯められたお湯を使うことで、給湯にかかる光熱費を大幅に削減できるというわけです。
エコキュートの注意点
このように非常に効率的なエコキュートですが、導入や使用にあたってはいくつかの注意点があります。
まず、設置スペースの問題です。
エコキュートは、ヒートポンプユニットと貯湯タンクユニットという2つの機器で構成されており、これらを設置するためのある程度のスペースが屋外に必要となります。
特に貯湯タンクは大型で重量もあるため、設置場所の確保と、しっかりとした基礎工事が不可欠です。
次に、運転音の問題です。
ヒートポンプユニットは、ファンが回転して空気を圧縮するため、運転中に低周波音を含む音が発生します。
音の大きさ自体はエアコンの室外機と同程度ですが、主に夜間に運転するため、寝室の近くや隣家の窓のそばなどに設置すると、騒音トラブルの原因となる可能性があります。
設置場所は、隣家への配慮も含めて慎重に選ぶ必要があります。
また、貯湯式であるため、「湯切れ」のリスクが常に伴います。
急な来客や家族の生活スタイルの変化で、お湯の使用量が想定を上回った場合、タンクのお湯を使い切ってしまう可能性があります。
湯切れを起こすと、割高な昼間の電力を使ってお湯を沸き増しする必要があるため、電気代が余計にかかってしまいます。
これを防ぐためには、家族の人数やお湯の使い方に合った、少し余裕のあるタンク容量のモデルを選ぶことが重要です。
さらに、エコキュートは貯めたお湯を給水で押し出して使う仕組み上、水道水の圧力よりも給湯圧が少し低くなる傾向があります。
シャワーの水圧が弱いと感じる場合があるため、水圧にこだわりがある方は、高圧給湯タイプのエコキュートを選ぶと良いでしょう。
これらの注意点を事前に理解し、対策を講じることで、エコキュートのメリットを最大限に引き出すことができます。
災害時や停電時の復旧スピード
近年、地震や台風などの自然災害が頻発する中で、住まいのエネルギー選択において「災害への強さ」は非常に重要な判断基準となっています。
オール電化とガス併用では、停電やインフラの断絶といった非常事態において、それぞれ異なる強みと弱みを持っています。
災害発生から日常を取り戻すまでの復旧プロセスを想定し、どちらがより安心できるかを比較検討してみましょう。
ライフラインの復旧順序
一般的に、大規模な災害が発生した際のライフライン(電気・水道・ガス)の復旧は、電気が最も早いと言われています。
これは、電気は電線という「線」で供給されているのに対し、ガスは地中に埋設されたガス管という「面」で供給されているため、被害状況の確認や修復に時間がかかるからです。
過去の大規模地震の事例を見ても、電気の復旧が数日で完了したのに対し、都市ガスの全面復旧には1ヶ月以上を要したケースもあります。
この観点から見ると、インフラの復旧スピードにおいては、オール電化が有利であると言えるでしょう。
電気が復旧しさえすれば、家中の機能が回復に向かいます。
停電時の影響
しかし、話はそう単純ではありません。
問題は、インフラが復旧するまでの「停電中」の生活です。
オール電化住宅は、すべてのエネルギーを電気に依存しているため、停電が発生すると全ての機能が完全に停止してしまいます。
IHクッキングヒーターでの調理、エコキュートからの給湯、エアコンによる冷暖房、照明など、生活に不可欠な機能が一切使えなくなります。
これはオール電化の最大のリスクであり、デメリットです。
一方で、ガス併用住宅の場合、停電してもガスが供給されていれば、一部の機能は維持できる可能性があります。
例えば、乾電池で点火できるタイプのガスコンロであれば、停電中でも調理が可能です。
また、ガスファンヒーターなどがあれば暖を取ることもできます。
ただし、現在の多くのガス給湯器は電気制御されているため、停電中はお湯を使えないケースがほとんどです。
エネルギー源が分散されていることによるリスクヘッジが、ガス併用の強みと言えます。
その他の災害対策
オール電化住宅には、停電時以外の災害対策として優れた点もあります。
それは、エコキュートの貯湯タンクです。
タンク内には常に370Lや460Lといった大量の水(またはお湯)が貯蔵されています。
災害による断水時には、このタンク内の水を非常用の生活用水として取り出して使用することができます。
飲用には適しませんが、トイレを流したり、体を拭いたりするための貴重な水源となります。
一方で、プロパンガスを利用しているガス併用住宅は、災害に対して非常に強いという特徴があります。
プロパンガスは各家庭に個別のガスボンベが設置されている「分散型エネルギー」であるため、配管の被害などを受けることがなく、供給が途絶えにくいです。
これらの点をまとめると、以下のようになります。
- インフラ復旧の速さ:オール電化が有利
- 停電中の生活維持:ガス併用が有利(一部機能)
- 断水時の備え:オール電化が有利(エコキュートの貯水)
- 供給の途絶えにくさ:ガス併用(プロパンガス)が有利
どちらか一方が絶対的に優れているわけではなく、それぞれに一長一短があります。
オール電化を選ぶ場合は、太陽光発電や蓄電池を導入して停電に備える、ガス併用を選ぶ場合は、停電時でも使えるガス機器を用意しておくなど、それぞれの弱点を補う対策を講じることが、災害に強い住まいづくりの鍵となります。
家族構成とライフスタイルに合う料金プラン
オール電化とガスどっちがお得かという問題の答えは、すべての人に共通するものではありません。
その家庭の家族構成や日々の生活リズム、つまりライフスタイルによって、最適なエネルギーの形とそれに合わせた料金プランは大きく変わってきます。
ご自身の家庭がどちらのタイプに当てはまるのかを分析することが、賢い選択への近道です。
オール電化が向いている家庭
オール電化のメリットを最大限に享受できるのは、特定のライフスタイルを持つ家庭です。
その典型が、「日中は仕事や学校で家を空けることが多く、夜間に在宅している時間が長い」という共働き世帯や学生のいる家庭です。
オール電化向けの電気料金プランは、夜間の電気代が安く、昼間の電気代が高いという特徴があります。
そのため、電気の使用が夜間に集中する家庭ほど、その恩恵を受けやすくなります。
エコキュートによる夜間の沸き上げはもちろん、食洗機や洗濯乾燥機、炊飯器のタイマー予約などを活用して、家事の多くを夜間に行うように工夫することで、電気代を効率的に削減できます。
また、家族の人数が多い家庭も、オール電化のメリットを活かしやすいと言えます。
お湯の使用量は家族の人数に比例して増えるため、割安な深夜電力で大量のお湯を沸かせるエコキュートの節約効果がより大きくなるからです。
ただし、その分、湯切れのリスクも高まるため、家族の人数プラス1人分程度の余裕を持ったタンク容量のエコキュートを選ぶことが重要です。
ガス併用が向いている家庭
一方で、ガス併用の方が適している家庭も多くあります。
例えば、「日中に在宅している時間が長い」専業主婦(主夫)のいる家庭や、在宅ワーク中心の方、小さな子供がいて昼間も家で過ごすことが多い家庭などです。
このような家庭では、昼間の電気使用量が多くなりがちです。
オール電化の料金プランでは割高な昼間の電気を多く使うことになるため、かえって光熱費が高くなってしまう可能性があります。
ガス併用であれば、昼間の活動時間帯もガスを効率的に利用できるため、トータルの光熱費を抑えられる場合があります。
また、料理にこだわりがあり、ガスコンロの強い火力を求める方にとっても、ガス併用は魅力的な選択肢です。
調理スタイルは日々の満足度に直結するため、経済性だけで判断すべきではない重要な要素と言えるでしょう。
さらに、家族の入浴時間がバラバラで、お湯を使うタイミングが予測しにくい家庭の場合も、ガス併用が安心です。
瞬間式のガス給湯器なら、湯切れの心配をすることなく、いつでも好きな時にお湯を使うことができます。
料金プランの選択が鍵
どちらのエネルギー形態を選ぶにせよ、重要なのは、自分のライフスタイルに合った料金プランをしっかりと選ぶことです。
オール電化を選ぶなら、どの時間帯が安くなるのかを正確に把握し、その時間帯に電気の使用をシフトさせる意識が必要です。
ガス併用を選ぶなら、電力会社とガス会社を同じ会社にまとめることで割引が受けられる「セット割」などを積極的に検討すべきです。
最近では、電力もガスも自由化が進み、多種多様な事業者から様々な料金プランが提供されています。
ご自身の家庭の電気やガスの使用量、使用時間帯を検針票などで一度確認し、複数の会社のプランをシミュレーションしてみることを強くお勧めします。
その上で、家族の将来的な変化(子供の成長や独立など)も見据えて、長期的な視点で最適な選択をすることが後悔しないためのポイントです。
都市ガスとプロパンガスの料金差
ガス併用住宅を検討する上で、絶対に見過ごしてはならないのが、供給されているガスの種類です。
家庭用のガスには、主に「都市ガス」と「プロパンガス(LPガス)」の2種類があり、どちらを利用するかによって、月々のガス料金、ひいては光熱費全体が大きく変わってきます。
この違いを理解することは、オール電化とガスどっちがお得かを正しく比較するための大前提となります。
供給方法とエリアの違い
都市ガスは、地下に埋設されたガス導管を通じて、各家庭に供給されます。
大規模なインフラ整備が必要なため、主に人口が集中する都市部やその周辺地域で利用されています。
原料はメタンを主成分とする液化天然ガス(LNG)で、空気よりも軽いという性質があります。
一方、プロパンガスは、プロパン・ブタンを主成分とする液化石油ガス(LPG)を、専門の業者がガスボンベに詰めて各家庭まで配送し、設置します。
大掛かりな導管が不要なため、郊外や山間部、都市ガスが整備されていない地域など、全国どこでも利用することが可能です。
プロパンガスは空気よりも重いという性質を持っています。
料金体系と価格の差
この2つのガスの最大の違いは、その料金にあります。
結論から言うと、プロパンガスは都市ガスに比べて料金が大幅に高いです。
一般的に、同じ使用量でもプロパンガスの料金は都市ガスの1.5倍から2倍程度、場合によってはそれ以上になることもあります。
この価格差が生まれる理由は、料金体系の違いにあります。
都市ガスは、かつては国の認可が必要な規制料金でしたが、2017年のガス小売全面自由化により、多くの地域で自由料金に移行しました。
それでもなお、料金設定には一定の公共性があり、価格競争も働きやすい環境にあります。
それに対して、プロパンガスは昔から完全な自由料金制です。
各販売店が独自に価格を設定できるため、同じ地域でも事業者によって料金が大きく異なることがあります。
また、ガスボンベの配送や保安点検といった人件費が価格に上乗せされるため、どうしてもコストが高くなる傾向にあるのです。
オール電化との比較における重要性
この料金差は、「オール電化 vs ガス併用」という比較の構図を大きく変える要因となります。
お住まいの地域が都市ガスエリアである場合、ガス併用のランニングコストは比較的安く抑えられるため、オール電化との差は小さくなります。
ライフスタイルや初期費用との兼ね合いで、どちらを選ぶかじっくり検討する価値があるでしょう。
しかし、お住まいの地域がプロパンガスエリアである場合、話は大きく変わります。
割高なプロパンガスを使い続けると、月々の光熱費は非常に高額になります。
このような状況では、初期費用をかけてでもオール電化に切り替えた方が、長期的に見て大幅な光熱費の削減につながる可能性が非常に高いです。
実際に、「プロパンガス料金の高さに悩み、オール電化にリフォームした」というケースは少なくありません。
したがって、ご自宅や転居先、新築を検討している土地で利用できるガスがどちらの種類なのかを、まず最初に確認することが何よりも重要です。
もしプロパンガスしか選択肢がないのであれば、オール電化をより積極的に検討するべきだと言えるでしょう。
逆に、すでにプロパンガスを利用していて料金に不満がある場合は、オール電化への切り替えシミュレーションと同時に、他のプロパンガス会社に見積もりを依頼して、価格交渉をしてみるのも一つの手です。
太陽光発電と組み合わせるメリット
オール電化とガスどっちがお得かを考える際、もう一つ視野に入れておきたいのが、太陽光発電システムとの連携です。
特にオール電化住宅は、太陽光発電と非常に相性が良く、組み合わせることで双方のメリットを最大化し、光熱費の削減効果を飛躍的に高めることができます。
この組み合わせがなぜ強力なのか、その理由を詳しく見ていきましょう。
昼間の割高な電気を自家発電でカバー
オール電化住宅で採用される電気料金プランの多くは、夜間の電気代が安い代わりに、昼間の電気代が割高に設定されています。
そのため、日中に在宅していて電気を使う機会が多い家庭では、オール電化の恩恵を受けにくいというデメリットがありました。
しかし、ここに太陽光発電システムを導入すると、状況は一変します。
太陽光発電は、その名の通り太陽が出ている日中に発電します。
つまり、電気代が最も高い時間帯に、発電した電気を家庭内で使うことができるのです。
エアコンやテレビ、パソコン、日中の調理などで消費する電力を、電力会社から購入するのではなく、自家発電でまかなうことで、電気代を大幅に削減できます。
これは、オール電化の最大の弱点を完璧に補う、理想的な関係と言えるでしょう。
余剰電力の活用と売電
日中に発電した電気のうち、家庭内で使いきれずに余った分(余剰電力)は、電力会社に売ることができます(売電)。
これにより、光熱費を削減するだけでなく、収入を得ることも可能です。
さらに、エコキュートと連携させることで、この余剰電力をより有効に活用する方法もあります。
通常、エコキュートは夜間にお湯を沸かしますが、太陽光発電と連携できる最新の機種の中には、翌日の天気予報などを考慮して、夜間の沸き上げ量を調整し、昼間の余剰電力を使ってお湯を沸き増しする「昼間沸き上げ機能」を持つものがあります。
これにより、売電するよりも自家消費した方が経済的メリットが大きい場合に、電気を無駄なくお湯という形で蓄えることができるのです。
蓄電池の導入でさらに進化
太陽光発電とオール電化の組み合わせに、さらに「家庭用蓄電池」を加えることで、エネルギーの自給自足に近づき、災害への備えも万全になります。
蓄電池を導入すれば、昼間に太陽光で発電した電気のうち、余った分を蓄えておくことができます。
そして、発電できない夜間や天候の悪い日に、その蓄えた電気を使うことで、電力会社から電気を買う量を極限まで減らすことが可能になります。
夜間の安い電気を買う必要すらなくなるかもしれません。
また、この組み合わせは災害時にも絶大な効果を発揮します。
万が一、停電が発生しても、日中は太陽光で発電した電気を、夜間は蓄電池に貯めた電気を使うことで、普段に近い生活を維持することができます。
オール電化の「停電に弱い」という弱点を、完全に克服することができるのです。
もちろん、太陽光発電システムや蓄電池の導入には、高額な初期費用がかかります。
しかし、国や自治体の補助金制度も充実しており、長期的に見れば、光熱費の削減や売電収入によって初期投資を回収することも十分に可能です。
オール電化を検討する際には、将来的なステップアップとして、太陽光発電や蓄電池との連携も視野に入れて計画を立てることを強くお勧めします。
結論としてオール電化とガスどっちがお得か
これまで、初期費用、ランニングコスト、安全性、災害時の対応、そしてライフスタイルとの適合性など、様々な角度からオール電化とガス併用を比較してきました。
では、最終的な結論として、オール電化とガスどっちがお得なのでしょうか。
その答えは、「あなたの家庭の状況によって異なる」というのが、最も誠実な回答になります。
どちらか一方が絶対的に優れているというわけではなく、それぞれの家庭が何を重視するかによって、最適な選択は変わってきます。
ここでは、これまでの議論を総括し、あなたが最適な選択をするための判断基準を改めて整理します。
オール電化を選ぶべき家庭のチェックリスト
以下のような条件に多く当てはまる家庭は、オール電化にすることで経済的なメリットや生活の快適性を享受できる可能性が高いです。
- お住まいの地域がプロパンガスエリアである
- 日中は仕事や学校で不在がちで、夜型の生活を送っている
- 火を使わない安全性やキッチンの清掃性を重視する
- 太陽光発電システムの導入を検討している、または既に設置している
- 光熱費の支払いを一本化してシンプルに管理したい
- 初期費用は高くても、長期的なランニングコストで回収したいと考えている
特に、プロパンガスを利用している場合は、オール電化への切り替えが最も効果的な光熱費削減策の一つとなります。
ガス併用を選ぶべき家庭のチェックリスト
一方で、以下のような条件に当てはまる場合は、従来のガス併用が適している、あるいは現状維持が賢明な判断となる可能性があります。
- お住まいの地域が都市ガスエリアで、ガス料金が比較的安い
- 在宅ワークや専業主婦(主夫)などで、日中の在宅時間が長い
- ガスコンロの強い火力での調理にこだわりがある
- 初期費用をできるだけ安く抑えたい
- 停電時にも調理などの一部機能が使える安心感を重視する
- 家族の入浴時間が不規則で、お湯切れの心配をしたくない
都市ガスエリアで、かつ日中の活動量が多い家庭では、ガス併用の方がトータルの光熱費を安く抑えられるケースも少なくありません。
最終判断の前に
最終的な決断を下す前には、必ず複数の施工会社やエネルギー会社から見積もりを取り、ご自身の家庭の光熱費の使用状況に基づいた具体的なシミュレーションを依頼することが重要です。
「我が家の場合、オール電化にすると月々いくら安くなるのか」「ガス併用を続ける場合、新しい料金プランでどれくらい変わるのか」といった、具体的な数字を比較検討することで、より納得感のある選択ができるようになります。
オール電化とガスどっちがお得かという問いに唯一の正解はありません。
本記事で提供した情報を参考に、ご自身の価値観とライフスタイルに最も合ったエネルギーの形を見つけ出してください。
本日のまとめ
- オール電化とガスどっちがお得かは家庭の状況による
- 初期費用は一般的にガス併用の方が安い
- オール電化はエコキュートとIHの導入費用が高め
- ランニングコストは深夜電力を活用できるオール電化が有利な場合が多い
- プロパンガスエリアではオール電化の経済的メリットが非常に大きい
- 都市ガスエリアではガス併用との光熱費の差は縮まる
- オール電化は基本料金が一本化できるのがメリット
- 安全性では火を使わないIHクッキングヒーターに分がある
- 災害時のインフラ復旧は電気が最も早い傾向にある
- 停電中はオール電化の全機能が停止するのが最大のデメリット
- エコキュートは湯切れのリスクや設置スペースの注意が必要
- ガス併用は調理の火力や湯切れのない安心感が魅力
- 日中在宅型のライフスタイルはガス併用向き
- 夜間中心型のライフスタイルはオール電化向き
- 太陽光発電とオール電化は非常に相性が良い組み合わせ

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |
●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇
勝手口がない家と風水|運気を上げる間取りと対策を徹底解説
檜風呂にリフォームする費用と後悔しないための全知識【完全版】
●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇

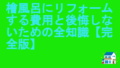

コメント