こんにちは、サイト管理人です
一生に一度の大きな買い物であるマイホームの購入は、多くの人にとって夢であり、同時に大きな挑戦でもあります。
特に、自分たちの理想を形にできる注文住宅は魅力的ですが、何から手をつけて良いのか分からず、不安を感じる方も少なくないでしょう。
新築を建てる時の流れは、実は非常に多くのステップに分かれています。
例えば、全体の期間はどれくらいかかるのか、総額の費用はどの程度見込めば良いのか、そして重要な土地探しはどう進めるべきか、など考えなければならないことは山積みです。
さらに、信頼できるハウスメーカー選びや、複雑な住宅ローンの手続き、後悔しないためのやることリストの作成も欠かせません。
この複雑なプロセスの中で、一つの選択が後々の満足度を大きく左右するため、失敗は避けたいものです。
この記事では、そんな新築の家づくりに関するあらゆる疑問や不安を解消するために、新築を建てる時の流れを計画段階から完成まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。
具体的な流れ図を示しながら、注文住宅を建てる上でのポイントや、専門家への相談のタイミングまで、網羅的に情報をお届けします。
この記事を読めば、家づくりの全体像が明確になり、自信を持って夢のマイホーム実現への第一歩を踏み出せるようになるでしょう。
◆このサイトでわかる事◆
- 新築を建てる時の全体的な流れと各ステップ
- 家づくりにかかる具体的な期間の目安
- 土地探しからハウスメーカー選びまでの重要ポイント
- 総費用と住宅ローンの賢い計画の立て方
- 注文住宅を建てる上でのメリットと注意点
- 家づくりでよくある失敗例とその回避策
- 各工程でやるべきことのチェックリスト
-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |
失敗しない新築を建てる時の流れ【計画編】
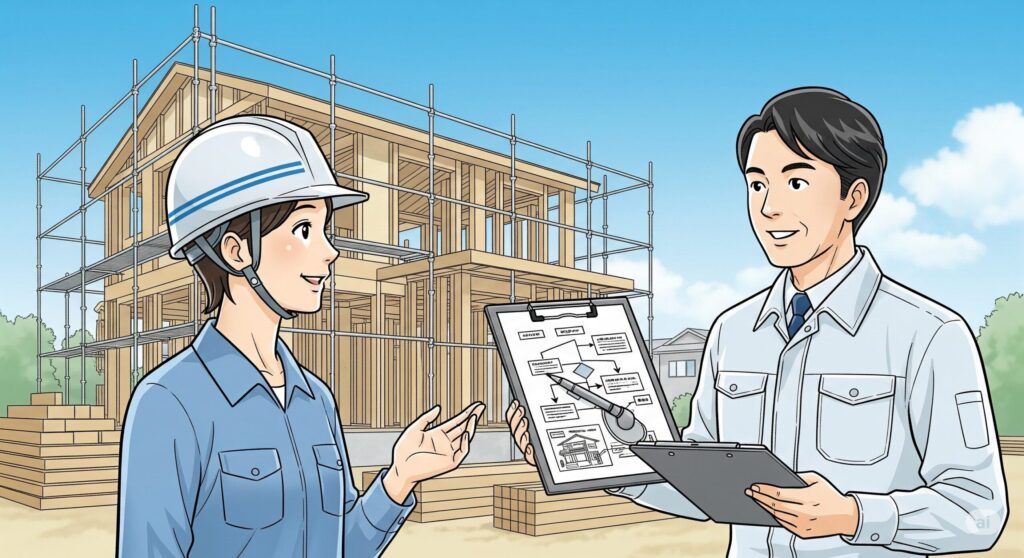
◆この章のポイント◆
- まずは「やることリスト」で全体像を把握する
- 家づくり全体の「期間」はどれくらい必要か
- 後悔しないための「土地探し」の進め方
- 理想の家を実現する「ハウスメーカー選び」
- こだわりを形にする「注文住宅」のポイント
まずは「やることリスト」で全体像を把握する
新築の家を建てるという壮大なプロジェクトを成功させるためには、まず全体像を正確に把握することが不可欠です。
そのために最も有効な手段が、「やることリスト」の作成に他なりません。
このリストを作ることで、複雑に見える家づくりのプロセスが整理され、今何をすべきか、次に何が待っているのかが一目瞭然となります。
漠然とした不安が具体的なタスクに変わることで、精神的な負担も軽減されるでしょう。
やることリストは、家づくりの羅針盤であり、計画的に、そして効率的に夢のマイホームを実現するための第一歩と言えるのです。
やることリストの作成手順
リスト作成は、家づくりの流れを時系列に沿って書き出すことから始めます。
大きく分けて「計画段階」「契約・設計段階」「工事段階」「完成・入居段階」の4つのフェーズで考えると整理しやすくなります。
契約・設計段階には、土地探し、ハウスメーカーや工務店の選定、プランの打ち合わせ、各種契約、住宅ローンの申し込みなどが該当するでしょう。
工事段階では、地鎮祭や上棟式といったイベント、工事の進捗確認、追加変更の検討などが主なタスクです。
そして最後の完成・入居段階では、完成立ち会い、引き渡し、登記手続き、引っ越し、近隣への挨拶などがリストアップされます。
リスト活用のメリット
やることリストを作成するメリットは計り知れません。
第一に、タスクの抜け漏れを防ぐことができます。
家づくりには無数の手続きや決定事項があり、記憶だけに頼るのは危険です。
リストがあれば、一つひとつ着実にクリアしていくことが可能です。
第二に、家族間での情報共有がスムーズになります。
家づくりは家族全員の協力が不可欠です。
リストを共有することで、誰が何を担当するのか、全体の進捗はどうかといった情報を全員が同じレベルで理解でき、協力体制を築きやすくなります。
ゴールまでの道のりが可視化されることで、見通しが立ち、漠然とした不安から解放されるでしょう。
「ここまで進んだ」という達成感も、次のステップへのモチベーションにつながります。
このように、最初に少し時間をかけて詳細な「やることリスト」を作成することが、結果的に新築を建てる時の流れをスムーズにし、後悔のない家づくりを実現する鍵となるのです。
家づくり全体の「期間」はどれくらい必要か
新築の家を建てると決めたとき、多くの人が気になるのが「一体どれくらいの期間がかかるのか」という点でしょう。
入居したい時期から逆算してスケジュールを立てるためにも、全体の期間を把握しておくことは非常に重要です。
一般的に、情報収集を開始してから新居に入居するまでの期間は、およそ1年から1年半程度が目安とされています。
もちろん、これは土地がすでにある場合や、建物の仕様、ハウスメーカーの状況などによって大きく変動します。
特に注文住宅の場合は、設計の打ち合わせに時間をかけることが多いため、建売住宅に比べて長くなる傾向にあります。
この期間を理解し、余裕を持った計画を立てることが、焦らずに理想の家づくりを進めるための秘訣です。
各ステップにかかる期間の目安
家づくりの期間は、いくつかのフェーズに分けて考えることができます。
それぞれのフェーズでかかるおおよつの期間を把握しておきましょう。
- 情報収集・計画期間(2〜6ヶ月): 家族でどんな家に住みたいかを話し合い、インターネットや住宅展示場で情報を集める時期です。予算計画や資金の準備もこの期間に行います。
- 土地探し・会社選び(3〜12ヶ月): 土地がない場合は、家づくりのプロセスで最も時間がかかるとも言われる土地探しから始まります。同時に、建築を依頼するハウスメーカーや工務店を選定し、比較検討します。
- 設計・契約期間(3〜6ヶ月): 建築会社と具体的な間取りや設備、デザインなどの詳細を詰めていく期間です。仕様が固まったら、工事請負契約を結び、住宅ローンの本審査申し込みも進めます。
- 建築工事期間(4〜6ヶ月): 建築確認申請の許可が下りたら、いよいよ着工です。基礎工事から始まり、上棟、内装・外装工事と進んでいきます。
- 完成・引き渡し(1ヶ月): 建物が完成したら、施主立ち会いのもとで最終チェックを行います。問題がなければ残金を支払い、鍵の引き渡し、各種登記手続きを経て入居となります。
これらの期間はあくまで目安です。
例えば、土地探しが難航したり、設計の打ち合わせでこだわりが強かったりすると、計画期間はさらに長引く可能性があります。
期間を短縮するためのポイント
少しでもスムーズに家づくりを進めたい場合、いくつかのポイントがあります。
これにより、設計の打ち合わせ段階での迷いが減り、意思決定が迅速になります。
また、信頼できる担当者を見つけることも大切です。
経験豊富な担当者であれば、様々な提案をしてくれたり、手続きを円滑に進めてくれたりするため、結果的に時間の節約に繋がります。
しかし、焦りは禁物です。
一生に一度の大きな買い物ですから、必要な期間をしっかりと確保し、一つひとつのステップを丁寧に進めることが、最終的に満足度の高い家づくりに繋がるのです。
後悔しないための「土地探し」の進め方
新築を建てる時の流れにおいて、「土地探し」は家の満足度を左右する最も重要な要素の一つと言っても過言ではありません。
どんなに素晴らしい家を建てても、その土台となる土地の環境が悪ければ、快適な生活は望めません。
後悔しない土地探しのためには、ただやみくもに探すのではなく、戦略的に進める必要があります。
立地、周辺環境、法的な規制、そして予算など、多角的な視点から物件を評価し、自分たちのライフスタイルに本当に合った土地を見つけ出すことが求められます。
このプロセスを丁寧に行うことが、理想の住まいづくりの礎を築くことになるのです。
土地探しを始める前の準備
本格的に土地を探し始める前に、まずは準備を整えることが成功の鍵を握ります。
第一に行うべきは、家族全員で「どんな暮らしがしたいか」を具体的に話し合い、希望条件の優先順位を決めることです。
例えば、通勤・通学の利便性、買い物のしやすさ、公園や病院など周辺施設の充実度、静かな環境、日当たりの良さなど、様々な要素が考えられます。
すべての希望を100%満たす土地を見つけるのは困難なため、「これだけは譲れない」という条件と、「妥協できる」条件を明確にしておくことが重要です。
次に、土地にかけられる予算を明確にします。
この予算を先に決めておくことで、見るべき物件の範囲が絞られ、効率的に土地探しを進めることができます。
土地探しの具体的な方法と注意点
土地を探す方法は主に3つあります。
一つ目は、不動産会社のウェブサイトや店舗で探す方法です。
情報量が多く、希望エリアの相場観を掴むのに役立ちます。
二つ目は、ハウスメーカーや工務店に相談する方法です。
建築のプロの視点から、その土地に希望の家が建てられるかどうかも含めてアドバイスをもらえる「建築条件付き土地」などを紹介してもらえるメリットがあります。
三つ目は、自分たちの足で希望のエリアを歩き、「売土地」の看板を探す方法です。
意外な掘り出し物が見つかる可能性もあります。
土地を検討する際には、必ず現地に足を運び、自分の目で確認することが不可欠です。
曜日や時間帯を変えて何度も訪れることで、平日と休日の雰囲気の違い、朝と夜の交通量や騒音、日当たりなどを体感できます。
また、ハザードマップで災害リスクを確認したり、都市計画法などの法規制について役所で調査したりすることも忘れてはなりません。
焦らず、じっくりと情報を集め、多角的に検討することが、後悔しない土地選びに繋がるのです。
理想の家を実現する「ハウスメーカー選び」
新築を建てる時の流れの中で、土地探しと並行して進めるべき重要なステップが「ハウスメーカー選び」です。
どの会社をパートナーに選ぶかによって、家の性能、デザイン、コスト、そして家づくりのプロセス全体の満足度が大きく変わってきます。
ハウスメーカーと一口に言っても、全国展開する大手から、地域に密着した工務店、設計の自由度が高い設計事務所まで、その特徴は様々です。
自分たちの価値観や建てたい家のイメージに合った会社を見極めることが、理想の家を実現するための絶対条件と言えるでしょう。
そのためには、各社の特徴をよく理解し、慎重に比較検討する必要があります。
ハウスメーカーの種類と特徴
まずは、どのような種類の建築会社があるのかを知ることから始めましょう。
大きく分けると以下の3つに分類できます。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 大手ハウスメーカー | 全国規模で事業を展開。ブランド力があり、商品ラインナップが豊富。 | 品質が安定しており、工期が比較的短い。倒産リスクが低く、保証やアフターサービスが手厚い。 | 広告宣伝費などが価格に反映され、坪単価は高め。規格化されている部分が多く、設計の自由度はやや低い。 |
| 地域密着型の工務店 | 特定のエリアで活動。社長や職人の顔が見え、地域特性を熟知している。 | 比較的コストを抑えやすい。仕様やデザインの自由度が高く、柔軟な対応が期待できる。 | 会社の規模が小さく、技術力や経営状態に差がある。保証内容は会社ごとに確認が必要。 |
| 設計事務所(建築家) | 施主の要望に合わせてゼロから家を設計。デザイン性を重視する場合に選ばれる。 | 唯一無二の独創的な家づくりが可能。複雑な土地や厳しい条件にも対応しやすい。 | 設計料が別途必要。設計から完成までの期間が長くなる傾向がある。 |
これらの特徴を理解した上で、自分たちが何を重視するのか(コスト、デザイン、安心感など)を明確にし、候補を絞り込んでいくことが大切です。
良いハウスメーカーを見極めるポイント
いくつかの候補が挙がったら、次はいかにして「良い会社」を見極めるかです。
そのためのアクションとして、住宅展示場やモデルハウス、完成見学会に足を運ぶことは欠かせません。
カタログだけでは分からない空間の広がりや素材の質感、空気感を肌で感じることができます。
家づくりは数ヶ月から一年以上に及ぶ長丁場です。
こちらの要望を真摯に聞いてくれるか、専門家として的確なアドバイスをくれるか、そして何より信頼できる人柄かを見極めましょう。
また、複数の会社から同じ条件で相見積もりを取り、提案されたプランや見積もり内容を比較検討することも必須です。
単に価格の安さだけでなく、なぜその価格になるのか、どのような仕様が含まれているのかを詳細に確認し、納得できる説明をしてくれる会社を選ぶべきです。
これらのステップを丁寧に踏むことで、安心して家づくりを任せられる最高のパートナーを見つけることができるでしょう。
こだわりを形にする「注文住宅」のポイント
新築を建てる方法として多くの人が憧れるのが「注文住宅」です。
注文住宅の最大の魅力は、なんといってもその自由度の高さにあります。
間取りやデザイン、キッチンやお風呂といった設備、壁紙や床材などの内装材に至るまで、自分たちのこだわりやライフスタイルに合わせて一つひとつ選ぶことができます。
まさに「世界に一つだけの我が家」を実現できるのが注文住宅なのです。
しかし、その自由度の高さゆえに、決めるべきことが多く、計画的に進めないと予算オーバーになったり、完成してから「こうすればよかった」と後悔したりする可能性も秘めています。
こだわりをしっかりと形にするためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。
注文住宅で実現できること
注文住宅では、既製品である建売住宅では叶えられない、様々なこだわりを反映させることが可能です。
例えば、以下のような要望も実現の可能性があります。
- 趣味を楽しむ空間: 音楽好きなら防音室、車やバイクが好きならビルトインガレージ、読書好きなら壁一面の本棚がある書斎など、趣味に特化した部屋を作ることができます。
- 家事動線を考えた間取り: キッチンから洗面所、物干しスペースまでを一直線につなぎ、家事の負担を軽減する効率的な動線を設計できます。
- 将来を見据えた設計: 子どもの成長に合わせて部屋を間仕切りできるようにしたり、老後を考えてバリアフリー設計にしたりと、ライフステージの変化に対応できる家にすることも可能です。
- デザインや素材へのこだわり: 自然素材をふんだんに使った温かみのある空間や、スタイリッシュでモダンなデザインなど、内外装の細部に至るまで自分たちの好みを追求できます。
これらのこだわりを実現するためには、建築会社との打ち合わせで、自分たちの希望を的確に伝える能力が求められます。
こだわりを上手に伝えるコツ
理想の家を形にするためには、頭の中にあるイメージを設計担当者と共有することが不可欠です。
そのためのコツをいくつか紹介します。
その際、「なぜそうしたいのか」という理由や背景も合わせて伝えると、担当者は意図を汲み取りやすくなり、より良い提案に繋がることがあります。
例えば、「リビングを広くしたい」だけでなく、「家族が自然と集まり、それぞれが好きなことをしていても気配を感じられる空間にしたいから」と伝えることで、単に広いだけでなく、居心地の良い空間設計を考えてくれるでしょう。
また、言葉だけでは伝わりにくいデザインのイメージは、雑誌の切り抜きやインターネットで見つけた画像をスクラップブックなどにまとめて見せると効果的です。
そして、予算には限りがあることを忘れてはいけません。
すべての要望を盛り込むと、あっという間に予算オーバーになってしまいます。
こだわりたい部分にはしっかりと予算をかけ、他でコストを調整するなど、メリハリをつけることが重要です。
どこに一番お金をかけたいのか、優先順位を明確にしておくことが、満足度の高い注文住宅を実現するための最後のポイントです。
新築を建てる時の流れで押さえるべきこと【実行編】
◆この章のポイント◆
- 無理のない「費用」計画と資金の準備
- 知っておきたい「住宅ローン」の基礎知識
- 不安を解消する専門家への「相談」の重要性
- よくある「失敗」例から学ぶ家づくりの教訓
- 「流れ図」で工事の進捗をしっかり確認
- 【まとめ】理想の家づくりへ!新築を建てる時の流れを再確認
無理のない「費用」計画と資金の準備
新築を建てる時の流れにおいて、計画段階と並行して最も重要になるのが「費用」に関する計画、すなわち資金計画です。
家づくりには、建物の建築費だけでなく、土地の購入費、税金や手数料といった諸費用など、様々なお金が必要になります。
一体総額でいくらかかるのかを把握し、自己資金と住宅ローンをどのように組み合わせるか、無理のない返済計画を立てられるかが、家づくりを成功させ、その後の生活を豊かにするための鍵となります。
どんぶり勘定で進めてしまうと、後々予算が足りなくなったり、ローンの返済に追われる苦しい生活になったりする可能性があります。
そうならないためにも、費用の内訳を正しく理解し、綿密な資金計画を立てることが不可欠です。
家づくりにかかる費用の内訳
新築にかかる費用は、大きく分けて「本体工事費」「別途工事費」「諸費用」の3つに分類されます。
これに加えて、土地を持っていない場合は「土地購入費」が必要になります。
- 土地購入費: 土地そのものの代金に加え、仲介手数料、登記費用、不動産取得税などがかかります。
- 本体工事費: 建物そのものを建てるための費用で、総費用の約75%〜80%を占めます。基礎工事、構造躯体、屋根、外壁、内装、基本的な設備などが含まれます。
- 別途工事費: 本体工事費には含まれない追加の工事費用で、総費用の約15%〜20%が目安です。例えば、古い家の解体費用、地盤改良工事、外構(駐車場、フェンス、庭など)、給排水やガスの引き込み工事、エアコンやカーテンの設置費用などがこれにあたります。
- 諸費用: 建築費以外にかかる手数料や税金などで、総費用の約5%〜10%を見ておく必要があります。具体的には、住宅ローンの手数料や保証料、火災保険料、登記費用、印紙税、不動産取得税、固定資産税の清算金などが含まれます。
ハウスメーカーの見積もりでは「本体工事費」のみが大きく提示されることが多いですが、
賢い資金計画の立て方
資金計画を立てる際の基本的なステップは、「総予算の算出」「自己資金の確認」「借入額の決定」です。
まず、現在の年収や家計の状況から、毎月無理なく返済できる住宅ローンの金額を算出します。
一般的に、年間の返済額が年収の25%以内(返済負担率25%)に収まるのが一つの目安とされています。
この毎月返済額から、借り入れ可能な総額を逆算します。
次に、自己資金として用意できる金額を確定させます。
これは預貯金から捻出しますが、病気や失業など万が一の事態に備えた生活防衛資金(生活費の半年〜1年分)や、子どもの教育費などは手を付けずに、あくまで余裕資金の中から考えることが重要です。
親からの資金援助(贈与)が見込める場合は、それも自己資金に含めますが、贈与税の非課税枠などを事前に確認しておきましょう。
この総予算の範囲内で、土地や建物の費用配分を決めていくことが、無理のない家づくりを実現する大原則です。
計画段階でファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、客観的なアドバイスをもらうのも非常に有効な手段です。
知っておきたい「住宅ローン」の基礎知識
ほとんどの人にとって、新築の家を建てる際の最大のパートナーとなるのが「住宅ローン」です。
数千万円という大きな金額を、長期間にわたって返済していくことになるため、その仕組みを正しく理解し、自分に合った商品を選ぶことが極めて重要になります。
金利のタイプ、返済方法、保証料など、住宅ローンには専門的な用語が多く、難しく感じてしまうかもしれません。
しかし、基本的な知識を身につけることで、金融機関の担当者やハウスメーカーの営業担当者の話をより深く理解できるようになり、より有利な条件で借り入れをすることが可能になります。
新築を建てる時の流れの中でも、特に慎重な判断が求められるステップです。
住宅ローンの種類と金利タイプ
住宅ローンは、提供する金融機関によっていくつかの種類に分けられますが、大きくは「公的ローン」と「民間ローン」に大別されます。
代表的なものとして、長期固定金利の「フラット35」や、各銀行が提供する独自のローンがあります。
そして、最も重要な選択が「金利タイプ」です。
金利タイプは主に以下の3つがあり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。
| 金利タイプ | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 変動金利型 | 半年に一度など、定期的に金利が見直されるタイプ。 | 一般的に当初の金利が固定金利より低く設定されているため、当初の返済額を抑えられる。 | 将来、市場金利が上昇すると返済額が増えるリスクがある。 |
| 全期間固定金利型 | 借り入れから完済まで金利が変わらないタイプ。フラット35が代表的。 | 返済額がずっと変わらないため、長期的な資金計画が立てやすい。金利上昇のリスクがない。 | 変動金利に比べて、当初の金利設定が高めになる傾向がある。 |
| 固定金利期間選択型 | 3年、5年、10年など、一定期間だけ金利が固定され、期間終了後に変動金利か固定金利かを再度選択するタイプ。 | 固定期間中は返済額が変わらない安心感と、変動金利の低さを両取りできる可能性がある。 | 固定期間終了後の金利がどうなるか不透明。金利が上昇していた場合、返済額が大幅に増える可能性がある。 |
住宅ローンの審査と手続きの流れ
住宅ローンを利用するためには、金融機関による審査を通過する必要があります。
審査は通常、「事前審査(仮審査)」と「本審査」の2段階で行われます。
事前審査は、ハウスメーカーと契約する前や、土地の購入申し込みをする段階で受けるのが一般的です。
年収や勤務先、勤続年数、自己資金の額、他に借り入れがないか(信用情報)などを基に、おおよその借入可能額を判断してもらいます。
この審査に通ることで、その後の計画が立てやすくなります。
本審査は、工事請負契約や売買契約を結んだ後に申し込みます。
事前審査よりも詳細な書類(物件の資料、公的な収入証明書など)が必要となり、審査もより厳格に行われます。
注文住宅の場合、土地の購入時、着工時、上棟時、完成時など、複数回に分けて融資が実行される「つなぎ融資」が必要になるケースが多いことも覚えておきましょう。
複数の金融機関のローン商品を比較検討し、自分にとって最も有利な条件のものを選ぶことが、賢い家づくりのポイントです。
不安を解消する専門家への「相談」の重要性
新築を建てる時の流れは、数多くの決断の連続です。
土地選び、資金計画、住宅ローンの選定、ハウスメーカーの比較、間取りの設計など、それぞれの分野で専門的な知識が求められます。
自分たちだけで全ての情報を収集し、最適な判断を下すのは非常に困難であり、大きな不安やストレスを伴うものです。
そんな時に力強い味方となってくれるのが、各分野の「専門家」の存在です。
適切なタイミングで専門家に相談することは、不安を解消し、間違いのない選択をするために不可欠です。
自分たちの判断に客観的な視点や専門的な知見を加えることで、より納得感のある家づくりを進めることができます。
誰に、何を相談すれば良いのか?
家づくりにおいては、様々な専門家が関わります。
それぞれの専門分野を理解し、相談すべき内容に応じて適切な相手を選ぶことが重要です。
- ファイナンシャルプランナー(FP): 主に「お金」に関する相談の専門家です。無理のない予算の立て方、長期的な視点での資金計画、最適な住宅ローンの選び方、生命保険の見直しなど、家計全体のバランスを考慮したアドバイスを提供してくれます。家づくりを考え始めた初期段階で相談するのが最も効果的です。
- ハウスメーカー・工務店の営業担当者: 家づくりの実務に関する最も身近な相談相手です。自社の商品の特徴、間取りや設計の提案、概算費用の見積もり、土地探しに関する情報提供など、具体的な家づくりのプロセスについて相談できます。
- 設計士・建築家: デザインや間取り、使い勝手など「設計」に関する専門家です。自分たちのライフスタイルやこだわりを伝え、それを形にするための具体的なプランを提案してもらえます。特にデザイン性の高い家や、変形地など難しい条件の土地に建てる場合に頼りになります。
- 不動産会社の担当者: 「土地」に関する専門家です。希望エリアの相場情報、法規制、周辺環境など、土地探しに関するあらゆる情報を提供してくれます。良い土地情報をいち早く手に入れるためにも、良好な関係を築いておくことが大切です。
- 司法書士・土地家屋調査士: 土地や建物の「登記」に関する専門家です。不動産の権利関係を法的に確定させるための手続きを代行してくれます。通常はハウスメーカーや金融機関から紹介されます。
専門家へ相談する際の心構え
専門家に相談する際には、いくつか心構えがあります。
まず、自分たちの要望や現状をできるだけ具体的に、そして正直に伝えることです。
事前に質問したいことをリストアップしておくと、相談時間を有効に活用できます。
次に、一人の専門家の意見を鵜呑みにしないことです。
特にハウスメーカーの担当者などは、自社に有利な情報を中心に話す可能性があります。
可能であれば、複数の専門家から意見を聞き、多角的な視点で物事を判断することが望ましいでしょう。
最後に、相談は無料の場合もあれば、有料の場合もあります。
特に独立系のファイナンシャルプランナーや建築家への相談は有料であることが多いですが、その費用を払ってでも得る価値のあるアドバイスはたくさんあります。
よくある「失敗」例から学ぶ家づくりの教訓
夢と希望に満ち溢れた新築の家づくりですが、残念ながら、完成後に「こうすればよかった」「思っていたのと違う」といった後悔の声が聞かれることも少なくありません。
新築を建てる時の流れには、多くの落とし穴が潜んでいます。
しかし、先輩たちがどのような点で失敗したのかを事前に知っておくことで、同じ過ちを繰り返すリスクを大幅に減らすことができます。
失敗例は、最高の反面教師です。
ここでは、家づくりでよくある失敗パターンをいくつかご紹介し、そこから得られる教訓を学びます。
これらの知識を身につけることで、より満足度の高い家づくりを目指しましょう。
計画・予算に関する失敗例
家づくりで最も多く、そして影響が大きいのが計画や予算に関する失敗です。
- 予算オーバー: 「あれもこれも」と夢を詰め込みすぎ、打ち合わせの段階でオプションを追加し続けた結果、最終的な請求額が当初の予算を大幅に超えてしまったケースです。特に「別途工事費」や「諸費用」の見積もりが甘いと陥りがちです。教訓は、
- 無謀な住宅ローン: 「少し背伸びをすれば大丈夫だろう」と、現在の収入に対してギリギリの住宅ローンを組んでしまい、教育費の増加や収入の減少によって返済が苦しくなるケースです。教訓は、返済負担率は余裕を持って設定し、将来のライフイベントも考慮した長期的な資金計画を立てることです。
- スケジュール遅延: 土地探しや設計の打ち合わせが長引き、予定していた入居時期に間に合わなくなるケースです。子どもの入学時期などが決まっている場合は特に問題になります。教訓は、各工程の期間を現実的に見積もり、予備期間を含んだ余裕のあるスケジュールを組むことです。
間取り・設計に関する失敗例
日々の生活の快適さに直結するのが、間取りや設計に関する失敗です。
- コンセントの不足・位置の不便さ: 「いざ住んでみたら、掃除機をかけるのに延長コードが必要」「ここにコンセントがあればスマホを充電しながら寛げるのに」といった失敗は非常によく聞かれます。教訓は、設計段階で家具の配置を具体的にシミュレーションし、生活導線を考えながら、コンセントの位置と数を決める
- 収納の不足: 「デザインを優先して収納スペースを削ったら、物が溢れて部屋が片付かない」という失敗です。特に、玄関のシューズクロークやキッチンのパントリー、季節物をしまうための納戸などは見落とされがちです。教訓は、現在の持ち物の量を把握し、将来増えることも想定して十分な収納量を確保することです。
- 生活動線の悪さ: 「洗濯機から物干し場までが遠い」「帰宅時にコートをかける場所がない」など、日々のちょっとした不便さがストレスになるケースです。教訓は、朝起きてから夜寝るまでの一日の動きを想像し、家事や生活の動線がスムーズになるような間取りを考えることです。
- 日当たり・風通しの悪さ: 図面だけでは分かりにくいのが日当たりや風通しです。隣の家の影になって日中も暗かったり、窓を開けても風が通らなかったりする失敗があります。教訓は、土地を決める際に周辺環境や時間帯による日の当たり方をしっかり確認し、窓の配置を工夫することです。
これらの失敗例を自分たちの計画に照らし合わせ、一つひとつチェックしていくことが、後悔のない家づくりに繋がります。
「流れ図」で工事の進捗をしっかり確認
計画段階や設計段階が無事に終わり、いよいよ工事請負契約を結ぶと、新築を建てる時の流れは「工事段階」へと入っていきます。
ここからは、図面上の計画が、職人たちの手によって徐々に現実の形になっていく、家づくりの中でも特にエキサイティングな期間です。
しかし、施主として「あとはお任せ」というわけにはいきません。
工事が計画通りに進んでいるか、図面と違うところはないかなどを確認するためにも、工事全体の工程、すなわち「流れ図」を理解しておくことが重要です。
各工程で何が行われるのかを知っておくことで、現場監督とのコミュニケーションもスムーズになり、安心して工事の進捗を見守ることができます。
着工から完成までの主な工事工程
建物の工事は、一般的に以下のような流れで進んでいきます。
全体の流れ図を頭に入れておきましょう。
- 地鎮祭・近隣挨拶: 工事の安全を祈願する儀式です。必須ではありませんが、多くの人が行います。また、工事中は騒音などで迷惑をかけるため、着工前にハウスメーカーの担当者と一緒に近隣へ挨拶回りをしておくと、その後の関係がスムーズになります。
- 地盤改良工事・基礎工事: 地盤調査の結果、地盤が弱いと判断された場合は改良工事を行います。その後、家の土台となる最も重要な部分、コンクリートの基礎を造ります。
- 建て方・上棟: 基礎の上に、柱や梁といった構造躯体をクレーンなどを使って一気に組み上げていきます。家の骨格が姿を現す、非常にダイナミックな工程です。このタイミングで「上棟式」を行うこともあります。
- 屋根・外壁工事: 構造躯体が雨に濡れないよう、まずは屋根の工事を行います。その後、サッシ(窓)の取り付け、外壁材の施工へと進みます。
- 内部造作工事: 天井、壁、床の下地作り、断熱材の充填、フローリング貼り、間仕切り壁の設置など、家の内部を造り込んでいきます。電気配線や給排水管の工事もこの段階で行われます。
- 内装・設備工事: クロス(壁紙)を貼ったり、塗装をしたりといった内装の仕上げ工事です。同時に、キッチン、トイレ、お風呂などの住宅設備の設置も行われます。
- 外構工事: 建物がほぼ完成した後、駐車場やアプローチ、フェンス、庭などの建物の外回りの工事を行います。
- 竣工(完成): 全ての工事が完了した状態です。
施主として工事中にやるべきこと
工事期間中、施主として積極的に関わることで、トラブルを防ぎ、満足度を高めることができます。
現場に行くことで、工事の進捗状況を自分の目で確認できるだけでなく、職人さんたちのモチベーションアップにも繋がります。
差し入れなどをして、良好なコミュニケーションを築くのも良いでしょう。
現場で疑問に思ったことや、図面と違うのではないかと感じたことがあれば、その場で職人さんに直接質問するのではなく、
これが現場の指揮系統を乱さないための重要なマナーです。
また、工事が進むと壁紙などで隠れてしまうコンセントの位置や、棚の高さなど、最終確認を求められる場面もあります。
図面だけでは分かりにくかった部分を、実際の空間で確認できる最後のチャンスです。
快く、そして丁寧に対応してくれる現場は、良い家づくりをしている証拠とも言えるでしょう。
【まとめ】理想の家づくりへ!新築を建てる時の流れを再確認
これまで、新築を建てる時の流れを計画段階から実行段階まで、各ステップに分けて詳しく解説してきました。
家づくりは、多くの人にとって一生に一度の大きなプロジェクトです。
たくさんの時間と労力、そしてもちろん費用がかかりますが、そのプロセス一つひとつが、未来の快適な暮らしを創り上げるための大切な要素となります。
漠然としたイメージから始まった家づくりも、やることリストの作成、期間や費用の把握、土地探し、ハウスメーカー選びといったステップを順に踏むことで、着実に形になっていきます。
また、住宅ローンの知識を身につけ、専門家への相談を上手に活用し、失敗例から教訓を学ぶことで、後悔のない選択ができるようになるでしょう。
そして、工事が始まったら流れ図を基に進捗を確認し、理想の家が完成する瞬間を待ちます。
最後に、この記事で解説してきた新築を建てる時の流れの要点をまとめます。
このまとめリストを、あなたの家づくり計画のチェックリストとして、ぜひご活用ください。
この長い道のりを楽しみながら、家族の夢が詰まった最高のマイホームを実現させましょう。
本日のまとめ
- 家づくりの第一歩は全体像を把握する「やることリスト」の作成から
- 情報収集から入居までの「期間」は約1年から1年半が目安
- 「土地探し」は希望条件の優先順位付けと現地確認が成功の鍵
- 「ハウスメーカー選び」は特徴を比較し担当者との相性を見極める
- 「注文住宅」は自由度が高い分こだわりと予算のメリハリが重要
- 「費用」は本体工事費以外に別途工事費と諸費用を含めた総額で考える
- 無理のない資金計画は自己資金と「住宅ローン」のバランスで決まる
- 住宅ローンは金利タイプの特徴を理解し自分に合ったものを選ぶ
- 不安や疑問はファイナンシャルプランナーなど専門家への「相談」で解消する
- 「失敗」例から学びコンセントの位置や収納計画は入念に
- 工事の進捗は「流れ図」で把握し現場にも足を運んで確認する
- 工事中の疑問点は現場監督を通して質問するのがマナー
- 家づくりは多くの決断の連続であり家族での情報共有が不可欠
- スケジュールには予備期間を設け余裕を持った計画を立てる
- 理想の家づくりとは新築を建てる時の流れを理解し楽しむこと
-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |
参考サイト
【注文住宅の流れ】期間や購入時の手続きを全解説!お金の流れ・注意点は? – 家づくりのとびら
ハウスメーカーで注文住宅を建てる流れ 家を建てる年間スケジュール
家づくりの流れ12ステップ!何から始めるかや期間をわかりやすく解説 | ヘーベルハウス – 旭化成
注文住宅を建てる流れと期間。土地探し・会社選びから完成までのポイント/注文住宅・土地探しマニュアル#2 – SUUMO
注文住宅で家を建てる流れ|事前準備から契約、完成後の入居まで – 持ち家計画

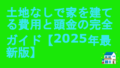
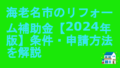
コメント