こんにちは、サイト管理人です
ご自宅のバリアフリー化や、将来の生活を見据えて「ホームエレベーターを後付けしたい」とお考えではありませんか。
年齢を重ねると階段の上り下りが負担になったり、重い荷物を運ぶのが大変になったりすることがあります。
そのような悩みを解決する手段として、ホームエレベーターは非常に有効です。
しかし、実際に設置を検討する上で最も気になるのが、ホームエレベーターの後付け費用ではないでしょうか。
一体どれくらいの価格で設置できるのか、工事費や維持費はどの程度かかるのか、具体的な相場が分からず不安に感じている方も多いかもしれません。
また、設置後のメンテナンスや税金についても気になるところです。
この記事では、ホームエレベーターの後付け費用に関するあらゆる疑問にお答えします。
費用の相場や詳細な内訳はもちろん、導入後の維持費、さらには少しでも負担を軽減するための補助金制度についても詳しく解説していきます。
2階建てや3階建ての住宅における費用の違いや、パナソニックなどの主要メーカーの価格傾向、設置にあたってのデメリットや注意点、そして後付けができないケースについても触れていきますので、ご安心ください。
この記事を最後まで読めば、ホームエレベーターの後付けに関する費用感が明確になり、ご自身の状況に合わせた計画を立てられるようになるでしょう。
階段昇降機との違いも比較しながら、最適な選択をするための一助となれば幸いです。
◆このサイトでわかる事◆
- ホームエレベーターの後付け費用の全体的な相場
- 本体価格や工事費などの詳細な内訳
- 電気代やメンテナンス料などの年間維持費
- 設置によって変動する固定資産税の詳細
- 費用負担を軽減する国や自治体の補助金制度
- メーカー別の特徴と価格傾向
- 設置に必要なスペースや後付けできない場合の条件

| 【PR】 リフォームをしようとする時に大切なのは「比較をすること」です。しかし実際には、自分で行おうとするととても大変ですし、数多く見積もりをしようとしたら心も折れてしまいます。 そこでおすすめなのがタウンライフの「一括見積り」です。日本全国の600社以上のリフォーム会社の中から、あなたに適したリフォーム会社から見積もりを受ける事ができます 見積もり比較することで、最大100万円程度節約になる事も!自宅に居ながらにして、いくつか項目を記入するだけで、簡単に完全無料で資料を取り寄せる事ができます |
あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪
ホームエレベーターの後付け費用の相場と内訳
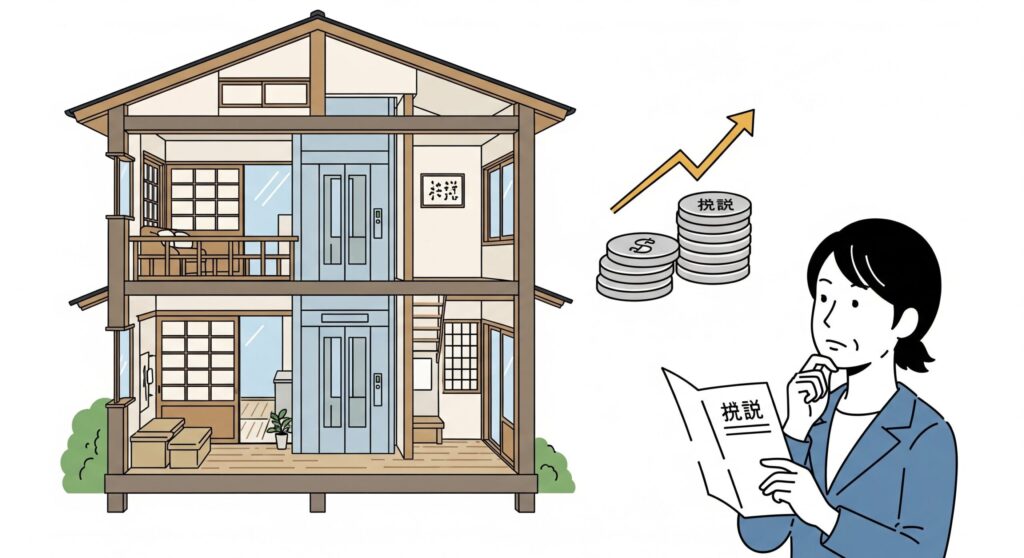
◆この章のポイント◆
- リフォームで設置する際の価格相場
- 費用の詳細な内訳を解説
- 本体価格と工事費について
- 導入後の維持費も考慮しよう
- 発生する固定資産税とは
リフォームで設置する際の価格相場
ホームエレベーターをリフォームで後付けする場合、その費用は一体どのくらいかかるのでしょうか。
多くの方が最も知りたい情報だと思いますが、結論から言うと、総額でおおよそ300万円から600万円程度が一般的な価格相場となっています。
もちろん、この金額はあくまで目安であり、いくつかの要因によって大きく変動することを理解しておく必要があります。
価格を左右する主な要因としては、「建物の構造」「階数」「エレベーターの種類」「設置方法」などが挙げられます。
例えば、建物の構造が木造か鉄骨コンクリート(RC)造かによって、工事の難易度や必要な補強が変わるため、費用に差が出ます。
一般的には、木造住宅の方が構造補強が大掛かりになりやすく、費用が高くなる傾向が見られます。
また、2階建ての住宅と3階建ての住宅では、当然ながら3階建ての方がエレベーターの移動距離が長くなり、必要な部材も増えるため、価格は上昇します。
3階建ての場合、2階建てに比べて50万円から100万円ほど高くなることが一つの目安となるでしょう。
以下の表は、建物の階数と構造による大まかな費用相場をまとめたものです。
| 建物の種類 | 価格相場(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 木造2階建て | 約350万円~550万円 | 構造補強工事が必要になる場合が多い。 |
| 鉄骨・RC造2階建て | 約300万円~500万円 | 木造に比べ補強工事が少ない傾向。 |
| 木造3階建て | 約400万円~600万円 | 階数が多くなる分、費用が上昇する。 |
| 鉄骨・RC造3階建て | 約350万円~550万円 | 建物の状態により費用は変動する。 |
この表からも分かるように、かなりの幅があることがお分かりいただけるかと思います。
これは、既存の住宅に後付けする場合、一軒一軒の家の状態が異なるためです。
例えば、エレベーターを設置するスペースを確保するために、間取りの変更や壁の撤去が必要になるケースもあります。
あるいは、建物の外側に増築して設置する方法を選択する場合もあり、その工事内容によって費用は大きく変わってきます。
したがって、正確な費用を知るためには、必ず専門の業者に現地調査を依頼し、詳細な見積もりを取ることが不可欠です。
複数の業者から相見積もりを取ることで、ご自身の住宅に合った適正な価格を把握することが可能になります。
初期費用は決して安いものではありませんが、将来の生活の質を大きく向上させる投資と考えることもできるでしょう。
費用の詳細な内訳を解説
ホームエレベーターの後付け費用が総額で300万円から600万円程度かかるとお伝えしましたが、その金額が具体的に何に使われるのか、詳細な内訳を見ていきましょう。
費用は大きく分けて「エレベーター本体価格」「設置工事費用」「諸経費」の3つに分類できます。
これらの内訳を理解することで、見積書の内容を正しく把握し、納得のいく計画を立てることができるようになります。
まず最も大きな割合を占めるのが「エレベーター本体価格」です。
これについては次の見出しで詳しく解説します。
次に「設置工事費用」です。
これも本体価格と同様に大きなウェイトを占める費用で、建物の状況によって大きく変動します。
そして、意外と見落としがちなのが「諸経費」です。
諸経費には、主に「建築確認申請費用」と「設計費用」が含まれます。
ホームエレベーターを設置することは、建築基準法上の「増築」や「大規模な修繕」にあたる場合があり、工事を始める前に役所や指定確認検査機関に「こういう工事をします」と申請し、許可を得る必要があります。
これが建築確認申請です。
この申請手続き自体に費用がかかり、また、手続きを代行してもらうための手数料も発生します。
申請費用の相場は10万円から30万円程度で、建物の規模や自治体によって異なります。
設計費用は、エレベーターをどこに、どのように設置するかの計画を立てるための費用です。
建物の強度計算なども含まれるため、安全な設置には不可欠な工程と言えるでしょう。
以下に、費用の内訳を一覧で示します。
- エレベーター本体価格:機種やサイズ、オプションによって変動。費用の大部分を占める。
- 設置工事費用:エレベーターの据付工事、建物の解体・補強工事、内装工事、電気工事など。
- 諸経費:建築確認申請費用、設計費用、構造計算費用など。
これらの費用は、見積書では「一式」としてまとめられていることもありますが、可能であれば詳細な内訳を提示してもらうことをお勧めします。
何にどれくらいの費用がかかっているのかを明確にすることで、費用の妥当性を判断しやすくなりますし、予算に応じたプランの調整もしやすくなるからです。
例えば、内装の仕上げ材をグレードダウンすることで費用を抑えるといった相談も可能になるかもしれません。
後から「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、費用の内訳をしっかりと確認することが大切です。
本体価格と工事費について
ホームエレベーターの後付け費用の中でも、特に大きな割合を占めるのが「本体価格」と「工事費」です。
この2つの要素について、さらに詳しく掘り下げていきましょう。
エレベーター本体価格
まず、エレベーターの本体価格ですが、これはメーカーや機種、仕様によって大きく異なります。
一般的に、本体価格の目安は250万円から450万円程度とされています。
価格を決定する主な要因は以下の通りです。
- 定員・サイズ:建築基準法でホームエレベーターの定員は最大3名までと定められています。一般的には2人乗りと3人乗りのモデルがあり、3人乗りの方がサイズが大きく、価格も高くなります。車椅子での利用を想定する場合は、3人乗りが必須となるでしょう。
- 駆動方式:主流なのは「ロープ式」と「油圧式」です。ロープ式は比較的コンパクトで省エネ性能に優れていますが、油圧式に比べて本体価格がやや高い傾向があります。一方、油圧式は乗り心地が滑らかという特徴がありますが、定期的なオイル交換が必要です。
- 階数・停止階数:2階建て用よりも3階建て用、4階建て用と階数が多くなるほど価格は上がります。また、同じ3階建てでも、全ての階に停止する仕様と、1階と3階のみに停止する仕様では、後者の方が安くなる場合があります。
- オプション:ドアの材質や色、手すりのデザイン、防犯カメラ、ナノイーなどの空気清浄機能、緊急地震速報対応など、様々なオプションがあります。オプションを追加すれば、その分価格は上昇します。
どの機能を重視するか、ライフスタイルに合わせて慎重に選ぶことが重要です。
設置工事費用
次に、設置工事費用です。
これはエレベーターを家に据え付けるための工事全般にかかる費用で、50万円から150万円以上と、建物の状況によって最も変動が大きい部分です。
工事費の主な内訳は以下のようになります。
- 解体・開口工事:エレベーターが通る昇降路を作るために、各階の床や壁、天井などを解体し、穴を開ける工事です。
- 構造補強工事:床や壁に穴を開けることで建物の強度が低下するため、それを補うために柱や梁を追加する工事です。特に木造住宅では重要な工事となります。
- エレベーター据付工事:昇降路にレールや本体を設置する工事です。
- 内装仕上げ工事:エレベーター周辺の壁や床をきれいに仕上げる工事です。クロス貼りやフローリング工事などが含まれます。
- 電気工事:エレベーターを動かすための電源を確保する工事です。専用のブレーカーを設置する必要があります。
これらの工事は、エレベーターを家の内部に設置するのか、外壁に沿って増築する形で設置するのかによっても内容が大きく変わります。
家の内部、例えば押し入れやクローゼットを改造して設置する場合は、既存の間取りへの影響が大きくなります。
一方、外付けの場合は居住スペースを削らずに済みますが、建物の外観が変わり、基礎工事なども必要になるため費用が高くなる可能性があります。
このように、本体価格と工事費は密接に関連しており、トータルでいくらかかるのかを正確に把握することが、ホームエレベーターの後付け費用を考える上で最も大切なポイントと言えるでしょう。
導入後の維持費も考慮しよう
ホームエレベーターの設置を考える際、初期費用である本体価格や工事費に目が行きがちですが、忘れてはならないのが導入後の「維持費」、いわゆるランニングコストです。
車にガソリン代や車検代がかかるように、ホームエレベーターも長く安全に使い続けるためには継続的な費用が発生します。
この維持費を計画に入れておかないと、後々「こんなはずではなかった」と家計を圧迫する原因にもなりかねません。
主な維持費は、「電気代」と「メンテナンス費用」の2つです。
電気代
まず電気代ですが、これは多くの方が心配される点かもしれません。
しかし、最近のホームエレベーターは省エネ設計が進んでおり、意外にも電気代はそれほど高くありません。
メーカーや機種、使用頻度によって異なりますが、一般的な家庭での使用(1日に10~20回程度)であれば、1ヶ月あたりの電気代は500円から1,000円程度が目安です。
これは、待機電力はごくわずかで、主にエレベーターが昇降するときにだけ電力を消費するためです。
エアコンや冷蔵庫といった24時間稼働する家電に比べれば、負担はかなり小さいと言えるでしょう。
メンテナンス費用
維持費の中で最も大きな割合を占めるのが、このメンテナンス費用です。
建築基準法では、ホームエレベーターの所有者は、その昇降機を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと定められています。
つまり、安全に乗り続けるためには定期的な保守点検が不可欠というわけです。
多くのメーカーでは、専門技術者による定期点検や消耗品の交換、故障時の対応などをパッケージにしたメンテナンス契約を用意しています。
契約プランにもよりますが、年間のメンテナンス費用は、おおよそ4万円から8万円程度が相場です。
契約には大きく分けて2つのタイプがあります。
- POG契約(パーツ・オイル・グリス契約):定期点検と、消耗品である油やグリスの補充・交換などが含まれる基本的なプランです。部品交換や修理が必要になった場合は、別途費用が発生します。
- フルメンテナンス契約:POG契約の内容に加えて、故障時の修理費用や部品交換費用も含まれる包括的なプランです。月々の費用はPOG契約より高くなりますが、万が一の急な出費を抑えることができます。
また、駆動方式が「油圧式」の場合は、これに加えて5年に1回程度のオイル交換が必要となり、その費用として約5万円が別途かかります。
これらの維持費を合計すると、年間で少なくとも5万円以上、多い場合は10万円近くの費用がかかる計算になります。
初期費用だけでなく、こうした長期的なコストもしっかりと把握し、家計の計画に組み込んでおくことが、安心してホームエレベーターを使い続けるための重要なポイントです。
発生する固定資産税とは
ホームエレベーターを設置すると、生活が便利になる一方で、税金の面で一つ変化があります。
それは「固定資産税」が上がることです。
見落とされがちなポイントですが、長期的な支出に関わることなので、事前にしっかりと理解しておく必要があります。
そもそも固定資産税とは、土地や家屋などの「固定資産」を所有している人に対して、その資産価値に応じて市区町村が課税する地方税です。
毎年1月1日時点の所有者に対して課税され、通常は年4回に分けて納付します。
では、なぜホームエレベーターを設置すると固定資産税が上がるのでしょうか。
その理由は、ホームエレベーターが家屋の一部と見なされ、家の「資産価値」を高める設備だと評価されるからです。
家屋の固定資産税評価額は、総務省が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、市区町村の担当者が一軒一軒の家屋を調査して決定します。
この評価額に、標準税率である1.4%を掛けたものが、年間の固定資産税額となります。
ホームエレベーターを設置すると、その分が家屋の評価額に上乗せされるため、結果として納税額が増えるという仕組みです。
では、具体的にどのくらい税額が上がるのか、気になるところだと思います。
これはエレベーター本体の価格や自治体の評価基準によって一概には言えませんが、一般的には年間で1万5千円から3万円程度、税額が上がると考えておくと良いでしょう。
評価額の算定基準は複雑で、一般には公開されていません。
エレベーターの本体価格の50%~60%が評価額の目安とされることもありますが、あくまで参考程度です。
正確な金額は、設置後の家屋調査が完了し、納税通知書が届くまで確定しません。
この固定資産税の増額は、エレベーターを所有している限り毎年続くものです。
月々に換算すれば千円~二千円程度の負担ですが、10年、20年という長い目で見ると、数十万円単位の支出になります。
ホームエレベーターの後付け費用を検討する際には、初期の設置費用やメンテナンス費用だけでなく、この固定資産税の増加分もランニングコストの一部として、長期的な資金計画に含めておくことが非常に重要です。
詳しい税額については、お住まいの市区町村の資産税課などに問い合わせてみると、概算を教えてもらえる場合もあります。
あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪
ホームエレベーターの後付け費用を抑えるポイント
◆この章のポイント◆
- 活用できる補助金制度の紹介
- エレベーターの種類で価格を調整
- 主要メーカーごとの価格傾向
- 設置に必要なスペースの条件
- ホームエレベーターの後付け費用を計画的に考えよう
活用できる補助金制度の紹介
ホームエレベーターの後付け費用は高額になりがちですが、幸いなことに、その負担を軽減できる可能性のある補助金や助成金制度が存在します。
これらを賢く活用することで、数十万円単位で費用を抑えることも夢ではありません。
制度は国が主体となって行うものと、お住まいの市区町村などの地方自治体が独自に行うものに大別されます。
国の補助金制度
代表的な国の制度として、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」があります。
これは、既存住宅の性能向上や子育てしやすい環境の整備などを目的としたリフォームに対して、国が費用の一部を補助する制度です。
ホームエレベーターの設置は、高齢者などが安全に移動できるようにするための「バリアフリー改修工事」に該当するため、補助の対象となる可能性があります。
補助額は工事費用の3分の1で、上限額が設定されています。
ただし、この制度を利用するには、住宅の耐震性を確保するなど、一定の条件を満たす必要があるため、誰でも利用できるわけではありません。
リフォーム業者と相談し、ご自身の住宅が対象になるか確認してみると良いでしょう。
地方自治体の補助金制度
お住まいの市区町村によっては、高齢者や障害者のいる世帯を対象に、住宅のバリアフリー改修費用を助成する独自の制度を設けている場合があります。
制度の名称や内容は自治体によって様々ですが、「高齢者住宅改修費助成制度」や「障害者住宅改造費助成」といった名前で実施されていることが多いです。
これらの制度は、ホームエレベーターの設置を直接的な補助対象としている場合もあれば、関連する工事費用の一部を助成してくれる場合もあります。
補助額や所得制限などの条件は自治体ごとに大きく異なるため、まずは市役所や区役所の福祉課、高齢者支援課などに問い合わせてみることが第一歩です。
介護保険の住宅改修費は使える?
よくある質問として、「介護保険は使えますか?」というものがあります。
要支援・要介護認定を受けている方が対象の「居宅介護住宅改修費」は、手すりの設置や段差の解消など、比較的小規模な改修を対象としています。
残念ながら、ホームエレベーターのような大規模な設備工事は、現在のところ介護保険の住宅改修の対象外となっています。
階段昇降機も同様に対象外です。
しかし、先述の通り、自治体によっては介護保険とは別に独自の補助金を用意しているケースがありますので、諦めずに調べてみることが大切です。
これらの補助金制度は、申請期間が定められていたり、予算に達し次第終了したりすることがほとんどです。
また、工事契約前に申請が必要な場合が多いので、計画段階で早めに情報を集め、リフォーム業者にも相談しながら手続きを進めるようにしましょう。
エレベーターの種類で価格を調整
ホームエレベーターの後付け費用を検討する上で、どの種類のエレベーターを選ぶかは価格を左右する非常に重要な要素です。
機能やデザインにこだわり始めると価格は青天井になりがちですが、ご自身のライフスタイルや予算に合わせて適切な種類を選択することで、費用を賢く調整することが可能になります。
価格調整のポイントとなるのは、主に「駆動方式」と「サイズ・定員」です。
駆動方式による価格の違い
前述の通り、ホームエレベーターの駆動方式には主に「ロープ式」と「油圧式」の2種類があります。
それぞれの特徴と価格の関係を理解しておきましょう。
| 駆動方式 | 特徴 | 価格傾向 | メリット・デメリット |
|---|---|---|---|
| ロープ式 | モーターでワイヤーロープを巻き上げてカゴを昇降させる方式。 | 油圧式に比べて本体価格はやや高め。 | メリット:省エネ性能が高い、機械室が不要で省スペース。 デメリット:定期的なオイル交換は不要だが、部品交換費用が高くなる可能性。 |
| 油圧式 | 油圧ポンプで油をシリンダーに送り込み、その圧力でカゴを押し上げる方式。 | ロープ式に比べて本体価格は比較的安価。 | メリット:乗り心地が滑らかで静か。 デメリット:消費電力が大きい傾向、5年に1度程度のオイル交換(費用約5万円)が必要。 |
初期費用を少しでも抑えたいのであれば、油圧式を選択するのが一つの方法です。
ただし、長期的に見ればオイル交換費用や電気代がかかるため、ランニングコストも含めたトータルコストで比較検討することが重要です。
一方、ロープ式は初期費用は高くなりますが、月々の電気代が安く、オイル交換も不要なため、ランニングコストを抑えたい方に向いていると言えるでしょう。
サイズ・定員による価格の違い
エレベーターのサイズ、つまり定員も価格に直結します。
定員は2人乗りと3人乗りが主流ですが、当然ながらサイズの大きい3人乗りの方が高価になります。
ここで重要なのは、「将来的に誰がどのように使うか」を具体的にイメージすることです。
例えば、現在はご夫婦2人での利用がメインでも、将来的に車椅子を使う可能性がある場合や、介護者が同乗する必要が出てくることを見越すのであれば、初期費用が高くても3人乗りを選んでおくのが賢明です。
一般的な車椅子の幅を考えると、2人乗りでは乗り降りが困難なケースがほとんどです。
逆に、主に荷物の運搬や、1人での移動が目的で、車椅子の利用を想定しないのであれば、コンパクトで価格も安い2人乗りで十分かもしれません。
また、不要なオプションを削ることも価格調整のポイントです。
デザイン性の高いドア材や高級感のある内装は魅力的ですが、本当に必要かどうかを冷静に判断しましょう。
標準仕様でも機能的には全く問題ありません。
このように、エレベーターの種類や仕様を一つひとつ検討し、ご自身の優先順位を明確にすることで、無駄なコストを削減し、ホームエレベーターの後付け費用を予算内に収めることが可能になります。
主要メーカーごとの価格傾向
ホームエレベーターを選ぶ際、どのメーカーの製品にするかという点も、価格や性能を比較する上で重要なポイントとなります。
国内のホームエレベーター市場では、主に「パナソニック」「三菱電機(三菱日立ホームエレベーター)」「日立」といった大手電機メーカーがしのぎを削っています。
それぞれのメーカーに特徴があり、価格帯も異なります。
ここでは、主要メーカーの価格傾向や製品の特徴について見ていきましょう。
パナソニック (Panasonic)
パナソニックは、家電製品で培った技術力を活かし、利用者の快適性や使いやすさを追求した製品ラインナップが特徴です。
特に、空気清浄機能である「ナノイー」を搭載したモデルは人気があります。
価格帯としては、2人乗りのコンパクトなモデルでメーカー希望小売価格が300万円前後からとなっており、比較的幅広い選択肢があります。
デザインのバリエーションも豊富で、住宅のインテリアに合わせて選びやすいのも魅力の一つです。
リフォームでの後付けに対応した省スペース設計のモデルも多く、既存住宅への設置にも強みを持っています。
三菱電機 (三菱日立ホームエレベーター)
三菱電機と日立のホームエレベーター事業が統合して生まれた三菱日立ホームエレベーターは、長年の実績と高い技術力に定評があります。
特に、エレベーターの基本性能である「速さ」と「静かさ」を両立させたモデルが強みです。
例えば、「スイ~とホーム」シリーズでは、利用状況に応じて最適な速度で運転する機能や、深夜でも静かに利用できるナイトモードなどが搭載されています。
価格帯は、2人乗りの標準的なモデルで400万円前後からと、やや高めの設定ですが、その分、安全性や快適性に関する機能が充実しています。
信頼性や耐久性を重視する方に選ばれることが多いメーカーと言えるでしょう。
各メーカーの比較表(目安)
| メーカー | 特徴 | 価格帯(本体+標準工事費) | 強み |
|---|---|---|---|
| パナソニック | 「ナノイー」搭載など快適機能が豊富。デザイン性が高い。 | 約300万円~ | 省スペース設計、リフォーム対応力 |
| 三菱電機 | 高速・静音運転など基本性能が高い。安全性・信頼性に定評。 | 約350万円~ | 高い技術力、充実した安全機能 |
| 日立 | 三菱と事業統合。堅実な製品づくりで安定した品質。 | 三菱電機に準ずる | 長年の実績、信頼性 |
※上記価格はあくまで目安であり、実際の販売価格は販売代理店や工務店によって異なります。
注意点として、メーカーが公表している価格は「メーカー希望小売価格」であり、実際の購入価格とは異なる場合が多いということを覚えておきましょう。
住宅設備と同様に、リフォーム会社や工務店がメーカーから仕入れる際の「掛け率」が存在するため、最終的な見積もり金額は、工事費込みで複数の業者から取得して比較することが不可欠です。
また、メーカーによってメンテナンス契約の内容や料金も異なります。
初期費用だけでなく、長期的なランニングコストも視野に入れて、総合的に判断することが、後悔しないメーカー選びのコツと言えるでしょう。
ショールームで実際に製品を見て、乗り心地や操作性を体感してみるのもおすすめです。
設置に必要なスペースの条件
「うちにホームエレベーターを設置したいけど、そもそも置く場所なんてあるのだろうか?」これは、多くの方が抱く疑問だと思います。
ホームエレベーターを後付けするには、当然ながら一定の物理的なスペースが必要になります。
この設置スペースの条件をクリアできなければ、残念ながら計画を進めることはできません。
ここでは、設置に最低限必要なスペースや、後付けができないケースについて解説します。
最低限必要な設置面積
まず、エレベーター本体を設置するための面積ですが、これは思っているよりもコンパクトです。
現在のホームエレベーターは技術が進歩し、省スペース化が図られています。
一般的に、最低でも約0.5坪、畳にして1畳分ほどのスペースがあれば設置が可能とされています。
具体的には、幅1m × 奥行き1.5m程度の広さがあれば、2人乗りのコンパクトなタイプを設置できる可能性が高いです。
車椅子対応の3人乗りタイプを希望する場合は、もう少し広いスペースが必要となり、約1坪(畳2畳分)が一つの目安となります。
このスペースを家のどこに確保するかが、リフォーム計画の鍵となります。
よくあるケースとしては、押し入れやクローゼット、階段横のスペースなどを改造して設置する方法があります。
家の中に適切なスペースがない場合は、外壁に沿って増築する「外付け」という選択肢も考えられます。
昇降路に関する条件
面積だけでなく、垂直方向のスペースも重要です。
エレベーターが上下に移動する空間を「昇降路」と呼びますが、この昇降路の最下部には「ピット(PIT)」と呼ばれる一定の深さの穴が必要になります。
また、最上階の天井裏にも「オーバーヘッド」と呼ばれる高さの空間が必要です。
これらの寸法は機種によって異なりますが、ピットの深さは50cm前後、オーバーヘッドの高さは2.5m前後が一般的です。
後付けリフォームの場合、1階の床を掘り下げてピットを確保する工事が必要になるため、建物の基礎の状態によっては工事が難しい場合もあります。
後付けができない(難しい)ケース
残念ながら、すべての住宅で後付けができるわけではありません。
以下のようなケースでは、設置が困難、あるいは不可能と判断されることがあります。
- 建物の構造上の問題:建物の強度が不足しており、エレベーターの重量や昇降路の開口に耐えられない場合。大規模な補強工事で対応できることもありますが、費用が非常に高額になります。
- 法的な規制:建ぺい率や容積率(敷地面積に対する建物の大きさの制限)に余裕がなく、外付けで増築するスペースがない場合。
- 「検査済証」がない住宅:建物が完成した際に、建築基準法に適合していることを証明する「検査済証」が交付されていない住宅(いわゆる違法建築など)には、原則としてエレベーターを設置できません。
最終的に設置が可能かどうかは、専門家による現地調査と診断が必要不可欠です。
「うちは狭いから無理だろう」と自己判断せずに、まずはリフォーム会社やメーカーに相談してみることをお勧めします。
プロの視点から、思いもよらない設置場所の提案を受けられるかもしれません。
ホームエレベーターの後付け費用を計画的に考えよう
この記事を通じて、ホームエレベーターの後付け費用に関する様々な側面を見てきました。
本体価格や工事費といった初期費用から、電気代やメンテナンス、固定資産税といった長期的な維持費まで、考慮すべき点は多岐にわたります。
高額な買い物だからこそ、後悔しないためには、その場しのぎではない計画的なアプローチが何よりも重要です。
まず、なぜホームエレベーターが必要なのか、その目的を明確にすることがスタート地点となります。
「親の介護のため」「自分たちの老後に備えて」「重い荷物の運搬を楽にしたい」など、目的によって選ぶべきエレベーターのサイズや機能は変わってきます。
例えば、車椅子での利用を最優先に考えるなら、3人乗りの広いタイプが必須でしょう。
目的が明確になれば、それに合った機種やメーカーを絞り込み、おおよその予算感を掴むことができます。
次に、その予算をどのように捻出するか、資金計画を立てましょう。
自己資金でまかなうのか、リフォームローンを利用するのか、選択肢はいくつか考えられます。
その際には、今回ご紹介した国や自治体の補助金制度を最大限に活用することを忘れないでください。
利用できる制度があるかどうかを事前に調べるだけで、数十万円の差が生まれる可能性があります。
そして、最も重要なアクションは、信頼できる専門業者を見つけることです。
複数の業者から相見積もりを取り、価格だけでなく、提案内容や担当者の対応などを比較検討しましょう。
「なぜこの工事が必要なのか」「この費用の内訳は何か」といった質問に、丁寧に分かりやすく答えてくれる業者は信頼できる可能性が高いです。
見積もりを取る過程で、ご自身の住宅の現状(構造的な強度や法的な条件など)も明らかになり、より具体的な計画へと進むことができます。
ホームエレベーターの後付け費用は、単なる出費ではありません。
それは、将来にわたる家族の安全と快適な暮らしを実現するための価値ある投資と言えるでしょう。
費用を正しく理解し、一つひとつのステップを丁寧に進めていくことで、きっと満足のいくリフォームが実現するはずです。
この記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪
本日のまとめ
- ホームエレベーター後付けの総費用相場は300万円から600万円
- 費用は建物の構造(木造・鉄骨)や階数で大きく変動する
- 主な内訳はエレベーター本体価格・設置工事費・諸経費の三つ
- 本体価格は250万円から450万円が目安で定員や駆動方式で変わる
- 工事費は建物の解体や補強が必要なため50万円から150万円以上と幅が広い
- 建築確認申請費用などの諸経費として10万円から30万円程度が必要
- 導入後の維持費として電気代とメンテナンス費用がかかる
- 電気代は月々500円から1000円程度が目安
- 年間メンテナンス費用は4万円から8万円程度が相場
- 設置により家の資産価値が上がり固定資産税が年間1.5万円から3万円程度増加する
- 国の長期優良住宅化リフォーム推進事業などの補助金が利用できる場合がある
- 自治体独自のバリアフリー改修助成金も要チェック
- 介護保険の住宅改修費はホームエレベーター設置には適用されない
- パナソニックや三菱などの主要メーカーで価格や特徴が異なる
- 設置には最低でも1畳程度のスペースが必要となる

| 【PR】 リフォームをしようとする時に大切なのは「比較をすること」です。しかし実際には、自分で行おうとするととても大変ですし、数多く見積もりをしようとしたら心も折れてしまいます。 そこでおすすめなのがタウンライフの「一括見積り」です。日本全国の600社以上のリフォーム会社の中から、あなたに適したリフォーム会社から見積もりを受ける事ができます 見積もり比較することで、最大100万円程度節約になる事も!自宅に居ながらにして、いくつか項目を記入するだけで、簡単に完全無料で資料を取り寄せる事ができます |
あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪
参考サイト
パナソニック ホームエレベーター/小型エレベーター
三菱日立ホームエレベーター株式会社
老後に備えて設置したいホームエレベーター。設置にかかる値段や注意点は? – LIFULL HOME’S
ホームエレベーターの導入、後悔しないために考えておくべきことは?助成金は使える? – SUUMO
家庭用エレベーターの価格相場と設置に関する費用や注意点をまとめて解説! | アイニチ株式会社
Google Search Suggestions
Display of Search Suggestions is required when using Grounding with Google Search. Learn more
ホームエレベーター 後付け 費用 相場 2階建て 3階建て
ホームエレベーター 後付け 工事費 内訳 確認申請
ホームエレベーター 維持費 電気代 メンテナンス
ホームエレベーター 固定資産税 いくら 上がる
ホームエレベーター 後付け 補助金 介護保険
ホームエレベーター メーカー 価格比較 パナソニック 三菱 日立
ホームエレベーター 後付け 設置スペース 条件



コメント