こんにちは、サイト管理人です
住み慣れた家の中にある、ほんの数センチの床の段差。
若い頃は気にならなかったその段差が、年齢を重ねるにつれて転倒の危険性を高め、車椅子や歩行器の利用を妨げる大きな障壁になることがあります。
また、小さなお子様がいるご家庭や、お掃除ロボットをスムーズに使いたいと考えている方にとっても、床の段差は悩みの種ではないでしょうか。
床の段差をなくすリフォームは、こうした日々の暮らしの不安や不便を解消し、家族みんなが安全で快適に過ごせる住環境を実現するための重要な一歩です。
しかし、実際にリフォームを考え始めると、解消にかかる費用はどれくらいなのか、どんな工事方法があるのか、バリアフリー化のための補助金は使えるのか、賃貸住宅でも可能なのか、信頼できる業者はどう選べば良いのか、といった様々な疑問が浮かんでくることでしょう。
特に費用相場や、介護保険の適用の可否は多くの方が気にされる点だと思います。
この記事では、床の段差をなくすリフォームを検討しているあなたが抱えるあらゆる疑問や不安を解消できるよう、必要な情報を網羅的に、そして分かりやすく解説していきます。
リフォームの基本的な知識から、成功させるための具体的なポイントまで、この記事を読めばすべてが分かります。
◆このサイトでわかる事◆
- 床の段差をなくすリフォームの費用相場
- 具体的なリフォーム方法とそれぞれの特徴
- リフォームのメリットと知っておくべきデメリット
- バリアフリー化で実現する安全な暮らし
- 活用できる補助金や介護保険の制度
- 信頼できるリフォーム業者の選び方
- 賃貸物件やDIYで段差を解消する際の注意点

| 【PR】 リフォームをしようとする時に大切なのは「比較をすること」です。しかし実際には、自分で行おうとするととても大変ですし、数多く見積もりをしようとしたら心も折れてしまいます。 そこでおすすめなのがタウンライフの「一括見積り」です。日本全国の600社以上のリフォーム会社の中から、あなたに適したリフォーム会社から見積もりを受ける事ができます 見積もり比較することで、最大100万円程度節約になる事も!自宅に居ながらにして、いくつか項目を記入するだけで、簡単に完全無料で資料を取り寄せる事ができます |
あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪
床の段差をなくすリフォームの基本的な知識
◆この章のポイント◆
- 解消にかかる費用相場はどのくらい?
- 主な工事方法の種類とそれぞれの特徴
- 知っておきたいメリット・デメリット
- 安全な暮らしを実現するバリアフリー化
- DIYでできることと限界
解消にかかる費用相場はどのくらい?
床の段差をなくすリフォームを検討する際に、最も気になるのが費用ではないでしょうか。
リフォーム費用は、段差のある場所、工事の範囲、そして採用する工法によって大きく変動します。
ここでは、場所別・工法別の費用相場について詳しく見ていきましょう。
まず、リフォームの対象となる場所ごとの大まかな費用感です。
部屋と部屋の間の敷居を撤去するような比較的小規模な工事であれば、数万円から対応可能な場合があります。
例えば、和室と洋室の間の敷居を撤去し、床の高さを揃える工事の費用相場は、およそ3万円~10万円程度です。
一方で、廊下と部屋全体の床を張り替えて高さを完全にフラットにするような大規模な工事になると、数十万円の費用がかかることも珍しくありません。
特に、浴室や洗面所といった水回りの段差解消は、床下での給排水管の調整が必要になるケースもあり、費用が高くなる傾向にあります。浴室の段差解消リフォームは、ユニットバスの交換を伴う場合、50万円~150万円以上かかることも考えられます。
次に、具体的な工法と費用の関係です。
費用を抑えたい場合に選ばれることが多いのが、既存の床の上に新しい床材を重ねて張る「かぶせ工法(重ね張り)」です。
この方法であれば、既存の床の解体・撤去費用がかからないため、6畳の部屋でおよそ8万円~15万円程度が相場となります。
ただし、床が全体的に高くなるため、ドアの開閉に支障が出ないかといった確認が必要不可欠です。
一方、既存の床を一度すべて剥がしてから新しい床を張る「張り替え工法」は、下地の状態を確認・補修できるというメリットがあります。
費用はかぶせ工法よりも高くなり、6畳の部屋で12万円~25万円程度が目安となりますが、床のきしみや断熱性の問題も同時に解決できる可能性があります。
ごく小さな段差であれば、費用をかけずに「すりつけ板」や「スロープ」を設置する方法もあります。
これは数千円から2万円程度で設置可能ですが、あくまで簡易的な対策であり、スロープ自体が新たなつまずきの原因になる可能性も否定できません。
以下に、場所と工法別の費用相場を表にまとめました。
| リフォーム箇所 | 工事内容 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 部屋と部屋の間 | 敷居の撤去・床の一部補修 | 3万円 ~ 10万円 |
| 玄関 | 式台の設置 | 5万円 ~ 15万円 |
| 廊下・部屋(6畳) | かぶせ工法(重ね張り) | 8万円 ~ 15万円 |
| 廊下・部屋(6畳) | 張り替え工法 | 12万円 ~ 25万円 |
| 洗面所・トイレ | 床の張り替え・高さ調整 | 5万円 ~ 20万円 |
| 浴室 | ユニットバス交換含む | 50万円 ~ 150万円 |
これらの費用はあくまで目安です。
正確な金額を知るためには、複数のリフォーム業者から見積もりを取り、内訳をしっかりと比較検討することが何よりも重要です。
主な工事方法の種類とそれぞれの特徴
床の段差をなくすリフォームには、いくつかの主要な工事方法が存在します。
どの方法を選択するかは、段差の状況、予算、そしてリフォームに求めるものによって決まります。
それぞれの特徴を理解し、ご自身の住まいに最適な方法を見つけましょう。
かぶせ工法(重ね張り)
かぶせ工法は、現在の床材の上に新しい床材を直接張り重ねていく方法です。
この工法の最大のメリットは、既存の床を解体する必要がないため、工期が短く、費用を抑えられる点にあります。
工事中の騒音やホコリも比較的少なく済むため、住みながらのリフォームにも適しています。
ただし、デメリットも理解しておく必要があります。
床の高さが上がるため、ドアの下部をカットするなどの調整が必要になったり、クローゼットの扉が開かなくなったりする可能性があります。
また、床下の状態を確認できないため、もし下地に腐食などの問題があった場合、根本的な解決にはなりません。
張り替え工法
張り替え工法は、既存の床材を一度すべて剥がし、新しい床材を張る方法です。
この方法の利点は、床下地(根太)の状態を直接確認し、必要であれば補修や補強を行えることです。
床のきしみや沈みといった問題も根本から解決できますし、床下の断熱材を追加して断熱性能を向上させることも可能です。
選べる床材の種類も豊富で、デザインの自由度が高いのも魅力と言えるでしょう。
一方で、解体作業が伴うため、かぶせ工法に比べて工期が長くなり、費用も高額になります。
工事期間中は、その部屋を使用できなくなるという点も考慮しておくべきです。
敷居の撤去
特に日本の住宅で多いのが、和室と廊下・洋室の間にある敷居による段差です。
この敷居を撤去するだけでも、つまずきのリスクは大幅に軽減されます。
敷居を撤去した後は、周囲の床との高さや見た目を合わせるための補修作業が必要です。
V字のレールを埋め込むなどして、違和感なく仕上げるのが一般的です。
比較的手軽に行えるリフォームですが、建物の構造によっては敷居が重要な役割を担っている場合もあるため、必ず専門家に相談してから実施してください。
すりつけ板・スロープの設置
これは本格的な工事というよりは、簡易的な段差解消法です。
数センチ程度の小さな段差に対して、両側から緩やかな傾斜をつける「すりつけ板」や「スロープ」を設置します。
ホームセンターなどでも購入でき、設置も比較的簡単なため、最も手軽で安価な方法です。
しかし、これは段差を「なくす」のではなく「緩やかにする」対策です。
スロープの角度や素材によっては、かえって滑りやすくなったり、車椅子での通行が困難になったりすることもあるため注意が必要です。
あくまで応急処置、あるいは賃貸物件で工事ができない場合の選択肢と考えると良いでしょう。
どの方法が最適かは一概には言えません。
リフォーム業者とよく相談し、現地調査をしてもらった上で、メリットとデメリットを総合的に判断することが大切です。
知っておきたいメリット・デメリット
床の段差をなくすリフォームは、多くの利点をもたらしますが、一方でいくつかの注意すべき点も存在します。
計画を進める前に、メリットとデメリットの両方をしっかりと把握しておくことで、後悔のないリフォームを実現できます。
床の段差をなくすリフォームのメリット
最大のメリットは、なんといっても「安全性の向上」です。
家庭内での高齢者の事故のうち、多くが転倒によるものと言われています。
床の段差は、すり足になりがちな高齢者にとって非常に危険なつまずきの原因です。この段差をなくすことで、転倒リスクを大幅に減らし、安心して室内を移動できるようになります。
次に挙げられるのが、「移動のしやすさ(バリアフリー化)」です。
段差がなくなれば、車椅子や歩行器、シルバーカーなどの利用がスムーズになります。
これは介護が必要になった場合だけでなく、ベビーカーを室内で使う際や、重い荷物を台車で運ぶときにも非常に便利です。
また、最近普及しているお掃除ロボットも、段差がないことで家全体を効率的に掃除できるようになり、家事の負担軽減にも繋がります。
さらに、「快適性の向上」も見逃せません。
敷居などの段差は、ドアを閉めていても隙間風の原因になることがあります。
段差を解消し床をフラットにすることで気密性が高まり、冷暖房の効率がアップする効果も期待できるでしょう。
部屋から部屋への視線が遮られなくなることで、空間が広く感じられるという視覚的なメリットもあります。
- 転倒事故の防止による安全性の向上
- 車椅子や歩行器が使いやすいバリアフリー化
- お掃除ロボットがスムーズに稼働し家事負担軽減
- 空間の広がりと冷暖房効率のアップ
床の段差をなくすリフォームのデメリット
一方で、デメリットとしてまず考えられるのが「費用」です。
先に述べたように、工事の範囲や方法によっては、決して安くはない費用がかかります。
予算をしっかりと計画し、どの範囲までリフォームを行うか慎重に検討する必要があります。
また、「工事期間中の生活への影響」も考慮しなければなりません。
特に床の張り替えを行う場合、工事中は部屋に入ることができず、家具の移動も必要になります。
騒音やホコリが発生するため、近隣への配慮も求められます。
技術的な注意点としては、「ドアの開閉に問題が生じる可能性」が挙げられます。
特にかぶせ工法で床を高くした場合、ドアの下部が床に擦れて開かなくなることがあります。
その場合はドアを削るなどの追加工事が必要になり、別途費用が発生する可能性も考えられます。
最後に、敷居が持っていた役割が失われるという点です。
例えば、和室と洋室を仕切る敷居には、部屋ごとのホコリの移動を防いだり、音の伝わりを和らげたりする役割がありました。
段差をなくすことで、これらの効果が薄れる可能性があることも覚えておきましょう。
これらのメリットとデメリットを天秤にかけ、ご自身のライフスタイルや将来の計画にとって、リフォームが本当に必要かどうかを判断することが重要です。
安全な暮らしを実現するバリアフリー化
床の段差をなくすリフォームは、単に床を平らにするだけの工事ではありません。
これは、年齢や身体能力にかかわらず、誰もが安全かつ快適に暮らせる住まいを目指す「バリアフリー化」の根幹をなすものです。
バリアフリーと聞くと、車椅子や介護が必要な方のための特別な改修というイメージを持つかもしれません。
しかし、その本質は「すべての人の生活障壁(バリア)を取り除く」という考え方にあります。
例えば、床の段差は高齢者の転倒リスクを高めるだけでなく、妊娠中の方や小さな子供にとっても危険な存在です。
また、視力が低下してきた方にとっても、わずかな段差は見えにくく、つまずきの原因となります。
床をフラットにすることは、こうした様々な世代の家族が共に安全に暮らすための普遍的なデザインと言えるでしょう。
さらに、床の段差解消は他のバリアフリーリフォームと連携することで、その効果を最大限に発揮します。
例えば、廊下やトイレ、浴室に手すりを設置するリフォームも代表的なバリアフリー工事です。
床がフラットであれば、手すりを伝ってより安全に移動することが可能になります。
同様に、開き戸を引き戸に交換するリフォームも人気があります。
引き戸は開閉時に体の移動が少なく、車椅子利用者でも扱いやすいのが特徴です。
床に段差がなければ、引き戸のレールを埋め込んでさらにスムーズな移動を実現できます。
また、見落とされがちなのが「ヒートショック」との関連性です。
ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こす健康リスクのこと。
冬場の暖かいリビングから寒い廊下やトイレへ移動する際に起こりやすいとされています。
部屋間の敷居などの段差は、ドアの下に隙間を作り、暖気が逃げたり冷気が入り込んだりする原因となります。
床の段差をなくし気密性を高めることは、家の中の温度差を少なくし、ヒートショックのリスクを軽減することにも繋がるのです。
このように、床の段差をなくすことは、物理的な障壁を取り除くだけでなく、健康上のリスクを減らし、精神的な安心感をもたらします。
将来を見据え、家族構成の変化に対応できる住まいづくりとして、バリアフリー化の中心にある床の段差解消は非常に重要な意味を持つのです。
DIYでできることと限界
リフォーム費用を少しでも抑えたいと考えたとき、「DIYで床の段差を解消できないだろうか」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、DIYで対応できる範囲は非常に限定的であり、本格的な段差解消には専門的な技術が必要です。
ここでは、DIYで可能なこととその限界について解説します。
DIYで可能な範囲
DIYで対応できるのは、主に「簡易的なスロープの設置」です。
ホームセンターやインターネット通販では、ゴム製、木製、プラスチック製など、様々な素材の室内用スロープが販売されています。
解消したい段差の高さに合った製品を選び、両面テープや接着剤で固定するだけで設置できるものも多く、手軽に試すことができます。
特に、1cm~2cm程度のわずかな段差であれば、こうした既製品のスロープでも移動のしやすさをある程度改善できるでしょう。
また、木材の加工が得意な方であれば、段差の幅や高さに合わせて自作のスロープを作ることも可能です。
ただし、表面を滑りにくく加工したり、端でつまずかないように角を滑らかにしたりといった配慮が求められます。
DIYの限界とリスク
一方で、床自体を工事して段差をなくす作業は、DIYの範囲をはるかに超えています。
床の張り替えや重ね張りには、専門的な知識と技術、そして専用の道具が不可欠です。
見様見真似で作業を行うと、様々なリスクが生じます。
例えば、床が水平にならずに傾いてしまったり、歩くとギシギシと音が鳴る「床鳴り」が発生したりすることがあります。
床材の間に隙間ができてしまい、そこから湿気が入り込んでカビや腐食の原因になることも考えられます。
最も危険なのは、床下の構造を理解せずに作業を進めてしまうことです。
床を支える根太や大引といった構造材を誤って傷つけてしまうと、家の耐久性そのものに影響を及ぼしかねません。
また、敷居の撤去も簡単そうに見えますが、前述の通り、建物によっては敷居が構造上の役割を担っている場合があります。
安易に撤去すると、建具の歪みなどを引き起こす可能性があります。
結局、DIYで失敗してしまい、後から専門業者にやり直しを依頼することになると、最初から依頼するよりも高額な費用がかかってしまうケースが少なくありません。
結論として、DIYはあくまで「応急処置」や「簡易的な対策」と位置づけるべきです。
家族の安全に直結する床の段差を本格的に解消したいのであれば、費用がかかったとしても、信頼できるリフォーム業者に依頼することが最も確実で安全な選択と言えるでしょう。
あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪
床の段差をなくすリフォームを成功させるポイント
◆この章のポイント◆
- 活用できる補助金や助成金制度
- 賃貸物件でリフォームする際の注意点
- 信頼できるリフォーム業者の選び方
- 工事期間の目安と流れ
- 理想の住まいへ、床の段差をなくすリフォームを考えよう
活用できる補助金や助成金制度
床の段差をなくすリフォームは、安全な住環境を整えるための重要な改修ですが、費用がネックになることもあります。
しかし、こうしたバリアフリーリフォームに対しては、国や地方自治体が費用の一部を補助する制度を設けている場合があります。
これらの制度を賢く活用することで、自己負担を大きく軽減できる可能性があります。
介護保険の住宅改修費
最も代表的な制度が、介護保険制度における「住宅改修費の支給」です。
要支援または要介護認定を受けている方が、自立した生活を送るために自宅を改修する場合に利用できます。
対象となる工事は定められており、「廊下、便所、浴室、玄関等の床材の変更(段差解消)」もその一つです。
具体的には、敷居の撤去、スロープの設置、床のかさ上げなどが対象となります。
支給限度基準額は、原則として20万円です。
そのうち、所得に応じて費用の7割~9割が保険から給付されるため、自己負担は1割~3割(2万円~6万円)で済む計算になります。
利用するには、まず担当のケアマネージャーや地域包括支援センターに相談し、工事前に市区町村への申請が必要です。
重要なのは、必ず「工事着工前」に申請手続きを完了させることです。
工事後の申請は認められないため、注意しましょう。
地方自治体の補助金・助成金制度
介護保険の対象ではない方でも、お住まいの市区町村が独自に設けている補助金制度を利用できる場合があります。
多くの自治体では、高齢者や障害者のいる世帯を対象に、バリアフリーリフォームへの助成を行っています。
制度の名称や内容は自治体によって様々です。
例えば、「高齢者住宅改修助成事業」や「障害者住宅改造費助成」といった名称で実施されています。
補助の対象となる工事内容や補助率、上限額も自治体ごとに異なります。
所得制限などの条件が設けられていることも多いため、まずはお住まいの市区町村のウェブサイトを確認するか、高齢福祉課や建築指導課などの担当窓口に問い合わせてみることが重要です。
これらの制度は、介護保険と併用できる場合とできない場合がありますので、その点も合わせて確認しておくと良いでしょう。
その他の制度
上記のほかにも、同居対応支援事業や、リフォーム減税(所得税の控除や固定資産税の減額)など、利用できる可能性がある制度はいくつか存在します。
リフォーム業者の中には、こうした補助金制度の活用に詳しいところもあります。
業者選びの際に、補助金申請のサポート経験が豊富かどうかも確認してみることをお勧めします。
費用負担を理由にリフォームを諦める前に、まずは利用できる制度がないか、積極的に情報収集を行いましょう。
賃貸物件でリフォームする際の注意点
賃貸マンションやアパートにお住まいの方の中にも、室内の段差に不便を感じている方は少なくないでしょう。
しかし、賃貸物件で床の段差をなくすリフォームを行うには、持ち家の場合とは異なる、いくつかの重要な注意点があります。
最も fundamental かつ重要なルールは、「必ず事前に大家さん(貸主)や管理会社の許可を得る」ことです。
賃貸物件はあくまで借り物であり、入居者には退去時に部屋を元の状態に戻す「原状回復義務」があります。
許可なく壁や床に手を入れるなどの工事を行うことは契約違反にあたり、退去時に高額な修繕費用を請求されたり、トラブルに発展したりする可能性があります。
まずは、なぜ段差を解消したいのか、その理由(高齢の家族のため、自身の怪我のためなど)を具体的に伝え、リフォームの必要性を丁寧に説明して相談することが第一歩です。
大家さんによっては、建物の資産価値向上に繋がるとして、快く許可してくれるケースや、費用の一部を負担してくれるケースも稀にあります。
もし工事の許可が得られた場合でも、誰が費用を負担するのか、退去時の原状回復はどこまで必要なのかといった点を、必ず書面で取り交わしておくことが重要です。
口約束だけでは、後々「言った、言わない」の争いになりかねません。
一方で、大規模な工事の許可が下りないことも十分に考えられます。
その場合は、原状回復が容易な方法で段差を解消するしかありません。
具体的には、前述した「置き敷きタイプのスロープ」の設置が最も現実的な選択肢となります。
これらは接着剤やネジを使わずに設置できるため、退去時には簡単に撤去できます。
また、最近では、既存の床の上に置くだけで設置できる、はめ込み式のフロアタイルやクッションフロアもあります。
これらを使って低い方の床をかさ上げすることで、段差を緩和することも可能です。
ただし、これらの方法でも、ドアの開閉に支障が出ないかなど、事前に十分な確認が必要です。
- 事前の許可:必ず大家さん・管理会社に相談し、書面で許可を得る。
- 書面での取り決め:費用負担や原状回復義務の範囲を明確にする。
- 原状回復可能な方法の検討:工事が不可能な場合は、置き敷きスロープなどを活用する。
賃貸物件におけるリフォームは、制約が多いのが実情です。
トラブルを避けるためにも、自己判断で進めることは絶対にせず、まずは貸主側とのコミュニケーションを丁寧に行うことを心がけてください。
信頼できるリフォーム業者の選び方
床の段差をなくすリフォームを成功させるためには、適切な工事方法や費用計画もさることながら、「信頼できる業者に依頼すること」が最も重要な要素と言っても過言ではありません。
しかし、数多くのリフォーム業者の中から、本当に信頼できる一社を見つけ出すのは簡単なことではありません。
ここでは、業者選びで失敗しないためのポイントを具体的に解説します。
まず基本となるのが、「複数の業者から見積もり(相見積もり)を取る」ことです。
1社だけの見積もりでは、その金額や工事内容が適正なのか判断できません。
少なくとも3社程度から見積もりを取り、内容を比較検討しましょう。
その際、単に総額の安さだけで選ぶのは危険です。
見積書の内訳が「一式」などと大雑把ではなく、どのような材料をどれだけ使い、どのような作業にどれくらいの費用がかかるのか、詳細に記載されているかを確認してください。
丁寧で分かりやすい見積書を作成してくれる業者は、信頼性が高いと言えます。
次に、「バリアフリーリフォームの実績が豊富か」を確認しましょう。
床の段差解消は、見た目をきれいにするだけでなく、利用者の安全を確保するという目的があります。
高齢者や車椅子利用者の身体的な特性を理解し、ミリ単位の精度で仕上げる技術が求められます。
業者のウェブサイトで施工事例を確認したり、過去に手掛けたバリアフリーリフォームについて具体的な話を聞いたりして、経験と知識が豊富かどうかを見極めることが大切です。
介護保険の住宅改修など、補助金制度の利用実績があるかどうかも良い判断材料になります。
担当者の人柄や対応も重要なチェックポイントです。
こちらの要望や不安を親身に聞いてくれるか、専門用語ばかり使わずに分かりやすく説明してくれるか、質問に対して的確に答えてくれるかなど、コミュニケーションの取りやすさを確認しましょう。
リフォーム中は何度もやり取りをすることになるため、安心して相談できる担当者でなければ、ストレスを感じてしまいます。
以下のチェックリストも参考にしてください。
- 建設業許可や建築士事務所登録などの資格を保有しているか
- リフォーム瑕疵保険に加入しているか(万が一の欠陥に備える保険)
- 工事後の保証やアフターサービスの内容は充実しているか
- 契約を急がせたり、大幅な値引きをちらつかせたりしないか
- 事務所の所在地が明確で、地域に根差した営業をしているか
大切な住まいを任せるパートナー選びです。
時間をかけて慎重に、そして複数の視点から業者を評価し、心から納得できる一社を選んでください。
工事期間の目安と流れ
実際に床の段差をなくすリフォームを依頼することが決まったら、どのような流れで進み、どれくらいの期間がかかるのかを把握しておくことが大切です。
事前に全体の流れと期間を理解しておくことで、スムーズに準備を進め、工事中の生活への影響も最小限に抑えることができます。
リフォームの一般的な流れ
リフォームは、以下のステップで進んでいくのが一般的です。
- 相談・問い合わせ
まずはリフォーム会社のウェブサイトや電話で、床の段差について相談します。この段階で、大まかな要望や予算を伝えます。 - 現地調査・ヒアリング
業者の担当者が自宅を訪問し、段差のある箇所の寸法や床下の状態などを詳しく調査します。同時に、家族構成やライフスタイル、リフォームへの具体的な希望などを詳細にヒアリングします。 - プラン提案・見積もり提出
現地調査の結果をもとに、具体的なリフォームプランと詳細な見積書が提出されます。複数のプランを提案してくれる業者もあります。内容をよく確認し、疑問点はすべて解消しておきましょう。 - 契約
プランと見積もりに納得したら、正式に工事請負契約を結びます。契約書の内容(工事期間、金額、支払い条件、保証内容など)は隅々まで目を通し、不明な点がないか確認してから署名・捺印します。 - 着工
契約内容に基づき、工事が開始されます。工事前には、近隣への挨拶を業者と一緒に行うのがマナーです。工事中は、家具の移動などが必要になります。 - 施工
床の解体、下地調整、新しい床材の設置といった作業が行われます。定期的に現場を確認し、進捗状況を見ておくと安心です。 - 完工・検査
工事が完了したら、業者の担当者と一緒に仕上がりをチェックします。傷や汚れ、不具合がないか、床が水平になっているかなどを細かく確認します。 - 引き渡し・支払い
検査で問題がなければ、引き渡しとなります。その後、契約に基づいて残金の支払いを行います。保証書や取扱説明書などを受け取って、すべて完了です。
工事期間の目安
工事にかかる期間は、その内容によって大きく異なります。
あくまで目安ですが、簡単なスロープの設置であれば半日~1日程度で完了します。
和室の敷居を撤去して周辺を補修するような工事は、1日~2日程度が一般的です。
6畳程度の部屋の床を「かぶせ工法」でリフォームする場合は、1日~3日、「張り替え工法」で行う場合は、下地の状況にもよりますが2日~5日程度を見ておくとよいでしょう。
家全体の床をリフォームするなど、大規模な工事になる場合は1週間以上かかることもあります。
また、床材などの資材の取り寄せに時間がかかる場合や、職人のスケジュールによっては、契約から着工まで数週間待つこともあります。
リフォームを希望する時期が決まっている場合は、余裕を持ったスケジュールで早めに業者に相談を開始することをお勧めします。
理想の住まいへ、床の段差をなくすリフォームを考えよう
ここまで、床の段差をなくすリフォームに関する様々な情報を見てきました。
費用や工事方法、メリット・デメリット、そして補助金の活用や業者選びのポイントまで、リフォームを検討する上で必要な知識は多岐にわたります。
はじめは漠然としていたリフォームのイメージが、少しずつ具体的になってきたのではないでしょうか。
床の段差をなくすリフォームは、単に見た目を良くするためのものではありません。
それは、日々の生活に潜む転倒のリスクを減らし、家族全員が安心して家の中を移動できるようにするための「未来への投資」です。
今は元気でも、10年後、20年後の暮らしを想像してみてください。
あるいは、親御さんや大切な人が、この先も安全に暮らし続けるために何が必要かを考えてみてください。
段差のないフラットな床は、車椅子や歩行器が必要になったときにも、スムーズな生活を支える基盤となります。
もちろん、リフォームには費用も時間もかかります。
だからこそ、事前の情報収集と計画が何よりも重要になるのです。
ご自身の住まいのどこに問題があり、どのような解決方法が最適なのか。
予算内で最大限の効果を得るためにはどうすれば良いのか。
この記事で得た知識をもとに、信頼できるリフォームの専門家とじっくり相談し、あなたとあなたの家族にとって最高のプランを見つけ出してください。
小さな一歩を踏み出すことで、日々の暮らしはもっと安全で、もっと快適なものに変わるはずです。
床の段差をなくすリフォームを通じて、誰もが笑顔で過ごせる理想の住まいを実現しましょう。
あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪
本日のまとめ
- 床の段差は家庭内での転倒事故の大きな原因となる
- リフォーム費用は工事の範囲や方法によって数万円から数十万円と変動する
- 主な工事方法は費用を抑えられる「かぶせ工法」と根本解決できる「張り替え工法」
- 小さな段差であれば簡易的なスロープ設置も選択肢のひとつ
- リフォームのメリットは安全性向上と車椅子なども使いやすいバリアフリー化
- デメリットは費用がかかることと工事期間中の生活への影響
- 本格的な床工事のDIYはリスクが高く専門業者への依頼が賢明
- 要介護認定者は介護保険の住宅改修費が利用できる可能性がある
- お住まいの自治体が設ける独自の補助金制度も確認する価値がある
- 賃貸物件でのリフォームは必ず事前に大家さんや管理会社の許可が必要
- 業者選びは複数の業者から見積もりを取り実績や対応を比較することが重要
- 工事期間は内容により半日から1週間以上と幅があるため事前の確認が不可欠
- 成功のカギは十分な情報収集と信頼できる業者との綿密な計画
- 家族の現在と未来の暮らしを見据えたリフォームを検討することが大切
- 床の段差をなくすリフォームで毎日の暮らしに安全と快適を実現しよう

| 【PR】 リフォームをしようとする時に大切なのは「比較をすること」です。しかし実際には、自分で行おうとするととても大変ですし、数多く見積もりをしようとしたら心も折れてしまいます。 そこでおすすめなのがタウンライフの「一括見積り」です。日本全国の600社以上のリフォーム会社の中から、あなたに適したリフォーム会社から見積もりを受ける事ができます 見積もり比較することで、最大100万円程度節約になる事も!自宅に居ながらにして、いくつか項目を記入するだけで、簡単に完全無料で資料を取り寄せる事ができます |
あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪
参考サイト
床の小さな段差をなくすためのリフォーム方法とポイント
安心安全な暮らしへ!バリアフリー床の段差解消リフォーム – 斉藤建築
段差をなくすリフォームとは?費用と補助金を紹介
段差解消のリフォーム方法と費用のポイント
床をバリアフリーにリフォームする費用・価格の相場は? – ハピすむ

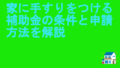

コメント