管理人のshinchikupapaです
愛犬との暮らしは、日々にかけがえのない喜びと癒やしをもたらしてくれます。
その大切な家族である愛犬が、安全で快適に過ごせる家を建てたいと考えるのは、飼い主さんにとって自然な願いではないでしょうか。
特に、自由に走り回れるドッグランのある家は、多くの愛犬家の憧れです。
しかし、理想を詰め込んだはずのマイホームで、後悔や失敗を感じてしまうケースも少なくありません。
「犬と暮らす家とドッグランと間取り」を考える際には、デザイン性だけでなく、愛犬の習性や安全性を深く理解し、計画に反映させることが何よりも重要になります。
例えば、日々の生活における愛犬の動線を考えた間取り、滑りにくい床材などの素材選び、気になる臭い対策や掃除のしやすさといった現実的な問題にも目を向ける必要があります。
また、ドッグランの設置にはどのくらいの費用がかかるのか、どのような設備があればより快適になるのか、具体的な情報を知りたい方も多いでしょう。
この記事では、注文住宅で犬と暮らす家とドッグランと間取りを実現するために知っておくべきポイントを、網羅的に解説します。
間取りの工夫から、安全性、費用、素材、必要な設備、そして気になる臭い対策まで、具体的な実例を交えながら、後悔しない家づくりのための知識を提供します。
平屋のメリットや、掃除の負担を軽減するアイデアなど、あなたの家づくりに役立つ情報がきっと見つかるはずです。
これから家づくりを始める方も、すでに計画を進めている方も、ぜひ本記事を参考にして、愛犬と家族全員が心から満足できる、最高の住まいを実現してください。
◆このサイトでわかる事◆
- 犬と暮らす家で後悔しないための計画の立て方
- 愛犬にとって安全で快適な動線の作り方
- ドッグランの設置にかかる費用と注意点
- 滑りにくく掃除しやすい床材や壁材の選び方
- 留守番中も安心できる便利な室内設備
- 平屋で実現する犬との暮らしのメリットと実例
- 気になる臭い対策と効果的な換気方法

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |
犬と暮らす家とドッグランと間取りで後悔しないための計画ポイント
◆この章のポイント◆
- まず考えたい愛犬のための動線と安全性
- 滑りにくく掃除がしやすい床などの素材選び
- ドッグランの設置に必要な費用と注意点
- 留守番時も安心な室内の設備とは
- 気になる臭い対策と効果的な換気方法
まず考えたい愛犬のための動線と安全性
犬と暮らす家とドッグランと間取りを計画する上で、最も優先すべきなのが「動線」と「安全性」の確保です。
人間にとっては快適な間取りでも、犬にとっては危険が潜んでいたり、ストレスを感じたりすることがあります。
愛犬が毎日を安全かつ快適に過ごせるよう、細やかな配慮を間取りに落とし込んでいきましょう。
まず動線計画ですが、これは「犬の行動パターン」と「飼い主の家事動線」の2つの視点から考えることが大切です。
犬の行動を考慮した動線計画
犬は室内と屋外を行き来することが多くなります。
特にドッグランを設ける場合、リビングや掃き出し窓から直接ドッグランへ出られるような間取りが理想的です。
これにより、犬はストレスなく内外を移動でき、飼い主も愛犬の様子を室内から見守りやすくなります。
また、散歩から帰宅した際の動線も重要です。
玄関から直接、足洗い場やグルーミングスペースにアクセスできる間取りにしておけば、家の中を汚すことなく、スムーズにお手入れができます。
この際、玄関土間を広く設計し、リードを外したり、体を拭いたりするスペースを確保するとさらに便利になります。
室内の動線では、犬が落ち着いて過ごせる「プライベートスペース」の確保も忘れてはなりません。
リビングの隅や階段下など、人の往来が少なく、静かで安心できる場所にケージやベッドを置くスペースを計画しましょう。
家事動線と犬の動線の融合
飼い主の家事動線と犬の動線が交錯しすぎると、お互いにとってストレスの原因となります。
例えば、料理中にキッチンを犬がうろつくと、衛生面でも安全面でも好ましくありません。
キッチンへの侵入を防ぐために、ゲートを設置できるような設計にしておくと安心です。
同様に、掃除のしやすさも動線計画の一環として考えましょう。
抜け毛や汚れが溜まりやすい場所を減らすため、家具の配置を工夫したり、コンセントの位置を掃除機の使いやすい高さに設置したりする配慮も有効です。
徹底したい安全対策
安全性は家づくりの基本ですが、犬と暮らす家ではさらに注意が必要です。
特に以下の点には配慮しましょう。
- 脱走防止対策
- 転倒・滑落対策
- 誤飲・感電対策
玄関ドアや庭のゲートは、犬が簡単に開けられないような鍵付きのものを選んだり、二重扉にしたりする工夫が効果的です。
窓からの飛び出しを防ぐためには、網戸ストッパーや柵の設置が欠かせません。
室内の階段は、滑りにくい素材を選び、必要であれば滑り止めマットを敷きましょう。
犬種によっては階段の上り下りが足腰に大きな負担をかけるため、スロープを設けたり、リビング階段を避けたりする選択肢も考えられます。
特に小型犬や老犬がいる家庭では、わずかな段差も怪我の原因になり得るため、可能な限りバリアフリー設計を心掛けることが重要です。
また、電気コードやコンセントは犬の目に触れない場所に配置するか、コードカバーで保護して感電事故を防ぎましょう。
観葉植物の中には犬にとって有毒なものも多いため、置く場所には細心の注意が必要です。
これらの動線と安全対策を設計段階からしっかりと計画することで、後悔のない、愛犬との快適な暮らしが実現できるでしょう。
滑りにくく掃除がしやすい床などの素材選び
犬と暮らす家づくりにおいて、床や壁などの素材選びは、愛犬の健康と飼い主の快適さを左右する非常に重要な要素です。
犬は一日の大半を床の上で過ごします。
そのため、滑りやすい床は足腰に大きな負担をかけ、脱臼や椎間板ヘルニアなどの原因になることも少なくありません。
また、抜け毛や粗相など、掃除の手間も考慮する必要があります。
床材選びの最重要ポイント
床材を選ぶ際に考慮すべきポイントは、主に以下の4つです。
- 滑りにくさ(防滑性)
- 耐久性・傷つきにくさ
- 防水性・耐アンモニア性
- 掃除のしやすさ
一般的なフローリングは、見た目はおしゃれですが、犬にとっては非常に滑りやすく、爪で傷がつきやすいというデメリットがあります。
そこでおすすめなのが、ペット用に開発された床材です。
例えば、表面に特殊なコーティングが施された防滑性の高いフローリングや、クッション性があり衝撃を吸収してくれるクッションフロア、タイルカーペットなどが挙げられます。
特にタイルカーペットは、汚れた部分だけを取り外して洗ったり交換したりできるため、粗相が多い子犬や老犬がいるご家庭には非常に便利です。
また、コルク材も滑りにくく、クッション性や断熱性に優れているため、犬の足腰に優しい素材として人気があります。
以下に、犬と暮らす家におすすめの床材の比較を表にまとめました。
| 床材の種類 | メリット | デメリット | おすすめの場所 |
|---|---|---|---|
| ペット用フローリング | 滑りにくい、傷がつきにくい、掃除がしやすい | 一般的なフローリングより高価 | リビング、廊下 |
| クッションフロア | 防水性が高い、クッション性がある、安価 | 耐久性がやや低い、見た目の質感が劣る場合がある | トイレ周り、水回り |
| タイルカーペット | 滑りにくい、汚れた部分だけ交換可能、防音性が高い | 毛やホコリが絡みやすい、ダニが発生しやすい | リビング、寝室 |
| コルクタイル | 滑りにくい、クッション性・断熱性が高い、防音性がある | 水に弱い、定期的なメンテナンスが必要 | リビング、寝室 |
壁材選びのポイント
壁材は、犬のよだれや体当たりによる汚れ、爪とぎによる傷に強い素材を選ぶことが大切です。
腰の高さまで、傷や汚れに強いパネル材(キッチンパネルなど)を張る「腰壁」は非常に有効な対策です。
拭き掃除が簡単で、壁紙のように張り替える手間もかかりません。
壁紙を選ぶ場合は、表面が強化された「ペット対応クロス」がおすすめです。
一般的なビニールクロスに比べて傷がつきにくく、消臭機能や抗菌機能が付加されたものもあります。
漆喰や珪藻土などの自然素材は、調湿効果や消臭効果が期待できる一方で、爪で引っ掻くと崩れやすいため、犬が直接触れない場所での使用を検討するのが良いでしょう。
素材選びは、初期費用だけでなく、長期的なメンテナンスコストや、愛犬の健康への影響も考慮して総合的に判断することが後悔しないための鍵となります。
ショールームなどで実際の素材感や滑りにくさを確かめ、専門家のアドバイスも参考にしながら、ご自身のライフスタイルと愛犬に最適な素材を見つけてください。
ドッグランの設置に必要な費用と注意点
庭に専用のドッグランがある家は、愛犬家にとって大きな魅力です。
いつでも自由に、そして安全に愛犬を走り回らせてあげられる空間は、運動不足の解消やストレス発散に繋がり、犬の健康維持に大きく貢献します。
しかし、ドッグランを設置するには、どのくらいの費用がかかり、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
ドッグラン設置費用の内訳
ドッグランの設置費用は、広さ、地面の素材、フェンスの種類などによって大きく変動しますが、主な内訳は以下の通りです。
- 整地・造成費用
- 地面(サーフェス)の費用
- フェンス・門扉の費用
- その他の設備費用(水栓、日よけなど)
例えば、30平方メートル(約10坪)程度の広さで、一般的なメッシュフェンスと人工芝を設置した場合、50万円から100万円程度が費用の目安となることが多いようです。
もちろん、DIYで施工範囲を広げれば費用を抑えることも可能です。
地面(サーフェス)選びの重要性
ドッグランの地面は、犬の足腰への負担、夏場の温度、メンテナンスのしやすさを考慮して選ぶ必要があります。
代表的な素材には、天然芝、人工芝、ウッドチップ、砂などがあります。
- 天然芝:見た目が美しく、クッション性も高いですが、定期的な芝刈りや雑草対策などのメンテナンスが不可欠です。
- 人工芝:メンテナンスが楽で、一年中緑を保てます。水はけの良いペット用の製品を選びましょう。夏場は表面温度がかなり高温になるため、日よけや散水などの対策が必要です。
- ウッドチップ:クッション性が高く、消臭効果も期待できます。ただし、定期的な補充が必要で、犬が誤飲しないよう注意が必要です。
- 砂・土:コストを抑えられますが、雨の日に泥だらけになったり、夏場に熱を帯びやすかったりするデメリットがあります。
どの素材にも一長一短があるため、愛犬の犬種や性格、ご自身のメンテナンスにかけられる時間などを考慮して選ぶことが重要です。
安全を確保するための注意点
ドッグランで最も重要なのは安全性です。
特にフェンスの高さと強度は、脱走や事故を防ぐために慎重に検討しなければなりません。
ジャンプ力のある犬種の場合は、1.5メートル以上の高さが必要になることもあります。
フェンスの下に隙間ができないように基礎を設ける、犬が掘り返して脱走しないようにブロックを埋めるなどの対策も有効です。
門扉には、犬が自分で開けてしまうことのないよう、必ずロック機能付きのものを選びましょう。
また、夏場の熱中症対策として、日陰を作れるような工夫も必須です。
シェードを設置したり、シンボルツリーを植えたりして、犬が涼める場所を確保してあげましょう。
ドッグランの近くに専用の立水栓を設置しておくと、水分補給や体を冷やす際に非常に便利です。
ドッグランは、ただ囲いを作るだけでは機能しません。
愛犬が一年を通して安全かつ快適に利用できるよう、専門家の意見も聞きながら、細部までこだわった計画を立てましょう。
留守番時も安心な室内の設備とは
共働き家庭が増え、犬だけで留守番をする時間も長くなる傾向にあります。
大切な愛犬が安全で快適に過ごせるよう、家を建てる段階で留守番に適した設備を整えておくことは、飼い主の安心にも繋がります。
ここでは、留守番時に役立つ室内の設備について具体的に解説します。
愛犬専用の居場所「ドッグスペース」
まず考えたいのが、愛犬が落ち着いて過ごせる専用のスペースの確保です。
リビングの一角や階段下などを利用して、ケージやクレートを置ける「ドッグスペース」を設けましょう。
ここは犬にとって自分だけのテリトリーとなり、留守番中の不安を和らげる効果が期待できます。
ドッグスペースを計画する際は、以下の点に配慮すると良いでしょう。
- 人の出入りが激しくない、静かな場所
- 直射日光が当たらず、風通しの良い場所
- 夏場の暑さ、冬場の寒さ対策ができる場所(エアコンの風が直接当たらないなど)
- 床は掃除しやすく、滑りにくい素材を選ぶ
スペースに余裕があれば、壁にリードフックを取り付けたり、ペット用品を収納できる棚を造作したりすると、さらに機能的になります。
見守りカメラとスマート家電の活用
近年の技術進化により、外出先からでもペットの様子を確認できる「ペットカメラ(見守りカメラ)」が非常に便利になっています。
単に様子を見るだけでなく、声をかけられたり、おやつをあげられたりする機能を備えた製品も人気です。
家を建てる際に、カメラを設置したい場所に電源コンセントやLANポートをあらかじめ設けておくと、配線がすっきりと収まります。
また、スマートフォンで操作できるスマート家電も、留守番時の心強い味方です。
特に夏場の室温管理は、犬の熱中症予防に不可欠です。
外出先からエアコンを操作できるスマートリモコンや、設定温度になると自動で運転を開始する機能を活用し、常に快適な室温を保つようにしましょう。
照明やカーテンの開閉を自動化すれば、生活リズムを整える手助けにもなります。
安全対策と誤飲防止の工夫
留守番中に最も心配なのが、思わぬ事故です。
犬が立ち入ってほしくないキッチンや階段、書斎などには、ベビーゲートやペットゲートを設置できるように、あらかじめ壁に下地を入れておくと取り付けがスムーズです。
また、電気コードやコンセントは、犬が噛んでしまわないように家具の裏に隠したり、コンセントカバーを付けたりする対策を徹底しましょう。
ゴミ箱は、いたずらされないように蓋付きのものを選んだり、収納内部に設置したりする工夫が必要です。
犬にとって危険な洗剤や薬品、人間の食べ物などは、必ず扉付きの収納に保管するように間取りの段階から計画しておくことが大切です。
これらの設備や工夫を家づくりに取り入れることで、飼い主は安心して外出でき、愛犬は安全で快適な留守番時間を過ごすことができるようになります。
気になる臭い対策と効果的な換気方法
犬と暮らす上で、多くの飼い主が直面する悩みが「臭い」の問題です。
動物である以上、ある程度の体臭や排泄物の臭いは仕方がありません。
しかし、家づくりの段階で適切な対策を講じておくことで、その悩みを大幅に軽減することが可能です。
ポイントは「臭いの発生源をコントロールすること」と「発生した臭いを効率的に排出すること」です。
臭いの発生源と対策
家の中の主な臭いの発生源は、犬の体そのもの、排泄物、そして犬が使用するベッドやマットなどです。
- トイレ周りの対策:犬のトイレを置く場所は、臭いがこもりやすく、掃除が頻繁に必要になります。このスペースの床や壁には、アンモニアに強く、拭き掃除がしやすい素材(クッションフロアやパネル材など)を採用するのがおすすめです。また、トイレの近くに専用の換気扇や消臭機能付きの小型換気扇を設置すると、臭いを素早く排出できます。
- ドッグスペースの素材選び:犬が日常的に過ごすベッドやケージ周りも臭いが染み付きやすい場所です。壁には調湿・消臭効果のある珪藻土や漆喰、あるいは消臭機能付きの壁紙を選ぶと効果的です。ただし、前述の通り、犬が直接爪をかける場所は避けるなどの工夫が必要です。
- シャンプー・グルーミングスペースの確保:定期的なシャンプーは、体臭を抑える基本です。浴室や洗面脱衣所、あるいは土間などに、犬を洗いやすいシャワー設備(ハンドシャワーなど)があると非常に便利です。乾かす場所も考慮し、コンセントの位置などを計画しておきましょう。
換気計画の重要性
臭い対策の基本であり、最も効果的なのが「換気」です。
現在の住宅は高気密・高断熱化が進んでいるため、計画的な換気が不可欠です。
建築基準法で義務付けられている「24時間換気システム」を正しく活用することが大前提となります。
その上で、犬と暮らす家ではさらに一歩進んだ換気計画を検討しましょう。
例えば、家全体の空気の流れを意識し、臭いがこもりやすいトイレ周りやドッグスペースに排気口を設け、新鮮な空気が取り込まれる給気口はリビングや寝室など、人が快適に過ごしたい場所に配置する、といった工夫です。
窓の配置も重要です。
風の通り道を考えて、対角線上に窓を配置すると、効率的な自然換気(通風)が可能になります。
地窓(床に近い低い位置の窓)と高窓(天井に近い高い位置の窓)を組み合わせると、温度差による空気の対流が生まれ、より換気効果が高まります。
空気清浄機や脱臭機の活用
換気計画を補う形で、高性能な空気清浄機やペット用の脱臭機を導入するのも有効な手段です。
これらを設置する場所をあらかじめ想定し、コンセントを配置しておくと、スマートに設置できます。
臭いの問題は、一度気になり始めると大きなストレスになります。
「これくらい大丈夫だろう」と安易に考えず、設計士や工務店とよく相談し、素材選びと換気計画の両面から、しっかりと対策を施した家づくりを進めることが、快適な共生生活の秘訣です。
犬と暮らす家とドッグランと間取りの具体的なアイデアと実例
◆この章のポイント◆
- 平屋で実現する犬との快適な暮らし
- 参考になるドッグラン付き住宅の実例集
- 散歩帰りに便利な足洗い場などの設備
- 毎日の掃除を楽にする間取りの工夫
- 家族と愛犬が共に満足する犬と暮らす家とドッグランと間取りの総括
平屋で実現する犬との快適な暮らし
近年、世代を問わず人気が高まっている平屋ですが、実は「犬と暮らす家」としても多くのメリットを持っています。
階段のないワンフロアの生活は、犬にとっても人間にとっても安全で、コミュニケーションが取りやすいという特徴があります。
ここでは、平屋が犬との暮らしに最適な理由と、その魅力を最大限に活かす間取りのアイデアについてご紹介します。
平屋が犬との暮らしに適している理由
平屋の最大のメリットは、何と言っても「階段がないこと」です。
- 足腰への負担軽減:犬種によっては、階段の上り下りが足腰に大きな負担をかけ、椎間板ヘルニアなどの病気のリスクを高めます。特に胴長短足の犬種や、関節が弱い小型犬、そしてシニア犬にとって、階段のない生活は健康を守る上で非常に重要です。
- 転落事故の防止:階段からの転落は、大きな怪我につながる危険な事故です。平屋であれば、その心配が根本的にありません。
- 家族との一体感:全ての生活空間がワンフロアに収まるため、犬は常に家族の気配を感じながら安心して過ごすことができます。飼い主も、どこにいても愛犬の様子に目が届きやすく、コミュニケーションが深まります。
- 庭(ドッグラン)との連携:平屋は構造的に庭との距離が近く、大きな窓を設置しやすいため、リビングから直接ドッグランへスムーズに出入りできるような間取りを実現しやすいという利点があります。
平屋を活かす間取りのアイデア
平屋のメリットを最大限に引き出すためには、間取りの工夫が鍵となります。
「コの字型」や「L字型」の建物形状は、特におすすめです。
建物で中庭を囲むような形にすることで、プライバシーを確保しながら、安全なドッグランスペースを生み出すことができます。
そして、その中庭に面して大きな窓やウッドデッキを設ければ、室内と屋外が一体化したような開放的な空間が生まれます。
犬は自由に外で遊び、飼い主はリビングでくつろぎながらその様子を見守る、といった理想的な暮らしが実現します。
また、回遊性のある動線計画も平屋ならではの工夫です。
例えば、リビング→ウッドデッキ→庭→玄関土間→リビングといったように、家の中と外をぐるりと一周できるような「回遊動線」を作ると、犬は探検気分で楽しく過ごせますし、家事動線としても効率的です。
このとき、床材の素材を切り替えることで、犬が入って良いエリアとそうでないエリアを視覚的に示す「ゾーニング」を行うと、しつけにも役立ちます。
平屋は、犬と家族が穏やかで豊かな時間を共有するための、最適なプラットフォームと言えるかもしれません。
土地の広さなどの条件が許すのであれば、犬と暮らす家を建てる際の有力な選択肢として、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
参考になるドッグラン付き住宅の実例集
理想の「犬と暮らす家とドッグランと間取り」を具体的にイメージするためには、実際の成功事例を参考にすることが一番の近道です。
ここでは、様々なライフスタイルや犬種に合わせたドッグラン付き住宅のアイデアを、いくつかの実例としてご紹介します。
実例1:リビングと一体化したウッドデッキ&ドッグラン
都心近郊の住宅地に住む、中型犬(ボーダーコリー)と暮らすアクティブな夫婦のケースです。
限られた敷地を有効活用するため、リビングの前に広々としたウッドデッキを設置。
リビングの床とデッキの高さを揃えることで、室内と屋外がシームレスに繋がる開放的な空間を演出しています。
ウッドデッキの先には、手入れのしやすい人工芝のドッグランが広がります。
リビングの大きな窓を開け放てば、犬はいつでも自由に外へ駆け出していくことができます。
飼い主は、キッチンで料理をしながらでも、愛犬が元気に遊ぶ姿を見守ることができ、安心です。
ドッグランの周りは、外からの視線を遮りつつ、風通しは確保できる高さのウッドフェンスで囲み、プライバシーと安全性を両立させています。
散歩帰りには、玄関脇に設けた温水も出る立水栓で足を洗い、そのままウッドデッキで体を乾かしてから室内に入るという、汚れない動線が確保されているのもポイントです。
実例2:プライベートな中庭ドッグランを持つ平屋
多頭飼い(トイプードル2匹)のシニア夫婦が、終の棲家として建てた平屋のケースです。
建物を「コの字型」に配置し、中央に完全プライベートな中庭ドッグランを実現しました。
この間取りの最大のメリットは、道路からの飛び出しの心配が一切なく、安心して犬を遊ばせられることです。
中庭に面して各部屋が配置されているため、家のどこにいても愛犬たちの気配を感じることができます。
ドッグランの地面には、足腰に優しい天然芝を採用。
芝の手入れは、ご主人の趣味と健康維持の一環になっています。
夏の日差し対策として、深い軒(のき)を設けており、強い日差しが室内に入るのを防ぐと共に、雨の日でも犬が少し外に出られるスペースとしても機能しています。
室内は完全なバリアフリーで、床材は滑りにくく、万が一粗相をしても掃除が簡単なペット用のクッションフロアを全面的に採用しています。
実例3:自然の地形を活かした広大なドッグラン
郊外の広い土地に住む、大型犬(ゴールデンレトリバー)と暮らすファミリーのケースです。
元々の緩やかな傾斜地を活かし、広々としたナチュラルな雰囲気のドッグランを作りました。
地面はあえて手を加えすぎず、一部にウッドチップを敷き詰めることで、犬が走り回っても足に負担がかからないように配慮しています。
敷地内には木陰を作る大きな木をそのまま残し、自然の地形を楽しみながら運動できる、犬にとって最高の遊び場となっています。
家事動線も工夫されており、キッチン横のパントリーから直接ドッグランへ出られる勝手口を設置。
家庭菜園で採れた野菜を運んだり、犬のお世話をしたりと、多目的に使える便利な動線です。
これらの実例はほんの一例です。
大切なのは、ご自身のライフスタイル、愛犬の犬種や年齢、そして土地の条件に合わせて、最適な形を模索することです。
多くの実例を参考にしながら、自分たちだけの理想の住まいを具体化していきましょう。
散歩帰りに便利な足洗い場などの設備
毎日の散歩は、犬との暮らしに欠かせない日課です。
しかし、雨の日や地面がぬかるんでいる日の散歩後は、足や体が汚れてしまい、家の中に入る前に綺麗にするのが一苦労、と感じている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
家づくりの段階で、散歩帰りに役立つ設備を計画的に導入しておくことで、この手間を大幅に軽減し、毎日の散歩をより快適なものにすることができます。
理想的な「足洗い場」の設置場所と機能
散歩帰りの汚れを家の中に持ち込まないためには、「足洗い場」の設置が非常に効果的です。
設置場所として最適なのは、玄関の土間や、玄関横の屋外スペース、あるいは勝手口の近くなど、散歩から帰ってきてすぐにアクセスできる場所です。
足洗い場に求められる機能は以下の通りです。
- 温水対応:冬場の散歩後、冷たい水で足を洗うのは犬にとって大きなストレスです。給湯器と接続し、お湯も使える混合水栓にしておくと、犬に優しく、汚れも落ちやすくなります。
- シャワーヘッド:通常の蛇口よりも、ハンドシャワータイプのものがおすすめです。足だけでなく、お腹周りや全身が汚れてしまった時にも、ピンポイントで洗い流すことができ非常に便利です。
- 深さと広さのあるパン(水受け):小型犬であれば、しゃがまずに作業ができるよう、少し高さのあるガーデンシンクタイプが便利です。大型犬の場合は、床レベルに広めの防水パンを設置し、その場で犬を洗えるようにすると良いでしょう。排水設備をしっかり整え、水はけを良くしておくことが重要です。
- リードフック:犬を洗っている間、両手が使えるように、近くの壁にリードを固定しておくためのフックがあると安全で便利です。
グルーミングスペースと収納計画
足を洗った後は、体を拭いたり乾かしたりする「グルーミングスペース」が必要です。
足洗い場の横に、犬が乗れるくらいの広さのタイル貼りのスペースや、すのこを敷いたエリアを設けると良いでしょう。
このスペースの近くに、タオルやドライヤーを使うための防水コンセント、そしてシャンプーやブラシ、タオルなどを収納しておくための棚や収納ボックスを設けておくと、一連の作業が非常にスムーズになります。
玄関土間を通常より広く設計し、この足洗い場、グルーミングスペース、そして関連用品の収納までを一体化した「ドッグスペース」として計画するのも、人気の間取りアイデアです。
散歩用のリードやうんち袋、レインコートなどもまとめて収納できれば、散歩の準備も帰宅後の片付けも格段に楽になります。
これらの設備は、後から追加しようとすると大掛かりな工事が必要になる場合があります。
犬との暮らしを具体的にシミュレーションし、設計段階で必要な設備をしっかりと間取りに組み込んでおくことが、後悔しない家づくりのための賢い選択と言えるでしょう。
毎日の掃除を楽にする間取りの工夫
犬と暮らす上で避けて通れないのが「掃除」の問題です。
抜け毛、皮脂汚れ、よだれ、足跡、そして時には粗相など、家の中は想像以上に汚れやすくなります。
この日々の掃除の負担を、少しでも軽くするためには、家づくりの段階で「掃除のしやすさ」を考慮した間取りや設備を取り入れることが非常に重要です。
掃除を楽にする間取りの基本
掃除のしやすさを追求した間取りのポイントは、「シンプルで凹凸が少ないこと」です。
- 段差をなくす:床の段差は、ホコリが溜まりやすく、ロボット掃除機がスムーズに動けない原因にもなります。可能な限り家全体の段差をなくすバリアフリー設計は、犬の安全だけでなく、掃除の効率化にも繋がります。
- 壁や角を減らす:部屋の隅や角は、抜け毛やホコリが溜まりやすい「デッドスペース」です。間仕切りの少ないオープンな間取りにしたり、壁の出隅・入隅を減らしたりすることで、掃除機がけが楽になります。
- 家具の配置計画:造り付けの収納や壁掛けテレビなどを活用し、床に直接置く家具を減らす「浮かす収納」は、掃除機をかける際に家具を動かす手間が省けるため、非常におすすめです。家具を置く場合も、脚付きで床との間に隙間があるデザインのものを選ぶと、ロボット掃除機が下を通り抜けることができます。
設備で掃除の負担を軽減する
最新の設備を上手に取り入れることも、掃除の時短に繋がります。
セントラルクリーナーは、各部屋に設けられた差込口にホースを接続するだけで掃除ができるシステムです。
排気が屋外に出るため、室内の空気を汚さずに掃除ができるというメリットがあり、アレルギーが気になる方にもおすすめです。
また、コンセントの配置も意外と重要です。
各部屋に十分な数のコンセントを設けるのはもちろん、廊下や収納内部など「ここに欲しかった」となりがちな場所にも計画的に配置しておくと、コードレス掃除機の充電や、様々な掃除用具を使う際に便利です。
素材選びと収納計画
前述の通り、床材や壁材を汚れがつきにくく、かつ拭き取りやすい素材にすることも、掃除を楽にするための基本です。
特に、犬のトイレ周りや水飲み場の床は、防水・防汚性能の高いクッションフロアやフロアタイルが適しています。
そして、散らかりがちなペット用品や掃除用具を、使う場所の近くにすっきりと収納できる計画も大切です。
リビングにペット用品専用のクローゼットを設けたり、洗面所に掃除用具をまとめて収納できるスペースを確保したりするだけで、部屋全体が片付きやすくなり、結果的に掃除のハードルも下がります。
「掃除は毎日のことだから」と割り切るのではなく、「毎日のことだからこそ、少しでも楽にしたい」という視点で間取りを工夫することが、犬との快適で衛生的な暮らしを長く続けるための秘訣です。
家族と愛犬が共に満足する犬と暮らす家とドッグランと間取りの総括
この記事を通じて、犬と暮らす家とドッグランと間取りを計画する上での様々なポイントをご紹介してきました。
愛犬は、私たちにとって言葉を話さない、しかし、かけがえのない大切な家族の一員です。
その家族が、毎日を安全で、健康で、そして心豊かに過ごせる住まいを創り上げることは、飼い主にとっての大きな喜びであり、責任でもあります。
後悔しない家づくりのためには、見た目のおしゃれさや人間の都合だけを優先するのではなく、犬の習性や特性を深く理解し、犬の視点に立って考えることが何よりも重要になります。
滑りにくい床材を選ぶこと、危険な場所へのアクセスを防ぐこと、安心して休める場所を確保すること。
これら一つ一つの細やかな配慮が、愛犬の心と体の健康を守ることに繋がります。
また、ドッグランの設置は、愛犬の運動不足やストレスの解消に大きな効果をもたらしますが、その計画には費用や安全対策、メンテナンスといった現実的な側面が伴います。
地面の素材は何が良いのか、フェンスの高さはどれくらい必要か、専門家のアドバイスも参考にしながら、ご自身の環境と愛犬に最適な形を見つけ出すことが大切です。
そして、忘れてはならないのが、飼い主自身の快適さです。
掃除のしやすさや、臭い対策、効率的な家事動線など、日々の負担を軽減する工夫を取り入れることで、心にゆとりが生まれ、愛犬と向き合う時間もより豊かなものになるでしょう。
犬と暮らす家とドッグランと間取りの計画は、愛犬への愛情を形にする、創造的で素晴らしいプロセスです。
本記事でご紹介したポイントを参考に、ぜひあなたと愛犬にとって最高の住まいを実現してください。
本日のまとめ
- 犬と暮らす家の計画は犬の安全性と動線を最優先する
- 床材は滑りにくく掃除がしやすいペット用素材が推奨される
- ドッグランの費用は広さや素材で変動し安全対策が必須
- 留守番時のためには専用スペースと見守りカメラが有効
- 臭い対策は換気計画と消臭効果のある建材で対応する
- 平屋は階段がなく犬の足腰に優しく安全性が高い
- コの字型やL字型の間取りでプライベートな中庭ドッグランが作れる
- 実例を参考に自分たちのライフスタイルに合った間取りを見つける
- 散歩帰りの足洗い場は温水シャワー付きが便利
- グルーミングスペースと収納を一体化すると動線がスムーズになる
- 掃除を楽にするには段差や凹凸の少ない間取りを心掛ける
- 家具を浮かせる工夫やロボット掃除機の活用も効果的
- 脱走防止のため玄関や庭のゲートには二重ロックなどの対策を施す
- 飼い主と愛犬双方の快適性を追求することが後悔しない秘訣
- 犬と暮らす家とドッグランと間取りは愛情を形にする作業である

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |
参考サイト
ドッグランをつくりたい方必見!ペットと暮らす家の実例を解説します! | 住まいの発見館|千葉県の新築戸建て|注文住宅
ドッグランの間取り一覧 – madree(マドリー)
【ペット×注文住宅】犬や猫と暮らす家の間取り実例を紹介 – ステーツ
「犬と暮らす家」の間取りやアイデア。5つの住宅実例から学ぶ!
注文住宅でペットの犬と楽しく暮らしたい!間取り例と費用相場を解説 – 家づくりのとびら


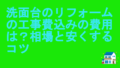
コメント