こんにちは、サイト管理人です
60才からの平屋の間取りを考え始めるとき、多くの希望と同時に、少しの不安も感じているのではないでしょうか。
これからの人生を豊かに、そして快適に過ごすための大切な住まいづくりですから、失敗はしたくないと誰もが思うはずです。
特に、夫婦二人の暮らしに合わせたコンパクトながらも機能的な空間、将来の身体的な変化を見据えたバリアフリー設計、そして気になる費用や収納の問題など、考えるべきことは多岐にわたります。
老後の生活を支える家だからこそ、間取りの一つ一つにこだわり、後悔のない選択をしたいものです。
この記事では、60才からの平屋の間取りを計画する上で重要なポイントを、具体的な間取り図や失敗例を交えながら、網羅的に解説していきます。
家事動線を考えた暮らしやすいレイアウトのヒントから、おしゃれで開放感のある空間づくりのアイデア、さらには土地探しや住宅ローンの注意点まで、あなたの疑問や悩みを解決するための一助となるでしょう。
この記事を読み終える頃には、あなたにとって理想の平屋の姿が、より鮮明になっているはずです。
◆このサイトでわかる事◆
- 60才からの平屋でよくある後悔と失敗のパターン
- 夫婦二人の生活に最適な坪数と間取りの考え方
- 将来安心して暮らすためのバリアフリー設計の要点
- 家事負担を減らす効率的な生活動線の作り方
- 平屋建築の費用相場と無理のない資金計画の立て方
- おしゃれで快適な2LDKや3LDKの具体的な間取り例
- 理想の平屋づくりを任せられる住宅会社の選び方


| 【PR】憧れの平屋での暮らし、実現しませんか? 「何から始めればいいかわからない」「たくさんの住宅会社を回るのは大変…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、自宅にいながらたった3分で、複数の住宅会社にオリジナルの家づくり計画を無料で依頼できます。 あなたのためだけに作成された「間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」が無料で手に入り、簡単に比較検討できるのが魅力です。 厳しい基準をクリアした信頼できる全国1,190社以上の優良企業が、あなたの理想の平屋づくりをサポートします。 情報収集だけでも大歓迎。まずは無料一括依頼で、理想のマイホームへの第一歩を踏み出してみましょう。 |
60才からの平屋の間取りで失敗しないための計画
◆この章のポイント◆
- 多くの人が経験する後悔のポイントとは
- 夫婦二人の暮らしに最適な坪数を考える
- 将来を見据えたバリアフリー設計の重要性
- 家事の負担を軽減する生活動線の工夫
- 建築にかかる費用の目安と資金計画
多くの人が経験する後悔のポイントとは
60才からの平屋づくりは、これからの人生を豊かにするための素晴らしい一歩です。
しかし、慎重に計画を進めないと、住み始めてから「こうすれば良かった」という後悔につながるケースも少なくありません。
ここでは、多くの方が経験する失敗や後悔のポイントを具体的に見ていきましょう。
これらの事例を知ることで、ご自身の家づくりで同じ轍を踏まないようにすることができます。
まず最も多い後悔の一つが、収納スペースに関する問題でしょう。
夫婦二人だからと収納を最小限に設計した結果、長年かけて増えた趣味の道具や思い出の品々、季節ごとの家電などが行き場を失ってしまうのです。
特に、普段使わないものの収納場所として屋根裏収納やロフトを考えがちですが、年齢を重ねると梯子の上り下りが大きな負担となり、結果的に「使えない収納」になってしまうことも考えられます。
次に、コンセントの位置と数もよくある失敗点として挙げられます。
若い頃とは違い、健康管理のための医療機器や、スマートフォン、タブレット、マッサージチェアなど、使う電化製品は意外と多いものです。
掃除機をかける際にも、部屋の隅々にコンセントがないと不便を感じるでしょう。
ベッドサイドやソファの近く、廊下など、実際の生活をシミュレーションして適切な場所に十分な数を設置しなかった後悔は、日々の小さなストレスとして蓄積していきます。
また、窓の大きさや位置に関する後悔も耳にします。
採光や風通しを重視して大きな窓を設置したものの、外からの視線が気になってしまい、一日中カーテンを閉めっぱなしというのでは本末転倒でしょう。
逆に、プライバシーを意識しすぎるあまり窓を小さくしすぎると、日中でも照明が必要な暗い部屋になってしまうかもしれません。
土地選びの段階で隣家との位置関係や道路からの視線を考慮し、適切な場所に適切な大きさの窓を配置することが重要になります。
さらに、寝室の広さや位置も慎重に検討すべきポイントです。
将来的に介護が必要になる可能性を考えると、ベッドの周りに十分なスペースがなかったり、トイレから遠かったりすると、本人だけでなく介助者の負担も大きくなってしまいます。
今は夫婦二人で同じ寝室でも、将来の健康状態の変化によっては部屋を分ける必要が出てくるかもしれません。
その際の柔軟性も考慮しておくと、より安心な設計と言えるでしょう。
最後に、良かれと思って取り入れた設備が、かえって生活を不便にするケースもあります。
例えば、デザイン性を重視した海外製のおしゃれな水栓やドアノブは、使い勝手が悪かったり、故障した際の修理が困難だったりすることがあります。
日々の暮らしで頻繁に使う設備は、デザインだけでなく、機能性やメンテナンスのしやすさも重視して選ぶ視点が欠かせません。
これらの後悔ポイントを事前に把握し、一つひとつ丁寧に対策を講じることで、心から満足できる平屋づくりへと繋がるのです。
夫婦二人の暮らしに最適な坪数を考える
60才からの平屋の間取りを考える上で、まず最初に直面するのが「どれくらいの広さが必要か」という坪数の問題です。
お子様が独立され、夫婦二人での生活が中心となるため、広すぎず狭すぎない、まさに「ちょうど良い」広さを見つけることが快適な暮らしの鍵となります。
一般的に、国土交通省が示す「誘導居住面積水準」によると、都市部以外での豊かな生活を送るために推奨される住宅の面積は、二人世帯で75平方メートル(約22.7坪)とされています。
しかし、これはあくまで一般的な目安であり、ライフスタイルによって最適な坪数は大きく異なります。
例えば、20坪から25坪(約66~82平方メートル)程度のコンパクトな平屋は、ミニマムな暮らしを求めるご夫婦に人気があります。
この坪数であれば、LDKに加えて夫婦それぞれの個室を持つ2LDKの間取りが十分に可能です。
掃除やメンテナンスの手間が少なく、光熱費も抑えられるため、経済的な負担を軽減できる点が大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、収納スペースが限られるため、持ち物の量を計画的に管理する必要があります。
一方で、趣味の部屋が欲しい、来客用の寝室を確保したい、というご夫婦には、25坪から30坪(約82~99平方メートル)程度の坪数が考えられます。
この広さがあれば、2LDKに加えて書斎やアトリエといったプラスアルファの空間を設けたり、ゆとりのある3LDKの間取りを実現したりできます。
孫たちが遊びに来た時に泊まれる部屋を用意しておくことで、家族との交流もより一層深まるかもしれません。
30坪を超えるようなゆとりのある平屋も、もちろん選択肢の一つです。
広いリビングや、夫婦それぞれの趣味に没頭できる個室、大容量のウォークインクローゼットなど、理想の暮らしを詰め込むことができるでしょう。
しかし、坪数が大きくなると建築費用や固定資産税も高くなる傾向にあります。
また、将来的に夫婦どちらか一人になった場合の維持管理の負担も考慮しておく必要があるでしょう。
最適な坪数を考える際には、現在のライフスタイルだけでなく、将来の生活の変化も見据えることが重要です。
- 現在の持ち物の量と、今後の増減の見込み
- 来客(子供や孫、友人)の頻度と宿泊の有無
- 夫婦それぞれの趣味や、家で過ごす時間の使い方
- 将来的な介護の可能性と、それに必要なスペース
- 予算と、維持管理にかけられる手間や費用
これらの要素を夫婦でじっくりと話し合い、優先順位をつけることが、後悔しない坪数選びの第一歩です。
モデルハウスや完成見学会に足を運び、実際の広さを体感してみるのも非常に参考になります。
数字だけでは分からない空間の広がりや、動線の感覚を肌で感じることで、ご夫婦にとって本当に必要な坪数が見えてくるはずです。
将来を見据えたバリアフリー設計の重要性
60才からの平屋づくりにおいて、バリアフリー設計は単なるオプションではなく、将来の安心な暮らしを守るための必須項目と言えるでしょう。
現在は健康で不自由なく生活していても、年齢を重ねるにつれて身体能力が変化することは自然なことです。
将来、車椅子での生活になったり、介助が必要になったりする可能性を視野に入れ、家づくりの段階から備えておくことが極めて重要になります。
バリアフリー設計の基本は、家の中の段差をなくすことです。
玄関の上がり框、リビングと和室の間の敷居、洗面所と浴室の入口など、わずかな段差でも転倒のリスクとなり得ます。
設計の段階で、これらの段差をすべてフラットにする計画を立てましょう。
特に、玄関アプローチにはスロープを設けることを強く推奨します。
車椅子での出入りはもちろん、ベビーカーを押す際や、重い荷物を運ぶキャリーケースを使う際にも非常に便利です。
次に、手すりの設置も欠かせません。
立ち座りの動作が多くなるトイレや、滑りやすい浴室には必ず設置しましょう。
また、廊下や玄関にも手すりがあると、歩行時の安定感が増し、転倒予防に繋がります。
すぐに必要なくても、将来的に手すりを設置できるよう、壁の内部に下地補強を施しておくだけでも、後々のリフォーム費用を大きく抑えることができます。
廊下やドアの幅も重要なポイントです。
一般的な廊下の幅は78cm程度ですが、車椅子がスムーズに通るためには、少なくとも85cm以上の幅が望ましいとされています。
特に、廊下の角を曲がる「コーナー部分」はさらに広いスペースが必要になるため、設計段階で考慮が必要です。
同様に、寝室やトイレのドアは、車椅子でも出入りしやすいように、有効開口幅が80cm以上確保できる引き戸にするのが理想的でしょう。
引き戸は、開き戸のように開閉スペースを必要としないため、空間を有効に使えるというメリットもあります。
水回りの設計も、将来を見据えて考えましょう。
浴室は、浴槽のまたぎが低いものを選び、洗い場には介助者が一緒に入れるくらいのスペースを確保すると安心です。
トイレも、車椅子で回転できる広さを確保し、介助スペースを考慮した配置にすることが望ましいと考えられます。
スイッチやコンセントの高さも、ユニバーサルデザインの視点を取り入れることをお勧めします。
一般的なスイッチの高さは床から110~120cmですが、車椅子に座ったままでも操作しやすいように、少し低めの90~100cm程度に設定すると、誰にとっても使いやすい家になります。
これらのバリアフリー設計は、決して特別なものではありません。
これからの暮らしを安全で快適なものにするための、いわば「未来への投資」です。
元気なうちから備えておくことで、将来どんな変化があっても、住み慣れた我が家で安心して暮らし続けることができるのです。
家事の負担を軽減する生活動線の工夫
年齢を重ねると、日々の家事も少しずつ負担に感じられるようになるかもしれません。
60才からの平屋の間取りでは、家事の効率を最大限に高め、身体的な負担を軽減する「生活動線」の工夫が、快適な暮らしを実現する上で非常に重要です。
生活動線とは、家の中を移動する際の人の動きを示す線のことで、特に家事に関する動きをまとめたものを「家事動線」と呼びます。
この動線が短く、シンプルであるほど、家事は楽になります。
家事動線を考える上で最も重要なのが、キッチン、洗面脱衣室(洗濯機置き場)、物干しスペース(ウッドデッキやサンルームなど)の位置関係です。
これら「水回り」と呼ばれる空間をできるだけ近くに集約させることが、家事効率を上げるための基本となります。
例えば、キッチンで料理をしながら洗濯機の様子を見に行ったり、洗濯が終わったらすぐに隣のサンルームに干したり、といった一連の作業がスムーズに行えます。
「ながら家事」がしやすくなることで、家事に費やす時間を大幅に短縮できるでしょう。
特に人気なのが、「回遊動線」を取り入れた間取りです。
これは、家の中に行き止まりがなく、ぐるぐると回り道できる動線のことを指します。
例えば、「キッチン → パントリー → 洗面脱衣室 → ファミリークローゼット → キッチン」といったように、家事に関連するスペースを繋げることで、無駄な往復をなくし、効率的に作業を進めることが可能になります。
来客時に、お客様にプライベートな空間を見せることなく水回りへ案内できるというメリットもあります。
また、洗濯に関する一連の作業をワンストップで完結できる間取りも、家事負担の軽減に大きく貢献します。
具体的には、「洗う(洗濯機)→ 干す(室内干しスペース)→ 乾かす(乾燥機)→ たたむ(作業台)→ しまう(ファミリークローゼット)」という流れを、洗面脱衣室とその周辺に集約させるのです。
天候を気にせず洗濯ができ、重い洗濯カゴを持って移動する必要がなくなるため、身体的な負担が劇的に軽くなります。
ゴミ出しの動線も見落としがちなポイントです。
キッチンで出た生ゴミや、各部屋で出たゴミをスムーズに集め、外部のゴミ置き場まで最短距離で移動できるような勝手口の配置を考えると、日々の小さな手間を省くことができます。
さらに、買い物から帰ってきた際の動線も考慮すると、より暮らしやすくなります。
玄関からパントリーやキッチンに直接アクセスできる間取りであれば、重い食料品などをすぐに収納することができ便利です。
これらの家事動線の工夫は、日々の暮らしの質を大きく左右します。
ご自身の家事のスタイルを思い返し、「どの作業に時間がかかっているか」「どの移動が負担に感じるか」を分析することが、最適な動線を見つけるための第一歩となるでしょう。
設計士に自分たちの暮らし方を具体的に伝えることで、より自分たちにフィットした、家事が楽になる間取りの提案を受けられるはずです。
建築にかかる費用の目安と資金計画
理想の60才からの平屋の間取りを思い描くとき、避けては通れないのが費用の問題です。
退職金やこれまでの貯蓄を元に、無理のない資金計画を立てることが、安心して家づくりを進めるための大前提となります。
平屋の建築費用は、主に「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」の3つに分けられます。
一般的に、総費用のうち本体工事費が約70~80%、付帯工事費が約15~20%、諸費用が約5~10%を占めると言われています。
本体工事費は、建物そのものを建てるための費用で、坪単価で計算されることが多い部分です。
平屋の坪単価は、木造の場合で60万円~100万円程度が相場とされていますが、使用する建材や設備のグレード、住宅会社の工法によって大きく変動します。
例えば、25坪の平屋を建てる場合、本体工事費は「25坪 × 坪単価60~100万円 = 1,500万円~2,500万円」がひとつの目安となるでしょう。
付帯工事費は、建物以外の工事にかかる費用です。
具体的には、古い家の解体費用、地盤改良工事費、給排水・ガスの引込工事費、外構工事費(駐車場、フェンス、庭など)、エアコンやカーテンの設置費用などが含まれます。
これは土地の状況によって大きく異なり、数百万円単位でかかることも珍しくないため、資金計画の段階で多めに見積もっておくことが重要です。
諸費用は、工事以外で必要となる手続き上の費用を指します。
不動産取得税や固定資産税などの税金、登記費用、火災保険料、住宅ローンを利用する場合はその手数料などが該当します。
これらも総額で100万円以上になることが多いため、忘れずに予算に組み込んでおきましょう。
資金計画を立てる際には、まず自己資金として用意できる金額を正確に把握することから始めます。
退職金や預貯金など、家づくりに充てられる資金をリストアップしましょう。
その際、老後の生活費や、病気や介護に備えるための予備費は必ず手元に残しておくことが大切です。
全ての資金を家づくりに注ぎ込んでしまうと、後々の生活が苦しくなってしまう可能性があります。
住宅ローンを利用する場合は、借入可能額と返済計画を慎重に検討する必要があります。
多くの金融機関では、完済時の年齢が80歳までと設定されているため、60代でローンを組む場合は返済期間が短くなる傾向にあります。
年金収入を考慮しながら、毎月無理なく返済できる金額を設定することが何よりも重要です。
親子でローンを組む「親子リレーローン」などの選択肢も検討してみる価値はあるでしょう。
最終的には、複数の住宅会社から相見積もりを取り、詳細な見積書の内容を比較検討することが不可欠です。
どこまでの工事が見積もりに含まれているのか、追加費用が発生する可能性はないかなど、不明な点は徹底的に確認しましょう。
明確で堅実な資金計画が、理想の平屋づくりを成功に導く土台となるのです。
快適な暮らしを叶える60才からの平屋の間取り具体例
◆この章のポイント◆
- 開放感と機能性を両立した2LDKのプラン
- 趣味や来客にも対応できる3LDKのレイアウト
- すっきり暮らすための十分な収納スペース
- 暮らしを豊かにする庭やウッドデッキの活用法
- 理想の60才からの平屋の間取りを実現する会社選び
開放感と機能性を両立した2LDKのプラン
夫婦二人の暮らしに最適な間取りとして、まず検討したいのが2LDKのプランです。
コンパクトながらも工夫次第で、開放感と高い機能性を両立させることが可能です。
60才からの平屋の間取りにおける2LDKは、リビング・ダイニング・キッチン(LDK)に加えて、夫婦それぞれのプライベート空間として利用できる2つの個室を設けるのが基本的な形となります。
この2つの個室をどう使うかが、暮らしの満足度を大きく左右するポイントです。
例えば、一つを主寝室とし、もう一つを趣味の部屋や書斎として活用するプランが人気です。
ご主人が読書やパソコン作業に集中できる空間、奥様が手芸や絵画を楽しめるアトリエなど、それぞれの時間を大切にできる場所があることで、生活にメリハリが生まれるでしょう。
この個室は、時には子供や孫が遊びに来た際のゲストルームとしても機能します。
開放感を演出するための鍵は、LDKの設計にあります。
平屋のメリットである天井高を活かし、勾配天井や吹き抜けを取り入れると、帖数以上の広がりを感じられる空間になります。
天井に梁を見せるデザインにすれば、おしゃれなアクセントにもなるでしょう。
また、LDKと庭を繋ぐ大きな掃き出し窓を設置することも効果的です。
窓の外にウッドデッキを設ければ、リビングの延長としてアウトドアリビングのように活用でき、内と外が一体となった開放的な空間が生まれます。
機能性を高めるためには、家事動線と収納計画が重要です。
2LDKのコンパクトな間取りだからこそ、水回りを集中させ、家事動線を最短にする工夫が活きてきます。
キッチンから洗面脱衣室、そしてファミリークローゼットへと繋がる回遊動線を取り入れれば、無駄な動きなく家事をこなすことができます。
収納については、各所に分散させるのではなく、一箇所にまとめたファミリークローゼットを設けることをお勧めします。
夫婦二人の衣類や季節のものをまとめて管理することで、部屋が散らかりにくくなり、衣替えの手間も省けるでしょう。
さらに、玄関横にシューズクローク兼用の土間収納を設けると、コートや傘、趣味のアウトドア用品などを気兼ねなく収納できて便利です。
将来の生活変化への備えも忘れてはなりません。
今は一つのLDKとして使っていても、将来的にリビングの一部を間仕切り壁や可動式家具で区切って、介護用のスペースとして使えるようにしておく、といった柔軟な発想も大切です。
2つの個室の間に、普段はウォークスルークローゼットとして使い、必要に応じて開け放てる引き戸を設けておけば、一体の広い部屋として使うことも可能になります。
このように、2LDKのプランは、限られた空間を最大限に活かす知恵と工夫が詰まった間取りです。
夫婦二人の心地よい距離感を保ちながら、開放的で機能的な暮らしを実現できる、非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
趣味や来客にも対応できる3LDKのレイアウト
趣味の時間を充実させたい、あるいは子供や孫たちが頻繁に遊びに来る、そんなライフスタイルを思い描いているご夫婦には、ゆとりのある3LDKのレイアウトが適しています。
60才からの平屋の間取りとして3LDKを選ぶことは、現在の快適さだけでなく、将来の多様な可能性にも備えることを意味します。
3LDKの基本構成は、LDKと3つの個室です。
この3つの個室をどのように活用するかが、プランニングの醍醐味と言えるでしょう。
一般的な使い方としては、まず一つを主寝室にします。
残りの二つの部屋の使い方が、暮らしの質を大きく左右します。
一つを常設のゲストルーム(客間)に充てるというプランは非常に人気があります。
いつでも気兼ねなく子供や孫を迎え入れることができ、宿泊してもらうことで、家族との絆を育む大切な拠点となります。
普段は空いている客間を、室内干しスペースとして活用したり、大型の荷物の一時置き場にしたりと、多目的に使える点もメリットです。
そして、もう一部屋を夫婦それぞれの、あるいは共通の趣味の部屋として活用するのです。
例えば、シアタールームとして大画面で映画を楽しんだり、フィットネスルームとして健康維持のためのトレーニングに励んだり、あるいは書斎やアトリエとして創作活動に没頭したりと、夢は広がります。
第二の人生を謳歌するための「基地」となる空間があることは、日々の生活に大きな喜びと張りを与えてくれるでしょう。
3LDKのレイアウトでは、パブリックスペースとプライベートスペースのゾーニングを意識することが重要です。
お客様をお通しするLDKやゲストルームは玄関に近い場所に配置し、主寝室などのプライベートな空間は、廊下の奥など、家族以外が立ち入りにくい場所に設けると、お互いに気兼ねなく過ごすことができます。
また、LDKと隣接する一部屋を、壁ではなく引き戸で仕切るプランもおすすめです。
普段は引き戸を開け放ってLDKと一体の広い空間として使い、来客時には戸を閉めて個室として利用する、といった柔軟な使い方が可能になります。
3LDKの坪数は、一般的に28坪~35坪程度が目安となります。
部屋数が増える分、それぞれの部屋が狭くならないように、全体のバランスを考える必要があります。
例えば、個室の広さは必要最低限の4.5畳~6畳程度に抑え、その分LDKや収納を充実させる、といったメリハリのある設計が求められます。
将来的な視点も大切です。
例えば、夫婦のどちらかが介護が必要になった際に、一部屋を介護スタッフの控え室として利用したり、介護用ベッドを置く部屋として使ったりすることも想定できます。
ゆとりのある3LDKの間取りは、こうした不測の事態にも対応しやすいという大きな安心感に繋がります。
趣味も、家族との交流も、そして将来への備えも諦めない。
そんなアクティブで豊かなシニアライフを実現するために、3LDKの平屋は非常に有効な選択肢となるでしょう。
すっきり暮らすための十分な収納スペース
「家は、暮らす人が作るもの。でも、家をすっきりと見せるのは収納だ」と言われることがあります。
特に、60才からの平屋の間取りにおいては、計画的で十分な収納スペースを確保することが、快適で安全な暮らしを維持するための重要な鍵となります。
年齢を重ねると、物を減らす「断捨離」も大切ですが、それでも長年連れ添った思い出の品や、趣味の道具、季節ごとの衣類や寝具など、手放せないものは意外と多いものです。
これらを適切に収める場所がなければ、家の中はあっという間に物で溢れ、散らかった空間はつまずきや転倒の原因にもなりかねません。
効果的な収納計画の基本は、「適材適所」の考え方です。
つまり、「使う場所の近くに、使うものを収納する」ということです。
この原則に従って、家の中の必要な場所に適切なタイプの収納を配置していきましょう。
まず考えたいのが、大容量の「集中収納」です。
その代表格がウォークインクローゼット(WIC)やファミリークローゼットでしょう。
夫婦二人の衣類やバッグ、季節家電などを一箇所にまとめて管理できるスペースを設けることで、各部屋に大きなタンスを置く必要がなくなり、空間を広々と使うことができます。
ハンガーパイプや可動棚を組み合わせることで、効率的に多くのものを収納可能です。
次に、玄関脇に設ける「シューズインクローゼット(SIC)」または土間収納も非常に有効です。
靴だけでなく、傘、コート、ベビーカー、ゴルフバッグ、ガーデニング用品など、屋外で使うものを室内に持ち込むことなく収納できます。
臭いや汚れが気になるものを気兼ねなく置けるため、室内を清潔に保つのに役立ちます。
キッチン周りには、「パントリー(食品庫)」を設けることを強くお勧めします。
常温保存できる食料品や飲料、防災用の備蓄、普段あまり使わない調理器具などをストックしておくための空間です。
パントリーがあることで、キッチンのキャビネットやカウンターをすっきりと保つことができ、調理作業もはかどります。
これらの大型収納に加えて、日々の生活でよく使うものを収めるための「分散収納」も重要です。
例えば、リビングにはテレビボード周りの収納や、壁面を利用したニッチ(飾り棚)、洗面脱衣室にはタオルや洗剤、着替えなどをしまえるリネン庫、トイレには掃除用品やトイレットペーパーを収納する吊戸棚など、それぞれの場所で必要となるものを、さっと取り出せる場所に設ける工夫が暮らしやすさに繋がります。
収納を計画する上で注意したいのが、奥行きです。
奥行きが深すぎる収納は、奥に入れたものが取り出しにくく、結果的に「死蔵品」を生む原因になります。
収納するものに合わせて、適切な奥行きを設定することが大切です。
また、年齢を重ねると高い場所や低い場所のものの出し入れが負担になります。
収納は、目線から腰高の、最も使いやすい「ゴールデンゾーン」を中心に計画し、可動棚などを活用して、将来の身体の変化に合わせて高さを調整できるようにしておくと、長く快適に使い続けることができるでしょう。
暮らしを豊かにする庭やウッドデッキの活用法
平屋の大きな魅力の一つは、地面との距離が近く、自然を身近に感じられることです。
その魅力を最大限に引き出してくれるのが、庭やウッドデッキの存在です。
60才からの平屋の間取りを考える際には、室内だけでなく、屋外空間とのつながりを意識することで、暮らしの豊かさや楽しみが何倍にも広がります。
ウッドデッキは、リビングの延長として機能する「もうひとつの部屋」と言えるでしょう。
リビングの床と高さを揃えたフラットなウッドデッキを設けることで、室内と屋外が一体となり、空間に広がりと開放感をもたらします。
天気の良い日には窓を開け放ち、デッキチェアを置いて読書を楽しんだり、夫婦でお茶を飲んだりと、気軽にアウトドア気分を味わえるのが魅力です。
屋根やオーニング(日よけ)を設置すれば、夏の日差しや多少の雨も気にせず、快適に過ごせる時間が増えるでしょう。
また、ウッドデッキは実用的なスペースとしても活躍します。
洗濯物や布団を干す場所として、あるいは鉢植えの植物を育てるサンルーム代わりとしても最適です。
滑りにくく、手入れのしやすい素材を選ぶことが、安全で長く使い続けるためのポイントです。
庭づくりは、シニアライフにおける大きな楽しみの一つになり得ます。
ガーデニングや家庭菜園は、適度な運動になるだけでなく、土に触れ、植物の成長を見守ることで、心に癒やしと充実感を与えてくれます。
しかし、広すぎる庭は手入れが負担になる可能性も考慮しなければなりません。
無理なく管理できる範囲で、「育てる楽しみ」と「眺める楽しみ」のバランスを取ることが大切です。
例えば、手入れのしやすいハーブや季節の花を中心に植えた花壇を設ける、あるいは、車椅子でも作業しやすいように高さを出した「レイズドベッド」で家庭菜園を楽しむ、といった工夫が考えられます。
雑草対策として、砂利やウッドチップ、防草シートなどを活用することも、メンテナンスの負担を軽減するために有効です。
庭に照明を設置すれば、夜には昼間とは違った幻想的な雰囲気を楽しむことができます。
ライトアップされた木々を眺めながら、ウッドデッキで夕涼みをする時間は、何にも代えがたい贅沢なひとときとなるでしょう。
防犯上の観点からも、庭の照明は有効です。
プライバシーの確保も忘れてはなりません。
道路や隣家からの視線が気になる場合は、デザイン性の高いフェンスや生け垣、あるいは背の高い樹木などを効果的に配置することで、プライベート感を保ちながら、緑豊かな景観を作り出すことができます。
庭やウッドデッキは、家という「ハコ」に、彩りや潤い、そして生活の楽しみを与えてくれる大切な要素です。
家の中から庭の緑を眺める時間、ウッドデッキで風を感じる時間。
そんな何気ない日常の瞬間が、これからの暮らしをより豊かで満たされたものにしてくれるに違いありません。
理想の60才からの平屋の間取りを実現する会社選び
どんなに素晴らしい間取りのアイデアがあっても、それを形にしてくれるパートナー、つまり信頼できる住宅会社を見つけなければ、理想の家づくりは始まりません。
特に、専門的な知識や配慮が求められる60才からの平屋の間取りにおいては、会社選びが成功の9割を占めると言っても過言ではないでしょう。
住宅会社には、大きく分けて「ハウスメーカー」「工務店」「設計事務所」の3つのタイプがあります。
それぞれの特徴を理解し、自分たちの家づくりに合った会社を選ぶことが重要です。
ハウスメーカーは、全国規模で事業を展開しており、ブランド力と豊富な実績が魅力です。
商品ラインナップが体系化されているため、品質が安定しており、工期も比較的短い傾向にあります。
モデルハウスやカタログが充実しているため、完成形をイメージしやすいのもメリットです。
一方で、仕様がある程度決まっているため、設計の自由度は工務店や設計事務所に比べて低い場合があり、価格も高めになることが考えられます。
工務店は、地域に密着した営業スタイルが特徴です。
その土地の気候や風土を熟知しており、柔軟な対応力と設計の自由度の高さが強みです。
ハウスメーカーに比べて広告宣伝費が少ない分、コストを抑えられる可能性もあります。
ただし、会社によって技術力やデザイン力に差があるため、過去の施工事例などをしっかりと確認し、信頼できる会社かを見極める必要があります。
設計事務所は、設計と工事監理を専門に行うプロフェッショナルです。
何よりも設計の自由度が高く、施主の要望にとことん向き合い、独創的でデザイン性の高い家づくりが可能です。
第三者の立場で工事を厳しくチェックしてくれる「工事監理」も、安心材料の一つでしょう。
ただし、設計料が別途必要になることや、設計から完成までの期間が長くなる傾向がある点は考慮しておく必要があります。
では、具体的にどのような基準で会社を選べば良いのでしょうか。
まず第一に、「平屋の建築実績」、特に「シニア世代の家づくり」の実績が豊富かどうかを確認しましょう。
バリアフリー設計や、老後の暮らしやすさを考えた動線計画など、専門的なノウハウを持っている会社は、より的確な提案をしてくれるはずです。
担当者との相性も、非常に重要なポイントです。
家づくりは、担当者と二人三脚で進めていく長い道のりです。
こちらの要望を親身になって聞いてくれるか、専門家として的確なアドバイスをくれるか、そして何よりも信頼できる人柄か、といった点をじっくりと見極めましょう。
完成見学会やOB宅訪問などのイベントに積極的に参加するのも良い方法です。
実際にその会社が建てた家を見て、触れて、空間を体感することで、図面だけでは分からない品質や雰囲気を確かめることができます。
可能であれば、実際に住んでいる施主の方から直接話を聞く機会があれば、会社の対応や住み心地など、貴重な生の声を知ることができるでしょう。
最後に、会社の経営状況や、引き渡し後のアフターサービス、保証制度についても必ず確認してください。
家は建てて終わりではありません。
末永く安心して暮らしていくために、長期的なサポート体制が整っている会社を選ぶことが、理想の60才からの平屋の間取りを実現するための最終的なゴールと言えるのです。
本日のまとめ
- 60才からの平屋は将来を見据えた計画が重要
- 収納不足やコンセント位置はよくある後悔ポイント
- 夫婦二人なら20坪から25坪がコンパクトで機能的
- 趣味や来客を考えるなら25坪から30坪の3LDKも視野に
- バリアフリー設計は未来の安心のための必須投資
- 家の中の段差解消と手すり設置は基本中の基本
- 家事動線は水回りを集約させると格段に楽になる
- 洗濯動線を一箇所で完結させる間取りが人気
- 総費用は本体工事費の他に付帯工事費と諸費用がかかる
- 老後の生活費を確保した無理のない資金計画を立てる
- 2LDKはLDKの開放感と個室のプライベート性が鍵
- 3LDKは趣味や家族との交流を豊かにする選択肢
- 収納は「集中収納」と「分散収納」の組み合わせが効果的
- ウッドデッキや庭は暮らしに潤いと楽しみをもたらす
- 理想の60才からの平屋の間取りの実現は信頼できる会社選びから


| 【PR】憧れの平屋での暮らし、実現しませんか? 「何から始めればいいかわからない」「たくさんの住宅会社を回るのは大変…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、自宅にいながらたった3分で、複数の住宅会社にオリジナルの家づくり計画を無料で依頼できます。 あなたのためだけに作成された「間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」が無料で手に入り、簡単に比較検討できるのが魅力です。 厳しい基準をクリアした信頼できる全国1,190社以上の優良企業が、あなたの理想の平屋づくりをサポートします。 情報収集だけでも大歓迎。まずは無料一括依頼で、理想のマイホームへの第一歩を踏み出してみましょう。 |
参考サイト
シニアに優しい平屋の間取りは?高齢者向けの家づくりのコツ | SUUMOお役立ち情報
【ルームツアー】60代の夫婦が建てた25坪の平屋/極寒地青森でも暖かい高断熱×老後も安心のバリアフリー設計でゆったり暮らす間取り – YouTube
「60代からの平屋暮らし」に関する注文住宅実例 (16件) – SUUMO
20坪台の老後に快適&おしゃれな平屋間取り図、60才からの家づくりのポイント
【ルームツアー】大好評!60歳からの家づくり、シニア夫婦25坪の平屋 – YouTube

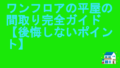

コメント