こんにちは、サイト管理人です
注文住宅で5人家族の暮らしを計画する際、多くの希望と同時に、たくさんの疑問や不安が生まれるのではないでしょうか。
理想の間取りはどうすれば良いのか、必要な広さや坪数はどのくらいなのか、そして最も気になる費用や価格はどれほどになるのか、考えるべきことは山積みです。
また、後悔しない家づくりのためには、子供部屋の考え方や、日々の家事を楽にする動線、十分な収納計画も欠かせません。
リビングやキッチンの使いやすさはもちろん、将来を見据えた設計が求められます。
土地探しから住宅ローンの計画まで、専門的な知識が必要な場面も多く、どこから手をつけて良いか迷ってしまう方も少なくないでしょう。
特に、30坪や40坪といった具体的な広さでどのような家が建つのか、あるいは平屋という選択肢はどうなのか、具体的なイメージを持つのは難しいかもしれません。
この記事では、注文住宅で5人家族が快適に暮らすための基本的な知識から、具体的な間取りの工夫、予算の立て方まで、あなたの疑問や不安を解消するための情報を網羅的に解説していきます。
家づくりで後悔しないために、しっかりとした知識を身につけ、家族みんなが笑顔で暮らせる理想のマイホームを実現させましょう。
◆このサイトでわかる事◆
- 5人家族に最適な家の広さと坪数の目安
- 後悔しないための基本となる間取りパターン
- 注文住宅の費用相場と具体的な予算計画の立て方
- 家族の将来まで見据えた子供部屋の設計ポイント
- 家事効率を格段に上げるための動線と収納の秘訣
- 失敗しない土地選びと住宅ローンの賢い活用法
- 家族が自然と集まる開放的なリビングの作り方

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |
注文住宅で5人家族が快適に暮らすための基礎知識

◆この章のポイント◆
- 必要な広さや最適な坪数は?
- 間取りは4LDKや5LDKが基本
- 費用の相場と予算の考え方
- 土地選びで失敗しないポイント
- 住宅ローンの賢い組み方とは
必要な広さや最適な坪数は?
注文住宅で5人家族が快適に暮らすためには、適切な広さの確保が最初のステップとなります。
一体どれくらいの坪数があれば、家族全員がゆったりと過ごせるのでしょうか。
この問いに答えるための指針として、国土交通省が公表している「住生活基本計画」が非常に参考になります。
この計画には、健康で文化的な住生活を送るために必要不可欠な「最低居住面積水準」と、豊かな住生活の実現を想定した「誘導居住面積水準」の2つの基準が示されています。
まず、最低居住面積水準では、5人家族の場合、50平方メートル(約15.1坪)と定められています。
しかし、これはあくまでも「最低限」の広さであり、注文住宅で理想の暮らしを追求するのであれば、目標とすべきは誘導居住面積水準のほうでしょう。
誘導居住面積水準には「一般型」と「都市居住型」があり、都市部以外の一般地域における5人家族の住宅面積は、150平方メートル(約45.4坪)が目安とされています。
一方で、都心とその周辺部を想定した都市居住型では、125平方メートル(約37.8坪)が目安となります。
これらの数字からも分かる通り、一般的に注文住宅で5人家族の家を建てる場合、35坪から45坪程度が現実的で、かつ満足度の高い暮らしを実現しやすいボリュームゾーンと言えるでしょう。
例えば、35坪(約115.7平方メートル)の広さがあれば、設計の工夫次第で、夫婦の主寝室と子ども3人分の個室を確保した5LDKの間取りも十分に実現可能です。
40坪(約132.2平方メートル)を超えてくると、各部屋の広さにゆとりを持たせられるだけでなく、ウォークインクローゼットやシューズインクローゼット、パントリーといった大型収納や、リモートワークに対応できる書斎、趣味の部屋といったプラスアルファの空間を設ける余裕も生まれてきます。
ただし、ここで注意したいのは、単純に坪数が広ければ広いほど良いというわけではない、という点です。
無計画に面積を広げると、建築費用や固定資産税が高くなるだけでなく、日々の掃除やメンテナンスの手間が増え、光熱費もかさむことになります。
最も重要なのは、坪数という数字に捉われるのではなく、家族のライフスタイルや価値観に合った、無駄のない空間設計を追求することです。
例えば、廊下などの移動スペースを最小限に抑え、その分リビングや収納スペースを広く取る、リビング階段や吹き抜けを採用して空間を立体的に活用する、といった工夫で、坪数以上の広がりと機能性を感じられる住まいを作ることが可能になります。
また、土地の形状や建ぺい率、容積率といった法的な制約も、実現可能な建物の大きさを左右する重要な要素です。
これらの専門的な要素も踏まえつつ、モデルハウスを見学したり、様々な施工事例を参考にしたりしながら、自分たちの家族にとって本当に「ちょうど良い」広さのイメージを具体的にしていくプロセスが、満足のいく家づくりの第一歩となるでしょう。
坪数別の特徴比較
家族のライフスタイルに合わせて最適な坪数を選ぶために、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
以下に、5人家族が注文住宅を建てる際によく検討される坪数ごとの特徴をまとめました。
| 坪数 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 30坪~35坪 | コンパクトで効率的な設計が求められる | 建築費用や固定資産税を抑えられる。冷暖房効率が良く、掃除やメンテナンスも楽。 | 収納や各部屋の広さが制限されやすい。将来の家族構成の変化に対応しにくい場合がある。設計力が問われる。 |
| 35坪~40坪 | 最も一般的でバランスの取れた選択肢 | 必要な部屋数と適度な収納をバランス良く確保できる。5LDKの間取りも現実的に計画可能。 | 設計の工夫がないと、ありきたりで平凡な間取りになりがち。優先順位を明確にする必要がある。 |
| 40坪~45坪 | ゆとりある豊かな空間を実現しやすい | 広いリビングや充実した収納、書斎や趣味室などプラスアルファの空間が持てる。 | 建築費用が高くなる傾向にある。光熱費や固定資産税などのランニングコストも増加する。 |
| 45坪以上 | 非常に贅沢で多目的な空間活用が可能 | 二世帯住宅も視野に入る広さ。ホームパーティーや趣味の部屋など多様なニーズに余裕で対応可能。 | 総費用が大幅に増加する。家族のコミュニケーションが希薄にならないよう、間取りの工夫が必要になる。 |
間取りは4LDKや5LDKが基本
注文住宅で5人家族の暮らしを具体的に描き始める際、間取りの基本となるのが部屋の数と配置です。
5人家族の場合、夫婦の寝室が1部屋、そして子どもたち3人分の部屋が必要となるため、これらをどう考えるかが最初の分岐点になります。
一般的に最もスタンダードな選択肢となるのが「4LDK」です。
これは、夫婦の主寝室1部屋と、子ども用の部屋を3部屋確保した間取りを指します。
ただし、子どもがまだ小さい場合、3人分の個室を最初から用意する必要はないかもしれません。
そこで人気なのが、大きな一部屋を将来的に二つに分けられるように設計しておく「可変性のある間取り」です。
例えば、10畳の子ども部屋のドアと窓、収納をあらかじめ二つずつ設けておけば、子どもたちの成長に合わせて、簡単なリフォームで5畳の個室二つに分割できます。
これにより、幼少期は兄弟で広々と使い、思春期にはプライバシーを確保するという、ライフステージに合わせた柔軟な対応が可能になります。
一方で、最初から子ども一人ひとりに独立した個室を与えたい、あるいは書斎や趣味の部屋、ゲストルームなど、プラスアルファの空間を確保したいと考えるのであれば、「5LDK」が理想的な間取りとなります。
5LDKであれば、2階に4つの居室を設けるといったプランも可能になり、それぞれのプライベートな時間を大切にする暮らしが実現しやすくなります。
しかしながら、部屋数を増やすことは、建物全体の坪数を大きくするか、一つひとつの部屋の広さをコンパクトにするかの選択を迫られることを意味します。
坪数が増えれば建築コストや固定資産税が上がり、部屋を小さくしすぎると使い勝手が悪くなる可能性があるため、慎重な判断が求められます。
本当に5つの居室が必要なのか、それともリビングの一角にスタディコーナーを設けたり、リビング横に多目的に使える小上がりの和室を設けたりすることで代替できないか、家族のライフスタイルと予算を天秤にかけながら検討することが重要です。
また、部屋数だけでなく、その配置も暮らしやすさを大きく左右します。
例えば、1階にLDKと水回りを集約し、2階にプライベートな居室をまとめるのが基本的なセオリーですが、1階に客間や将来の夫婦の寝室としても使える和室や洋室を一部屋設けておくと、来客時に気兼ねなく使ってもらえたり、老後も平屋のような感覚で暮らせたりと、様々なメリットが生まれます。
間取りを考える上で最も大切な視点は、現在の家族の姿だけでなく、10年後、20年後の暮らしを具体的に想像することです。
子どもたちの成長と独立、そして自分たちの老後までを見据えた、息の長い視点を持つことが、長く愛せる家づくりの成功の秘訣と言えるでしょう。
費用の相場と予算の考え方
注文住宅で5人家族の家を建てるという夢を現実にする上で、避けては通れないのが「費用」の問題です。
一体どれくらいの予算を見込んでおけば良いのか、その相場観を掴むことは、計画の第一歩として非常に重要です。
住宅金融支援機構が毎年公表している「フラット35利用者調査」の2022年度版データを見てみると、土地の購入と建物の建築を合わせた「土地付注文住宅」の全国平均費用は、約4,694万円となっています。
また、すでに土地を所有している場合などの「注文住宅(建物のみ)」の平均費用は、約3,717万円です。
ただし、これはあくまで全国の平均値であり、地価の高い首都圏や近畿圏、東海圏などの都市部では、平均を上回る傾向にあります。
例えば、首都圏における土地付注文住宅の平均費用は5,406万円と、全国平均より700万円以上も高くなっています。
このように、建築するエリアや依頼するハウスメーカー・工務店のグレード、建物の坪数、そして導入する設備の仕様によって、費用は大きく変動することを理解しておく必要があります。
注文住宅の総費用は、大きく分けて「本体工事費」「別途工事費」「諸費用」という3つの要素で構成されています。
- 本体工事費: 建物そのものを建てるための費用で、基礎工事や構造躯体、内外装、住宅設備などが含まれます。一般的に、総費用の約70%~75%を占めます。
- 別途工事費: 建物本体以外にかかる工事費用です。地盤の状態によっては必要になる地盤改良工事や、駐車場・フェンスなどの外構工事、上下水道やガスの引き込み工事などがこれにあたります。総費用の約15%~20%が目安です。
- 諸費用: 工事以外にかかる各種手続きの費用のことです。不動産取得税や登記費用、住宅ローンを組むための手数料、火災保険料、印紙税などが含まれ、総費用の約5%~10%を見ておく必要があります。
予算を考える上で陥りがちなのが、広告などで目にする「坪単価」だけで建築費用を判断してしまうことです。
坪単価に含まれるのは本体工事費のみであることが多く、別途工事費や諸費用を考慮していなかったために、最終的な見積もり額が想定を大幅に超えてしまうというケースは後を絶ちません。
資金計画を立てる際は、必ずこれら3つをすべて含んだ「総額」で考える癖をつけることが極めて重要です。
具体的な予算計画の第一歩は、自分たちが用意できる「自己資金(頭金)」の額と、住宅ローンで「借入可能な額」を正確に把握することから始まります。
一般的に、住宅ローンの無理のない年間返済額は、税込み年収の25%以内が安全なラインとされています。
例えば、世帯年収が800万円であれば、年間の返済額は200万円、月々約16.6万円が目安となります。
この返済額と希望する返済期間、そして想定される金利から、おおよその借入可能額をシミュレーションできます。
自己資金と借入可能額を足した金額が、家づくりにかけられる予算の総額です。
この総額から、土地を購入する場合はその費用を差し引いたものが、建物にかけられる予算となります。
限られた予算の中で理想を叶えるためには、「こだわりたい部分」と「コストを抑える部分」のメリハリをつける、優先順位付けが不可欠です。
構造や断熱性といった家の基本性能は妥協せず、内装や一部の設備は将来のリフォームも見据えて標準的なグレードにするといった、賢いコストコントロールを心がけましょう。
土地選びで失敗しないポイント
注文住宅の満足度は、建物の設計やデザインだけでなく、その家が建つ「土地」によっても大きく左右されます。
どんなに素晴らしい家を建てたとしても、立地環境が悪ければ、日々の暮らしに不満やストレスを感じてしまうことになりかねません。
特に注文住宅で5人家族の暮らしを考える場合、子育て環境や日常生活の利便性は、土地選びにおける極めて重要な判断基準となります。
後悔しない土地選びのために、必ずチェックすべきポイントを具体的に見ていきましょう。
第一に、子どもたちのための「教育環境と安全性」です。
学区となる小中学校までの距離は、地図上の直線距離だけでなく、実際の通学路を歩いて確認することが不可欠です。
交通量の多い道路を横断する必要はないか、歩道は整備されているか、夜間に暗く危険な場所はないかなど、親の目で厳しくチェックしましょう。
また、子どもたちがのびのびと遊べる公園や、知的好奇心を満たす図書館、地域の子育て支援センターといった施設が近くにあるかどうかも、豊かな子育て環境を構成する大切な要素です。
第二に、「日常生活の利便性」です。
毎日の食料品や日用品の買い出しに利用するスーパーやドラッグストア、いざという時に頼りになる病院やクリニック、各種手続きに必要な金融機関や郵便局などが、徒歩や自転車で行ける範囲にあると、暮らしの利便性は格段に向上します。
車が主な移動手段となる場合でも、週末の渋滞状況や、商業施設の駐車場の入りやすさなどは確認しておきたいポイントです。
加えて、最寄り駅やバス停までの距離、電車の運行本数や終電の時間も、夫婦の通勤や子どもたちの将来の通学を考えると、見過ごすことはできません。
第三に、「周辺環境と安全性」です。
土地を見に行く際は、晴れた日の昼間だけでなく、平日と休日、朝と夜など、異なる時間帯や曜日に複数回訪れることを強くお勧めします。
昼間は静かでも夜は騒がしかったり、平日は問題なくても週末は交通量が激増したりすることがあるからです。
近隣に工場や飲食店など、騒音や臭いの発生源となる施設がないかも確認しましょう。
さらに、家族の安全を守る上で絶対に欠かせないのが、災害リスクの確認です。
自治体が公表しているハザードマップを利用して、洪水による浸水想定区域や、土砂災害警戒区域、地震時の液状化リスクなどを必ず確認し、できるだけ安全な土地を選ぶよう努めてください。
第四に、土地そのものが持つ「物理的な条件」です。
快適な生活の基本となる日当たりや風通しは、南側に道路があるか、隣家との距離は十分に取れるかなどによって決まります。
土地の形状(正方形に近い整形地か、旗竿地などの不整形地か)や、道路との高低差、接している道路の幅員なども、建てられる家の間取りや駐車のしやすさ、さらには追加の造成費用などに直接影響してきます。
最後に、見落としがちなのが「法的な規制」です。
「用途地域」によって建てられる建物の種類が制限されていたり、「建ぺい率」や「容積率」によって敷地面積に対する建物の大きさが定められていたりします。
これらの規制を事前に確認しておかないと、「希望していた3階建てが建てられない」「庭を確保する十分なスペースが残らない」といった事態に陥る可能性があります。
土地選びは、不動産会社や建築会社の専門家と相談しながら、多角的な視点で慎重に進めることが成功の鍵です。
住宅ローンの賢い組み方とは
注文住宅という人生で最も大きな買い物において、ほとんどの人が利用することになるのが住宅ローンです。
住宅ローンは、30年、35年といった非常に長期間にわたって返済が続くため、その組み方次第で、将来の家計に与える影響は計り知れません。
賢く、そして無理なく住宅ローンを組むための重要なポイントを理解しておきましょう。
まず最初に理解すべきは、住宅ローンの「金利タイプ」です。
金利タイプは、大きく分けて「変動金利型」「全期間固定金利型」「固定金利期間選択型」の3種類が存在します。
- 変動金利型: 一般的に3つのタイプの中で最も金利が低く設定されており、当初の返済額を抑えられるのが最大のメリットです。しかし、半年に一度金利が見直されるため、将来的に市場金利が上昇すると、返済額も増加するリスクを伴います。
- 全期間固定金利型: 代表的なものに「フラット35」があります。借入時の金利が返済終了まで変わらないため、将来の金利上昇リスクがなく、返済計画が立てやすいという絶大な安心感が魅力です。その分、金利は変動金利型よりも高めに設定されるのが一般的です。
- 固定金利期間選択型: 3年、5年、10年、20年など、契約時に定めた一定期間だけ金利が固定されるタイプです。固定期間が終了すると、その時点の金利で再度金利タイプを選び直す(変動金利にするか、再び固定金利にするか)必要があります。
どの金利タイプが最適かは、個々の家計状況やリスク許容度、将来の金利動向に対する考え方によって異なります。
例えば、共働きで収入に余裕があり、金利上昇にも対応できる資金力がある家庭なら、低金利の恩恵を受けやすい変動金利型が有利かもしれません。
一方で、これから子どもの教育費が本格的にかかってくる時期を迎える家庭など、将来の支出増に備えて月々の返済額を確定させておきたい場合は、全期間固定金利型の安心感が何物にも代えがたいでしょう。
次に重要なのが、「無理のない借入額」を設定することです。
金融機関の事前審査で提示される「融資可能額」は、あくまで「金融機関が貸せる上限額」であり、自分たちが「将来にわたって無理なく返済し続けられる額」とは必ずしも一致しません。
先にも述べた通り、年収に占める年間返済額の割合(返済負担率)は、25%以内に抑えるのが安全な水準とされています。
現在の家計収支だけでなく、将来の昇給や、逆に病気や転職による収入減のリスク、子どもの進学プラン、親の介護の可能性など、長期的なライフプランニングに基づいて、余裕を持った資金計画を立てることが極めて重要です。
さらに、住宅ローンを選ぶ際には、金利の低さだけでなく、「団体信用生命保険(団信)」の内容もしっかりと比較検討する必要があります。
団信は、ローン契約者に死亡または高度障害といった万が一の事態が発生した際に、ローンの残債が保険金によって弁済される制度で、住宅ローンを組む際には加入が義務付けられていることがほとんどです。
最近では、基本的な保障に加えて、がんや3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)、8大疾病などを保障する、より手厚い特約が付いた団信も増えています。
これらの特約は、金利に0.1%~0.3%程度上乗せされる形で提供されることが多いですが、民間の生命保険に別途加入するよりも割安な場合も少なくありません。
自分たちの健康状態や家系などを考慮し、必要な保障を見極めることも、賢いローン選びの一環です。
繰り上げ返済のしやすさや手数料の有無、各種手数料の安さなども含め、複数の金融機関の商品を総合的に比較し、自分たちの家族にとって最も有利な住宅ローンを見つけ出しましょう。
注文住宅で5人家族の後悔しないための間取りの工夫
◆この章のポイント◆
- 将来を見据えた子供部屋の考え方
- 暮らしやすさを左右する収納計画
- 家事の効率を上げる動線のポイント
- 開放感を演出するリビングの作り方
- 理想の注文住宅で5人家族の暮らしを叶えるために
将来を見据えた子供部屋の考え方
注文住宅で5人家族の家を建てる際、3人のお子さんのための部屋をどう計画するかは、間取りを考える上で非常に楽しく、同時に頭を悩ませるテーマです。
子どもたちの成長段階や性別、そして家族の教育方針によって最適な答えは異なりますが、後悔しないための最大のキーワードは「将来の可変性」をあらかじめ設計に盛り込んでおくことです。
子どもたちがまだ保育園や小学校低学年といった小さい時期は、完全に独立した個室を与えるよりも、兄弟姉妹が一緒に遊んだり勉強したりできる、広いオープンスペースを用意する方が、協調性やコミュニケーション能力を育む上で良い影響を与えるという考え方があります。
このアプローチで人気なのが、「間仕切りリフォーム」を前提とした設計です。
例えば、新築時には10畳や12畳といった広めの一部屋だけを用意しておき、将来、子どもたちがそれぞれのプライベートな空間を必要とする年齢(中学生頃が一般的)になったタイミングで、壁や可動式の間仕切り家具を設置して、5畳や6畳の個室2部屋に分割するという方法です。
この将来の分割をスムーズかつ低コストで実現するためには、新築時にいくつかの「仕込み」をしておくことが極めて重要になります。
- 出入り口の確保: 将来2部屋になった際のそれぞれの出入り口として、ドアをあらかじめ2つ設置しておきます。
- 採光と通風の確保: 部屋を分割しても、それぞれの部屋で十分な明るさと風通しが確保できるように、窓を左右に分けて配置します。
- 設備配線の分散: 照明のスイッチやコンセント、テレビアンテナ端子、エアコン用のスリーブ(壁の穴)と専用コンセントも、2部屋での使用を想定して、あらかじめ両サイドにバランス良く配置しておくと、リフォーム時の電気工事が不要になります。
- 収納の事前設置: クローゼットなどの収納も、あらかじめ左右対称に2つ設けておけば、部屋を分けた際にそれぞれの部屋の収納としてそのまま機能します。
これらの準備を怠ると、いざリフォームする際に、壁の解体や大規模な電気工事が必要となり、想定外の費用と時間がかかってしまう可能性があります。
一方で、最初から3人分の個室を用意するプランを選ぶ家庭ももちろんあります。
その場合の部屋の広さは、4.5畳から6畳程度が一般的です。
ベッドと学習机、そして本棚やクローゼットを置けばほぼ埋まる広さですが、部屋の形状をできるだけ凹凸のない正方形や長方形に近づけることで、家具のレイアウトがしやすくなり、面積の数字以上に広く感じられる空間を作ることが可能です。
さらに長期的な視点を持つならば、子どもたちが成長し、やがて独立して家を巣立っていった後の「空き部屋」の活用法まで考えておくと、より無駄のない家づくりができます。
例えば、夫婦それぞれの書斎やアトリエとして使ったり、二つの部屋をつなげて広いゲストルームにしたり、あるいはシアタールームやフィットネススペースといった趣味の空間に変えることも考えられます。
子ども部屋は、子どもが家で過ごす時間の大半を占める大切な場所であると同時に、いずれは役目を終える可能性がある「期間限定の空間」でもあります。
この両方の側面を理解し、現在の使いやすさと将来の柔軟性を両立させる計画を立てることが、賢い選択と言えるでしょう。
暮らしやすさを左右する収納計画
注文住宅を建てた人が後悔した点のアンケート調査で、常に上位に挙げられるのが「収納」に関する問題です。
「収納はたくさん作ったつもりだったのに、実際に暮らしてみたら全然足りなかった」「収納の場所が悪くて、結局リビングに出しっぱなしになってしまう」といった声は後を絶ちません。
特に5人家族ともなると、衣類や靴、学用品、おもちゃ、部活動の道具、趣味のアウトドア用品など、モノの量は時間と共に増え続ける一方です。
快適で散らかりにくい家を実現するためには、単に十分な収納量を確保するだけでなく、「どこに」「何を」「どのように」収納するかを徹底的に考え抜いた、戦略的な収納計画が不可欠です。
収納計画の基本原則は「適材適所」です。
つまり、モノを使う場所のすぐ近くに、そのモノをしまうための専用の収納スペースを設けることが、片付けのハードルを下げ、家をすっきりと保つための最大の秘訣となります。
注文住宅で5人家族の家において、特に設置を検討したい効果的な収納スペースをいくつかご紹介します。
シューズインクローゼット(土間収納)
玄関の横に、靴を履いたまま出入りできる収納スペースを設けるものです。
家族5人分の大量の靴をすっきりと収納できるのはもちろん、濡れた傘やコート、ベビーカー、三輪車、外遊び用のおもちゃ、さらにはゴルフバッグやキャンプ用品といった、室内には持ち込みにくいモノを気兼ねなく置けるため、非常に重宝します。
棚を可動式にしておけば、ブーツなどの高さのある靴や、収納するモノの大きさに合わせてレイアウトを自由に変更でき、スペースを無駄なく活用できます。
パントリー(食品庫)
キッチンやその周辺に設ける食品専用の収納庫です。
週末にまとめ買いした食料品や飲料のストック、ホットプレートやミキサーといった普段あまり使わない調理家電、そして災害時に備えた備蓄品などを一括で管理できます。
パントリーがあることで、キッチンのワークトップや食器棚を常にすっきりと保つことができ、調理の効率も格段に向上します。
ファミリークローゼット
家族全員の普段着る衣類を、一か所にまとめて収納する大型のクローゼットです。
例えば、洗面脱衣所の隣にランドリールームとファミリークローゼットを隣接させれば、「洗濯機から出す→室内干しする→乾いたらその場でたたむ→すぐ横のクローゼットにしまう」という一連の作業が、最小限の移動距離で完結します。
この「洗濯動線の効率化」は、特に子育て世帯の家事負担を劇的に軽減する効果があります。
収納量を計画する際の一般的な目安として、延床面積の12%~15%程度を収納スペースに充てると良いとされています。
しかし、ただやみくもに収納を増やせば良いというわけではありません。
例えば、奥行きが深すぎる押入れは、奥に入れたモノが取り出しにくく、結果として何が入っているか分からない「死蔵品」を生み出す温床になりがちです。
収納内部の棚の奥行きや高さ、ハンガーパイプの位置などを、そこに収納したいモノのサイズ(例えば衣装ケースの幅や、コートの丈など)に合わせてミリ単位で設計することが、本当に使いやすい収納を実現するためのプロの技です。
家づくりを始める前に、一度、自分たちの持ち物をすべてリストアップし、「これはどこにしまうのが最適か」をシミュレーションしてみることを強くお勧めします。
家事の効率を上げる動線のポイント
毎日の料理、洗濯、掃除といった家事は、少しでも楽に、効率的にこなしたいものです。
この家事の負担を大きく左右するのが、住宅の間取り、特に「動線」の設計です。
動線とは、家の中を人が目的を持って移動する際の経路のことであり、この動線がスムーズで無駄がないほど、日々の暮らしは快適になります。
家事の効率化を考える上で最も重要なのが「家事動線」です。
これは、キッチン、洗面脱衣所、物干しスペースなど、家事を行う主要な場所を結んだ線のことで、この動線はできるだけ短く、シンプルに交差しないように計画するのがセオリーです。
注文住宅で5人家族の家を設計する際に、ぜひ取り入れたい動線の工夫が「回遊動線」です。
回遊動線とは、家の中のある場所からスタートして、行き止まりなくぐるりと一周して元の場所に戻れるようにした間取りのことです。
例えば、「キッチン→パントリー→洗面脱衣所・ランドリールーム→ファミリークローゼット→リビング→キッチン」といったように、家事に関連するスペースを環状につなぐことで、驚くほど家事の効率は向上します。
料理をしながら洗濯機を回し、合間に洗濯物を干すといった、複数の家事を同時進行する際にも、無駄な行き来がなくスムーズに動けます。
また、朝の忙しい時間帯に、キッチンへ向かうお母さんと洗面所へ向かうお子さんがぶつかる、といった「交通渋滞」も緩和できます。
特に使用頻度の高いキッチン周りの動線は、使いやすさを徹底的に追求したいポイントです。
シンク、コンロ(IHヒーター)、冷蔵庫の3つの設備を結んだ三角形の距離を「ワークトライアングル」と呼びますが、この3辺の合計が3.6メートルから6.0メートル程度に収まるように配置すると、数歩の移動で主要な作業がこなせる、最も効率的なキッチンになると言われています。
また、買い物から帰ってきた際に、玄関からパントリーや冷蔵庫に直接アクセスできる動線も、重い食料品を運ぶ負担を軽減してくれる、非常に人気の高い間取りです。
洗濯に関する動線も、暮らしやすさを大きく左右する要素です。
「洗う(洗濯機)→干す(物干しスペース)→たたむ・アイロンがけ(作業台)→しまう(クローゼット)」という一連の作業が、できるだけワンフロアで、かつ最短距離で完結するように計画することが理想です。
従来のように「1階で洗濯して、重い洗濯カゴを抱えて2階のバルコニーに干しに行く」という動線は、毎日のこととなると大きな負担になります。
最近のトレンドは、1階の洗面脱衣所の隣に、室内干しが完結するランドリールームや、そのまま屋外のテラスに出られる勝手口を設けるプランです。
さらに、その近くに前述のファミリークローゼットを配置すれば、洗濯に関する家事はほぼその一角で完結させることが可能になります。
家事動線だけでなく、朝の身支度や帰宅時の手洗い・着替えなどをスムーズにする「生活動線」も合わせて考慮に入れることで、さらにストレスフリーな住まいが実現します。
家族全員の1日の動きをシミュレーションしながら、最適な動線計画を練り上げていきましょう。
開放感を演出するリビングの作り方
リビングは、家族団らんの中心であり、ゲストを招き入れる家の顔とも言える大切な空間です。
注文住宅で5人家族がゆったりと快適にくつろげるリビングにするためには、実際の面積以上に「開放感」を感じられるような設計の工夫を取り入れることが非常に効果的です。
リビングに圧倒的な開放感と明るさをもたらす代表的な手法が「吹き抜け」です。
1階リビングの天井をなくし、2階の天井までを一つの大きな空間としてつなげることで、縦方向への視線の広がりが生まれ、空間を実際の坪数以上に広く、ダイナミックに見せる効果があります。
吹き抜けの高い位置に窓(ハイサイドライト)を設ければ、隣家が迫っているような土地でも、プライバシーを確保しながら安定した自然光を部屋の奥まで取り込むことができ、日中は照明いらずの明るいリビングが実現します。
また、吹き抜けを通じて1階と2階にいる家族の気配が自然と伝わりやすくなり、「リビングで過ごすお母さん」と「2階の子ども部屋で遊ぶ子ども」の間のコミュニケーションが円滑になるというメリットも期待できます。
ただし、吹き抜けを採用する際には注意点もあります。
暖かい空気が上昇しやすいため、冬場の暖房効率が下がりやすいこと、音が響きやすいこと、2階の床面積がその分減少することなどです。
これらのデメリットを克服するためには、家全体の気密性・断熱性(住宅性能)を高めること、空気を循環させるためのシーリングファンを設置すること、断熱性の高い窓を採用するなどの対策をセットで検討することが不可欠です。
「リビング階段」も、空間の広がりを演出するのに有効な手法として人気があります。
従来、廊下やホールに設置されることが多かった階段をリビング内に取り込むことで、その分の廊下のスペースをリビングの一部として活用でき、空間をより広く使えるようになります。
また、子どもが学校から帰ってきた時や、友人の家に遊びに行く際に、必ずリビングを通ることになるため、家族が自然と顔を合わせる機会が増え、コミュニケーションが取りやすいという教育的なメリットを重視する家庭も多いようです。
さらに、外部空間とのつながりを巧みに演出することも、開放感を得るための重要なテクニックです。
リビングの窓を床から天井までの大きな掃き出し窓にし、その先にリビングの床と高さを揃えたウッドデッキやタイルテラスを設けることで、室内と屋外が一体化したような視覚的な広がりが生まれます。
天気の良い日には窓を開け放ち、セカンドリビングとしてバーベキューやティータイムを楽しむといった、暮らしの楽しみも広がります。
内装の色使いも、空間の印象を大きく左右します。
壁や天井といった面積の広い部分の色を、白やアイボリー、明るいベージュなどの明るい色(膨張色)で統一すると、光が部屋全体に反射して、空間をより広く明るく見せる効果があります。
これらのテクニックを巧みに組み合わせることで、たとえ限られた面積のリビングであっても、家族5人が心地よく過ごせる、開放感あふれるくつろぎの空間を実現することが可能です。
理想の注文住宅で5人家族の暮らしを叶えるために
これまで、注文住宅で5人家族が快適に、そして後悔なく暮らすための様々な知識と工夫について詳しく解説してきました。
適切な広さや坪数の考え方から、4LDKや5LDKといった間取りの基本、そして将来を見据えた子供部屋のあり方や、日々の暮らしやすさを左右する収納計画、家事の効率を劇的に上げる動線のポイントまで、家づくりには本当に多くの検討事項が複雑に絡み合っていることをご理解いただけたかと思います。
また、建物のことだけでなく、数千万円にも及ぶ費用の相場や現実的な予算の立て方、長期にわたる住宅ローンの賢い組み方、そして何よりも暮らしの基盤となる土地選びの重要性など、理想のマイホームを実現するためには、一つひとつ丁寧に向き合わなければならないプロセスが数多く存在します。
これらすべての要素を、ご主人や奥様の希望、3人のお子さんたちの個性や成長、そして家族全体のライフスタイルと将来のライフプランを重ね合わせながら、最適なバランス点を見つけ出していく、創造的で根気のいる作業こそが、注文住宅の家づくりそのものと言えるでしょう。
注文住宅の最大の魅力は、なんといっても、建売住宅やマンションでは決して得られない「自由度の高さ」にあります。
しかし、その自由度の高さは、時に「何から手をつけて良いか分からない」「選択肢が多すぎて決められない」といった迷いや不安の原因にもなり得ます。
そんなときに、家づくりの羅針盤となるのが、家族みんなで話し合って明確にした「優先順位」です。
「これだけは絶対に譲れないという条件は何か」「ある程度は妥協できる、あるいはコストを調整できる点はどこか」を事前に共有しておくことで、計画の途中で意見が対立したり、方向性がぶれたりすることを防ぎ、スムーズで満足度の高い意思決定につながります。
「子どもたちが家中を走り回れる、開放的な吹き抜けリビングは何よりも優先したい」「共働きだから、洗濯動線の効率化は絶対に譲れない条件だ」といったように、その家族にとっての核となる価値観を定めることが、ぶれない家づくりの確かな軸となるのです。
そして、その家族の想いを専門的な知識と技術で翻訳し、具体的な「かたち」にしてくれるのが、建築会社や設計事務所といった家づくりのプロフェッショナルです。
私たちの漠然とした要望に真摯に耳を傾け、メリットだけでなくデメリットも正直に伝え、私たちの想像を超えるような、より良い提案をしてくれる。
そんな信頼できるパートナーと出会い、二人三脚で家づくりを進めていくことが、理想の注文住宅で5人家族の暮らしを叶えるための、最も確実で、そして最も楽しい道のりとなるはずです。
この記事が、これから家づくりという素晴らしい冒険に旅立つあなたの、そしてご家族の、確かな一歩となることを心から願っています。
本日のまとめ
- 注文住宅で5人家族に必要な広さは35坪から45坪が現実的な目安
- 間取りの基本は夫婦寝室と子供部屋3室を確保できる4LDKや5LDK
- 土地と建物を合わせた総費用の全国平均は約4,700万円
- 予算計画は本体工事費の他に別途工事費や諸費用も含めた総額で考える
- 土地選びでは子育て環境や生活利便性、災害リスクの確認が不可欠
- 住宅ローンは年収の25%以内の返済負担率で無理のない借入額を設定する
- 子供部屋は将来の間仕切りを想定した可変性のある設計が人気
- 収納計画は適材適所の考え方で必要な場所に十分な量を確保する
- シューズインクロークやパントリー、ファミリークローゼットが特に有効
- 家事動線は回遊性を持たせ、洗濯動線を一か所にまとめると格段に楽になる
- リビングは吹き抜けやリビング階段、ウッドデッキで開放感を演出できる
- 家づくりでは家族内での優先順位を明確にすることが成功の鍵
- 要望を形にしてくれる信頼できる建築会社を見つけることが最も重要
- 長期的な視点でライフステージの変化に対応できる家づくりを心掛ける
- 理想の注文住宅は家族全員の想いを共有し作り上げるものである

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |
●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇
神奈川のファミリーで住みやすい街ランキング!子育て世代必見
神奈川県で老後に住みやすい街ランキング!選び方の5つのポイント
●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇
参考サイト
5人家族みんなが楽しく暮らすための遊び心満載の半平屋|注文住宅の施工事例
「マイホーム5人家族間取り図」に関する注文住宅実例 (100件) – SUUMO
5人家族 間取り検索結果 注文住宅 東京 – sumuzu(スムーズ)
5人家族の施工事例・建築実例 | 注文住宅なら建築設計事務所フリーダムアーキテクツ
【ルームツアー】30坪 5人家族が暮らす参考にしたい間取り設計の家/子どもが3人いても安心な収納計画/吹き抜けのある開放感たっぷりの17帖リビング/回遊できる家事ラク動線/熊本注文住宅 – YouTube
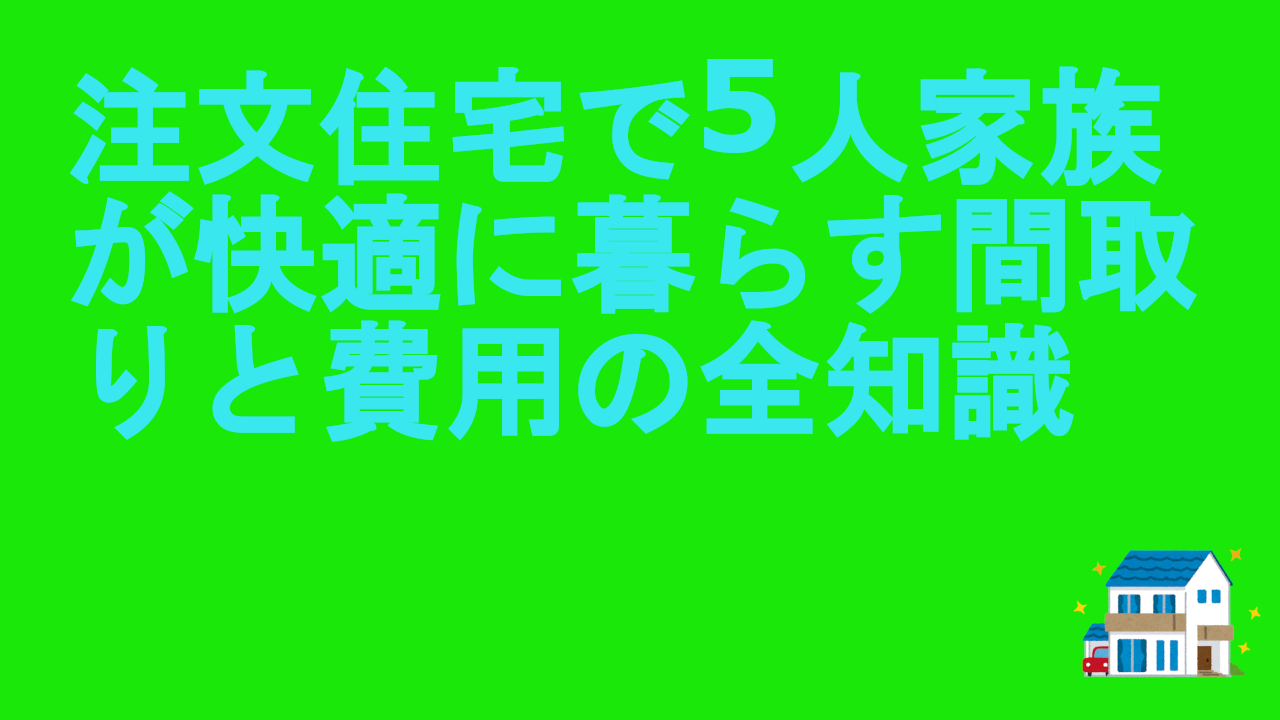


コメント