こんにちは、サイト管理人です
40代という人生の節目を迎え、ご自身の城を持つことを考え始める方は少なくありません。
特に、頭金1000万という具体的な数字が見えてくると、その夢は一層現実味を帯びてきます。
しかし、同時に多くの疑問や不安が頭をよぎるのではないでしょうか。
例えば、頭金1000万で40代で家を購入することは、本当に現実的なのでしょうか。
現在の年収で組める住宅ローンの金額や、毎月の無理のない返済額はどのくらいになるのか、具体的なシミュレーションが必要だと感じているかもしれません。
また、物件価格以外にかかる諸費用の存在や、購入後のライフプラン、特に子どもの教育費や自分たちの老後資金とのバランスをどう取るべきか、悩みは尽きないことでしょう。
物件選びにおいても、新築か中古マンションか、あるいは建売住宅か、それぞれのメリット・デメリットを比較検討したいところです。
この記事では、そうしたあなたの悩みに寄り添い、頭金1000万で40代で家の購入を成功させるための具体的な道筋を、専門的な視点から分かりやすく解説していきます。
◆このサイトでわかる事◆
- 40代の住宅ローン借入額と年収の関連性
- 無理のない住宅ローン返済額の計算方法
- 住宅購入時に見落としがちな諸費用
- 購入後のライフプランニングの重要性
- 老後資金と教育費のバランスの取り方
- 新築・中古物件のメリット・デメリット
- 専門家を活用した賢い家選びの進め方
-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |
頭金1000万で40代で家の購入を現実にする計画
◆この章のポイント◆
- 住宅ローンの借入可能額と年収の目安
- 無理のない返済額のシミュレーション
- 頭金以外に必要となる諸費用の内訳
- 購入後のライフプランと資金計画の重要性
- 将来を見据えた老後資金の確保
住宅ローンの借入可能額と年収の目安
頭金1000万円を用意できた40代の方が次に考えるべきは、「自分はいくらまで住宅ローンを借りられるのか」という点でしょう。
金融機関が融資額を決定する際の最も重要な指標の一つが年収です。
一般的に、住宅ローンの借入可能額は年収の5倍から7倍程度が目安とされています。
しかし、これはあくまで一般的な目安であり、勤務先の規模や勤続年数、他の借入状況などによって変動します。
ここで具体的な年収別の借入可能額の目安をテーブルで見てみましょう。
| 年収 | 借入可能額の目安(年収の5倍) | 借入可能額の目安(年収の7倍) |
|---|---|---|
| 500万円 | 2,500万円 | 3,500万円 |
| 600万円 | 3,000万円 | 4,200万円 |
| 700万円 | 3,500万円 | 4,900万円 |
| 800万円 | 4,000万円 | 5,600万円 |
例えば年収600万円の方であれば、3,000万円から4,200万円程度の借り入れが見込める計算になります。
ここに自己資金である頭金1000万円を加えると、4,000万円から5,200万円の物件が購入の視野に入ってくるわけです。
ただし、40代という年齢を考慮すると、金融機関は返済期間をシビアに見る傾向があります。
例えば、35年ローンを組む場合、完済時年齢が75歳を超えてしまうため、金融機関によっては返済期間が短縮される可能性も考慮しなくてはなりません。
また、忘れてはならないのが、金融機関が提示する「借入可能額」と、あなたが安心して返済し続けられる「返済可能額」は必ずしもイコールではないという事実です。
金融機関はあくまで個人の支出の詳細までは把握せずに融資額を算出します。
そのため、提示された上限額まで借りてしまうと、後々の生活が苦しくなるケースも少なくありません。
金利のタイプ(変動金利か固定金利か)によっても総返済額は大きく変わるため、審査申し込みの前に、自身のライフスタイルに合った返済計画を立てることが重要です。
無理のない返済額のシミュレーション
借入可能額を把握した次に重要なステップは、毎月、そして長期間にわたって無理なく支払える返済額を算出することです。
この指標として広く用いられるのが「返済負担率」です。
返済負担率とは、年収に占める年間返済額の割合のことで、一般的に20%から25%以内に収めるのが理想的とされています。
30%を超えると家計への負担が大きくなり、貯蓄や急な出費への対応が難しくなる可能性があるため注意が必要です。
年収別の無理のない返済額の目安は以下の通りです。
| 年収 | 返済負担率20%の場合の年間返済額 | 返済負担率20%の場合の月々返済額 | 返済負担率25%の場合の年間返済額 | 返済負担率25%の場合の月々返済額 |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 100万円 | 約8.3万円 | 125万円 | 約10.4万円 |
| 600万円 | 120万円 | 10.0万円 | 150万円 | 12.5万円 |
| 700万円 | 140万円 | 約11.7万円 | 175万円 | 約14.6万円 |
| 800万円 | 160万円 | 約13.3万円 | 200万円 | 約16.7万円 |
それでは、具体的なシミュレーションをしてみましょう。
年収700万円の方が、頭金1000万円を使い、4500万円の物件を購入するケースを考えます。
借入額は3500万円です。
このローンを金利1.5%(全期間固定)、返済期間30年で組んだ場合、月々の返済額は約12万円となります。
この場合、年間返済額は144万円となり、年収700万円に対する返済負担率は約20.5%です。
これならば、一般的に推奨される25%以内という基準をクリアしており、比較的無理のない返済計画と言えるでしょう。
しかし、これはあくまで金利が変動しない場合の計算です。
もし変動金利を選択した場合、将来的に金利が上昇すれば毎月の返済額も増加します。
金利が1%上昇するだけで、月々の返済額が1.5万円から2万円程度増えることもあり得ます。
そのため、変動金利を選ぶ場合は、金利が上昇しても家計が破綻しないか、余裕を持った資金計画を立てておくことが極めて重要になります。
頭金以外に必要となる諸費用の内訳
住宅購入において、物件価格ばかりに目が行きがちですが、それ以外にも現金で支払う必要がある「諸費用」の存在を忘れてはいけません。
頭金1000万円を全額物件の頭金に充てられるわけではなく、この諸費用分を差し引いて考える必要があります。
諸費用の金額は、購入する物件の種類(新築か中古か、マンションか戸建てか)や価格によって異なりますが、一般的に新築物件で物件価格の3%~7%、中古物件で6%~10%程度が目安です。
仮に5000万円の物件を購入する場合、中古であれば300万円から500万円程度の諸費用が現金で必要になる計算です。
主な諸費用の内訳は以下の通りです。
- 仲介手数料:不動産会社に支払う手数料。物件価格の3%+6万円+消費税が上限。
- 印紙税:売買契約書に貼付する印紙代。契約金額によって異なる。
- 登録免許税:土地や建物の所有権を登記する際にかかる税金。
- 不動産取得税:不動産を取得した際に一度だけかかる税金。
- ローン保証料・事務手数料:住宅ローンを組む際に金融機関に支払う費用。
- 火災保険料・地震保険料:万が一の災害に備えるための保険料。
- 固定資産税清算金:売主が支払ったその年の固定資産税を日割りで精算するお金。
これらの諸費用は、住宅ローンに含めて借り入れできる場合もありますが、金利が高くなるなどのデメリットもあるため、できる限り自己資金から支払うのが望ましいと言えるでしょう。
したがって、頭金1000万円のうち、いくらを諸費用に充て、残りを頭金として物件価格に充当するのか、事前にしっかりと計画を立てておくことが重要です。
また、これらに加えて引っ越し費用や新しい家具・家電の購入費用なども別途かかってくることを念頭に置いておきましょう。
購入後のライフプランと資金計画の重要性
40代での住宅購入は、20代や30代の購入とは異なり、残りの職業人生や退職後の生活をより具体的に見据える必要があります。
家を買うことはゴールではなく、あくまで豊かな人生を送るためのスタートです。
そのためには、購入後の長期的なライフプランとそれに伴う資金計画が不可欠となります。
まず考えるべきは、住宅ローンの返済以外に、将来どのようなライフイベントが待ち受けているかです。
例えば、子どもの進学、車の買い替え、親の介護、自分自身の転職や独立など、様々な可能性が考えられます。
これらのイベントにはまとまった資金が必要となるため、住宅ローンを返済しながらでも対応できるような貯蓄計画を立てなくてはなりません。
そこで役立つのが、将来の収入と支出を時系列でまとめた「キャッシュフロー表」の作成です。
これを作成することで、将来どのタイミングで資金が不足しそうか、あるいは余裕が生まれそうかを視覚的に把握できます。
また、住宅購入後に発生し続ける維持費も忘れてはいけません。
- 固定資産税・都市計画税:毎年かかる税金。
- 修繕費:外壁塗装や給湯器の交換など、経年劣化に伴うメンテナンス費用。マンションの場合は管理費・修繕積立金が毎月かかります。
- 火災保険料の更新料:数年ごとに更新が必要。
これらの費用をあらかじめ見積もっておき、毎月の返済額とは別に積み立てておくことが賢明です。
さらに、万が一の事態に備える「団信(団体信用生命保険)」の内容をしっかり確認しておくことも大切です。
死亡・高度障害時だけでなく、がんや三大疾病などの特約を付けることで、病気で働けなくなった際のリスクにも備えられます。
余裕がある時に繰り上げ返済を検討するなど、柔軟な返済計画も視野に入れ、長期的な視点で家計を管理していく意識が求められます。
将来を見据えた老後資金の確保
40代で家を購入する際に、教育費と並んで最も慎重に検討すべきなのが老後資金との両立です。
住宅ローンという長期にわたる負債を抱えながら、いかにして豊かなセカンドライフを送るための資金を確保するかは、非常に重要なテーマとなります。
多くの金融機関では住宅ローンの完済時年齢を80歳未満と設定しているため、40代で35年ローンを組むと、完済は70代後半になります。
65歳で定年退職した場合、退職後も10年以上にわたって返済が続く計算です。
この期間、年金収入の中から住宅ローンを支払い続けるのは、決して楽なことではありません。
そのため、理想を言えば、住宅ローンは定年退職を迎える65歳までに完済しておくのが望ましいと言えるでしょう。
これを実現するためには、いくつかの方法が考えられます。
- 返済期間を短く設定する:例えば、返済期間を25年や20年に設定します。月々の返済額は増えますが、総返済額を圧縮でき、老後の負担を大きく軽減できます。
- 繰り上げ返済を積極的に活用する:子育てが一段落したり、収入が増えたりしたタイミングで、まとまった資金を繰り上げ返済に充てます。これにより、返済期間を短縮することが可能です。
また、住宅ローンの返済と並行して、老後資金の準備も計画的に進める必要があります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)といった税制優遇制度を最大限に活用し、コツコツと資産形成を続けることが重要です。
「住宅ローンがあるから老後資金の準備は後回し」という考え方は非常に危険です。
キャッシュフロー表を作成し、住宅ローンの返済、教育費の支出、そして老後資金の積立という3つのバランスを常に意識しながら、資金計画を管理していく必要があります。
住宅購入はゴールではなく、あくまで豊かな老後を迎えるための一つの手段と捉える視点が大切です。
頭金1000万で40代で家選びを成功させるコツ
◆この章のポイント◆
- 子どもの教育費を考慮した資金計画
- 新築か中古か?物件選びのポイント
- 中古マンション購入時の注意点
- 建売住宅を選ぶメリットとデメリット
- 専門家への相談で不安を解消する方法
- まとめ:頭金1000万で40代で家の購入を成功させるために
子どもの教育費を考慮した資金計画
40代の多くの方にとって、住宅資金と並ぶ大きな支出が子どもの教育費です。
住宅ローンの返済が本格化する時期と、子どもの教育費がピークを迎える時期は重なることが多く、この二大支出をいかに乗り切るかが、家計の安定を左右します。
教育費は、子どもの進路によって大きく変動します。
文部科学省の調査によると、幼稚園から高校まですべて公立の場合の学習費総額は約574万円ですが、すべて私立の場合は約1,838万円にも上ります。
さらに大学に進学すれば、国公立で約243万円、私立文系で約408万円、私立理系では約551万円が追加で必要となります。
子どもが2人、3人といる場合、その負担はさらに大きくなります。
この教育費のピークは、一般的に高校から大学にかけての期間にやってきます。
この時期に住宅ローンの返済も重なることを想定し、あらかじめ計画的に資金を準備しておくことが不可欠です。
具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。
- 児童手当を全額貯蓄に回す:子どもが生まれ、中学校を卒業するまで支給される児童手当を使わずに貯めておくだけで、約200万円の資金を準備できます。
- 学資保険やNISAを活用する:毎月コツコツと積立を行い、計画的に教育資金を準備します。特に、ジュニアNISAなどを活用すれば、非課税の恩恵を受けながら効率的に資産形成が可能です。
- 住宅ローンの借入額を調整する:教育費の負担が大きい時期に備え、あえて住宅ローンの借入額を抑え、毎月の返済額に余裕を持たせるという考え方も重要です。
住宅購入を考える際には、まず子どもの教育プランを具体的に描き、将来必要となる資金額を概算することから始めましょう。
その上で、住宅にかけられる予算を決定するという手順を踏むことで、「家は買ったけれど、子どもの進学費用が足りない」といった最悪の事態を避けることができます。
新築か中古か?物件選びのポイント
頭金1000万で40代で家を探す際、多くの人が「新築」と「中古」のどちらを選ぶべきかで悩むことでしょう。
それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが優れていると一概に言うことはできません。
自身のライフスタイルや価値観、そして予算に合わせて最適な選択をすることが重要です。
ここでは、新築物件と中古物件の主な特徴を比較してみましょう。
| 項目 | 新築物件 | 中古物件 |
|---|---|---|
| 価格 | 高い傾向にある | 比較的安い |
| 立地 | 郊外や駅から離れた場所になりがち | 駅近など利便性の高い場所で見つかりやすい |
| 設備・仕様 | 最新の設備が導入されている | 古い場合が多い(リノベーションで一新可能) |
| 税制優遇 | 住宅ローン控除などの優遇措置が大きい | 築年数などの要件があり、受けられない場合もある |
| 状態 | 誰も住んでいないため、精神的な満足度が高い | 前の居住者の使用感がある。劣化状況の確認が必須 |
| 選択肢 | 供給が限られるエリアもある | 市場に出回っている物件数が多く、選択肢が豊富 |
頭金1000万円という予算を考慮すると、同じ予算でも中古物件の方が、より良い立地や広い面積の物件を選べる可能性が高いと言えます。
特に、都市部や駅周辺など利便性を重視する場合、中古物件は非常に魅力的な選択肢となります。
一方で、最新の設備や耐震性能、そして何よりも「誰も使っていない真新しい家」という満足感を求めるのであれば、新築物件が有力候補になるでしょう。
また、中古物件の場合は、購入費用に加えてリノベーション費用がかかることも念頭に置く必要があります。
最近では、中古物件を購入して自分の好みに合わせて大規模なリノベーションを施す「中古+リノベーション」という選択も人気を集めています。
どちらを選ぶにせよ、物件の価格だけでなく、将来的な資産価値やメンテナンスコスト、そして何よりも自分たちの家族がそこでどのような暮らしを送りたいかを具体的にイメージすることが、後悔しない物件選びの鍵となります。
中古マンション購入時の注意点
選択肢の多さや価格の手頃さから、中古マンションは40代の住宅購入において有力な選択肢の一つです。
しかし、新築とは異なり、建物の状態や管理状況にばらつきがあるため、購入前には慎重なチェックが欠かせません。
特に以下の3つのポイントは必ず確認するようにしましょう。
1. 管理状況
マンションの資産価値は、建物の管理状況に大きく左右されます。
エントランスや廊下、ゴミ置き場などがきれいに保たれているか、掲示板の情報は整理されているかなど、共用部分の状態を自分の目で確かめることが重要です。
管理が行き届いているマンションは、住民の意識も高く、将来にわたって快適な生活が期待できます。
2. 長期修繕計画と修繕積立金
マンションは経年劣化するため、十数年ごとに大規模な修繕工事(外壁塗装、屋上防水など)が必要となります。
そのために、将来どのような修繕をいつ、いくらくらいの予算で実施する予定なのかを示した「長期修繕計画」が存在します。
この計画がきちんと策定されているか、そして計画通りに修繕が実施されているかを確認しましょう。
さらに重要なのが、その修繕費用を賄うための「修繕積立金」です。
毎月徴収される修繕積立金が、計画に対して十分な額であるか、滞納している住戸はないかなどをチェックする必要があります。
積立金が不足していると、将来的に一時金が徴収されたり、積立金が大幅に値上げされたりするリスクがあります。
3. 建物の耐震性
日本は地震大国であるため、建物の耐震性は命に関わる重要なポイントです。
建築基準法における耐震基準は、1981年6月1日に大きく改正されました。
これ以降の基準を「新耐震基準」と呼び、それ以前を「旧耐震基準」と呼びます。
新耐震基準は「震度6強から7程度の揺れでも倒壊しない」ことを基準としており、旧耐震基準の物件に比べて格段に安全性が高まっています。
中古マンションを選ぶ際は、できる限りこの新耐震基準で建てられた物件を選ぶのが安心です。
これらの情報は、不動産会社の担当者に依頼すれば、「重要事項調査報告書」などの書類で確認することができます。
一生に一度の大きな買い物だからこそ、手間を惜しまず、納得がいくまで調べることが大切です。
建売住宅を選ぶメリットとデメリット
戸建てを希望する場合、選択肢は大きく分けて「注文住宅」「建売住宅」の2つになります。
注文住宅が土地探しから設計まで一から作り上げるのに対し、建売住宅は土地と建物がセットで販売される完成済み、あるいは建築中の住宅です。
特に、予算や入居時期を重視する40代にとって、建売住宅は魅力的な選択肢となり得ます。
建売住宅の主なメリットとデメリットを整理してみましょう。
メリット
- 価格が比較的安い:土地の仕入れや建材の大量購入、設計の共通化などにより、注文住宅に比べてコストが抑えられています。
- 実物を見て判断できる:完成済みの物件であれば、間取りや日当たり、設備などを実際に確認してから購入を決められます。
- 入居までの期間が短い:すでに完成しているため、契約から引き渡しまでの期間が短く、スピーディーな住み替えが可能です。
- 手続きがシンプル:土地と建物を同時に契約するため、手続きが比較的簡単です。
デメリット
- 間取りやデザインの自由度が低い:すでに設計が決まっているため、自分たちのライフスタイルに合わせた自由な間取り変更などはできません。
- 建築過程が見えない:完成済みの物件の場合、基礎工事や断熱材の施工など、見えない部分の品質を確認することが困難です。
- 品質にばらつきがある:施工会社によって、建物の品質に差が出ることがあります。
建売住宅を選ぶ際に特に注意したいのが、デメリットの2番目と3番目、つまり「品質」の問題です。
価格が安いことには理由があり、中にはコスト削減のために部材のグレードを下げたり、施工が丁寧でなかったりするケースも残念ながら存在します。
そこで強くお勧めしたいのが、第三者の専門家による「ホームインスペクション(住宅診断)」を利用することです。
建築士などの専門家が、買主の代わりに建物の状態を客観的にチェックしてくれます。
費用はかかりますが、欠陥住宅を購入してしまうリスクを考えれば、安心のための必要経費と捉えるべきでしょう。
価格や立地だけでなく、信頼できる施工会社が建てたのか、そして可能であればホームインスペクションを利用して、品質をしっかりと見極めることが、建売住宅選びで成功する秘訣です。
専門家への相談で不安を解消する方法
ここまで、頭金1000万で40代で家を購入するための様々な情報をお伝えしてきましたが、多くの専門用語や考慮すべき点があり、一人ですべてを判断するのは難しいと感じた方もいらっしゃるかもしれません。
住宅購入は、人生で最も大きな買い物の一つであり、その決断には大きな不安が伴うのが当然です。
そんな時は、一人で抱え込まずに、その道のプロフェッショナルである専門家の力を借りるのが賢明な選択です。
住宅購入において頼りになる専門家は、主に以下の2者が挙げられます。
1. ファイナンシャル・プランナー(FP)
FPは、お金の専門家です。
特定の不動産会社や金融機関に属さない独立系のFPに相談すれば、中立的な立場からあなたの家計を診断し、最適な資金計画を提案してくれます。
「この物件価格は、私たちの年収にとって妥当か」「住宅ローンを組んだ後の教育費や老後資金は大丈夫か」といった、お金にまつわる漠然とした不安を、キャッシュフロー表などを用いて具体的に可視化してくれます。
相談料はかかりますが、無理なローンを組んで将来破綻するリスクを考えれば、その価値は十分にあると言えるでしょう。
2. 信頼できる不動産会社の担当者
物件探しのパートナーとなる不動産会社の担当者選びも、住宅購入の成否を分ける重要な要素です。
良い担当者は、単に物件を紹介するだけでなく、あなたの希望や不安を丁寧にヒアリングし、メリットだけでなくデメリットやリスクについてもしっかりと説明してくれます。
また、地域の情報に精通しており、学区や治安、将来性など、データだけでは分からない情報を提供してくれることもあります。
複数の不動産会社を訪ね、いくつかの担当者と話をしてみて、「この人なら信頼できる」と思えるパートナーを見つけることが大切です。
住宅購入は情報戦の側面もあります。
インターネットや書籍で自ら情報収集することはもちろん重要ですが、最終的な判断を下す前に、客観的で専門的な視点を持つ専門家のアドバイスを求めることで、より納得感のある、後悔のない選択ができるようになるはずです。
まとめ:頭金1000万で40代で家の購入を成功させるために
この記事では、頭金1000万で40代で家の購入を検討している方に向けて、資金計画から物件選びのポイント、そして専門家の活用法まで、多角的に解説してきました。
40代での住宅購入は、決して遅いということはありません。
むしろ、社会人として経験を積み、自己資金もしっかりと準備できるこの時期は、住宅購入の好機とも言えます。
重要なのは、20代や30代とは異なる40代ならではの視点、つまり「将来のライフプラン全体を見据えた計画性」を持つことです。
借入可能額に振り回されるのではなく、自分たちにとっての「無理のない返済額」を基準に予算を立てること。
物件価格以外にかかる諸費用の存在を忘れず、手元の現金を残しておくこと。
そして、住宅ローンの返済と、子どもの教育費、自分たちの老後資金という「人生の三大支出」のバランスを常に意識すること。
これらのポイントを押さえ、必要であればFPなどの専門家の力も借りながら、一歩一歩着実に計画を進めていくことが、頭金1000万で40代で家の購入を成功へと導く鍵となります。
この記事が、あなたの夢のマイホーム実現への一助となれば幸いです。
本日のまとめ
- 40代での住宅購入は計画性が成功の鍵
- 頭金1000万円は大きなアドバンテージになる
- 年収の5倍から7倍が借入額の一般的な目安
- 借入可能額と返済可能額は同じではない
- 返済負担率は年収の25%以内が理想
- 頭金とは別に物件価格の1割程度の諸費用が必要
- 購入後のライフプランをキャッシュフロー表で可視化する
- 住宅ローンは65歳までの完済を目指すのが望ましい
- 老後資金の準備(iDeCoやNISA)も並行して進める
- 教育費のピークとローン返済の重複に備える
- 中古物件は同じ予算で好立地・広さを狙える可能性がある
- 中古マンションは管理状況と長期修繕計画の確認が必須
- 建売住宅はホームインスペクションの利用を検討する
- 資金計画の不安はFPに相談して解消する
- 信頼できる不動産会社の担当者を見つけることが重要
-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |
●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇
若いうちに家を買うメリットとは?後悔しないための知識
頭金なしで20代で家を買う!知っておくべき全知識
●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇
参考サイト
住宅購入に関する調査(2023年)|ARUHI
40歳貯金なし…家を買うのは難しい? リアルな事情を踏まえた住宅ローンの考え方 – LIFULL HOME’S
住宅購入で頭金の相場はいくら?40代は頭金1000万円が必要? – Wednesday
家は40代で買いなさい!今の30代が1000万円以上トクをするマイホーム購入法 – ダイヤモンド・オンライン
ずっと固定金利の安心 【フラット35】


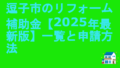
コメント